ツピダンサス(Schefflera pueckleri)の育て方

ツピダンサスの育て方
ツピダンサスは比較的育てやすい部類の植物です。20度前後の気温がベストです。水やりは土が乾いたら受け皿から滲み出てくるくらいたっぷり与えてあげます。その際、受け皿に溜まった水は根腐れの原因になりますので、必ず捨てるようにして下さい。
高温多湿の地域が原産地ですので、土に水を与えるだけでは乾燥してしまうことがあります。定期的に霧吹きなどで葉水を与え、湿度を保ってあげるようにしましょう。明るい日差しを好みますので、春や秋などにはしっかり日に当ててあげると元気に育ちます。
しかしあまり強い日差しに当たると葉焼けを起こしてしまうことがありますので、夏場などは直射日光に当たらないよう気をつけて上げる必要があります。前述の通り、寒さには弱いので、冬場は最低でも5度以下にならない室内で管理します。
水を吸収する力が弱まりますので秋から冬にかけては乾燥気味にして育てます。ただし、葉水だけは切らさないように注意しましょう。肥料は春〜秋頃に観葉植物用の液体肥料か、置き肥料を与えてあげます。肥料を与えると、葉の艶が良くなります。
大きくなりやすい植物ですので、あまり大きくしたくない場合、肥料は控えめにします。もし大きくなりすぎた場合は剪定をして切り戻してあげるといいでしょう。4月から5月頃に剪定してあげると、夏頃までには綺麗な樹形に戻ります。
鉢の底から根が溢れてきたら根詰まりを起こしていますので、植え替えをしてあげます。また2年以上植え替えをしていない場合も同様です。鉢から丁寧に取り出し、割り箸などで古い土を落とし、腐ってしまっている根があれば切り落としておきます。
用土は赤玉土と腐葉土とバーミキュライトを6:3:1くらいの割合で混ぜたものを使用します。もちろん、観葉植物用の用土を使用しても構いません。鉢の底には軽石などを敷いておくと、根腐れの防止になります。
カイガラムシやアブラムシなどの害虫がつきやすいのがネックです。葉水を表裏にしっかり与えておくとある程度の予防になりますが、もし虫が発生した場合はウェットティッシュか古い歯ブラシなどで丁寧に駆除をし、観葉植物用の殺虫剤を散布しておきましょう。
ツピダンサスの栽培の注意点
ツピダンサスは再生力が強いので、栽培も比較的容易です。ツピダンサスは挿し木や茎伏せ、取り木によって増やすことが出来ます。挿し木で増やす場合、元気のいい若い枝を10〜15センチほどに切り揃え、挿し穂にします。たくさん葉が付いていると、
そこからどんどん水を蒸発させてしまうので、数枚残して余分な葉は取り除きます。残した葉は紐などでまとめて、水分が蒸発しにくいようにしてあげると発根が早まります。葉を全部落としてしまうと光合成が出来なくなってしまうので、必ず数枚は残すようにして下さい。
すぐに土に植える前に、水で薄めたメネデールに20〜30分ほど付けて水を吸わせておくと、挿し穂が弱まりにくくなり、より効果的です。切り口に植物成長調整剤のルートンをまぶします。パーライトとバーミキュライトを1:1でまぜたもの、
もしくは挿し木用の用土を入れた鉢に挿し、根が出るのを待ちます。挿し木を行う場合、その際の用土には肥料は入れないように気をつけて下さい。肥料が入っている用土では上手く発根しません。茎伏せはある程度太さのある茎を挿し穂にする方法です。
挿し木より短めに茎を切り落とし、栽培用ポットなどに横向きに置きます。その際、必ず節の部分が含まれるようにして下さい。新芽は節の下の部分から出てくるものです。茎の表面が出るように軽く土をかぶせて栽培します。
この場合、小さめの株が育ちますので、ミニ観葉植物やハイドロカルチャー用の株として育てたい場合に向いています。節の数だけ株が出来ますので、一度にたくさん増やしたい時にも有効です。斑入りの品種などは栽培が難しいので取り木によって増やします。
株の上から30センチくらいの所で、節の真下の部分を利用します。カッターなどで1〜2センチ分ほど表皮を円状に剥ぎ取ります。水をしっかりしみこませた水苔をその部分に巻き付け、水分が蒸発しないようにビニールで2重に覆い被せます。
水苔に水の代わりに薄めたメネデールを使用すると、より効果的です。2ヶ月ほどすると発根してきますので、親株から水苔ごと切り離します。その際、せっかく出てきた根を傷つけないように丁寧に切り取って下さい。軽く水苔を落としてあげた後は、
観葉植物用の用土に植え替えてあげるとその内新芽が出てきます。翌年にはしっかりとした株に成長することでしょう。取り木による栽培では、挿し木や茎伏せに比べて大きめの株に育ちます。
種付けで増やしたい方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらツピダンサスの種子は入手が困難です。極稀に通販やオークションサイトなどで販売されることもありますので、根気よく探してみるのもいいかもしれません。
ツピダンサスの歴史
ツピダンサスの原産地はインド、マレー半島などの熱帯アジア地域になります。「ツピダンサス・カリプトラツス(Tupidanthus calyptratus)」という名前をつけられていたことから、一般的にツピダンサスと呼ばれるようになりました。
しかし、最近では「シェフレラ・プエクレリ(Schefflera pueckleri)」という名前で流通していることが多いです。また、葉の形が傘に似ていることからアンブレラツリーと呼ばれることもあります。そもそもの生息地が高温多湿地域ですので、
大きな葉を広げて強い日差しや風から人や家を守ってくれます。最近では葉に黄色い斑の入る『ゴールデンキング』 という名前の美品種も出まわるようになってきましたが、繁殖が難しくなるため、その分希少価値は高めです。
ツピダンサスの特徴
何と言っても大きな葉が特徴的です。光沢のある深い緑の葉はとても魅力的で、存在感があります。葉は若干厚めでしっかりしています。シェフレラによく似た植物ですが、シェフレラより樹高は高くなります。性質上、曲がりやすいとう特徴があります。
前述の通り、白や黄色の斑の入る品種もありますが、若干生育は難しくなります。常緑性で葉が落ちにくいので、室内インテリアとして人気が高く、一般的な園芸店やホームセンターなどでも手軽に手に入れることが出来ます。
トロピカルな面と、まるで盆栽のような渋さを兼ね備えた植物ですので、どんなインテリアにもマッチしてくれるのも人気の理由の一つです。手入れも比較的簡単で初心者の方にもお勧めの植物です。しかし、そもそもが熱帯に生息する植物ですから、寒さには弱めです。
5度以下になってしまう冬場には注意が必要ですので、夏〜秋まで屋外で育てている場合、冬場には室内に取り込んであげましょう。半日陰でも十分に生育できますので、部屋のコーナーなどの若干暗めになってしまう所に置いても大丈夫です。
また、カイガラムシがつきやすいという弱点もあります。春先にはアブラムシがついてしまうこともありますので、もし害虫が出てしまった場合は早めに駆除してあげる必要があります。剪定をしてあげると、脇から新芽が出てきます。
他の観葉植物と比較すると、バランスを整えやすく、自由度も上がります。ただし伸びすぎると、樹形が乱れてしまったり傾いてしまったりしてしまうので、あまり大きくしたくない場合には定期的に剪定してあげましょう。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アフェランドラ・スクアロサ‘ダニアの育て方
タイトル:アカリファの育て方
タイトル:シェフレラ・アルボリコラの育て方
-

-
エニシダの育て方
エニシダはギリシャ語のクローヴァーや詰草といった意味の言葉に由来していると言われています。ヒトツバエニシダ属 が、和名の...
-

-
トマトの栽培における種まきや植え付けの時期及び育て方について
トマトは世界一の需要量を誇る野菜で、日本でも比較的良く食されています。気候的にも栽培に適する事から、家庭菜園レベルであっ...
-

-
タイタンビカスの育て方
タイタンビカスの特徴といえばやはり色の鮮やかさと力強さでしょう。先程も述べましたが日本で開発されたまったく新しい品種です...
-

-
ヘビウリの育て方
インド原産のウリ科の多年草で、別名を「セイロン瓜」といいます。日本には明治末期、中国大陸を経由して渡来しました。国内では...
-

-
インドゴムノキ(Ficus elastica)の育て方
日本でも一部の温暖な地域では戸外で育ちますが、寒冷地では鉢植えで育てます。ミニサイズの鉢から大型のものまで、様々な趣のあ...
-

-
ハバネロの育て方
ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられ...
-

-
タチツボスミレの育て方
タチツボスミレに代表されるスミレの歴史は大変古く、日本でも最古の歌集万葉集にスミレが詠まれて登場するというほど、日本人に...
-

-
植物の育て方の楽しみについて
家の中で育てる植物には、いわゆる観葉と菜園の2種類があります。いずれについても多様な種類が存在しますが、ある程度成長した...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
エビネの育て方
エビネは古くから日本に自生するランの仲間です。北海道、東北から本州、四国、九州と幅広く自生しているため日本人にも古くから...



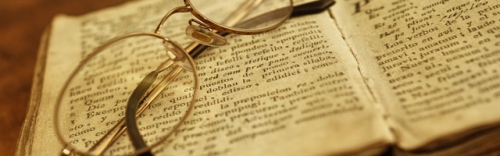





ツピダンサスの原産地はインド、マレー半島などの熱帯アジア地域になります。「ツピダンサス・カリプトラツス(Tupidanthus calyptratus)」という名前をつけられていたことから、一般的にツピダンサスと呼ばれるようになりました。しかし、最近では「シェフレラ・プエクレリ(Schefflera pueckleri)」という名前で流通していることが多いです。