ゼフィランサスの育て方

ゼフィランサスの育てる環境について
特徴でも書いたように多くの種類があり、品種にもよりますが、一般的に半耐寒性のものと耐寒性のものとに分かれます。半耐寒性のもは場合によっては霜などにやられてしまい屋外では冬を越せないこともありますが、耐寒性のものならば霜にあたっても枯れないので冬を越すこともでき、
そのままでよいの面倒が少ないものとなります。半耐寒性のものは、屋外の場合は霜よけをするか、もしくは室内に取り込むのが良いようです。原産地からも推測される通り、日当たりの良い場所が特に好適です。乾燥地域のイメージがありますが、別名であるレインリリーの名からも、
どちらかといえば少しだけ湿った場所を好むようです。ただし日当たりに関しては若干は適応性があり、明るい日陰などでも花は咲くことが多いようですが、それでも、日当たりの良いところよりは花の数が増えないようで、暗い日陰となると、ほとんど花が咲かないままに消えていくと事例をよく耳にします。
育てる土壌としては水はけの良い肥沃な土壌を好み、プランターでも育ちますが、庭や花壇での植えつけが向いているようです。多年草なのでそのままにしておいても再度シーズンになれば花を楽しめることが多いです。
繁殖力も強く、また病気や虫の害についても強く、丈夫でもあるため、非常に育てやすい園芸植物と言えるでしょう。さらに、春に植えればその年のうちに花が見られるので、その点でも初心者向きと言えるかもしれません。
種付けや水やり、肥料について
まずは育てる環境でもあったように、特に日当たりに気を付けて植えつけ場所を選びます。鉢植えでも十分に育ち、そういった鉢植え、プランターなどにしておけば場所の移動も簡単ですので、季節によって場所を調整するのも有効でしょう。
育て方、特にみずやりとしては鉢植えの場合は他の植物の基本的な水やりと同様で、土の表面が乾いたらたっぷりと水をやることが肝心です。庭や花壇などの地植えの場合は基本的には自然に降る雨による水やりだけで十分で放置しておいても良いですが、
乾燥後に球根が適度に湿っていると花が一気に多く咲きますので、夏場に雨の降らない日が続くようであれば水を遣るのが花を咲かせるコツとなります。メリハリのある乾燥と湿潤の繰り返しが好きな植物で、特に成長時期である夏場にたくさんの日光と、たっぷりの雨を受けると、秋口に咲く花の花付きが非常によくなります。
肥料については、最初に植えつける際に土に化成肥料をたっぷり混ぜておきましょう。その後については生育を見ながら成長に応じて、生育期間中に1回から2回ほど追肥を与えるようにしましょう。土は赤玉土と腐葉土をおおよそ7対3で混ぜたものを使用すると好適です。
注意点はたくさんあり、花を多く、長く咲かせるためには以上のような点に気を付けることが必要ですが、虫による害も受けにくく、病気にもなりにくい丈夫な品種ですので、特に地植えの場合は比較的放置しておいても環境が合えば十分に花を楽しむことができるようです。
増やし方や害虫について
庭や花壇、その他畑など地植えの場合も、鉢やプランターなどの場合も、基本的に毎年植え替えをする必要は全くありません。どちらかと言えば植えっぱなしのほうが根を強く張り、よく育つようです。特にプランターなどの鉢植えは十分根を張ってくれたほうが花付きもよくなります。
ただし、何年か経過し、球根が増えすぎて極端な過密状態に陥ると、今度は花の数が減ってきます。鉢植えの場合はおおよそ2年から3年、地植えの場合はおおよそ4年から5年を目安に、球根の間隔を広げる意味で植え替えを行います。適しているのは春先、3月から4月の間となります。
株分けと同様に植えつけも3月から4月に行います。この際は、深さ10㎝、球根同士の間隔は10㎝から15㎝ほどを目安にするようにします。一方でこれ以上開けてしまうと咲いたときの見栄えが若干劣りますので注意してください。ここまでで書きましたが、基本的には球根が自然に増えていきますので、
意識せずとも増えていきます。さらに、花が終わると種ができますのでそれを収穫し、蒔くことで増やすこともできます。植え替えの際に他の場所を確保すればどんどん増えていくことでしょう。病害虫には強いと言われており、病気や害虫の心配はほとんどと言っていいほどありません。
多年草でもあり、増やしやすくもあることから、非常に育てやすい、初心者向きの品種と言えます。また、一つ一つの花の咲く期間は数日と短いですが、時期になると次から次へと開花するため、長く花も楽しめます。
ゼフィランサスの歴史
ゼフィランサスについては、ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物のことをまとめてそう名づけられています。名前の由来はギリシャ神話からで、西風の神、ゼピュロスから付けられていると言われており、これに花を意味するアンサス(anthos)を付けて、
ゼフィランサスと付けられたということですが、はっきりした由来は分かっていません。名づけられた際に、ヨーロッパ世界から見て西側、アメリカ大陸中米や西インド諸島などに自生していたことから付けられたという話も残っています。
日本へは江戸時代の終わりから明治時代に観賞用園芸種として渡来してきており、それから現代までに野生化し、現在はいたるところで見られています。日本ではサフランもどきとも呼ばれます。これは、渡来してきたころはサフランと呼ばれていたものが、
実際にサフランが入ってきた際に紛らわしいからということでこのような名前になったようです。他にもタマスダレとも呼ばれます。これは、細長い線のような葉が直立して並ぶ姿をすだれに見立てて名づけられました。花は実際にサフランに似ているところもありますが、
種としては別物になります。花としては不本意な命名になるかもしれません。もともとは名前の由来でも書いたように原産はメキシコなど中央アメリカ、西インド諸島などを中心に、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸にまで広がっていた花で、35から40種ほどがあるとも言われています。
ゼフィランサスの特徴
ゼフィランサスはその中が細かい種に分かれており、数十種もありますが、耐寒性、もしくは半耐寒性となっています。花はほとんどの種類で6月から9月の、初夏から秋の始めにかけて咲いていきます。花の色は白色、桃色、黄色などが主だった色ですが、
種どうしの交配が比較的に容易なことから、さまざまな色を掛けあわせ、受け継がれた多種多様な色合いのものが存在しています。また、雨が降った後に一斉に開花することが多いことで知られており、その特徴からレインリリーとも呼ばれています。
近いものとしてハブランサスとはよく似ており、混同されることも多いのですが、ハブランサスはななめあるいは横に向いて咲くのに対して、ゼフィランサスの花は真上を向いて咲いていきます。ヒガンバナ科は同じ特徴を持つ植物が多いのですが、全ての部位にリコリンという成分を含み有毒となります。
葉をニラなど、鱗茎をノビルなどと間違えて食し、中毒を起こす例がかなりの数報告されています。リコリンは吐き気を催す作用があり、多量に摂取すると死亡する例もある毒ですので、致死量はそれほど少量ではなく、水溶性で水に流れて消えるとは言え、取扱いには注意すべき植物です。
野生種ともなっていて生息地は本州、四国、九州、沖縄などにまで広がっているように丈夫な種で、日本でも園芸植物として広く栽培され、その色の多彩さ、雨上がりに一斉に咲くその神秘的な風情で多くの人々から支持されています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シラーの育て方
タイトル:カマッシアの育て方
タイトル:アキザキスノーフレークの育て方
タイトル:タンジーの育て方
タイトル:タチツボスミレの育て方
-

-
アボカドの育て方
アボカドは7000年以上前から栽培されているという言い伝えがあります。アボカドは南アメリカ北部からメキシコ高地が原産で、...
-

-
チューリップ(アラジン)の育て方
チューリップにおいては日本に来たのは江戸時代とされています。その時にはほとんど普及することはなかったようですが大正時代に...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
春の風物詩 チューリップの育て方について
桜の花に次いで春の風物詩となる植物がチューリップです。独特のふっくらとした形が特に女性に人気があります。卒業式や入学式な...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
インドゴムノキ(Ficus elastica)の育て方
日本でも一部の温暖な地域では戸外で育ちますが、寒冷地では鉢植えで育てます。ミニサイズの鉢から大型のものまで、様々な趣のあ...
-

-
大きなサツマイモを育て上げる
サツマイモは特別な病害虫もなく農園での育て方としては手が掛からないし、家族でいもほりとして楽しむことできる作物です。
-

-
アネモネの育て方
地中海沿岸が原産地のアネモネは、ギリシャ神話ではアドニスという美少年が流した血から生まれた花という説もあり、古くからヨー...
-

-
ゼフィランサスの育て方
ゼフィランサスについては、ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物のことをまとめてそう名づけられてい...
-

-
ボリジの育て方
この花については、シソ目、ムラサキ科、ルリジサ科に属するとされています。一年草なので1年で枯れてしまいます。高さとしては...




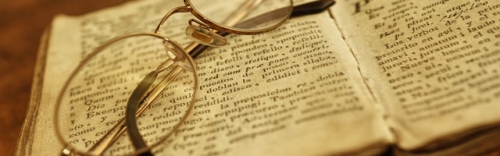





ゼフィランサスについては、ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物のことをまとめてそう名づけられています。