トウヒの仲間の育て方

育てる環境について
トウヒが良く育つ環境は、生息地原産地に見られるように比較的気温が低く、日光を浴びやすい高山地域が適していることが分かります。よって、熱帯地域や温暖湿潤気候の地域での栽培は、不向きであると言えます。日本は四季という気候に恵まれ、
四方を海に囲まれている島であり北海道から本州の東北地方まで寒冷時期が長い地域があるということが、トウヒを育てる環境に最も適していると言えます。自然に繁殖している原生林では、育った木の種が口落ちた木を苗床にして育つという、樹木自身がバランスをとりながら繰り返して、
本来のサイクルを保って来ました。近年ではトウヒの育成力が強いとはいえ、無謀な樹木伐採や山林開拓により食物に困った鹿などが稚樹を食べてしまうなど、深刻な問題となっている一面もあります。庭や私有地でトウヒを育てたい場合、
環境が適していると放って置いてもトウヒは育てやすい樹木と言えます。しかし、トウヒは種類によって巨木となりますので充分なスペースが無いことと手入れが出来ない場合は、観賞用樹木としては向かないとも言えます。充分なスペースのある庭先や私有地で育てたい場合は、
定期的に小まめな剪定を行い高さを保つなどの工夫を行うと良いでしょう。寒冷の原生林に増え育つ力を持ちある程度の気温変化や環境に対しては強さのあるトウヒですが、酸性雨、排気ガスなど人為的な公害に弱い面があります。逆に言えば、トウヒが良く育つ環境であれば、空気がきれいで公害の要素が無い場所と言えます。
種付けや水やり、肥料について
トウヒはかなり大型となる樹木です。地植えを行う場合と、鉢から植え替える場合は予め充分なスペースと間隔を保って植えつけて行くこととなります。トウヒの育て方は、鉢植えからでも始められます。成長が始まればさほど難しくはありませんが暑さに対する弱点はあります。
冬仕度の早い寒冷地では、トウヒの種まきは5月頃に行います。通常の種まきに適しているのは9月~10月下旬に蒔き終えることが理想です。土表面が乾いたら充分な水やりを行います。2年ほど様子を見ながらそのような水やりを繰り返します。
2年ほどしたら庭などの地植えに切り替えます。植え替え時期については、鉢を使わずに元々地植えをしていたなら植え変える必要はありません。地植え後は基本、水やりは行わずに成長を見守りますが、夏の暑さには弱い傾向がありますので極度に日当たりがある場合は、
日陰に鉢を移動することと気温が暑い時間帯を避けて水やりを行います。また、鉢植えにある時に、光化学スモッグなどの注意報が出た場合は、軒下や玄関先など直接公害に触れないような環境に移動する配慮を試みると良いです。元肥となる肥料は土に混ぜますが、
固形の物を少量使用します。追肥としての与え方は鉢植えの場合、化成肥料を春に与えます。地植えの場合は冬場に有機肥料を根元を取り巻くように入れます。鉢の場合に気をつけたいことは、肥料を与えすぎると成長が早くなりすぎるか、根腐れを起こす原因にもなるので与える量にも注意が必要です。
増やし方や害虫について
トウヒの増やし方は、接木でも挿し木でも行えます。時期は、2月~3月が適していると言えます。接木は、樹木の根元からではなく、枝で取り分けて別の樹木を台として繋ぎ、同種を増やしていくことです。時として、台となる木の種が異なっていた場合に花が咲く樹木などでは、
咲き分けといって1つの木から色違いの花が見られることがそれです。根がなくても、元々根のある樹から養分をもらいつなぎ目が融合することによって、新たに樹木の本数を増やして行けます。1本のトウヒが成長すれば、2本目3本目と接木の方法を用いる事によって、
個々に根を張らせる必要がなくなります。接木行うには台となる木の準備が必要となるため、行うことを想定して最初の種付け時から何らかの準備をしておくと時期が来た時にすぐに取り掛かることができます。トウヒを世話をして行く上で気を付けたいことに害虫の問題が出て来ます。
トウヒに付く害虫には、樹皮から穴を開けてもぐりこみ樹液を養分として成長する害虫がいます。トウヒの樹皮を観察した時に、3mm程度の直径の穴と木屑が粉末状についていたら中にキクイムシと呼ばれる害虫がいる可能性があります。
キクイムシには大きく2つに分類され、さらにその中で多くの種類があり、世界中に分布しています。キクイムシの中でもマツ科の樹木を好んで寄生する種があります。トウヒの樹の害虫には、キクイムシの他、蜂の仲間やハマキ虫などがあり、
葉を養分とする害虫では蛾がいます。それらは、幼虫の養分確保のため卵を産み付けていきます。トウヒを育てている山林などでは、これらの害虫が発生する時期には大掛かりな農薬散布を行って駆除していることも見られます。
トウヒの仲間の歴史
トウヒはマツ科に属する樹木であり、漢字で表すと唐檜と書き表されます。漢字の由来から日本には、飛鳥時代~平安時代現在の中国である唐王朝時代に、遣唐使によって持ち込まれました。日本に最初に持ち込まれた元の種に関しては定かではありません、
エゾマツが変化してトウヒとなったとされています。現在トウヒの仲間は、同種で30種以上が確認されています。トウヒの中で、ヤツガタケトウヒは絶滅危惧種として指定され、長野県と山梨県にまたがる山に生息が確認されています。トウヒの海外での生息地は、
北半球に多く見られ北東アジアやドイツにも生息し、日本では、北海道から福島県まで分布しています。日本で主に見られる種には、アカマツ、ハリモミなどがトウヒの仲間です。オウシュウトウヒまたはドイツトウヒと呼ばれるものは、
長さのある木材となるため古代より船の一部であるマストに木材として使われたことから、ギリシャ神話の海の神に捧げられたとされています。中世ヨーロッパ時代の後期から、原野や山を覆っていた広葉樹林に足される形で寒さに強く生育が早い種であるトウヒの植林が、
ドイツの一部地域の人々によって行われました。その後トウヒは繁殖力が強いため、人の手を介さずとも自然とアルプス地方に渡り、山々を埋め尽くすように広がって行きました。それらのことから現在までヨーロッパが原産であるオウシュウトウヒは、アルプスの山岳地帯やスカンジナビア半島、シベリアにかけて広く分布しています。
トウヒの仲間の特徴
トウヒの仲間は同科の針葉樹であるマツの葉の形状にみられる尖った葉を持つことが特徴です。トウヒは日当たりが悪く多湿な地域では、良く育たちません。寒い地域である場所の方が、トウヒの生育環境に適していると言えます。北米には世界最大級の巨木となるシトカトウヒが存在し、
高さは95メートルにも及びます。クリスマスツリーとして用いられるモミノキも同科であり、特にトウヒとは樹木の形状も葉の付き方も類似しています。但し、葉の形状を見比べると扁平なものが見られますが、ドイツトウヒはひし形になります。モミノキの葉はやや幅広いのに対して、
トウヒの葉の幅は細長い形状であり、マツの葉ほどの鋭さはありません。トウヒの仲間には、マツの木が持つ松ぼっくりのような実がなります。マツの場合は、松ぼっくりが枝の上を向いて着きますが、トウヒの場合は、下に垂れ下がるような形で付き、
比較的細長い形状であり鱗のような麟辺の状態は細かいことが特徴です。また、種子は落ちても麟辺は落ちずに残るということがマツ科の松ぼっくりとの違いです。トウヒの多くの用途は、建築材料として使用されています。そのほとんどが、北米や北欧からの輸入により供給されています。
日本ならではの用途の1つで、トウヒの部分の質により襖のはりや障子枠にも用いられます。個々の目的に適した産地別のトウヒで良質な物は、弦楽器や高級家具としても使用されています。中でも将棋盤、碁盤に於いては高額で取引される事が有名です。その他の使用例としては、樹液や新芽が薬用として用いられることがあります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:トサミズキの育て方
-

-
ランタナの育て方
一つの花の中にとても多くの色を持つランタナは、とても人気の高い植物で多くの家の庭先で見かける可愛らしい花です。ランタナ(...
-

-
ヘスペランサの育て方
ヘスペランサは白い花を持つ美しい植物でり、日本だけに留まらず多くの愛好家がいます。花の歴史も深く、大航海時代にまで遡る事...
-

-
ガマズミの育て方
ガマズミはその名前の由来がはっきりとわかっていません。一説によるとガマズミのスミは染の転訛ではないかというものがあり、古...
-

-
ダーウィニアの育て方
ダーウィニアの特徴を挙げていきます。まずは、植物の分類ですが、ダーウィニアはダーウィニア属のフトモモ科に属します。このダ...
-

-
ソテツの育て方
この植物に関してはソテツ目の植物になります。裸子植物の種類に当たり、常緑低木になります。日本においてはこの種類に関しては...
-

-
ベンジャミンゴムノキの育て方
この植物はイラクサ目、クワ科、イチジク属となっています。イチジクの仲間の植物になります。それほど高くに低い木で、高さとし...
-

-
ヘチマの育て方
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実...
-

-
シクノチェスの育て方
シクノチェスはラン科の植物で独特の花を咲かせることから世界中で人気となっている品種で、15000種以上の品種があるとされ...
-

-
ミズアオイの育て方
かつてはこのように水辺に育っている植物を水菜ということで盛んに食べていたそうで、万葉集の歌では、春日野に、煙立つ見ゆ、娘...
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...




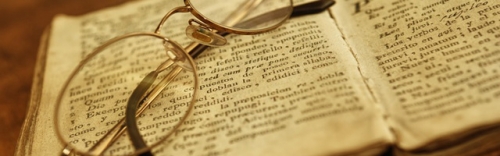





トウヒはマツ科に属する樹木であり、漢字で表すと唐檜と書き表されます。漢字の由来から日本には、飛鳥時代~平安時代現在の中国である唐王朝時代に、遣唐使によって持ち込まれました。