ハスの育て方

ハスの育てる環境について
ハスは生息地がインドやアジア圏ということもあり、日光をとても好む植物です。日光が不足すると花が咲かないことがありますので、一日を通してよく日の当たるところに置くことが育て方のコツです。冬でも水面が凍る程度の寒さには耐えます。
水生植物ですので、穴の開いていない鉢やカメなどに水と土を入れて育てていきます。最近ではビオトープの人気にともなって色々なサイズの睡蓮鉢などが販売されていますので、それらを利用するとよいでしょう。品種によっては、小さな器でも育てられるものもあります。
水底に敷くのは粘土質の高い用土を使うようにします。田畑の用土をふるいに掛けて、とろとろになるまでよく混ぜたものを使用します。田畑の土が手に入らない場合は、水生植物用の用土を使用したり、赤玉土と腐葉土を8:2ほどの割合で混ぜたものを使うとよいでしょう。
いずれにしても元肥が重要になってきますので、苦土石灰や有機石灰などもあらかじめ混ぜ込んでおきます。用土から水面までは少なくとも5〜10センチの高さになるようにしましょう。夏場は水が蒸発しやすくなりますので、一定の水量を保つように気をつけるようにしましょう。
また、この時期は水の中にボウフラが発生することがあります。ボウフラ対策として、水中にメダカや金魚などを一緒に入れてあげるとそれらがボウフラを餌にして駆除してくれます。その際には鉢に入れる水はカルキを抜いたものをしようし、酸欠防止に水草などを用意しておきましょう。
ハスの種付けや水やり、肥料について
ハスを種から育てる場合、適期は4月から9月頃です。種の殻は非常に固いので、あらかじめ種の丸い方の表皮を下の白い部分が見えるまでヤスリ等で削っておく必要があります。その後、水の中に浸して発芽させます。コップなどの小さめの容器で大丈夫です。水は濁りやすいのでマメに交換しましょう。
水温は25度ほどあれば大丈夫でしょう。1〜2週間ほど経てば芽が出てきます。芽が4〜5センチほどになったら種の殻ごと土に埋めて育てていきましょう。その際、芽が水面から出ないように気をつけます。種から育てる場合、1年目で開花させることは難しいと言われています。
根気よく大事に育てて、翌年美しい花が咲くのを楽しみにしましょう。ハスを育てるコツとして、元肥として用土の中に肥料を入れておくことが重要です。最初に植えつける際に、しっかりと土づくりをして、肥沃な状態にしておきましょう。
4月〜9月ごろは一月に一度くらいの割合で追肥をしてあげます。チッソ・リン酸・カリウムを1:1:1ほど与えるか、緩効性の化成肥料を与えても大丈夫です。花が散って、葉が枯れ始めてきたら肥料を与えるのは控えるようにしましょう。
水の管理も重要なポイントとなってきます。常に容器に水が張っている状態を保つようにしましょう。特に夏場は日差しが強いので蒸発には要注意です。毎朝水をあげ、水をかき混ぜてあげることによってボウフラなどの害虫予防にもなりますし、酸素補給にもなります。
ハスの増やし方や害虫について
ハスは種まきと株分けによって増やすことが出来ます。種から育てるのはなかなか難しく、なおかつその年に花をつけるのは難しいので、レンコンを使用した方がお勧めです。容器で栽培していると、年々株が小さくなって花を付けなくなってしまうので、出来れば毎年株分けをするようにしましょう。
適期は2月〜3月頃になります。新芽を付けた塊茎(種レンコン)を3~4節に切りわけます。その際、しっかり育った大きいものを選ぶようにしましょう。親株と同様、粘土質のサラリとした用土を使用します。土の上に種レンコンを横にして植えつけます。
その上からそっと土をかぶせて、水を張ります。水深は15センチほどが理想的です。日当たりの良い所で水が乾かないように注意しながら管理します。しばらくすると2〜3枚の葉が出てきますので、その時期から追肥をしてあげるようにします。
最初の内は少なめにし、徐々に様子を見ながら与えるようにしましょう。時折、葉や花にアブラムシが発生することがあります。アブラムシが発生すると養分を吸われて株が弱ってしまいますので、発生を確認したら早めにアブラムシ用の殺虫剤で駆除するようにします。
腐敗病や褐斑症といった病気になることがあります。腐敗病にかかると葉だけではなく、せっかくの塊茎まで腐ってしまいますので、発生してしまった部分は早めに取り除きます。病気の予防としては、乾燥に注意することと、枯れた葉を放置しないことが重要です。またボウフラの発生防止に水はこまめに取り替えましょう。
ハスの歴史
ハスはインド亜大陸を原産とするハス科の水生植物です。その歴史は植物の中でも特に古く、1億4000万年前には既に地球上に存在していたとも言われています。水中の土中に塊茎を作りその部分はレンコンとして食されます。インドから中国に渡り、その後日本に渡ってきました。
2000年以上前に既にレンコンは食用とされていたことが分かっています。奈良時代の文献にもレンコンを食べていた記述があります。穴の空いたレンコンは「先を見通す」という意味合いがあり、縁起のいい食べ物としてもよく知られています。
ハスの花は非常に美しく、淡く繊細でありながら荘厳さも兼ね備えています。近年、ビオトープの流行に伴ってハスの花を栽培される方も増えてきました。ビオトープに使用される、いわゆる観賞用のハスは塊茎があまり大きくなりませんので、食用には向きません。
花托部分が蜂の巣に似ていることから「ハチス」と呼ばれ、そこから「ハス」となったと言われています。また、仏教の中では「蓮華」として呼ばれています。ハスは宗教に関わりが古く、ヒンズー教や仏教では象徴的な花として親しまれてきました。
如来像の蓮華座などで目にしたことのある方も少なくないでしょう。またハスの花と聞けば、お釈迦様を連想される方も多いのではないでしょうか。多くの文献に登場し、詩歌や和歌にも詠まれています。「一蓮托生」などの語源にもなっているほどで、実に古くから人々に愛されてきたことがわかります。
ハスの特徴
ハスは水面から立派な茎を伸ばし、その上に悠々とした花を咲かせます。その見た目の美しさは、他の草花を圧倒します。また、丸くて大きな蓮の葉も印象的です。水面を覆い隠す蓮の葉は撥水性があり、コロコロと可愛らしい水滴を作ります。
ハスの葉には泥の中から伸びてきたにもかかわらず汚れがつかず、水滴で虫なども絡めとって自浄するという特徴があります。この効果をロータス効果(ハス効果)といい、科学的な分野に利用されてます。主に塗料や布などの撥水と防汚に活かされています。
甘みの部分を取り出して餡などに加工されることもあります。また、生薬としての効能も認められており、鎮静、滋養強壮の薬としても利用されてます。日本では茎の部分を切りそろえて煮物にしたり、地下茎のレンコンを食べる場合が殆どです。レンコンは歯ごたえがよく、
調理方法も多岐にわたっているので日本でも古くから調理し、食されてきました。栄養価が高い上に食物繊維を豊富に含んでいるので、特に便秘にお悩みの女性や、ダイエット中の方にはお勧めです。よく似ているので同種と思われがちですが、ハスと睡蓮は別物です。系統も全く異なり、睡蓮の地下茎は太りません。
スイレンの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:温帯スイレンの育て方
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
クレマチス ネリー・モーサーの育て方
この花についての特徴としては、まずはキンポウゲ目、キンポウゲ科、キンポウゲ亜科の種類となります。さらにセンニンソウ属に属...
-

-
アベリアの育て方
アベリアはハナゾノツクバネウツギのことで、ラテン語の属名アベリアで呼ばれています。公園などで植え込みとしてよく植えられて...
-

-
ヘメロカリスの育て方
ヘメロカリスの生息地はアジア地域で、原種となっているものは日本にもあります。ニッコウキスゲやノカンゾウ、ヤブカンゾウなど...
-

-
ブルーハイビスカスの育て方
ブルーハイビスカスは別名をアリオギネ・ヒューゲリーやライラック・ハイビスカスといいます。属名はギリシャ語の結合したや分割...
-

-
オリエンタルポピーの育て方
オリエンタルポピーは地中海沿岸からイラン等の西南アジアが原産地のケシ科ケシ属の仲間です。スイスの遺跡から種子が発見されて...
-

-
プチアスターの育て方
キク科カリステフ属のプチアスターというこの花は、中国北部やシベリアを原産国とし1731年頃に世界に渡ったと言われておりま...
-

-
コルチカムの育て方
コルチカムの科名は、イヌサフラン科で属名は、イヌサフラン属(コルチカム属)となります。和名は、イヌサフランでその他の名前...
-

-
ケストルムの育て方
ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとさ...




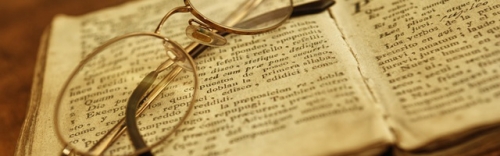





ハスはインド亜大陸を原産とするハス科の水生植物です。その歴史は植物の中でも特に古く、1億4000万年前には既に地球上に存在していたとも言われています。