ピラミッドアジサイ(ハイドランジア・ パニュキュラータ)の育て方
育てる環境について
ピラミッドアジサイは別名ハイドランジア・_パニュキュラータという品種で紫陽花の仲間ですが、ユキノシタ科に分類されることがあります。その育て方で気をつけたいのが育てる環境です。紫陽花の仲間は湿った土地を好む印象がありますが、この品種の栽培には基本的に水はけの良い土地が最適です。土が乾燥しすぎるところは株が弱くなるので避けますが、
日当たりは確保したほうが花付きは良くなります。ただし耐陰性もありますので一日に数時間程度の日照があれば元気に育ちます。午前中のみ日が当たる場所などを選ぶのが良いでしょう。また夏の強い日照には弱く葉焼けを起こしてしまうことがありますので夏場の西日が当たるような場所での栽培は避けるのが無難です。
土の質に関しては北海道から九州の日本全土に自生していることから考えてもあまり選びません。ただし水はけがよく、有機質に富んでいるところのほうが株が丈夫に育ちますので、庭植えをする場合には甘玉土に完熟腐葉土や堆肥を好き込んだものを使って植えつけるのが良いでしょう。もちろん市販の培養土でも良く育ちます。
植え付けに関しては庭植え、鉢植えどちらでも良く育ちます。適期はこの品種が落葉する11月から3月にかけての休眠期です。根鉢の3倍程度の深さ、幅の植え穴を掘って底に有機肥料を入れて直接根に触れないようにして植え付けましょう。鉢植えの場合には用土に緩行性のつぶ状肥料を混ぜておくと良く育ちます。
種付けや水やり、肥料について
ピラミッドアジサイの栽培の水やりは頻繁に行います。特に植え付けから2年以内の若い株は水を必要としますので、土の表面が乾いたらたっぷりと水をやりましょう。水の量が足りないと土の表面にしか湿り気が行かずに根が表面に集まってしまい、しっかり鉢に回らないので弱い株になってしまいます。
庭植えの場合でも植え付けて2年いないはたっぷりと水を与えましょう。2年以上経過した株には水やりの必要はありませんが余りにも乾燥しすぎる時期には水をやりましょう。特に夏の高温期には土がカラカラに乾燥してしまうので、株元に腐葉土や藁を敷くマルチングをすることで乾燥を緩和させることができるでしょう。
特に鉢植えの場合には水切れを起こしやすいので注意が必要です。水切れを起こすと葉がチリチリに乾燥してしまうので表面が乾いたらたっぷりと水やりをし、夏場には朝夕二回の水やりが最適と言えるでしょう。肥料に関してはあまり必要ありませんが植え付けの際に腐葉土や緩行性のつぶ状肥料を与える程度で良いでしょう。
または庭植えの場合には1月に有機肥料を寒肥として株の周辺に埋めておくと良いでしょう。鉢植えの場合には成長を開始する3月に株元に緩行性のつぶ状肥料を追肥しましょう。植え付けの際の用土はこだわる必要はありませんが、水はけの良い土地を好むので、赤玉土と腐葉土を混ぜて水はけを確保するのが良いでしょう。水切れを嫌うので、乾燥させすぎないことに注意すればピラミッドアジサイは育てやすい品種です。
増やし方や害虫について
ピラミッドアジサイは強健な品種なので病気や害虫がつくことはほとんどありません。増やす際には挿し木で行うのが一般的です。3月から4月の生育を始めた時期、または6月下旬から7月上旬の成長した若い茎が充実している梅雨時期に挿し木を行います。春に行う場合には昨年伸びた枝を使い、夏に行う際には今年伸びた若い木を使います。
5センチから10センチの長さに斜めにカットしますが、この際にはハサミではなくよく切れるカッターかナイフを使います。ハサミを使うと組織が潰れてしまうので、カッターでできるだけ組織をつぶさないように切り取りましょう。切り取った木を清潔な用土にさします。用土はバーミキュライトやパーライト、鹿沼土などがよいでしょう。
直射日光を当てずに明るい日陰で管理します。すると発根してきますのでビニールポットの赤玉土などに植え付けるようにしましょう。さし床が乾燥しないように水を切らさないように管理するのがポイントです。また株分けで増やすこともできます。株分けは落葉する11月から3月の休眠期に行います。
寒冷地の場合には寒い時期に株分けをすると根が傷んでしまうので3月から4月に行うのが良いでしょう。また、とり木という方法で増やすこともできます。株の根元に土を盛り、発根後に根を付けた状態で切り離し、別に植え付けます。またピラミッドアジサイは剪定も重要です。開花後の芽吹き前に行うのですが、背が高くなりすぎた枝などを切り戻してコンパクトに管理することができます。
ピラミッドアジサイの歴史
ピラミッドアジサイは別名ハイドランジア・_パニュキュラータというアジサイの仲間ですが、もともと日本原産の植物で、昔から自生していた日本を生息地としていました。アジサイの歴史は古く日本最古の歌集である万葉集に詠われているほど古くから日本人に愛されてきました。
その後の平安時代などの文献には見られないものの、江戸時代に入って医師であり自然科学者でもあるシーボルトが紫陽花を愛し、日本植物誌という書物を書いて日本の紫陽花を世界に伝えました。また、アジサイは1700年代にヨーロッパに渡り、イギリス王立植物園で栽培されるようになるのをきっかけに欧州にも広く親しまれるようになりました。
品種改良も盛んに進められて、色もカラフルなものが作られるようになり、ピンク、青、白、赤などたくさんの園芸品種が生み出されるようになりました。こうした品種改良されたアジサイは現在は西洋アジサイと言われ日本に逆輸入されて愛されています。アジサイの名前の由来は藍色が集まったという意味です。
ピラミッドアジサイはノリウツギの仲間としても分類されますが、ノリウツギはもともと6月に咲くことが多いことから水無月というところから名前がつけられました。このピラミッドアジサイはノリウツギが品種改良されて作られたもので、ノリウツギに比べて華やかな装飾花が人気を集めています。ノリウツギは楚々とした魅力が好まれ、ピラミッドアジサイはごうかなボリュームが好まれています。
ピラミッドアジサイの特徴
ピラミッドアジサイは北海道から九州に自生している落葉する低木に分類されます。日本での歴史も古く元々は樹液を和紙の糊として利用したことからノリウツギという名前になっています。庭木、花木として分類され樹高は2メートルから3メートルにまで成長します。開花期は7月から9月に咲く夏の花です。
色は白いものが多く、耐寒性、対暑性にも優れている育てやすい品種です。初心者でもそだてやすい美しい花木です。花は円錐形の花房を持ち、半円形の一般の紫陽花とは少し趣が違います。通常の紫陽花が梅雨の時期に開花するのに比べ、この品種はさらに遅い梅雨明けに咲くので花が少なくなった夏の庭を彩ってくれる貴重な存在です。
花弁のように見える円錐形を形作っているものは実はシベが退化した装飾花の額に当たり、花弁ではありません。萼によりボリュームのある美しい円錐形の花房が保たれています。アジサイ科で分類されることも多いのですが、ユキノシタ科として分類されることもあるのが特徴です。ほとんどの品種が美しい白い色をしており、
夏の日差しに輝き映える人気の品種です。暖かい地域では白い花が咲き進むとグリーンを帯びてきて、これが寒冷地になるとうっすらとピンク色になりこれも美しく人気を集めています。紫陽花というと湿った土地を好む印象がありますがこの品種は紫陽花よりも日照を好むので日当たりの良い場所が育ちやすいです。栄養に富んだ日当たりの良い場所に植えましょう。
-

-
ブラックベリーの育て方
ブラックベリーの始まりは古代ギリシャ時代までさかのぼることができるほど古いです。このブラックベリーは人々から野生種として...
-

-
イースターカクタスの育て方
ブラジル原産の多肉性植物で、4月初旬の頃のイースター(春分後の最初の満月の後の日曜日)に開花するカクタス(サボテン科)で...
-

-
セイヨウムラサキの育て方
セイヨウムラサキの特徴について書いていきます。日本を本来の生息地とするムラサキと比較してみると、茎に特徴があります。茎が...
-

-
タマネギの育て方
タマネギはユリ科に属する野菜で、100グラムあたりリンが30mg、カリウムは160mg、ビタミンB1が0.04mg、食物...
-

-
ジギタリスの育て方
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではない...
-

-
シロハナノジスミレの育て方
スミレ科スミレ属の多年草ですが日本ではどこでも比較的見られる品種で、本来のスミレよりも鮮やかな色で、素朴なスミレらしさは...
-

-
西洋クモマソウの育て方
原産地はヨーロッパ北部といわれています。漢字で書くと雲間草で、ユキノシタ科の植物です。雲に届きそうな高い山間部に生息する...
-

-
植物の育て方を押さえてオリジナルな庭づくりを楽しみましょう
最近では、様々な所でガーデニングなどの園芸講座が開かれています。自分オリジナルな庭を作ることが出来るため、一つの趣味とし...
-

-
アリアケスミレの育て方
アリアケスミレは日本原産の本州から四国、九州に自生するスミレの仲間ですが、山野草としても扱われて盛んに栽培されています。...
-

-
上手な植物の栽培方法
私たちが普段生活している場所では、意識しないうちに何か殺風景だなとか、ごちゃごちゃ物がちらかっているなとかいう、いわゆる...




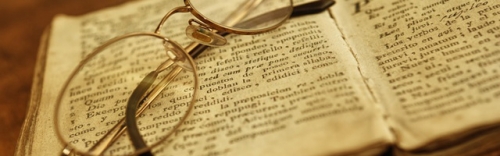





ピラミッドアジサイは別名ハイドランジア・_パニュキュラータというアジサイの仲間ですが、もともと日本原産の植物で、昔から自生していた日本を生息地としていました。ピラミッドアジサイは北海道から九州に自生している落葉する低木に分類されます。日本での歴史も古く元々は樹液を和紙の糊として利用したことからノリウツギという名前になっています。庭木、花木として分類され樹高は2メートルから3メートルにまで成長します。