オミナエシの育て方

オミナエシの育てる環境について
オミナエシを栽培するのに適した場所は日当たりが良い場所ですが、土が乾きすぎると生育に支障が出てくるので強烈な西日が当たるような場所は避けたほうが良いです。特に真夏は直射日光は避け、柔らかい陽射しにあたるようにしたほうがよりきれいな形に育ちます。
日陰は成長しにくいですし、花付きも悪く、場合によっては枯れてしまいますのでなるべく日向のぽかぽかした感じの場所を探してあげるほうが良いでしょう。土は地植えにするのであれば少し湿り気があるような場所が向いています。
鉢植えにするのであれば水はけが良いことが条件になりますので、赤玉土と鹿沼土をそれぞれ4、腐葉土を2の割合で混ぜ合わせたものを使うようにするのが良いです。地植えに一度してしまったものは植え替えはしなくても良いですが、鉢植えの場合は植え替えする必要があります。
根詰まり防止のために毎年行なうほうが良く、やり方は鉢から抜いた株の根の先を3分の1ほどカットしてから新しい土に植え替えます。根をカットしておくと新しい根が出てきて水や肥料をしっかりと吸収することができるようになるのです。植え付けは3月から4月頃が良いですが、
植え替えするのであれば3月頃が適しているでしょう。同属の高山性の品種の植物を一緒に植えることで庭をロックガーデンに仕上げることもできます。草丈を調整してない場合にあまりに草丈が伸びて倒れてくるようであれば、支柱を立てて支えてあげる必要があります。
種付けや水やり、肥料について
水は地植えの場合は一度根付いてしまえば特に与える必要はなく、雨水だけでも十分です。しかし夏はどうしても土が乾きやすいですから株元を敷きワラなどで覆って地下茎や根を守ってあげるのが良いでしょう。鉢植えの場合は土の表面が乾いた時にたっぷりと与えるようにします。
肥料は植える時に遅効性の化成肥料を土に混ぜ込んでおくといいですし、開花後の10月から11月頃には骨粉入りの固形の油粕などを追肥として与えておくのが良いです。肥料を与える時のコツはあまり与えすぎないようにすることです。
あまり多く与えてしまうと枝や葉ばかりが茂って不恰好な見ためになってしまうことがあるのでそこはバランスを考えて与えるのが良いです。そして種付けに関してはたくさん増やしたい場合にオススメです。開花後にはそこに種が入った房ができますので、これが熟す頃まで待って種を採取するようにしたらいいです。
しかしこぼれ種などで増えていくことも考えられるので、必要ない分は花茎ごとカットしておくといいです。株が大きくなっているようであれば、種まきだけではなく株分けをして増やしていくのも良いです。株分けする時には子株のあまり小さいものをとらないようにしておきます。
株分けをするのであれば11月頃もしくは3月頃に行なうのが良いでしょう。種まきしたものは発芽率も良いので順調にいけばその年には咲かせることができます。株分けは大きな株でも2分割ほどにしておくのがベストです。
増やし方や害虫について
種で増やしていく場合は開花後にできる果実が茶色く熟すまで待ち、茎ごと刈り取ってしばらく乾燥させておきます。それから果実から種だけを取り出して封筒などに入れ、冷蔵庫で種まきの時期まで保管しておきます。種まきは3月から4月上旬頃が良いでしょう。
種まきする時には平鉢やビニールポットを利用して土を入れておき、そこに種をまきます。発芽するまでは乾燥しないように管理します。発芽してからはあまりに込み合っている場所は間引きして、ある程度の大きさになっているようであれば鉢や花壇に植え替えするようにしましょう。
株分けするのであればあまり小分けにしないように気をつけ、手ではなかなかちぎることは難しいので園芸用のハサミなどを使うと良いです。害虫は特にはありませんが、病気は白いカビが原因で植物の葉の表面などが粉をふいて白くなってしまう、
うどんこ病や葉の裏側にオレンジ色の小さなつぶつぶや赤褐色の斑点ができ、 葉が枯れてしまう立ち枯れ病が出ることがありますので注意しましょう。うどんこ病にかかるのは稀で、どちらかというと立ち枯れ病のほうがかかることが多いです。
もし、うどんこ病にかかってしまったとしても重症化することはあまりありません。特に水はけの悪い場所に置いていると立ち枯れしやすくなってしまいます。もし症状が出てしまった場合は感染したものを除去し、植えている土を盛って水はけが良くなるようにしたり、水はけの良い用土を使うようにしたりするのが良いです。
オミナエシの歴史
オミナエシは多年草で無病息災を願って食べる秋の七草の一つです。原産や生息地は日本を始めとした東アジア一帯です。草丈は20cmから1mほどで育てやすいので初心者の方にも向いています。オミナエシは古い時代から詩や歌、絵画などにも登場しており、園芸品種もいくつかあります。
学名はパトリニア・スカビオシフォリアといい、このパトリニアというのはフランスの植物学者E. L. M. Patrinが由来となっています。漢字では女郎花と書きますが、これは遊郭の女郎ではなく、オミナエシの花が昔の女性がよく食べていた粟飯に似ていることから女飯と呼ばれ、
それが時代と共にオミナエシに変わっていったといわれています。また別の説では女植の略だという説やおみなは女を表し、へしはなるべしという意味を表していて、花の姿が女性を連想させるからとする説、女性の美しさより勝るということでおみな圧し、
おみな減しでヲミナエシになったという説もあります。別名には花が粟に似ていることからアワバナやアワゴメバナというのがあります。またオミナエシの根の部分を煎じたものは敗醤と呼ばれており、利尿作用、解熱作用、解毒作用があるとされており、
今でも漢方のようにして利用されることがあります。よく似た花にはオトコエシというのがあります。こちらは白い花を咲かせます。オトコエシとつけられたのはオミナエシよりも丈夫で、女性的というよりは男性的だからだということです。
オミナエシの特徴
オミナエシは庭植えだけではなく、鉢植えや切花として利用されることも多い多年草です。8月から10月頃にかけて毎年黄色い花を咲かせます。花の形は小花がまとまって咲き、まるで円錐のような形をとります。葉は根元から出て細長い楕円形をしており、
茎につく葉は根元の葉とは少し違い、切れ込みが深く入っていて羽のような形をしています。この深い切り込みがないものは変種になり、ハマオミナエシと呼ばれます。地下茎を横に伸ばしていく習性があるので、鉢植えの場合は少し注意が必要です。
この地下茎が地上に出てしまう場合があり、そうなるとそこが乾燥して株が枯れてしまうことがあるからです。また春になると地下茎部分から子株が出てくるのですが、ここに最初に生える葉は親株の株元に出てくる葉とは違いますし、間違えて雑草のように抜いてしまわないようにしましょう。
草丈はなるべく抑えるようにしたほうが花付きが良いですし、強い風が吹いた時にも倒れにくくなります。ある程度の高さにまで育ったら、芽の先のほうを摘むことでワキから新しい芽を出させておくと良いです。切花にする場合は水がにおいやすいので、できるだけこまめに水をかえてあげるほうが良いです。
開花後も花自体は色を保っているので、とても長い期間楽しむことができます。花房全体の大きさは15cmから20cmほどになります。耐寒性も耐暑性もありますので、育て方はそれほど手間はかからず、比較的簡単に育てられます。
-

-
グズマニアの育て方
パイナップル科グズマニア属の観葉植物です。常緑性で、熱帯アメリカが原産です。背丈は25〜50cmほどで、横幅は35〜60...
-

-
ミルトニオプシスの育て方
花の種類としては、ラン科、ミルトニオプシス属になります。園芸の分類としてはランになり、多年草として楽しむことが出来る花に...
-

-
マムシグサの育て方
マムシグサは、サトイモ科テンナンショウ属です。サトイモ科に属するので、毒性はあるものの、用途としては、毒を取り除いて食用...
-

-
ハナニラの育て方
ハナニラは別名セイヨウアマナやアイフェイオンといいます。原産地はアルゼンチンで、生息地は南米メキシコからアルゼンチンの辺...
-

-
サンショウ(実)の育て方
学術的な系統では、ミカン科サンショウ属ということで、柑橘類に所属しているということも面白いですが、香料関係の植物は、この...
-

-
ミントの育て方
ミントは3500年ほど前の古代ギリシャですでに生薬として利用されていました。歴史上でも最も古い栽培植物として知られていま...
-

-
トウモロコシ(スイートコーン)の育て方
トウモロコシは夏になるとお店の店先に登場する夏を代表する野菜です。蒸かして食べたり、焼きトウモロコシで食べたり、つぶだけ...
-

-
プルンバゴの育て方
プルンバゴは、イソマツ科、ルリマツリ属(プルンバゴ属)となります。また、和名は、ルリマツリなどと呼ばれています。プルンバ...
-

-
フロックスの育て方
フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の植物の総称で、現時点で67種類が確認されています。この植物はシベリアを生息地と...
-

-
ヤマユリの育て方
ヤマユリは、ユリ科、ユリ属になります。和名は、ヤマユリ(山百合)、その他の名前は、エイザンユリ、ヨシノユリ、ハコネユリ、...




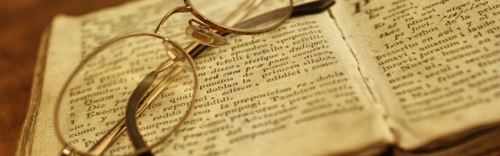





オミナエシは多年草で無病息災を願って食べる秋の七草の一つです。原産や生息地は日本を始めとした東アジア一帯です。草丈は20cmから1mほどで育てやすいので初心者の方にも向いています。オミナエシは古い時代から詩や歌、絵画などにも登場しており、園芸品種もいくつかあります。