スネールフラワーの育て方

育てる環境について
スネールフラワーは日光がよく当たる場所を好むので日当たりが良い場所で育てるのがポイントです。冬は室内に取り込むことで越冬させることができます。種などを採取するか挿し木で増やすつもりであれば外で地植えをして花付きの良さを楽しむのもありです。
霜の心配がなくなった頃にまた外に出して日光に当ててあげるようにするのが良いです。土は水はけの良いものが向いています。鉢植えにする場合は小粒の赤玉土を7に腐葉土を3で混ぜ合わせたものか花の培養土に小粒の赤玉土を2割程度混ぜたものを使うと良いです。
赤玉土を混ぜることで水はけが断然良くなるからです。しかしもし鉢植えを6号以上の大きさのものを使うのであれば、土は小粒の赤玉土だけではなく、中粒のものも同じ量だけ混ぜ込んでから使うようにします。植え付けは4月から5月までの間に行います。
植え替えも同じ時期にしますが、1年か2年に1度は植え替えるようにしないと根詰まりを起こしてしまうことがあるので注意が必要です。苗を購入したい場合は園芸店で春に売られていることがありますので、見つけたらすぐに植えつけるようにしましょう。
鉢植えに植える場合は支柱を立ててあげるとツル性なのでそこに絡まって大きく成長していきます。庭に地植えするのであればネット以外にもフェンスを利用してツルを絡ませるように誘引していくと見た目にもきれいに見えますし、ツル同士が絡まないので花もきれいに咲きます。
種付けや水やり、肥料について
水やりは春から秋頃にかけては生育期なので土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにします。特に真夏は土が乾燥しやすいので水切れしないように気をつけましょう。冬は逆に休眠期になりますので水は控えめにしておきます。肥料は植え付けをする時に元肥を与えておきます。
元肥は緩効性の肥料を土に混ぜ込んでおくのが良いです。元肥を入れていれば追肥の必要は特にはありませんが、もし元肥を入れないようであれば生育期である春から秋にかけて緩効性の化成肥料や液体肥料を与えるようにします。
肥料はチッ素とリン酸、カリの三つの割合が同じもしくはリン酸が少し多めに含まれているような肥料を適量、置き肥するようにします。庭に元肥を施す場合は牛糞などを混ぜ込んでおくのが良いです。肥料は与えれば与えるほど元気に育つというわけではありません。
与え過ぎによって逆に生育を悪くして枯らしてしまうこともありますので、肥料は適量与えるようにするのが良いです。種付けに関しては花が咲き終わった後でそのまま花茎を放置しておくことで果実がなります。細長いマメのような果実で、中には俵形の濃い茶色の種が入っています。
種付けは自然に受粉していればいつの間にかなっていることが多いですが、もし自然受粉が難しいようであれば、大きな花びらを後ろ側にめくってみると自然と管から雄しべと雌しべが出てくるので人工的に擦りつけるなどして受粉させてあげると実がなることが多いです。
増やし方や害虫について
育て方では害虫は特にカイガラムシに注意をしましょう。カイガラムシは幼虫の間であれば薬剤も効きやすいですが、成虫になってしまうとその名の通りカイガラのようなものに覆われてしまいますので薬剤の効果はほとんど期待できません。
そのため、退治するのであれば幼虫の間にしてしまうのがベストです。もし成虫になってしまっているのを見つけたら古い歯ブラシなどを使ってこすり落としてしまうのが一番良いです。葉茎が混み合ってしまうとカイガラムシが発生しやすいので、
あまりに茂っているようであれば風通しを良くしてあげるためにも余分な葉茎はカットしてしまいます。病気は過湿にしてしまうと灰色かび病になってしまいがちなので、水の与え過ぎには気をつけます。増やし方は一番簡単なのは挿し木です。
4月から9月頃までの間に剪定した枝などを利用して5cmから7cmほどの長さの茎をバーミキュライトや小粒の赤玉土に挿しておきます。古い土ではなく新しい土に挿しておくことが大事です。種まきは暖かい土地であれば採取してすぐにまいてしまっても大丈夫ですが、そうでなければ翌年の春に種まきをするまで保管しておくようにします。
封筒などに入れて冷蔵庫に入れておくのが良いです。種まきで発芽させるには温度なども重要なポイントとなりますが、初心者の方であまり自信がないという場合は種まきと共に挿し木もしておくことで増やしていくことは可能になります。挿し木は土ではなく、ビンに水を入れて挿しておいても発根します。
スネールフラワーの歴史
スネールフラワーの原産地や生息地は中央アメリカから南アメリカの熱帯地域です。ベネズエラであるというのがよく言われていることです。マメ科ササゲ属で、別名はヴィグナ・カラカラやファセオルス・カラカラ、クライミンゴ・エスカルゴで、英名はスネール・バインです。
このスネールフラワーという名前のスネールというのは蕾がスネールつまりカタツムリの形に似ていることから名付けられたといわれています。また属名であるヴィグナは17世紀のイタリア人植物学者であるドミニコ・ヴィーニャ氏の名前が由来となっています。
カラカラというのは原産地であるベネズエラのカラカスのという意味があります。現在はまだスネールフラワーの苗はそれほど安価ではありませんが、国内で栽培されている場合の多くは今流行りのグリーンカーテンとしての役割をさせるためでもあります。
スネールフラワーはカタツムリという名前がついてはいますが、非常に成長するのが早く、グリーンカーテンとして植えておくとあっという間に大きくなって立派なカーテンになってくれます。しかし成長が早い分だけ植える場所は考えておかなければ大変なことになってしまいます。
暖かい国が原産なだけに耐暑性はあり、夏でも元気に育ちますが、逆に耐寒性はあまりなく、冬場は外で育てるのは暖かい地方以外では外で越冬させるのは難しいです。しかし0度あれば越冬は可能なので、昔から室内で冬の間は育てられてきました。
スネールフラワーの特徴
スネールフラワーは常緑性の多年草で、つる性なので5mから6mほどまで伸びます。花は直径が4cmから5cmほどあり、1つの房に3輪から5輪ほどがまとまって開花します。生育はとても旺盛ですからグリーンカーテンとして利用されることもしばしばあり、ここ数年で人気が出てきています。
ネットに絡ませる以外では8号から10号ほどの鉢で大型のあんどん仕立てにしても良いでしょう。暖かい地域であれば外で植えてあっても敷きワラなどをすることで越冬させることが可能となります。室内で越冬させることを考えれば鉢であんどん仕立てにしておくほうが移動もさせやすいので便利です。
開花時期は6月から10月頃で、花色は薄紫色をしています。1つの花は3日から4日ほど咲き続けてくれるので長く花を楽しむことができます。花をどのくらい咲かせたいかによっても地植えにするか鉢植えにするかを決めるポイントになります。
鉢植えで植えるよりも地植えのほうが花はたくさん付きます。しかし越冬させるには難しいので、そういう場合は多年草というよりは1年草として考えておきましょう。冬になる前に鉢植えとして室内に取り込む予定でいるのであれば、
ある程度剪定をしておく必要があります。剪定をするのは草丈の3分の1から2分の1ほどまでの長さにまで切り戻してしまってから移動させるのがオススメです。こうすることで場所をとることもありませんし、翌年もまた花を咲かせます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:センダイハギの育て方
タイトル:西洋オダマキの育て方
-

-
ベッセラ・エレガンスの育て方
この花については、ユリ科のベッセラ属に属します。花としては球根植物になります。メキシコが生息地になっていますから、暑さに...
-

-
トリトニアの育て方
トリトニアはアヤメ科トリトニア属の多年草になり、南アフリカ原産の植物です。トリトニアには40種から50種ほどのさまざまな...
-

-
キツリフネの育て方
特徴として、被子植物、双子葉植物綱、フウロソウ目、ツリフネソウ科、ツリフネソウ属になっています。属性までツリフネソウと同...
-

-
クウシンサイの育て方
クウシンサイは中華料理やタイ料理などで使われる野菜で、主に炒め物やおひたし・天ぷらなどの料理として食べられています。その...
-

-
アメリカテマリシモツケの育て方
アメリカテマリシモツケは、北アメリカが原産だと考えられており、現在テマリシモツケ属の生息地はアジア東部や北アメリカ、メキ...
-

-
ガジュマルの育て方
原産地からもわかるように亜熱帯地方を生息地とする、クワ科の常緑高木です。沖縄ではガジュマルを「幸福をもたらす精霊が宿って...
-

-
アッツザクラの育て方
アッツザクラはアッツという名前はつきますが、アッツ島にあるものではなく、原産や生息地は南アフリカです。ではなぜアッツザク...
-

-
ゼラニウムについての説明と育て方
フウロウソウ科であるゼラニウムは、南アフリカに自生する温帯性の宿根草であり、欧米ではベランダや窓辺の花として最も多く目に...
-

-
ギンヨウアカシアの育て方
ギンヨウアカシアの原産地はオーストラリアで、南半球の熱帯や亜熱帯を主な生息地としています。ハナアカシア、ミモザ、ミモザア...
-

-
ポテンティラ・メガランタの育て方
ポテンティラ・メガランタは別名をハナイチゴや西洋キンバイといいます。葉がイチゴのものに似ていて愛らしい黄色の花を咲かせま...




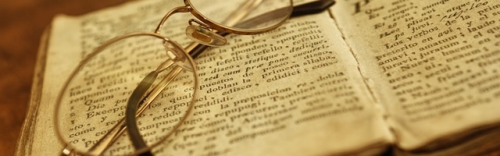





スネールフラワーの原産地や生息地は中央アメリカから南アメリカの熱帯地域です。ベネズエラであるというのがよく言われていることです。マメ科ササゲ属で、別名はヴィグナ・カラカラやファセオルス・カラカラ、クライミンゴ・エスカルゴで、英名はスネール・バインです。