プテリスの育て方

プテリスの育てる環境について
プテリスの育て方は、明るい日陰で育てると良いでしょう。屋外でも室内でも可能ですが、直射日光が当たらないようにすることがポイントです。直射日光は、葉っぱをいためてしまう可能性が高まるからです。レースのカーテン越しの日光は可能です。
最低温度は3度以上で育てましょう。シダ科の中では比較的丈夫なため、初めて観葉植物を育てるという方にもおすすめです。バスルームや、キッチンなどに置くのも良いでしょう。直射日光は強過ぎますが、あまり暗い部屋で育て続けてしまうと、
葉っぱの色が変わりやすくなりますので、気をつけましょう。丈夫で鮮やかな色の葉っぱに育てたい場合には、明るい日陰がベストです。プテリスは、成長にしたがって、葉っぱが密生しやすくなる特徴があります。密生した場合は、葉っぱが重なっていき、株元が枯れやすくなります。
また、葉っぱが重なり合ったところから枯れてしまいますので、適度に隙間があくようにカットしましょう。室内で育てるのが難しいという場合には、土が凍らないように冬場は鉢のまわりを覆うなどの工夫をすれば乗り越えられる可能性は高まります。
低温や冷たい風から守ることができます。冬場は水やりを控えて乾かし気味に管理をしましょう。初めてプテリスを育てたいという場合には、プテリスの中でも、アルボリネアータがおすすめです。耐陰性と、耐寒性があるのが特徴的です。ですが、土と葉っぱの乾燥には気をつけましょう。
種付けや水やり、肥料について
水やりについては、土の表面が乾いてきたらたっぷりあげることが大切です。夏場などは土がよく乾くため、毎日水をあげると良いでしょう。水切れや、湿度が不足すると、葉っぱの先が縮れてきてしまいます。そのため、葉っぱには霧吹きで水分を与えてあげ、湿度を保つことも大切です。
冬場は、土が乾いてから2日、3日してから与え、葉っぱに霧吹きで湿度をあげる程度にします。室内に置いていると、エアコンなどで葉っぱが乾燥しやすくなりますので、注意しましょう。植え替え時期は、鉢の底から根っこがでてきて、根詰まりになったら行ないます。
根鉢の3分の1ほどを崩してから、植え替えると良いでしょう。鉢は一回り大きなものを選びましょう。一年から二年に一度行なう目安です。植え替えの時期は5月から6月がおすすめです。赤玉土を6に対して、腐葉土を4ほどの割合で土をつくりましょう。
肥料については、春から秋頃までを目安に与えます。液体肥料などが良いですが、肥料がなくとも良く育ちます。育成期の春から秋にかけて元気がない状態が見られた場合には、即効性がある液肥をあげるのはおすすめです。葉っぱが乾いてチリチリの状態になってしまうと、
回復は難しいので、水やりには気をつけましょう。チリチリになってしまった葉っぱや、ダメージを受けてしまった茎は切り戻して、たっぷり水を与えてあげると、再生する可能性もあります。全体的にダメージを受けてしまった場合には、地上部を全て切り戻すことが必要です。
増やし方や害虫について
子株が沢山できた場合は、株分けをすることで増やすことも可能です。植え替えの時期に同時に行いましょう。根詰まりなど、水が切れた状態が続くと全体が枯れてしまいますので、株分けをして防ぐことをおすすめします。増やした場合には、寄せ鉢にも向いています。
寄せ鉢を行なう際には、湿度の高い環境を好む性質をもった他の種類のものと一緒に植えることがポイントです。洋ランなど、他の植物に添えて植えることもでき、鉢が落ち着くのでおすすめです。テラリウムにも向いています。ですが、抽水栽培はできませんので注意しましょう。
また、アレンジをする際におすすめなのが、ディッシュガーデンです。ディッシュガーデンは、お皿の上で育てる方法です。和風なアレンジに仕上げることができます。作り方は、お好みのお皿を用意して、根腐れ防止剤を敷きます。そして、観葉植物専用の用土をのせて、プテリスを植え付けていきます。
色がついた砂として人気のカラーサンドなどで表面をかざることもできます。葉っぱに汚れなどが目立つようになってきたら、元から切り取りましょう。害虫はつきにくい性質をもっていますが、春から秋にかけてカイガラムシやハダニがつく可能性もあります。
夏場の高温乾燥期は、ハダニが発生しやすくなるため、薬剤の散布をしましょう。プテリスは、栄養葉と、胞子葉の役割をしている二種類の異なった葉っぱを出しますが、病気ではありません。また、葉っぱの裏に黒い胞子がつきますが、病害虫ではありません。
プテリスの歴史
プテリスはシダの仲間です。イノモトソウ科の常緑多年性シダ類に入ります。世界ではおおよそ300種類が分布しています。観葉植物として昔から人気があり、美しい葉をもっています。熱帯の半耐寒性の種類のものが多く販売されているため、冬場は室内に入れると良いでしょう。
原産地は日本に自生しているオオバノイノモトソウや、アマクサシダ、イトモトソウなど25種類ほどがあります。オオバノイノモトソウは、イノモトソウよりも大きく育つ特徴があり、葉っぱの幅も広くなっています。日本では、関東や北陸以西が原産となっています。
イノモトソウは、石垣などに良く見られるシダです。関東よりも西の本州や、四国、九州、沖縄が原産地となっています。その他、プテリスは世界各国の温帯から熱帯地方が生息地となっています。耐寒性は3度以上を好むため、やや弱い性質をもっているものの、耐暑性は高いのが特徴です。
羽片の主脈に白い色の斑が大きく入っているアルボリネアタや、葉っぱの先端がしし葉で、白色の斑が主脈に大きく入っているものが有名です。また、マツザカシダは、白色の大きな斑が入っているためアルボリネアタにとても良く似ていますが、異なる種類です。
ホコシダ品種のフイリイノモトソウは、特に昔から人気があります。ヨーロッパで作出し、日本には、明治後期に渡来しました。その特徴は、羽片に、白い色の斑が大きく入っており、美しい品種として知られています。
プテリスの特徴
プテリスは、多年草で、草の丈は5センチから50センチほどとなっています。羽状の葉っぱが3枚あるクレティカの園芸種が流通量が多く、一般的となっています。斑入りの葉っぱや、緑葉などがあります。株元から長い葉茎を立ち上げて、株立ち状に成長するのが特徴的です。
やわらかい印象をもった葉っぱと、細い茎が特徴で、室内の空間をおだやかな雰囲気にしてくれると人気があります。和風のインテリアや、洋風のインテリア、どちらにもマッチし、アレンジを行なうことを楽しむこともできます。ミニ観葉植物や小鉢などが育てやすいでしょう。
大きく育てすぎた場合には、葉っぱが蒸れたり、根っこが腐りやすくなりますので気をつけましょう。また、プテリスは株元に葉っぱが多くでる特徴があります。クレティカアルポリネアタは、プテリスの代表的な品種で、ミニ観葉植物としても人気があります。
葉っぱに銀白色の斑があります。クレティカクリスタタは、葉っぱが細いのが特徴的で、先端が丸くなります。少し縮れたような状態になるのも特徴です。また、ファウレイと呼ばれているものは、中国が原産となっており、繊細で小型な姿です。
人気の品種のうちのひとつとなっています。日本では、伊豆諸島や紀伊半島、九州の原産のものもあります。ミニ観葉植物として購入し、大きく育った場合は葉っぱの印象が大きく異なるため、変化を楽しむこともできます。和名はハチジョウシダと呼ばれています。
-

-
イワチドリの育て方
イワチドリは、ラン科ヒナラン属の球根の多年草です。本州では中部地方より西の範囲に生息地としており、さらに四国地方にも自生...
-

-
リナリアの育て方
リナリアの名前の由来は生物学者だったリンネが提唱していた一つ一つの生物につけられた名前で、ギリシャ語でアマという意味があ...
-

-
ガマの育て方
多年草で、水中の泥に地中茎を伸ばし成長します。ガマの穂と呼ばれる円柱型の穂をつけます、冬には枯れて根茎のみになります。ガ...
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
コダチアロエの育て方
アロエの種類は約300種類にものぼり、大変種類が多い植物になります。日本で良く見られるアロエは”コダチアロエ”と呼ばれ、...
-

-
ミヤマオダマキの育て方
ミヤマオダマキはキンポウゲ科のオダマキ属になります。ミヤマオダマキの特徴としては、葉はハート形になっていても、その丸美帯...
-

-
ヘリオプシスの育て方
特徴としてはこの花は1年草になります。キクイモモドキの名前の元になっているキクイモに関しては多年草ですから、その面では異...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
コウリンカの育て方
コウリンカはキク科の山野草で、50センチくらいに成長し、7月から9月頃には、開花時期を迎えます。2007年に環境省のレッ...
-

-
デンドロビウム(キンギアナム系)の育て方
デンドロビウムは、ラン科セッコク属の学名カナ読みでセッコク属に分類される植物の総称のことを言います。デンドロビウムは、原...




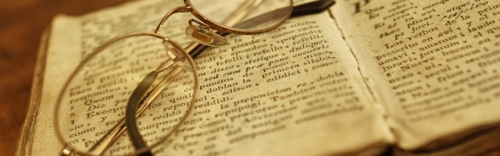





プテリスはシダの仲間です。イノモトソウ科の常緑多年性シダ類に入ります。世界ではおおよそ300種類が分布しています。観葉植物として昔から人気があり、美しい葉をもっています。