コウリンカの育て方

育てる環境について
コウリンカは、絶滅危惧種に指定されているくらいなので、栽培は容易ではありません。花そのものは、風通しが良く、日当たり、水はけのよい居場所を好むとありますが、庭先で生育しているのはあまり見かけません。大きな声でコウリンカ育てているよという方は、ほぼいないので自身で試行錯誤するしかないでしょう。
挑戦したい方は、キク科の育て方を真似てみるのも手です。しかし分布からわかるように北は福島県というようにあまりにも寒い地方では発見数がほぼないので、多年草とはいえ温度管理には注意が必要ですが実際ははっきりとはしていません。発見した場所が冬にどれくらいの気温まで下がるのかという情報も必要になってきます。
長野では割と見かけるのでもしかしたら寒さに強いのかもしれません。そして、山中に生息するとはいえ草原のようなところやススキ畑で見かけることが多いのが特徴です。湿地を嫌う傾向があるので、庭先に植えるならかならず水はけのよいところをお勧めします。プランターにすると、日当たりのよいところに移動できるのでよいかもしれませんね。
菊もやはり、日当たりが良く水はけがいい環境が適しています。自身が採取してきた環境を再現する、つまり、そこの土を持ち帰りプランターに植えて管理するのが良いのかもしれませんが、環境によくないのでお勧めはできません。栽培方法が確立されていないのも個体数の減少につながっています。自然のまま、咲く時期になったらそこに出向いて観賞するのが、花にとっても自然とっても一番良いことです。
種付けや水やり、肥料について
あまり、栽培方法が確立していない植物なので育てるのはとても試行錯誤の繰り返しになるでしょう。キクは肥料切れは禁物ですが、山野草はそもそも、落ち葉や動物のフンなどが肥料になります。その年によって落ち葉の数も違うし動物の数も違いがあります。その環境の土をこまめに入れ替えてあげるのが肥料の代わりになるでしょう。
そして水やりは、湿地を嫌うので、水はけのよい環境にしてあげること。つまり、根腐れを防がなくてはなりません。植物の管理の基本として水やりは土が乾いたら上げることです。採取してからすぐに水を上げてしまうと根腐れの危険が増してしまいます。まずは、湿った状態の土に植えて、乾いたらたっぷり鉢底からあふれるくらいにあげてみて下さい。
どんな植物も、枯れそうになったときに水を上げると必死で吸い上げます。コウリンカもそこはキクと同じ育て方で、次回の水やりも同じで、土が乾いてからにしましょう。ちょこちょこ上げるのは植物の根に大きな負担をかけてしまいます。そして、根腐れをおこしついには枯れてしまいます。
そうならないように、基本は水の上げ方が重要です。湿地を嫌う植物には水の上げ方をきちんと行ってください。そもそも、きちんとした栽培方法の確立がされていない植物なので細心の注意を払い育てなくてはいけません。さらに個体数の減少に手を貸すようなことの無いように個々の特徴に合わせた環境、肥料、温度に気を配りましょう。
増やし方や害虫について
キクの繁殖は、主に挿し木・株分け・根挿しです。菊の場合だと1~2年で株分けをしますが、もともと山野草なので庭に植えた場合は、自然のままでいいのかもしれません。しかし、鉢やプランターで栽培がうまくいって、根が混んできたようならやはり、キクと同じように、株分け等の作業が必要になるでしょう。
もともと、多年草なので株分け、根挿しで増やせるのではないでしょうか。害虫に関しては、記載されている文献が少ないので正直わかりません。ついてしまった虫を調べて一つずつ退治してくことが得策です。ちなみに、キクの場合は、白さび病・黒さび病・褐さび病、黒斑病・褐斑病、立枯症、べと病、灰色かび病、アブラムシ類の付着、
アザミウマ(スリップス)類、ハダニ類、ハモグリバエ、キクスイカミキリ、チョウ目害虫、紋々病など、上げるときりがないほどにあります。これらすべてにかかるとは限りませんが、環境が変わって株が弱るとかかりやすくなりますので、それぞれの症状が現れたらそれに見合った対処を速やかに行いましょう。梅雨時期は特に、湿気のせいでかび病にかかりやすくなります。
プランターや、鉢に植えているなら雨を避けてあげてください。庭に植え付ける場合は、絶対に水はけのよいところに植えましょう。珍品種を育てているということを忘れずに、しっかりと管理していきましょう。そうすることで、減少を防げるのなら良いことではありませんか。が、ただ、きれいだからとむやみに採取することの無いようにしてほしいです。
コウリンカの歴史
コウリンカはキク科の山野草で、50センチくらいに成長し、7月から9月頃には、開花時期を迎えます。2007年に環境省のレッドリストに載っているれっきとした絶滅危惧種です。原産は、日本です。生息地については、本州といわれていますが、九州でも存在するといった情報もあります。あまり、情報の多い植物ではありません。
よく撮影されているものは、長野の山中が多いですね。オレンジというか、レンガ色というか、緑の中にいるとすごく映える色合いで、細長い花びらがとてもきれいです。植物を絶滅させてしまう大きな要因は、開発による自然破壊、大気汚染などです。また、心無い方の園芸目的の乱獲です。
緑に映えるオレンジは、登山客の心を取り込んでしまうほどの美しさです。採取してはダメとわかっていてもつい、手が伸びてしまいます。レッドデータブックの調査によると、絶滅危惧植物にランクされた種は、これらが大半の原因だということが明らかになりました。開発行為は、人間の生活区域が野山を削ってしまうほどの大規模なものになってしまっているということが多く、
昔からそこに存在していた植物、ここでいうコウリンカという植物はまさにそれが主な原因で、絶滅危惧種に指定されてしまいました。さらに採取することでその数はどんどんと減って行き、加速してしまいました。人間の身勝手な行動で、とても美しい花を、結局は失うことになってしまわないようにしましょう。
コウリンカの特徴
日本が原産のコウリンカ、本州中部に個体数は多いです。東は福島から,西は広島県まで広く分布しています。九州には変種のタカネコウリンギクや,高山帯にはよく似た別種のタカネコウリンカが生育しているそうです。とても特徴がある花で、濃いオレンジ色の花を初夏に咲かせます。
その花びらは、とても細く咲きはじめは枯れていると思わせることもありますが、その後とても美しく開花します。草丈は50センチくらいで風通しが良く日当たりのよい場所を好みます。花の盛りには、舌状花がだんだんと下を向き徐々に枯れていきます。すっと伸びた一つの茎につく花は3個から6個ぐらいです。多い時には10個ぐらいのこともあります。
葉には鋸歯があり、下から上に向かってだんだんと小さくなっていきます。多年草ということですが、多くはなぞがおおい山野草です。しかし、その花は一目みるとその鮮やかな色合いに誰しも目を奪われてしまうほどです。キク科の植物の中で似ているといえば、マーガレットみたいな感じです。花びらはマーガレッドよりも細く花びらと花びらの間がもう少し感覚が開いているものを想像するとよいかもしれません。
そして、濃いオレンジ色、場所によっては黄色っぽいものもあるそうですがたぶん土の酸性度によるものだと考えられます。キク科のキオン属にあたるコウリンカの毒性はあまり知られていませんが、キオン属の中には、一部、アルカロイドを含むものもあり、家畜が食べて中毒を起こすことがあるので、万が一口に含んでしまったら速やかに吐き出し病院へ行きましょう。
-

-
カラミンサ・ネペタの育て方
カラミンサ・ネペタはレッサー・キャットミント、レッサー・カラミントなどとも呼ばれる南ヨーロッパ原産のシソ科の芳香性多年草...
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...
-

-
バラ(つるバラ)の育て方
バラの種類は、かなりたくさんありますが一般的には世界で約120種類あると言われています。記録によれば、古代ギリシアの時代...
-

-
我が家で行っている家庭菜園のコツを紹介します
我が家では、猫の額ほどの庭ではありますが、自分たちの食べるものは自分たちで出来るだけ作ろうというモットーで家庭菜園を営ん...
-

-
マグノリアの育て方
マグノリアはアジアとアメリカなどが原産で生息地のモクレン属の植物です。中国では玉蘭、白蘭などと呼ばれており、品格のある高...
-

-
ペンステモンの育て方
ペンステモンが文献に初めて登場したのは1748年のことでした。その文献を書いたのはジョン・ミッチェル氏でした。その当時の...
-

-
サンザシの育て方
サンザシの原産地は中国で、主に北半球の温帯を生息地としています。日本や中国に自生している種類の中には、花や実が美しいもの...
-

-
ミント類の育て方
ミントは丈夫で育てやすいのが特徴です。家庭菜園でも人気があり、少しのスペースさえあれば栽培することが出来ます。ミントには...
-

-
イカリソウの育て方
イカリソウは古くから強壮剤の漢方薬として用いられ、秦の時代の始皇帝も用いていたといわれています。日本でも自生し、春を代表...
-

-
タチツボスミレの育て方
タチツボスミレに代表されるスミレの歴史は大変古く、日本でも最古の歌集万葉集にスミレが詠まれて登場するというほど、日本人に...




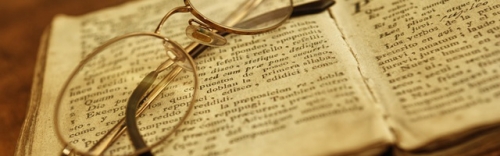




コウリンカはキク科の山野草で、50センチくらいに成長し、7月から9月頃には、開花時期を迎えます。2007年に環境省のレッドリストに載っているれっきとした絶滅危惧種です。原産は、日本です。生息地については、本州といわれていますが、九州でも存在するといった情報もあります。