ミヤマオダマキの育て方

育てる環境について
和名としてはミヤマオダマキで別名深山苧環ともいいます。科名はキンポウゲ科であり、属名はオダマキ属となっています。この花の育て方ですが、基本的には日当たりの良いところで栽培することです。ただ、夏の暑い時である7月から9月上旬までは、30%から40%の遮光も必要となります。
というのも、日焼けをしてしまいますので、葉が黒く変色したりします。遮光をすることで、高温障害を防ぐことになりますので、夏の感想防止と鉢の中の温度をあげないためにも、環境づくりと言うものが大切です。また、土には軽石や鹿沼土の小粒を満たしたものを敷き詰めて置くと、水はけも良く効果的です。
軽石、硬質鹿沼土もしくは日向土に桐生砂もしくは赤玉土といった小粒を等量配合します。その配合は2:4:4の割合で混ぜてください。配合が難しく考えてしまう、または面倒を感じてしまうのであれば、市販の山野草用の土を使いましょう。冬は、北風に当たらないようなところに置いてください。ミヤマオダマキ以外にも、オダマキの種類が欲しいのであれば、
カナダオダマキのアクイレギア・カナデンシスやクロバナオダマキのアクレギア・ヴィリディフローラにフウリンオダマキのアクレギア・エカルカラータ、二色風鈴オダマキがあります。生息地が互いに違うオダマキを育ててみるのも、また一興でしょう。色んなオダマキを見て、花を楽しんでみてはいかがでしょうか。いずれも、育て方は難易度が高くありません。
種付けや水やり、肥料について
ミヤマオダマキの育て方だけでなく、種付けや水やりに肥料についてです。植物はなんでもそうですが、日照時間の照り具合によっては水を十分に与えなければならない物です。特に土が乾く初夏から夏にかけては十分な水やりが必要です。目安としては、表土が乾いたら水を与えること、
そして庭植えの場合は晴れ間が続いて土が乾燥しないかぎりはさほど与えなくても十分です。土が濡れているのに、水をさらに上げれば、根腐れをしてしまいますので注意も必要です。また、肥料についてですが、植え替えの際には元肥としてリン酸とカリウムを多めにして、緩効性化成肥料を3号鉢ならば二つまみくらいを施します。
3月から9月くらいまでは、週に一度くらいに液体肥料を2000倍くらいに薄めて差します。真夏は3000倍くらいで良いでしょう。庭に植える場合はしなくても良いくらいです。植え付けや植え替えですが、毎年一年置きくらいにします。やる頃は、芽が出る2月や3月上旬位に合わせて行いましょう。
植え替える際には、根の太いごぼうのような主根を傷つけないようにしてください。種付けの場合は6月から7月に採取し、冷蔵庫で保存して良く年の2月か3月ごろに種まきをします。巻けば、発芽がとても良いので間隔を空けて種付けをしてください。また、間隔がないとするのであれば、芽吹いた際に植え替えをしてあげましょう。順調にいけば成長して、二年目に花が咲きます。ここが、オダマキのとの違いです。
増やし方や害虫について
この花を増やすには、種まきや株分けにと言った物があります。種から増やすのであれば、6月から7月に採取したものを保管し、そして良く年の2月から3月のはじめの頃に種をまいていきましょう。また、株分けをして増やすならば、植え替えと同時に行ってください。古くなった根茎を自然に分かれたところの部分から分けていきます。
繋がってる場合は、それぞれの芽に根があるので、切って分けてください。ただし、切り口には癒合剤や殺菌剤を塗っておきましょう。そうすることで、保護ができます。この種類の花は、オダマキ同士で交雑しやすい種類とも言えます。交雑種を作らないためにも、複数の親株との間隔を開けて植えることが大事です。
交雑種を楽しみたいのであれば、別に構いません。そして気を付けたいのが、病気と害虫でしょう。病気は軟腐病にうどんこ病です。軟腐病は、茎の根元が腐ってしまい、枯れてしまうことがあるので気を付けましょう。栽培場所では、風通しの良い所、そして水はけの良い用土を使うことが、予防となります。
そして害虫はヨトウムシ、ハダニ、アブラムシです。ヨトウムシは、春と秋を中心に出てきます。時期になったら毎夜見回って殺虫するしかありません。また、発生している初期段階で葉ごと摘み取ってください。ガーデニング用に販売されているオダマキとミヤマオダマキは、同じオダマキ属に属していても、多少の育て方が違ってきます。その点を気にしながら、楽しく育ててください。
ミヤマオダマキの歴史
初夏を感じる頃、各家庭の庭には色とりどりのオダマキが咲き誇っています。ちょっと変わったお花をつけるオダマキは日本原産の花でもあります。その日本原産のオダマキを、ミヤマオダマキといいます。日本原産のオダマキですが、大まかに分けると、もう一種類の物があります。
それが西洋オダマキと呼ばれる物です。基準変種のオダマキは、ミヤマオダマキに似ていますが、大きいので原種であるオダマキと区別ができます。そして西洋オダマキですが、こちらの歴史は古く明治時代に入ってきた物です。ぱっと見た目は同じように見えますが、良くみると西洋オダマキの方が尖がった感じがします。
綺麗に咲きますが、どちらかというと、国産原産のオダマキの方が丸美か買ったかたちで優しい感を抱きます。日本減殺のもので、在来のものでもう一種あるのがヤマオダマキがあります。こちらは、黄色一色を探せるもので、距という部分である花の後ろにある袋状のものが真っすぐに伸びています。これの変種がオオヤマオダマキというものがあり、
こちらは距が内側に曲がっています。この他にも、ダイセンオダマキというものがあり、これはオダマキとヤマオダマキの交雑種としてできた花です。オダマキは、原産地としては日本だけでなくサハリンや千島南部に朝鮮北部、そして日本の中部地方以北とされています。いずれにしても、原産国が日本のものであれ、西洋のものであれ、古くからあるお花と言えましょう。
ミヤマオダマキの特徴
ミヤマオダマキの特徴としては、葉はハート形になっていても、その丸美帯びているところがギザギザといった面白い葉っぱをしています。また、白粉をお簿多葉は、3つに分かれているのも特徴です。お花も変わっていて、下向きに咲いていることと、花茎を伸ばして花をいくつもの花を咲かせます。
独特な花の形は、直径三センチほどで、可愛らしくも感じます。そんなミヤマオダマキの根っこは、とても太く、ゴボウのような主根があります。家庭で育てられているオダマキと良く似ていますが、普通のオダマキよりは小さく見えがちです。ただ、育てるにも高山植物と同じ手入れをしなければならないのが、このミヤマオダマキの特徴でしょう。
ミヤマオダマキは、多年草で草丈も10センチから20センチほどです。オダマキに比べると多少草丈が低い感があります。さらに、開花期となのが4月から5月です。ガ-デニングで育てられている色とりどりのオダマキは、開花期は大体が5月から6月です。それを思うと、日本原産種であるミヤマオダマキの方が開花が早く咲くようです。
花の色も、オダマキのように多様な色があるのとは違い、紫とピンクに白といったシンプルな色です。栽培としても、普通のオダマキよりは多少難しいと言えますが、それでも育てやすいのが特徴です。見て楽しむのであれば、盆栽として咲かすのもまた趣向としては良いでしょう。さらに耐寒性が強いというのも、扱いやすいです。
-

-
オステオスペルマムの育て方
オステオスペルマムは南アフリカを生息地としているキク科の草花です。従来は「ディモルホセカ」の仲間に入っていたのですが、形...
-

-
ヘンリーヅタの育て方
特徴として、まずブドウ科、ツタ属であることです。つまりはぶどうの仲間で実もぶどうに似たものをつけます。しかし残念ながら食...
-

-
オミナエシの育て方
オミナエシは多年草で無病息災を願って食べる秋の七草の一つです。原産や生息地は日本を始めとした東アジア一帯です。草丈は20...
-

-
ブルーキャッツアイの育て方
ブラジル原産の多年草である”ブルーキャッツアイ”。日本では観賞植物として栽培されています。別名はオタカンサスと呼ばれる花...
-

-
デージーの育て方
ヨーロッパおよび地中海原産の草花です。自生の生息地であるヨーロッパでは野草として、ごく自然に芝生に生えています。デージー...
-

-
ダンギクの育て方
中国や朝鮮半島、台湾、日本が原産地となるダンギクは、30センチから80センチほどになる山野草です。日本では九州や対馬地方...
-

-
チューリップの育て方
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから...
-

-
キンシウリの育て方
キンシウリは19世紀末期に中国、朝鮮半島から日本に伝わった覚糸ウリ(かくしうり)が訛って、呼び名がついたと言われています...
-

-
ナズナの育て方
植物分類としては、アブラナ科のナズナ属となります。高さは20から40センチで、花の時期は2月から6月にかけて。ロゼッタ状...
-

-
ショウガの育て方
現在では日本人の食生活にすっかりと定着しているショウガですが、実は原産地は熱帯性の動植物の生息地である熱帯アジア(インド...




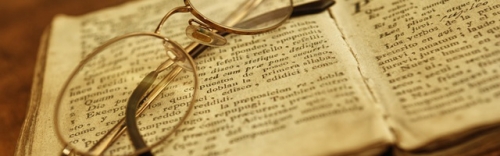





ミヤマオダマキはキンポウゲ科のオダマキ属になります。ミヤマオダマキの特徴としては、葉はハート形になっていても、その丸美帯びているところがギザギザといった面白い葉っぱをしています。また、白粉をお簿多葉は、3つに分かれているのも特徴です。