クリ(栗)の育て方

クリ(栗)の育てる環境について
クリは他の多くの植物と同様に日当たり良好な環境を好みます。庭に植える場合には日当たりのよい場所を選択する様にするとよいでしょう。そうでない場合に比べて成長がしっかりとしますので安心して育てることが出来ます。鉢植えで育てる場合には移動させることが可能です。
だから、それほど心配する必要はないと言えますが、置き場所に関しては日当たりを意識するようにしましょう。それ以外についてはそれほど意識しなければならないことはありません。元々日本の風土には適応している品種であり、特別な配慮をしなくてもよく育つという特徴を持っています。
しかしながら寄り多くのクリの実を手に入れたいと考えているのであれば何かしらの対策を取っておくことも重要です。例えば剪定などはそのために必要な作業の人っとして重要です。剪定のタイミングは落葉後の12月から2月ごろが最適です。剪定をしなくても結実はするのですが、
大きくなりすぎてしまうためにコンパクトに収めたいのであれば重要であると言えます。しかしながら剪定をする場合にはよく注意して行わないと花が咲く花芽を摘み取ってしまうことになるので注意が必要です。
花が咲くのは柿と同じく先年の枝の先端に花芽が生じるというものです。花芽は混合花芽であり、そこから新しい枝も伸びて行くという仕組みになっています。そのため切り過ぎてしまうと成長の可能性を摘み取ってしまうことにもなりますので注意が必要であると言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
クリの植え付けや植え替えについては12月から2月にかけての冬の時期が最適な機関であると考えられています。鉢植えで育てている場合には注意しないと根詰まりを発生させてしまいますので鉢の大きさや成長の具合にもよりますが2年に一回は大きなものへ変えていくことが必要になると言えるでしょう。
水やりに関しては庭に植える場合には特に必要はないと言えるでしょう。他の多くの果樹と同じく、鉢植えでなければ自然環境の中から何とかして水分を探し出すようになります。余程長い期間日照り続きで水が無いという状況を除けばそのままにしておいても特に問題はないでしょう。
しかしながら鉢植えでの栽培をしているのであれば水分は与えない限り手に入らないことも珍しくありません。過度な乾燥は一気に枯死につながりますので表面が白く渇くような状態になったらたっぷりの水を与えるようにすることが推奨されます。
肥料に関しては庭に植える場合には2月と10月に、鉢植えの場合には2月、5月、10月に有機質の肥料か即効性化成肥料のいずれかを撒くと良いでしょう。この肥料は与えなくても枯れることはありませんが、より多くの高品質な結実を望むのであれば、
行っておいた方が良いものであると言えます。この様な対処をすることで数多くの実を付ける可能性を高めます。なお、自家受精できないという特徴がありますので肥料とは別に受粉についての対策を取っておくことも結実のためには重要であると言えます。
増やし方や害虫について
クリの木の増やし方はつぎ木が有効です。4月上旬から下旬にかけて休眠木つぎ、8月中旬から下旬の芽つぎで増やすことが可能です。この様な方法で育てていく育て方が有効に作用します。一方で気をつけなければならない病気としては胴枯病があります。
この病気は枝や幹が枯れてしまうという種類のものであり、対策に関してはある程度はっきりとしています。それ以外に特に問題となる病気もありませんので安心して育てることが出来ると言えるでしょう。それよりも心配しなくてはならないのは害虫に関してです。
人間が好んで食用にする栗の実は害虫にとっても非常に望ましい餌となります。主な害虫としてはクリミガ、シギゾウムシ、カイガラムシ、アブラムシ、カミキリムシなどが挙げられます。この内クリミガやシギゾウムシは栗の実の中に入り込んで食害を発生させる害虫ですので非常に厄介な存在です。
気が付かずに食べてしまっても問題はないのですが、好んで受け入れることが出来るものではありません。そのため避けるための注意が必要であると言えるでしょう。その他の害虫は果樹の方にダメージを与える虫であるため、過度に発生した場合には、
薬品を使用して駆除をする必要に迫られる場合があります。特に成長過程にある場合には枯れてしまう可能性もあるため、素早い判断が必要になる場合があるのです。なお、食用にする場合はクリ」の実を長時間水につけておくと虫が出てくるためわかるようになっています。
クリ(栗)の歴史
クリの歴史は非常に古いものであり、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡からも数多くの栗が出土しています。そのため有史以前から日本にはクリが自生している生息地であり、日本を原産とする種類のものもあると言えるでしょう。
推定ではありますが5000年はクリを食用としてきた歴史があることになります。平安時代の初期には京都の丹波で栽培がおこなわれてきた記録が残っており、その後徐々に広がってきていると言えます。古事記や日本書紀と言った古文書にもその名前は登場しており、
乾燥させたクリであるかちぐりや、蒸して粉にしたひらぐり等の名前も残されています。この様に歴史に名前を残している丹波のクリは現代においても名産品であり、その名前を轟かせているのです。現在日本では複数の種類のクリが栽培されており、
日本で最も広く栽培されている「筑波」と呼ばれている品種をはじめとして様々な種類が誕生しています。「丹沢」「銀寄」「石鎚」「利平」「国見」「岸根」「伊吹」「ぽろたん」等近年になって開発された品種も存在しており、如何に日本人に愛されている植物であるかがうかがえます。
この様に極めて長い歴史を持っているクリは現在も日本文化に深く組み込まれている存在として、秋の味覚を提供してくれる果樹として楽しまれています。なお、クリは中国等他の国においても栽培されている植物であり、似た見た目を持っている数多くの品種が存在しています。日本においても天津甘栗は有名です。
クリ(栗)の特徴
クリは日本人にはなじみ深い植物であり、秋の味覚として全国的に楽しまれているものでもあります。いわゆる一般家庭に植えられている果樹としては一般的ではありませんが、季節感のある植物として人気が高いものでもあります。実は栽培も比較的容易であり、
限られたスペースでも育てることが可能であるという特徴を持っています。環境さえ許せば住宅の屋上を利用して育てることも不可能ではありません。桃栗三年柿八年と言いますが、実際にクリは植え付けから1~2年程度で収穫することが可能です。根っこには菌根菌が矯正しており、
痩せた土地でも良く育つのが特徴です。放っておけば大きくなる気ではありますが、適切に剪定をすればコンパクトなサイズに育てることも不可能ではありません。結実させる時期も早めにしておくとよいでしょう。愛されている植物であるということもあり、
様々な品種改良がおこなわれており魅力的なものも数多く存在しています。早生から晩生まで様々な特徴を持った品種がありますので好みに合った品種、あるいは環境的に育てやすい品種を選ぶとよいでしょう。なお、結実させるためには複数のクリを揃えておくことが確実です。
自家受精はしませんので風に任せるしかありませんが、近くに異なる果樹があれば可能性は高くなると言えます。あるいはつぎ木によっても同じような効果が得られますが、十分に結実させるための方策は環境に合わせて選ぶことが推奨されます。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:コノテガシワの育て方
タイトル:ゲッケイジュの育て方
タイトル:クルミの育て方
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
ミヤコササの育て方
ミヤコササは、イネ科でササ属の多年草です。北海道の南部から九州までの太平洋側に生息していますから、山地でよく見るササ類で...
-

-
マツバギクの育て方
原産地が南アフリカなどの砂漠地です。日本には明治の初期に暖地で広がりました。マツバギクは葉が松葉のような形をしてサボテン...
-

-
ネムノキの育て方
ネムノキは原産地が広く、日本や朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ、インドなどが代表的なものとなっています。このほかにもイラン...
-

-
デンドロビウム・ファレノプシス(デンファレ)の育て方
デンドロビウム・ファレノプシスとはデンファレとも呼ばれる洋ランの一種です。着生植物の一種で、熱帯地方の木の上が生息地のも...
-

-
ロータスの育て方
「ロータス」は、北半球の温帯、主に地中海付近の島国を原産として約100種類もの品種が存在するマメ科ミヤコグサ科の多年草で...
-

-
デュランタの育て方
クマツヅラ科ハリマツリ族(デュランタ属)の熱帯植物です。形態は低木です。和名には、ハリマツリ、タイワンレンギョウ、などの...
-

-
イポメアの育て方
ヒルガオ科サツマイモ属の植物です。一般的にはサツマイモの名前で知られています。原産地には諸説あり、アフリカ、アジア、メキ...
-

-
ボタンの育て方
牡丹の原産は中国の西北部だと考えられています。この地域では、もともとは観賞用ではなくて、薬として用いられていたそうです。...
-

-
ハギの育て方
ハギの花は、日本人には古くから愛されており、万葉集に最もたくさん読まれている落葉性の低木です。生息地は、温帯、亜熱帯など...




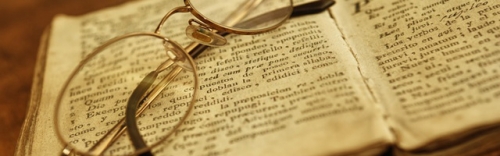





クリの歴史は非常に古いものであり、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡からも数多くの栗が出土しています。そのため有史以前から日本にはクリが自生している生息地であり、日本を原産とする種類のものもあると言えるでしょう。