コノテガシワの育て方

コノテガシワの育てる環境について
耐暑性・耐寒性に優れているため植える場所に関してはそこまで神経質になる必要はありません。ただより大きく生育させたいのであれば、なるべく日当たりのよい場所を選ぶようにした方が良いでしょう。そして日当たりのよい場所で複数のコノテガシワを並べて育てる場合には、なるべく広く間隔を取ることが必要です。
コノテガシワは縦にも横にも大きくなっていきますから、あまりにも間隔を詰めてしまうと成長した後で互いに日の光を妨げあい、環境を悪くしてしまうことがあります。高さ1.5メートルの状態で横幅は1~1.3メートルほどになりますから、間隔を考えて植えるようにしましょう。
土質に関しても特に神経質になる必要はありませんが、よりよく生育させたいのであれば水はけのよい土を選ぶことが必要です。専用の土を用意するのであれば、赤玉土と完熟腐葉土を2:1の割合で混合させた土がベストです。また中にはコノテガシワを鉢に植えたいという人もいますが、
その場合には事前にある程度のサイズを予測しておくことが必要になります。特にコノテガシワは環境さえ良ければどんどん大きくなっていきますから、育つたびに環境を大きく生育できるようにしていくとなると、かなりの手間がかかってきてしまいます。
樹高50センチほどの状態で購入するのであれば直径20センチほどの鉢があれば問題ありませんから、事前に鉢のサイズと、想定する樹高のバランスを考えておくようにしましょう。東北以北などの豪雪地帯であっても、
コノテガシワが枯死するようなことはほとんどありませんが、積雪が激しくなると枝割れが発生して美観を損ねることがありますので、雪が積もってしまった場合にはなるべく早い段階で雪落としをしておくことが必要になります。
種付けや水やり、肥料について
コノテガシワを種で購入して生育させるということはほとんどありません。もちろん種から生育させることが出来ないわけではありませんが、市販されているものの多くはある程度成長した苗の状態で販売されていますから、育成をスタートするのであればまずは苗を植えることが必要になるでしょう。
非常に頑強な性質を有しているために苗の植え付けに関してもある程度自由な時期に行うことができますが、最も適しているのは11~3月の間、もしくは梅雨の時期です。庭植え、鉢植えのどちらであっても土の底に有機質肥料か緩効性化成肥料を元肥として入れておきましょう。
また、先述したとおりコノテガシワは縦にも横にもよく育つ性質を持っていますから、あまり距離を詰めて植えてしまうと後になってから日照量不足などが発生してしまうこともありますから、事前にどこに、どれくらいの間隔で植えるのかと言うことを考えておくことが必要です。
生育後の水やりに関しては土が極度に乾いていない限り特に必要はありませんが、植え付けから2年未満の株の場合は土の表面が乾いた段階でたっぷりの水をあげることが必要です。2年経過するまでは生育しきったコノテガシワほど頑強では無いため、なるべくこまめに状態をチェックして世話をしてやるようにしてください。
次に肥料に関してですが、庭植えの場合は2月ごろに有機質肥料を寒肥として株元の周辺に埋めておけばその他には必要ないでしょう。鉢植えの場合は3月に化成肥料を株元に追肥しておけば問題ありません。基本となるのは日ごろの世話と環境の管理であり、肥料をそこまで必要としないのも特徴の一つなのです。
増やし方や害虫について
2~3月ごろに挿し木をすることで増やすことができます。挿し木をする前年に伸びた枝の先端から10センチほどの穂木をとり、切り口を斜めに切り整えてから2時間ほど水をあげ、鉢に入れた土に差しておけば大まかな作業は完了です。その後は乾燥しないように鉢を透明なビニール袋に入れて密閉し、
直射日光の当たらない明るい場所で管理するようにしてください。次に病気や害虫についてですが、まず病気に関してはほとんど心配ありません。ただ害虫に関してはスギドクガやミノガ類が発生しやすくなっていますので注意が必要です。スギドクガは4~6月、7~8月の年二回にかけて食害が発生しますが、
樹の内側で食害を発生させるために外見的には分かりづらいのがネックです。放置していると内側から食い荒らされてしまいますから、これらの時期には樹木の周辺を確認して糞が落ちていないかどうかを見るようにしましょう。次にミノガ類、要するにミノムシによる食害ですが、主に春と7~8月にかけて発生します。
秋には葉を食べた幼虫がミノを作って越冬しますが、防除をするのであればこの段階で行う必要があります。ミノがぶら下がっていると「抜けがらだから気にする必要はないだろう」と思ってしまうこともありますが、ミノガ類は自身のミノの中に産卵して増殖しますから、
ミノを放置していると翌年、さらに多くの食害が発生することになります。特に複数のコノテガシワをならべて生育している場合だと、一つの木から別の木へ被害が拡大することもありますから、必ず対処するようにしてください。
コノテガシワの歴史
コノテガシワは中国の全域を生息地とする常緑樹で、中国では古くから寺院に植えられる樹木として利用されていました。一年を通して葉を落とさずに茂ることから原産地の中国では「百木の長」と呼ばれるほど大切にされてきた歴史を有しており、古代中国の歴史書にも登場するほど歴史のある植物となっています。
日本国内においても平安時代には既に漢方の原料としてコノテガシワの種子が使用されていたほか、同様に漢方の原料にするために栽培されていたとされています。現在のように園芸用の植物として日本国内に輸入されてきたのは18世紀ごろであるとされており、
この頃から現代にかけて日本の各地に植えられるようになりました。子どもが手の指を上に広げたように手を伸ばすことが名前の由来であるとされており、日本国内では主に公園や庭などに植えられている姿をよく見ることができます。また日本国内のコノテガシワと言うことで言えば、
黒金山の祥應寺に植えられているものが有名です。祥應寺のコノテガシワは享保十一年、西暦にして1726年に移植された二本の木のうちの一つであるとされており、その樹齢は600年以上にもなるとされています。幹周2.9メートル、幹高12メートルにもなる巨大な木であり、
コノテガシワとしては国内最大級のものであるとされ、国分寺市が指定する指定天然記念物として認められました。現在残っている方とは別のコノテガシワは残念ながら昭和七年に枯死が確認されてしまいましたが、その根株は掘りだされた後で開運地蔵尊として祥應寺墓苑の入り口に立っています。
コノテガシワの特徴
コノテガシワの特徴は生垣に適したその性質にあります。年間を通じて葉を落とさない常緑樹であるために落ち葉の処理による負担が他の樹木と比べても比較的少なく、耐寒性・耐暑性ともに優れているという特徴があるため、全国各地で栽培されるようになりました。
特に手を加えずとも環境さえ良ければどんどん大きく育ってくれるため育て方としても難しいことが少なく、園芸初心者が最初に植える木としてはまさにうってつけといえるでしょう。またコノテガシワであっても品種によって色を変えることも特徴であり、
現在日本国内で普及している品種にはセンパーオーレアやオーレア・ナナといったような品種があります。このうちオーレア・ナナは一般的に樹高が10メートル以上にもなるコノテガシワの中でも比較的コンパクトにまとまる性質を有していますから、グランドカバーとしてガーデニングに広く利用されるようになりました。
色合いに関しても季節に合わせて変化させるという特徴があり、生育期には木緑色から濃い緑色といった清々しい色合いを、秋から冬にかけては茶色や褐色と言ったような寂しさを感じさせる深みのある色合いを持つようになるため、庭に植えて四季の移り変わりを、
見るうえでも適しています。ただ品種によっては生育が早く、長く放置していると自宅の屋根ほどの高さまで成長していくこともありますから、事前にしっかりと品種の特徴を見て、適したものを選ぶようにするべきであるということは忘れないようにしましょう。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ギョリュウバイの育て方
タイトル:ジャカランダの育て方
タイトル:サンシュユの育て方
タイトル:サカキの育て方
-

-
グラマトフィラムの育て方
グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロ...
-

-
ブルメリア・クロセア・オーレアの育て方
ユリ科という情報が多いので、ユリ科の同じような植物が近縁種ではないかということもわかります。ネギ科は、もともとユリ科だっ...
-

-
スナップエンドウの育て方
スナップエンドウは若くてみずみずしい食感を楽しませてくれる春の食材です。このスナップエンドウはグリーンピースとして知られ...
-

-
ミニゴボウの育て方
ミニゴボウにかぎらず、野菜の中で形の小さい種類のものは昔からあったのですが、あまり受け入れられてきませんでした。育ちが悪...
-

-
ポテンティラの育て方
この花の科名としてはバラ科になります。キジムシロ属、ポテンティラ属ともされています。あまり高くまで成長することはなく、低...
-

-
ヨウシュコバンノキの育て方
日光を浴びる事で、成長を促進させないと、葉っぱの白い斑が消えてしまう事があります。白い斑は新芽の間の事なので、しっかりと...
-

-
オキザリスの育て方
オキザリスはカタバミ科カタバミ属の多年性の植物です。原産地は南アメリカや南アフリカですが、非常の多くの種類があり、世界中...
-

-
ハーデンベルギアの育て方
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベル...
-

-
タツタソウの育て方
タツタソウ(竜田草)は別名イトマキグサや、イトマキソウ(糸巻草)と呼ばれているメギ科タツタソウ属の植物です。花色は藤紫色...
-

-
ソレイロリアの育て方
特徴としては、イラクサ科の植物とされています。常緑多年性の草になります。草の高さとしてはそれ程高くなりません。5センチぐ...




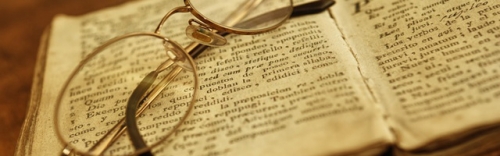





コノテガシワは中国の全域を生息地とする常緑樹で、中国では古くから寺院に植えられる樹木として利用されていました。一年を通して葉を落とさずに茂ることから原産地の中国では「百木の長」と呼ばれるほど大切にされてきた歴史を有しており、古代中国の歴史書にも登場するほど歴史のある植物となっています。