クロバナロウバイの育て方

育てる環境について
耐寒性と耐暑性双方に優れ、気温に左右されないので、北海道から沖縄まで日本全国で育てることができます。直植えの庭木としてはもちろん、鉢植えにしてもよく育ちます。枝が細くあまり樹高も高くないので、花壇の一角に植えても良いでしょう。
日光を好みますが、もともと樹勢が強いので日陰にもそれなりの耐性があります。病害虫にも強いため、育て方にそれほどコツはなく、ほとんど手を掛けなくても比較的簡単に育てることができます。管理上の注意としては、育て方そのものよりも、毒がある植物だということを十分留意して、
特に果実が成る時期に小さな子供やペットが口にしないようにする必要があります。生育環境としては、屋外の日当たりがよく水はけのよい場所が最も適しています。地面から枝を伸ばして株を広げるので、周囲に広めに場所を取ると良いでしょう。鉢植えの場合は広めのものに植えましょう。
ただし、唯一極端な乾燥には弱いので、真夏の西日にだけは注意が必要です。西日の当たらない位置に植えるか、真夏は半日陰になるように植物の陰で根元をカバーするようにすると良いでしょう。腐葉土などを含んだ腐植質に富んだ土に植えておけばすくすくと育つので、
冬季と開花する時期から結実する時期にかけて必要に応じて追肥する程度で良くなります。また、花木の一種ではありますが、剪定についてはほとんど必要ありません。勢いよく育ち大きな葉を広げますが、枝の数はそれほど多くなく、
枝の間がそれほど込み合いすぎることはありません。分枝しにくく木の形が崩れることもそうそうないので、老いて花付きの悪くなった枝や、完全に枯れた枝を落とす程度で十分です。
種付けや水やり、肥料について
一般家庭向けには庭木の苗として出回っています。これを購入することになるでしょう。植え付けや植え替えは、生長が落ち着く10月下旬から11月下旬か、極寒期を越えて寒さが和らぐ2月下旬から3月下旬に行いましょう。庭や花壇への直植えの場合は、
株の根の大きさの2倍の深さまで土を掘る必要があります。掘り上げた土には、腐葉土や完熟堆肥など有機質が豊富な土を混ぜ込んで、生育に適した植え土を作ります。穴に株を据えて用土を被せて植え終わったら、株のまわりに十分に水を注ぎ、株を傷つけないように注意しながら棒などでつついて、
株の根と植え土を馴染ませるようにしましょう。鉢植えの場合は余裕を持った深めの鉢に植えましょう。土は同様に庭土と腐葉土と完熟堆肥を混ぜ合わせたものを使います。庭土がなければ赤玉土などで構いません。屋外栽培なので、水やりはほとんど自然に任せても構いません。
乾燥には弱いので、極端に雨が少なかったり、気温が上がって土が乾燥してしまったりするようなら与えましょう。また、真夏だけは意識して朝か夕方に与えるようにしましょう。陽の高い時間に与えると根が蒸されてしまうので、日差しの弱い涼しい時間にしてください。
肥料もほとんど必要ありません。与える場合は寒肥として2月から3月下旬に与えるか、開花後の結実のために養分が必要になる6月に与えると良いでしょう。緩効性の化成肥料や、固形の油かすを株の周りに置いて与えます。また、植え付けや植え替えの時に施してもよいでしょう。
増やし方や害虫について
増やし方は、挿し木と株分けです。種から増やすのは一般的ではありません。挿し木は6月上旬から7月下旬に行います。その年の春以降に伸びたまだ若い枝を、先端から5cmほど切って使います。切った枝はすぐには植え付けずに、まずは水揚げをおこないます。
バケツなどの水の入った容器に挿しておいて、十分に水を吸わせましょう。これをしておくと、その後の生長がよりスムーズになります。1時間ほど水あげを行ったあと、土に挿します。土は挿し木用に市販されている配合済みの用土か、小粒の赤玉土などの水はけのよい清潔な土を使います。
その後の育て方は、水をたっぷりとやるように意識して、日陰に置いて管理するようにすると良いでしょう。株分けには吸枝を使います。吸枝は地下の茎から出ている根の付いた枝のことで、地表近くに伸びています。3月以降の春に切り分けて、植木鉢などに植え付けます。
土は苗と同様に腐食質が豊富なものを選びます。庭への直植えなどで土の量に余裕があるなら、元の株の周りの土を少し貰って混ぜ込んでも良いでしょう。どちらかといえば、挿し木よりこちらの株分けの方がより簡単に増やすことができます。根がどんどん広がるので、余裕を持った大きめの鉢に植え、
窮屈そうなら10月には庭や花壇、あるいはもっと大きめの植木鉢に植え替えると良いでしょう。こちらも植え付け直後はしっかりと水をやり、根がしっかり定着するまで乾燥させないようにしましょう。クロバナロウバイには特に注意すべき病気や害虫はありませんので、消毒や殺虫の手間は一切かかりません。
クロバナロウバイの歴史
クロバナロウバイは北アメリカ南東部原産の低木で、原産地全域の山林や人里周辺を生息地としています。漢字では黒花蝋梅と書き表され、花や枝葉から強い芳香を放つためニオイロウバイ(匂い蝋梅)とも呼ばれています。この匂いがとても甘くフルーティーなので、
英名ではストロベリーシュラブ(Strawberry shrub)と呼ばれるようになりました。また、樹皮からも匂いがするのでインディアンによって香辛料として使用されていた経緯から、カロライナオールスパイス(Carolina allspice)という英名もあります。
分類学上はロウバイ科クロバナロウバイ属に分類されていて、同じクロバナロウバイ属で見た目がよく似ているアメリカロウバイとしばしば混同されますが、それぞれ別々の品種です。お互い別々の属に分類されていて外見も異なりますが、毒草のロウバイの一種なのでロウバイと同じく全株に毒性があり、
特に果実の種子に強い毒性を持ちます。実際に被害が報告されており、アメリカのテネシー州でこの木の果実を口にした家畜の中毒被害が出たことがあります。日本には明治中期に渡来したとされています。現在は全国の植物園で目にすることができるほか、庭木として一般家庭での栽培用の苗も流通しています。
暑さにも寒さにも耐性があり、強靭で育てやすいので、日本全国で栽培することができるので庭木として親しまれています。また、外来種ではありますが、趣のある姿から日本の華道や茶道とも親和性が高く、生け花などの切り花や茶席の茶花としても利用されています。
クロバナロウバイの特徴
樹高2m程度の落葉性の低木で、日本では5月から6月に黒紫にも暗赤褐色にも見える花を咲かせます。花は枝の節々に1、2輪ずつ咲き、キクやハスのような細い花弁がいくつも重なって、球形に近い形を形作ります。また、花の萼(がく)の部分と花弁の色が全く同じなので境目が見つけられません。
結実する木なので、花が終わった後には大きめのブドウの粒のような形状の果実をつけます。葉は鮮やかな緑色していて花より少し大きく、表面と裏面に柔らかい毛が生えていて、枝を中心に4方向に広がります。枝はかなり細く、樹高も0.5mから1m程度と小さめです。
花はもちろん葉や枝からもイチゴに似た強い芳香がするのが最大の特徴で、葉を千切ったり枝を切ったりしただけでも甘い香りが広がります。混同されやすいアメリカロウバイに比べると、こちらの方が花の大きさがやや小ぶりで香りが強く、葉の両面に毛があるという違いがあります。
開花した姿はもちろん、結実した姿もとても趣のある花木ですが、果実に含まれる種子を中心として葉や枝など全体に毒性を持ちます。主な有毒成分はアルカロイドの一種「カリカンチン」で、他にも「シネオール」、「ボルネオール」、「ファルネゾール」、「キモナンチン」を含んでいます。
特に種子を人間や動物が摂取すると中枢神経麻痺や激しい痙攣などの症状を引き起こします。そのため、あくまで観賞して楽しむに留め、絶対に食用してはいけません。見かけはほっそりとしていてか弱く見えますが、耐暑性にも耐寒性にも優れており、
日本の蒸し暑い夏にも冬にも耐え抜きます。目立った病害虫もおらず、安定して育てることができます。あまり脇芽を出さないので枝を増やすことはできにくいのですが、その分剪定の手間が省けて管理がしやすいとも言えます。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ケショウボクの育て方
-

-
リビングストーンデージーの育て方
リビングストーンデージーは秋に植えれば春頃に花が咲きます。しかし霜には弱いのでなるべく暖かい場所に移動させるか、春に植え...
-

-
エパクリスの育て方
エパクリス属と呼ばれる花は、なんと31属もあり、種類に関しましては、400種類程度あります。原産地は主にオーストラリアに...
-

-
イワカガミダマシの育て方
イワカガミダマシはソルダネラ・アルピナの和名ですが、漢字では岩鏡騙しといい、ヨーロッパのアルプス山脈やピレネー山脈、アペ...
-

-
マイヅルソウの育て方
こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ていま...
-

-
カロコルタスの育て方
カロコルタスは、別名をバタフライチューリップと呼ばれていて、花の色も色とりどりにあります。ユリ科としての上品さと大きく派...
-

-
タニウツギの育て方
タニウツギはスイカズラ科タニウツギ属の落葉小高木です。スイカズラ科の多くは木本で一部はつる性や草本です。タニウツギは田植...
-

-
ハヤトウリの育て方
原産地はメキシコ南部から熱帯アメリカ地域で、アステカ文明やマヤ文明のころから食べられてきたと記録されている野菜です。はじ...
-

-
アルテルナンテラ‘千日小坊’の育て方
園芸店や生花店などでは千日小坊という常緑多年草が売られています。これはペルーやエクアドルといった中米原産の植物です。アル...
-

-
バジルの育て方
原産国や生息地はインド地方といわれ、ヒンドゥー教の神に捧げる高価な植物だったのです。人々の幸福を願う意味が込められ、寺院...
-

-
ニオイスミレ(スイートバイオレット)の育て方
ニオイスミレは、別名でスイートバイオレットとも呼ばれています。スミレ科のスミレ属に属しています。耐寒性多年草で、原産地は...




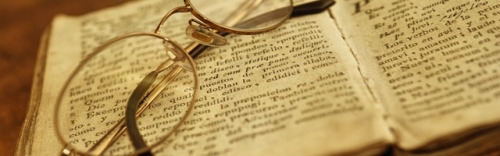





クロバナロウバイは北アメリカ南東部原産の低木で、原産地全域の山林や人里周辺を生息地としています。漢字では黒花蝋梅と書き表され、花や枝葉から強い芳香を放つためニオイロウバイ(匂い蝋梅)とも呼ばれています。