カレックスの育て方

育てる環境について
多くの種類は日の当たるところでも当たらないところでも育ちます。日当たりの良いところの方が育ちが良くなる種もありますが、日当たりが良すぎるところでは歯が痛む種もあります。たとえば、白い斑が入る品種の場合、歯が痛みやすいです。
このような場合には日当たりの強い場所におくのではなくて、半日陰が適しています。銅葉のものや黄色葉の品種はその逆で、日当たりの良いところにおかないと良い色になりませんから、日当たりの強いところで育てるようにしましょう。鉢植えで育てるのであれば、
水はけが良く、また通気性のある土壌を選ぶと良いです。市販されている草花用の培養土を用いると手軽で良いです。赤玉土を中心として腐葉土を3割くらい混ぜ込んでおくと良いです。それぞれの品種で育てる環境については違いがありますが、全体的に見ればそれほど環境は選ばないと言えるでしょう。
極端に温度が低かったり、ありは極端に日当たりが悪かったりしなければ、枯れることなく育ちます。また、株が大きくなるとすぐに株分けして増やすことができますから、色々なところに植えてみると良いでしょう。土壌が肥沃である必要は特にありません。
急いで成長させたいのであれば痩せた土地はあまり適していませんが、急がないのであれば痩せた土地でも問題はありません。育て方としてはそれほど難しくはありません。難易度は低めだと思っても良く、初心者にとっても育てやすい植物だと言えるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
新しく植え付ける時期は旺盛に成長している時期が適しています。カレックスの場合には3月から4月に成長が始まりますから、植え付けとしては適しています。植え付けるときに株分けをするのも良い方法です。品種によっては大きな株になることがありますから、
株と株の間の距離をとっておいた方が良いでしょう。30センチから50センチくらい間隔を開けて植え付けるようにします。肥料は、植え付けの時にやっておくだけで十分です。緩効性化成肥料を植え付ける場所にすき込んでおくと良いです。追肥をしなくても育ちます。
できるだけ早く育てたいという場合には肥料を与えると良いですが、この場合には春から秋にかけて液体肥料を与えると良いです。水やりについては庭植えの場合と鉢植えの場合とで異なります。庭植えの場合、植え付けてから根が張るまでは水やりをこまめにやった方が良いですが、
根が張ってしまえば必要ありません。そのままにしておいても元気に育ちます。夏の暑い時期で、土壌の乾燥が続くときなどには少し水やりをした方が良い場合もありますが、基本は何もしなくて良いです。鉢植えの場合、乾燥には注意が必要です。
生命力が強いために、根が張りやすいです。鉢の間に根が張りすぎると乾燥しやすくなります。ある程度の乾燥には耐えることができますが、極端に乾燥するような状況は好ましくありませんから、こまめにチェックして乾きすぎていれば水やりをするようにします。
増やし方や害虫について
株分けで増やすのが最も基本です。育てていれば数年で株は大きくなってきます。株が大きくなれば掘り上げて株を分けます。3月から4月の間に株分けすると、その後はすぐに成長が始まって定着しやすくなります。3月から4月の間に株分けをすると良いです。
タネで増やすこともできます。タネを蒔く時期は9月から10月、あるいは3月から5月頃です。カレックスは光発芽種子ですから、光が当たらないと発芽しないという点に注意が必要です。ですから、土をかぶせすぎないように注意しなければなりません。
できるだけ薄く土をかぶせましょう。注意しておかなければならないのは斑入りの葉の品種です。タネで増やした場合、斑入りについてはそれが引き継がれないことが多いです。発芽した株に引き継がれるかどうかは運の問題ですが、引き継がれない場合が多いですし、
引き継がれたとしても、元の感じとは異なることが多いです。ですから、斑入りの葉のある品種をそのまま増やしたいと思った場合には、株分けによって増やすのが良いです。斑入にこだわらない場合には、タネで増やすのも良い方法だと考えられます。
株分けするときには、あまり小さくしない方が良いです。たとえば1本だけにすると育たずに枯れてしまう可能性が高くなります。あまり大きくする必要はありませんが、軽くひとつかみくらいの大きさにしておくことは必要でしょう。カレックスは病気の被害や害虫の被害に遭うことはあまりありません。
カレックスの歴史
カレックスはカヤツリグサ科の植物の一つ属です。ですから一つの種を指すのではなく、実際には多くの種が含まれます。変異しやすい特徴がありますから、原種の生息地は世界中だと言っても良いでしょう。それぞれの種には原産の場所があります。
ですから、世界的に色々なところで用いられているのですが、日本の文化に根付いているものとしてはカサスゲなどがあります。菅笠という言葉を聞いたことがあると思います。平安時代に登場し、そして江戸時代まで色々なところで用いられていました。
現在では帽子に取って代われていますが、現在でも祭などでは用いられています。カサスゲは北海道から九州まで、平地ならどこまにでも分布しています。高さは1メートルくらいになることもあります。菅笠以外には、蓑などにも用いられました。地域によっては縄に用いられることもあります。
このようなことから、栽培されていた時期もあります。最近では利用用途があまりないために栽培はされていません。日本には元々カレックスが自生していましたし、海外にも多く存在します。かつては栽培用に使われていたことが少なかったために、
日本に帰化するものは少なかったのですが、現在ではいくつかの帰化種があります。現在のところ、世界で2,000種があると言われていて、現在も新しい種が誕生しているとも言われています。現在でも種分化を進めている途上にあり、今後も種の数は増えていくと考えられます。
カレックスの特徴
カレックスは世界に2,000種もある属ですから、特徴はそれぞれで異なりますが、共通した特徴はいくつかあります。まず、根が強く張ることです。根が強いために、路肩の土留めに用いられることもあります。基本的には多年生の草本です。環境に合わないときに一年生になることがあります。
たとえば寒い地域では一年生になることもあります。全体としては多年生草本だと考えられます。一ヶ所にいくつもの株ができるものがありますが、地下茎のあるものは遠くに別の株ができ、まばらな集団になります。花茎は葉の間から伸びて開花しますが、
花茎があまり伸びないものもあります。特徴的な点としては雄花と雌花が別になっていることが上げられます。近縁の主では、もともと区別がなかったものが、進化とともに区別ができてきたものがありますが、カレックスの場合には過去に同じであったという痕跡はなく、
最初から雄花と雌花が別にできていたのだと考えられています。世界中の色々な地域に存在しますが、温帯が多いです。変異しやすい傾向があり、それぞれの地域に適応して変化していると考えられます。たとえば草原として群生する場合もありますし、
森林の中にあることもあります。他にも海岸に群生していることもありますし、塩性湿地などにたくさん生えていることもあります。厳しい環境に耐えられる種もあり、中央アジアの乾燥した草原の中には、カレックスが優占種となっているものもあります。
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
クロウエアの育て方
クロウエアはオーストラリア島南部原産の、ミカン科クロウエア属の常緑小低木です。クロウエアの名は、イギリスの植物学者・園芸...
-

-
アカネスミレの育て方
特徴としてはバラ類、真正バラ類に該当します。キントラノオ目、スミレ科、スミレ属でその中の1種類になります。スミレの中にお...
-

-
ルリマツリの育て方
「ルリマツリ」は、南アフリカ、オセアニア原産のイソマツ科プルンバゴ属常緑小低木です。半つる性の熱帯植物であり別名「プルン...
-

-
カラーの育て方
観葉植物カラーは南アフリカが原産で、8種ほどの自生種の確認がされています。生息地はもともと湿地で、中でも「エチオピカ」は...
-

-
アメリカアゼナの育て方
アゼナ科アゼナ属で、従来種のアゼナよりも大きく、大型だが花や葉の姿形や生育地はほとんどが同じです。特徴はたくさんあります...
-

-
イカリソウの育て方
イカリソウは古くから強壮剤の漢方薬として用いられ、秦の時代の始皇帝も用いていたといわれています。日本でも自生し、春を代表...
-

-
イキシオリリオンの育て方
花については被子植物、単子葉類になります。クサスギカズラ目とされることがあります。ヒガンバナ科に属するとされることもあり...
-

-
クロバナロウバイの育て方
クロバナロウバイは北アメリカ南東部原産の低木で、原産地全域の山林や人里周辺を生息地としています。漢字では黒花蝋梅と書き表...
-

-
初心者でもできる、へちまの育て方
へちま水や、へちまたわし等、小学校の時にだいたいの方はへちまの栽培をしたことがあると思います。最近は夏の日除け、室温対策...




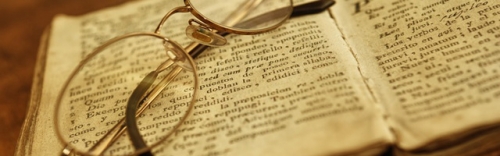





カレックスはカヤツリグサ科の植物の一つ属です。ですから一つの種を指すのではなく、実際には多くの種が含まれます。変異しやすい特徴がありますから、原種の生息地は世界中だと言っても良いでしょう。それぞれの種には原産の場所があります。