テイカカズラの育て方

テイカカズラの育て方
テイカカズラは半日陰や明るい日陰に植えてあげるとよく育ちます。植え付けは5月から9月頃にかけて行ないます。湿潤を好むので、土が乾きやすい場所であれば堆肥や腐葉土を土に混ぜ込んでおき、できるだけ水持ちが良い湿潤な状態にしておきます。
地植えにする場合は枝をある程度切っておき、余計な水分が蒸発しないようにしたほうがいいです。一度根付いてしまえば強いです。剪定はほとんど必要ありませんが、何か好みの形に仕立てたいということであればマメにするといいです。
特に形を決めようと考えていなければ飛び出ている余計な枝を切り落とす程度でOKです。フェンスやポールなどに絡ませたいと考えているのであれば、株元から出ている枝を1本か2本程度に絞り、それをメインにして育てていくとうまく絡ませやすいです。
肥料は特に必要ありません。水やりに関しては朝か夕方にたっぷりと水を与えるようにします。これは庭植えで夏の高温の時期だけで、それ以外の季節は水を与える必要はなく、雨が降った時だけで十分です。鉢植えにしたいのであれば、水は通年土を乾かしすぎない程度に与えます。
春の生育期と夏の高温期はしっかりと与えるようにしなくてはいけません。病気は特にはありませんが、害虫はアブラムシとカイガラムシに注意しなければいけません。蔓が混み合ってしまうと特に風通しが悪くなってアブラムシやカイガラムシが発生しやすくなりますので枝を間引いてしまうのがベストです。
栽培する上での注意はある?
テイカカズラは肥料を与える必要もありませんし、根付いてしまえばほとんどすることはありません。しかしもしグリーンカーテンにしたいということならば太い蔓を2本ほど以外は地際で切ってしまいましょう。あとは伸び過ぎた蔓を切り戻す程度でOKです。
形を整えたい場合は花が咲き終わった後になるべく早い時期に剪定してしまうのがコツです。害虫はアブラムシかカイガラムシが発生する恐れがあります。蔓が混み合ってしまった時に発生しやすいので、時々枝を間引いてあげます。カイガラムシはいらない歯ブラシなどを使って落としてしまいます。
鉢植えをしている場合は2年から3年に一度は鉢上げを行なうのが理想です。これは根詰まりを防ぐためで、2まわりもしくは3まわりくらい大きめの鉢に植え直してあげるのが良いでしょう。蔓性植物ですから鉢で楽しむことができる限界がありますので、数年したら庭植えにしてあげるのが良いです。また苗を購入する時にはどういう目的で購入したいのかをよく考えてから品種を選ぶといいです。
種付けをして増やすことは可能?
テイカカズラはとり木と挿し木で増やすことがほとんどです。挿し木をする場合は6月中旬頃から8月上旬までに行います。元気そうな若い茎を10cmから15cmほどにカットし、葉を2枚か3枚ほど残して他を取り除いておきます。それを土に挿して乾かさないようにします。若い茎を選ぶのは古い茎では根が出にくいからです。
とり木をする場合は5月に行います。まずは気根の出ているところを探し、そこに湿らせた水苔をまいておくと根が出てきますので、すぐ下の部分で茎を切り離して鉢に植え付けてしまいます。とり木の場合は挿し木とは違って太めの茎でも根は出てくれやすいです。
種付けさせることももちろん可能です。花が咲き終わった後にそのままにしておくとそこに種がつきます。花は高い場所で咲くことが多いのでなかなか近くでは見られませんが、鉢植えなどで育てていれば見つけやすいでしょう。種が入っている房は果実なのですが、果実は通常2つで1セットです。
1本あたりの長さは20cmほどあります。中には長さが2.5cmほどの冠毛がついている種が入っています。この種の長さは1.3cm前後です。種よりも冠毛のほうが長いのです。晩秋になるとこの果実が割れて、中に入っていた種は冠毛を利用して風に吹かれて飛んでいきます。
そういう意味ではたんぽぽに似ています。日本で自生していますから特に寒い地域でなければ勝手に芽が出てしまいますので、果実が出来た時点で必要な分だけ残し、他は摘み取ってしまっておくのがいいです。茎を切った時に切り口から乳白色の液体が出てきますが、これは有毒ですからきれいに洗い流してしまいましょう。
手には直接触れないように手袋などをして触るのが良いです。アーチやトレリス、壁面カバー、グランドカバーに最適です。側にある樹木に登って巻きついていきますので、絡ませたくない樹木があればそこへ行かないようにしっかりと蔓を別のものに先に絡ませるようにしておきます。
花が咲いていない時には葉を楽しむこともできますからグリーンカーテンにすると涼しいだけではなく、目の保養にもなります。観賞用に栽培されているものもあり、斑入りのハツユキカズラと葉が赤みがかっているゴシキカズラはよく知られています。
テイカカズラの歴史
テイカカズラという名前の由来は鎌倉時代初期にいた歌人である藤原定家です。定家は後白河法皇の娘である式子内親王に恋するのですが、内親王は神社に仕えて一生を終え、恋が成就することはありませんでした。しかし内親王亡き後も定家は彼女を想い続けて亡くなったということです。
亡くなった後、この2人の墓は比較的近い場所に作られていたのですが、ある日、定家の墓から伸びた蔓が内親王の墓に巻きついたということからこの名がついたといわれています。原産や生息地は日本ですが、朝鮮半島にも同じく自生しています。
また鎌倉時代より前になりますと日本で一番古い歴史書物である古事記にテイカカズラのことが出てきます。天の岩戸という物語の中に出てくる天のうすめの命が天の香山で天のまさきを葛として舞ったという記録があり、この葛というのがテイカカズラのことだといわれているのです。
これによって、この時代の人々がテイカカズラの蔓を使って髪を結っていたというものです。そう考えると、かなり古い歴史があることがわかります。熊野地方では林の中や山裾などによく自生していますが、特に海沿いには樫の木などの高木に蔓がつたって登ることがあります。
テイカカズラの特徴
キョウチクトウ科で蔓は2mから10mにも及びます。育てるのはそれほど難しくありませんから初心者の方でも育てることができるでしょう。また耐寒性や耐暑性もそれほど悪くはありませんが、寒い地域での植栽は少し難しいです。花は5月から6月頃にかけて咲き、直径2cmほどで白やピンク色をしています。
花びらは1枚1枚に角度がついていてまるでスクリューのように見えます。蔓を伸ばしてたくさん花をつけると非常に美しい光景を見ることができます。属名はトラケロスペルムムといい、ギリシア語の首という意味があるトラケロスと種という意味があるスペルマがくっついてできたものです。
以前は分類上、チョウセンテイカカズラの変種とされていたため別々のものとして扱われていましたが、現在ではどちらもテイカカズラとして扱われています。変種には花や葉が大きめのチョウジカズラ、別種に少し花が小さめのリュウキュウテイカカズラやトウキョウチクトウなどがあります。
かかりやすい病気などは特にありませんが、害虫は少し気をつけておくといいです。植えるのは半日陰もしくは明るい日陰が向いています。ジャスミンに似た花の香りがするのが特徴です。
ハーブの育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ハツユキカズラの育て方
タイトル:スタージャスミンの育て方
タイトル:キャットミントの育て方
-

-
ホトケノザの育て方
一概にホトケノザと言っても、キク科とシソ科のものがあります。春の七草で良く知られている雑草は、キク科であり、シソ科のもの...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
タアサイの育て方
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言わ...
-

-
エンドウの育て方
古代エジプトの王の墓から発見されたというエンドウは、地中海地方と中国が原産地や生息地とされています。日本には10世紀のこ...
-

-
アッケシソウ(シーアスパラガス)の育て方
アッケシソウはシーアスパラガスと呼ばれているプラントであり、国内総生産第一位の国が属している地帯などの寒帯の地域を生息地...
-

-
さつまいもの育て方
さつまいもは原産が中南米、特に南アメリカ大陸やペルーの熱帯地方と言われます。1955年にさつまいもの祖先に該当するイポメ...
-

-
ヒュウガミズキの育て方
原産地は本州の福井県、京都府、兵庫県の北部、です。近畿地方(石川県〜兵庫県)の日本海側の岩場の、ごく限定された地域に自生...
-

-
エラチオール・ベゴニアの育て方
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります...
-

-
ミョウガの育て方
種類としてはショウガ目、ショウガ科、ショウガ属となっていますから、非常にショウガに近い植物であることがわかります。開花の...
-

-
つい捨てちゃう、アボカドの育て方
最近では、サラダやグラタン、パスタなどに使われることもなりスーパーでもよく見かけるようになったアボカド。「森のバター」や...




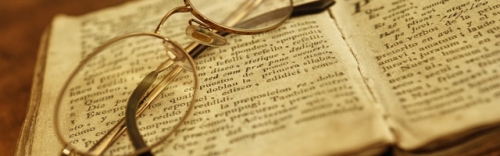





テイカカズラという名前の由来は鎌倉時代初期にいた歌人である藤原定家です。定家は後白河法皇の娘である式子内親王に恋するのですが、内親王は神社に仕えて一生を終え、恋が成就することはありませんでした。しかし内親王亡き後も定家は彼女を想い続けて亡くなったということです。