コリウスの育て方

コリウスを栽培する上でのコツ
コリウスは栽培する上でちょっとしたコツがあります。例えば芽を摘み取ることです。葉を観賞するものなのでボリュームを出したほうが美しいことから、草丈が伸びて本葉が1枚になったらてっぺんにある芽を摘み取ってしまいます。こうすることで脇のほうから新しい芽が出るのでボリュームを出すことができます。
そしてこの脇芽が伸びてきたら同じようにてっぺんにある芽を摘み取ってしまうということを繰り返していき、納得できるボリュームにさせることができるのです。レインボー系のものは脇芽が出にくいものなので、この作業をかなり重要になります。これをしないと草丈だけ伸びているひょろっとした見栄えになってしまいます。
秋頃になったら伸びすぎてる枝は全部切ってしまえばまた脇から新しい芽が出て成長します。また日光が不足すると葉の色がきれいに出ないのである程度は日光にあたるようにしたほうが良いですが、逆に強過ぎる日光は葉がやけどしてしまうのでよくありません。
葉がやけどすると枯れてしまいます。寒さにはあまり強くありませんので、鉢植えであれば11月くらいになったら室内の日当たりが良い場所に移動させてあげると良いでしょう。水やりは土が乾いている時にたっぷりとあげるのが丈夫な育て方のポイントです。
コリウスを増やしたい場合
簡単に増やしたいのであれば挿し木をするのが一番簡単です。挿し木は園芸店でも売っていますし、すでに植えてあるコリウスの枝を切って使っても良いです。やり方は花が咲いていない若い枝を10cmくらい切って下のほうにある葉は取り除いてから筋の下辺りを斜めに切って鉢などにさします。
たくさん挿し木したい時には切った枝の切り口を水の中につけておくのが良いです。発根させて冬を室内で越させ、春になったら庭に植えるということもできます。種付けさせて、それを植えるのはどちらかというと初心者の方には向いていません。できれば種付けさせるより春頃に出てくる苗を使ったほうがオススメです。
コリウスは紫色の花が咲きますが、葉を楽しみたいのであれば花は摘み取ってしまったほうがいいです。花が咲いてしまうとそちらに栄養を奪われるため、葉の色が褪せてしまうからです。種付けをさせたいのであればそれ用に花が枯れるまで待つというのも一つの方法です。
種付けさせた時に種を採取する場合は細かいものなのであわてて落としてしまわないようにしましょう。種をまくのであれば4月後半もしくは5月頃からが良いです。寒さには弱いですし、発芽する温度も高いのであまりに早い季節に植えてしまうと発芽率が低くなってしまうのです。
コリウスの育て方
コリウスを植える前には土にゆっくりと作用するタイプの肥料をまぜこんでおくのが育て方のコツの一つです。植えた後に肥料を与えるのは葉の色が薄いなと感じる時や落ちてしまう時などです。こういう場合は薄めにのばした液体肥料を様子をみながら与えるのが良いでしょう。
ただしコリウスはもともとそれほど肥料を必要としない植物ですから、基本はあまりあげないようにして必要な時だけ与えるようにしたほうが良いです。あまりに肥料が多い時には葉の模様が消えてしまったり葉の色が鈍くなってしまうからです。土は腐葉土を多めにすることで乾燥しにくい土作りをします。小粒の赤玉土を5、腐葉土5と半々に混ぜ合わせるのがコリウスを栽培する土としては適しています。
鉢植えに植える場合は鉢から根がはみ出てしまうほど成長した頃に一回り大きな鉢に植え替えてあげるのが良いです。直に土に植えている場合は冬になると寒さで枯れてしまうので植え替えする必要はありません。育て方ではそれほど注意しなければいけないものはありませんが、栽培する上では害虫に要注意です。
特に葉を食べるのが大好きなヨトウムシは気をつけましょう。ヨトウムシは日中は姿を見せず、夜になると出てきて葉を食い荒らします。ヨトウムシがいるかどうかチェックするにはコリウスの株の周りの土に掘られた後やフンのようなものがあるかどうかを見ることです。日中は土の中に隠れていますので株の周りの土は要チェックです。
おかしいなと思ったら周りの土を軽く掘ってみてヨトウムシがいればその場で取り除いてしまいましょう。苗で植えた場合は強い日差しにいきなりあてるよりは徐々に強い日光にも慣れるように気長にやってみるのが良いです。そうすると夏の強い日光にも耐性ができて元気に過ごさせることができます。
葉の色を楽しみたい場合はやはり日光は必要ですが、もし日光があまりあたらないという場合でも枯れてしまうわけではありませんから育てることは可能です。ただ葉の色はきれいに出ませんし、成長もそれほど早くないという点は承知しておく必要があります。梅雨の時期になるとかなり成長しますのでボリュームが一気に出てきます。
コリウスの歴史を知ろう
コリウスはシソ科の植物で、和名は金襴紫蘇、別名はニシキジソといいます。ただし金襴紫蘇の名前で呼ぶ人は渡来した当時はたくさんいたものの現在では少なく、コリウスと園芸店などでも呼ばれています。日本には明治時代中期頃に渡来したといわれています。コリウスの生息地は熱帯アフリカ、熱帯アジア、オーストラリア、東インド諸島、フィリピンなどです。
原産はインドネシアのジャワ島といわれています。コリウスはシソ科ではありますが、梅干などと一緒につけこまれる食べるシソとは違って、食べることはできず、観賞するためだけのものです。ちなみにこのコリウスという名前にはもともとラテン語で鞘という意味があります。おしべの形が由来となっています。
実生系と栄養系の2種類があって、実生系ですと種子をまいて育てるのですが、親の遺伝子とは違うものを引き継ぐので見た目も変化する可能性が高いです。栄養系は花が咲きにくいというのが特徴で、枝が分かれることによって大きく成長してくるので草丈は大きいものでは1メートルを超すようになることもあります。挿し木で増やすこともできるので、渡来してからもその種類はかなり多くなっています。
コリウスの特徴とは
本来は多年草ですが、日本では一年草の扱いになっています。葉の色はエンジ色、オレンジ、サーモンピンク、明るい黄色などがあります。開花時期は6月から8月の暑い時期なのですが、観賞することができる時期はもっと長く、4月頃から11月頃まで見ることができます。草丈はおよそ20cmから60cmほどになります。
園芸上では細かく分類されていて、レインボー系、フリンジ系、ケアフリー系、サーベル系などがあります。これらは実生系のものです。実生系とは種から育てるもののこと、栄養繁殖系というのもあり、こちらはヨーロッパからきた挿し木で増やすタイプのものです。育てやすいので初心者の方でも向いていますが、寒さには少し弱いところがあります。
あとはシソ科だけに日光が不足してしまうとせっかくの葉の色がきれいにつかない場合がありますので適度に日光があたる場所で育ててあげるのが良いでしょう。この植物は花というよりも葉の色を観賞するものですから、葉がバランスよくついているほうが見栄えが良く、美しいです。そのため、時々手入れをしてあげることによってボリュームが出て見た目にもきれいに見せることができます。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アガパンサスの育て方
タイトル:サルビア・スプレンデンスの育て方
-

-
グリーンカーテンの栽培方法。
地球は温暖化の一途を辿っています。日本では、温暖化対策の1つとして、グリーンカーテンを導入している家庭や市区町村が増えて...
-

-
ポリキセナの育て方
この花の特徴としては、ヒアシンス科になります。種から植えるタイプではなく、球根から育てるタイプになります。多年草のタイプ...
-

-
セージの育て方
セージの基本種、「コモンセージ」は、薬用サルビアの別名通り、古くから薬用に利用されてきました。サルビアは、学名では「Sa...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...
-

-
シキミの育て方
シキミはシキビ、ハナノキ、コウノキなどとも呼ばれる常緑の小喬木です。以前はモクレン科でしたが、現在ではシキミ科という独立...
-

-
アルケミラ・モリスの育て方
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケ...
-

-
ミラクルフルーツの育て方
小さな赤い果実のミラクルフルーツは、あまり甘くなく、食した後、しばらくは、酸味のあるものを食べると、甘く感じ、とてもおい...
-

-
コマツナの育て方
コマツナの歴史は国内では江戸時代まで遡ります。東京の江戸川区の小松川で栽培されていたことが、小松菜という名前になった由来...
-

-
ヒナソウの育て方
ヒナソウは、北アメリカ東部が原産の草花で毎年花を咲かせる小型の多年草です。日本に入ってきたのは昭和時代の後期に園芸植物と...




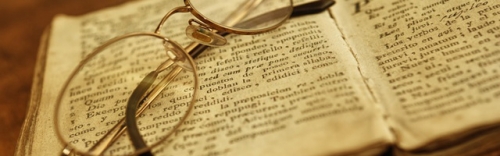





コリウスはシソ科の植物で、和名は金襴紫蘇、別名はニシキジソといいます。ただし金襴紫蘇の名前で呼ぶ人は渡来した当時はたくさんいたものの現在では少なく、コリウスと園芸店などでも呼ばれています。日本には明治時代中期頃に渡来したといわれています。コリウスの生息地は熱帯アフリカ、熱帯アジア、オーストラリア、東インド諸島、フィリピンなどです。