イポメアの育て方

イポメアの育てる環境について
育て方のポイントとして、暑い、日当たりの良すぎるくらいの場所で管理することです。半日陰でも育ちますが、真夏の直射日光の下でも元気に育ちます。庭が狭くて他の植物に半日陰を譲りたいという人ならば、イポメアの利点を活用して、イポメアには日照りの強い場所を与えて、
他の植物を半日陰に置いてあげるのも良いでしょう。春〜秋にかけては戸外でなるべく日光に当てるように管理しましょう。冬は寒さでやられてしまわないように、鉢ならば10月下旬ごろになったら室内に入れて、ガラス越しに日光に当てるようにします。
こうしておけば冬に葉を枯らすことなく、常緑で越冬可能です。庭植えの場合には、霜が降りる時期になると葉が枯れるので、芋を掘り上げて暖かい場所で越冬させ、春に植え付ければ再び楽しめます。用土には、普通の土を使えばOKです。園芸用の普通の土というのは、
小粒赤玉土:腐葉土=7:3の割合で作った混合土です。この土ならば、水はけ良く育てることが出来ます。庭でグラウンドカバーにしたり、フェンスなどに蔓を絡めてあげるのも良いでしょう。こうすることで葉がバランスよく広がり、見応えがアップします。
生息地が南国だったということもあり、暑く、日当たりの良い環境に置いてあげることが大切です。土質はそれほどこだわらないものの、腐葉性のある土壌のほうが元気に生育するので、腐葉土を混ぜてあげるようにしましょう。あとは冬の低温に注意しましょう。
イポメアの種付けや水やり、肥料について
春になって霜が降りる心配がなくなったら、花壇やプランターに植え付けます。鉢植えで出回っているものを入手した場合には、ポットのサイズに気をつけます。例えば3号ポット(直径約9cm)であれば、5〜6月に5〜6号ポット(直径約15〜18cm)に植え付けるようにしましょう。
だいたい2倍のサイズの鉢に植え替えると覚えておくと良いです。水やりについては、手のかからない植物です。春〜秋は鉢の土が乾いたら水やりをして、冬は乾かし気味に管理します。特に葉が落ちている場合には、ほとんど水は与えなくても良いです。
葉から水が蒸発しますから、葉が落ちている場合にはほとんど乾く恐れがないからです。冬でも葉が残っているならば、葉に直接霧吹きなどで水をかけて乾燥を防ぐのも良い方法です。肥料は、春〜秋の生育期に緩行性化成肥料を2カ月に1回施します。
もしくは、速効性の液体肥料を10日に1回か2週間に1回施してあげると良いです。緩行性の肥料はじわじわと効くので、これから育つような時に適しています。速効性の肥料は植物が弱っている時に与えるとその日のうちに効いて、元気を回復してくれます。
基本的には元肥を与えれば、追肥はほとんど必要ありません。サツマイモ属の特徴として、栄養のない荒れた大地でも育つということがあります。なので、イポメアも栄養がほとんどなくても育ってくれます。葉を元気にさせるためには窒素分の多い肥料が適していますが、それほど気にしなくても問題なく育ちます。
イポメアの増やし方や害虫について
挿し芽で増やすことが出来ます。適期は6〜9月です。茎を10cmほど切り、先端の葉2〜3枚を残して下葉は落とします。パーライト:バーミキュライト=1:1の割合で混ぜた用土に、茎の1/3〜1/2くらいを挿します。その後は明るい日陰で管理します。挿し床が乾かないように管理すれば、約1カ月くらいで鉢上げ可能です。
病気は、黒斑病や立ち枯れ病にかかることがあります。どちらも春〜秋の生育期に発生する病気です。黒斑病が生じたら早めに薬剤散布で対処します。立ち枯れ病になってしまったら、発病した苗は処分してしまいましょう。害虫は、アブラムシが発生することがあります。
室内で育てる場合には年中発生します。庭など戸外では、春〜秋にかけて新しく出てきた葉の裏に発生します。アブラムシが葉についてしまうと、葉が縮れてしまったり、巻いてしまう原因になります。イポメアは葉を鑑賞するための植物ですから、アブラムシは最大の天敵です。
見つけたら駆除するようにしましょう。特に葉を綺麗にしようとして窒素分の多い元肥を施してしまうと、アブラムシが発生しやすくなります。なので、与えすぎには注意が必要です。また、地上部が乾燥しすぎていると発生することがあるので、
その場合には床を湿らせてあげると良いでしょう。数が少ないうちであれば、セロテープやガムテープを使って葉にくっつけて駆除することも可能です。また、牛乳:水=1:1の割合で混ぜた液体を散布すると、アブラムシが呼吸出来なくなるので駆除出来ます。
イポメアの歴史
ヒルガオ科の植物で、一般的にはサツマイモの名前で知られています。原産地には諸説あり、アフリカ、アジア、メキシコ中央などの説があります。現在最も有効視されているのは、中南米です。サツマイモの歴史は古く、紀元前3000年には作物として栽培されていた歴史が残っています。
日本に入って来たのは1600年代で、南方から渡来したと言われています。サツマイモは荒地でも育つ頑丈な植物であるため、救荒作物として利用されてきた時代もあります。江戸の飢饉の時には、サツマイモによって飢餓に対処しようとした動きもありました。
日本でもたくさんの品種があり、ムラサキイモなど可食部が紫色の品種もあります。園芸用の品種には、葉を鑑賞する目的で作られた斑入りのものや、葉が細長いものなどの変わり種もあります。園芸用に出回っているイポメアは、この観賞用に作られた品種のことです。
カラーリーフとしてアレンジメントに使うなどの利用法もあり、人気があります。現在よく使われているのは、グラウンドカバーなどです。蔓(つる)が這って広がるので適しているのです。葉がライム色のテラスライム、葉の色が茶色や紫色の種類、斑入りのトリカラーなどが人気のある品種です。
もとはサツマイモなので、根はサツマイモと同じように芋状になっています。ただし、食用ではなく観賞用として品種改良されているため、食用ほどの大きさには育ちません。あくまでも観られることに特化した植物です。
イポメアの特徴
ヒルガオ科サツマイモ属の植物です。食用として用いられるサツマイモと同属の植物ですが、イポメアは主に葉を鑑賞する目的で使われます。そのため、食用のサツマイモに比べると根の芋はあまり太くなりません。イポメアは葉の種類が豊富で、繁殖力が旺盛です。
そのため、グラウンドカバーとしても人気があります。基本的には一年草扱いのカラーリーフで、春に庭植えして冬に枯れます。最大の特徴は、夏の暑さに強いことです。他の植物がへたばってしまうような暑さでも、イポメアはピンピンしています。というよりも、
暑さが足りないと生育不良を起こすことがあります。完全に夏向きの観葉植物ということです。園芸品種の中では、比較的安いのも特徴です。もともとサツマイモでしたし、ニッチな植物であまり知られていないことが理由です。花が咲くこともありますが、
日本では鹿児島や沖縄といったかなり暖かい地方でないと花を咲かせるのは難しいです。ただ、暖かく管理してあげれば、多少は花がつくこともあります。イポメアは強い植物なので、暑さにも耐えられますし、日本の高温多湿の気候にも耐えることが出来ます。ただ、冬の寒さには若干弱いです。
だいたい15℃を下回ってしまうあたりから、葉が枯れてしまいます。基本的にはサツマイモと同じような感覚で育てられます。秋には一応根にサツマイモができますが、これは食べてもあまり美味しいものではないようです。食用のサツマイモとは異なると思っておいたほうが良いでしょう。
-

-
ブライダルベールの育て方
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライ...
-

-
セントポーリアの育て方
セントポーリアの原産はアフリカです。アフリカに進出していたドイツが、現在のタンザニアあたりを生息地としていた花を見つけた...
-

-
アーティチョークの育て方
アーティチョークの原産地や生息地は地中海沿岸部や北アフリカで、古代から栽培されているキク科のハーブです。紀元前から高級な...
-

-
コカブの育て方と種まきの時期
コカブは球の直径が4から5センチのカブで、葉にはビタミンA、Cが多く含まれています。コカブの栽培は、虫の食害にだけ気を付...
-

-
ツルバキアの育て方
ツルバキアは、原産、生息地共に南アフリカのものが多くあり、主に24種類が自生しています。ユリ科のツルバキア属に属していま...
-

-
ガーベラの育て方について
ガーベラは、キク科の花であり、毎年花を咲かせる多年草です。園芸では、鉢花や切り花などに広く利用され、多数の園芸品種が存在...
-

-
ポポーの育て方
この植物の特徴においては、まずはモクレン目であることがあげられます。そしてバンレイシ科に属する植物になります。バンレイシ...
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
レモングラスの育て方
多くのハーブが、原産地や生息地などがはっきりしているのに対して、レモングラスは野生種が見つかっていないために、原産がどこ...
-

-
カタセタムの育て方
カタセタムの科名は、ラン科、属名は、カタセタム属になります。その他の名称は、クロウェシアと呼ばれることもあります。カタセ...




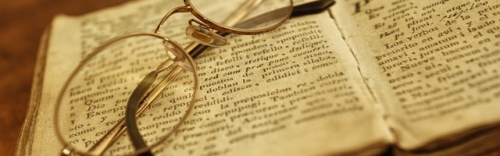





ヒルガオ科サツマイモ属の植物です。一般的にはサツマイモの名前で知られています。原産地には諸説あり、アフリカ、アジア、メキシコ中央などの説があります。現在最も有効視されているのは、中南米です。