ネオレゲリア(Neoregelia)の育て方

ネオレゲリアの種付け
花が終わった頃から、株が次第に枯れていきますので、鑑賞時期が終わった株は基部から切り取って、脇に出ている子株を株分けして植え替えを行います。植え付けに最適な時期は5月~9月上旬とされています。
ネオレゲリアの育て方
ネオレゲリアを育てる際には、植え付け直後から1ヶ月程度は明るい日影に置いて養成を行います。その後は、高温多湿で明るい場所を好みますので移動させましょう。日光が不足してしまうと、葉っぱの模様が薄くなってしまいますので明るい室内に置きます。
ただし、逆にあまり光が強すぎても、葉の色彩が薄くなってしまいますので、夏の間だけは、半日陰程度の場所で管理をします。湿度は高温多湿な環境を好み、生育に最適な温度は20℃~30℃程度です。寒さには意外にも強く、5℃程度には十分耐える事ができる植物ですので、室内での栽培であれば越冬は容易に行う事ができます。
ネオレゲリアは一度花が咲くとその株からは花が咲かないようになっています。ですが、横から出てくる新しい株を株分けして植えつければまた花を咲かせる事ができます。花を咲かせたい場合や根づまりを起こしてしまった場合には、この株分け作業が必要になります。
水やりに関しては、ネオレゲリアは根が退化していて、水を吸い上げる力が無くなってしまっています。ですので、根は土に固定する程度の役割で水分は葉っぱから吸収します。春~秋までは、はっぱの根元の筒状の部分に水がずっと溜まっているように見えますが溜まっていると言っても大量に水を吸収する事はありません。
溜められる量も決まっていて限られています。4月~10月までの間は、1ヶ月に2回~3回与えます。窓の近くで風通しが良く、乾きやすい場所の場合には3回、風通しのあまりよくない場所の場合には2回程度を目安に与えましょう。特に夏の間は、この水の量の有無に特に気をつけて栽培します。
11月~3月の冬の間は、1ヶ月に1回程度で十分です。水を与える際には、葉の上からも水を与えて葉の付け根の筒状になっている部分にも水が入るようにします。水やりのたびに筒の中の水が入れ替わるようにたっぷりと与えるようにします。
葉っぱの根元のくぼみにずっと同じ水が溜まっているような場合には、ティッシュなどを使って吸い出すなどの作業を行います。そのままにしておいてしまうと水が腐ってきてしまい、やがてネオレゲリアも枯れてしまいます。受け皿に溜まった水分もこまめに捨てるようにしましょう。
肥料は、春から秋にかけての育成期の間は、2ヶ月~3ヶ月に1回程度、植え込み資材1リットルあたり5グラム程度の粒状肥料を株元にバラ撒くように与えます。または、2週間に1回程度、液体肥料を1000倍に薄めたものを水やりの代わりに与えます。
ネオレゲリアを育てるポイント
ネオレゲリアの株分けの詳しい方法は、子株を親株から切り離して、ミズゴケなどを用いて植え付けを行います。花後に行いますが、寒い時期は避けるようにして、4月~10月頃の暖かくなる時期まで待って行いましょう。
子株の葉が少ない場合には活着しない事があるので、葉が5枚~6枚程度になってから切り離しを行います。また、親株と近い位置で切り離してしまうと株の基部が筒状になって活着しなくなってしまいますので注意が必要です。
栽培している間に下葉が枯れてきますので、枯れてきたら除去します。植え付け後1ヶ月ほどで根が出始めますので、初根を確認したら観葉植物の専門用土を入れた鉢に植え替えを行いましょう。この際に、根は水苔に包んだまま植え替えを行っても問題ありません。
ネオレゲリアの花を咲かせる事で、葉の美しい色彩を表現する事が出来るようになります。ある程度の大きさになると、アナナス類は全て開花処理によって開花させる事ができます。花を開花させる専用の薬剤も販売されています。
この薬を葉面散布するか葉筒への注入処理を行えばすぐに開花させる事ができます。もっと簡単に行うには葉筒の中に水を十分に入れてカーバイトの小豆粒位の塊固まりを投入する事でも効果を得る事ができます。
害虫、は5月~10月頃までの間にカイガラムシやハダニがつく事があります。カイガラムシは風通しの悪い室内に置く事で発生しますので、風通しには注意しましょう。カイガラムシが発生してしまった場合には、古い歯ブラシなどを利用してこそぎ落とします。
ハダニが発生してしまった場合にも早めに防除するようにしましょう。また、葉に丸い茶褐色の斑点がつく炭そ病が発生してしまった場合にも風通しをよくして、被害を受けてしまった葉は取り除きます。
ネオレゲリアの歴史
ネオレゲリアの原産国は、ブラジルとされています。生息地は熱帯~亜熱帯アメリカで、97種生息している着生植物です。品種も非常に多く、その数は4000品種以上にまで至っています。その多くは、株がロゼット状になっていて、葉緑の部分には、とげがあります。
ネオレゲリアが生息している場所は、その多くが木の幹や岩上に着生して育ちます。開花の時期になると、下部中央の筒状部の中に剣山状の花をつけますが、花は筒状部までの上までは伸び出さないようになっています。
よく栽培されている品種はネオレゲリア・カロライナエの品種である‘フランドリア‘があり、開花期になると中央の部分の葉が深赤色に色づき、長期間鑑賞する事ができます。また、ツマベニアナナスの和名があるネオレゲリア・スペクタビリス、小型の品種である
‘ファイアーボール‘、葉緑に桃色の覆輪斑が入っている‘ファイアーボール・バリエガタ‘、またこれによく似た姿で葉が緑色をしている‘リオ・オブリオ‘という品種のものがあります。
ネオレゲリアの特徴
ネオレゲリアの一番の特徴は花は咲きますが、観葉植物である事です。ヤドクガエルが産卵する植物としてもよく知られています。ネオレゲリアの株はロゼット状に広がり、葉は丸く、大きく広がります。株の中央の部分には水がたまります。
ここに水を溜める事で株を熟成させる事ができます。鮮やかな葉を広げる為まるで造花のようにも見え、中央部分の花付近はまるでスプレーを吹きかけたように赤くなる為‘つくりもの‘と思われる事が多いのも特徴です。
観葉植物として栽培するには置き場所を選びますが、見た目のインパクトと少し無機質な感じが現在では人気が出てきています。ネオレゲリア属は着生種なので、多くの品種が葉を鑑賞するものになっています。種間などの交雑品種が多く育成されています。
本種とされているものも交雑育成種です。ストロンを出して群生する小型種で、葉の長さは10センチ~15センチ程度、葉は光沢があります。育成には時間がかかる植物で、開花までには2年以上の期間が必要となります。
また、一度開花した株は再び花をつける事はなく、花が終わった後に株が子株が育ってきますので、それを切り取り株分けを行います。葉の色彩が独特でトロピカルな雰囲気を作りだします。ネオレゲリアは品種により株の大きさや葉色などが異なっています。大きさでは小型種のものが人気です。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ゲッキツの育て方
タイトル:アレカヤシの育て方
タイトル:コルディリネの育て方
-

-
ニーレンベルギアの育て方
ニーレンベルギアはナス科の植物で、紫色や白色などの花を咲かせる草花です。古くから人気が高い草花の一種であり、杯状に整う花...
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...
-

-
ゴーヤの栽培こでまりの育て方あさがおのの種まき
種物屋さんに行くといろいろ知識の豊富な方がいらっしゃいますのでわからない時はまずはそういう専門家に相談してみます。そうし...
-

-
デンドロキラムの育て方
デンドロキラムの科名は、ラン科で属名は、デンドロキラム属です。その他の名前は、ライスオーキッドと呼ばれています。デンドロ...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
グレコマの育て方
グレコマの科名は、シソ科 / 属名は、カキドオシ属(グレコマ属)となります。和名は、カキドオシ(垣通し)、その他の名前:...
-

-
植物の育て方にはその人の心があらわれます。
自宅で、植物をおいてあるところはたくさんあります。お部屋に置いておくと部屋のイメージがよくなったり、空気を浄化してくれる...
-

-
ハナショウブの育て方
ハナショウブとは6月の梅雨の時期に花を咲かせる花弁の美しいアヤメ科の多年草です。原産は日本や中国などのアジア圏になります...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
アストランティア・マヨールの育て方
アストランティア・マヨールは、中央・西部ヨーロッパが原産のセリ科の宿根草で、生息地は主にヨーロッパからアジアの西部にかけ...




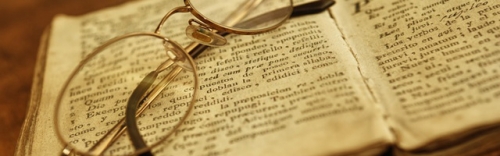





ネオレゲリアは株を植えつける植物で、種からの栽培方法はありません。株の植えつけを行う際には、ヤシの実チップや水ごけを使用して、植え込み資材1リットルあたり5グラムの粒状肥料を混ぜ合わせたものに植え付けます。