アオマムシグサの育て方

育てる環境について
アオマムシグサは日陰の湿った場所で自生するので、栽培する際には半日陰のような状態にすると良いです。湿度の高い林床を好むので水はけの良い土、又は腐葉土が適していると思われます。家庭で生育させる場合であれば植え付け時期は12月~2月頃の寒い時期が適しています。育て方は下記の通りです。
庭に植える場合はまず球根を植える場所を耕します。30センチ~50センチ程度でOKです。耕せたら30センチ程の穴を掘り、ホームセンターなどで市販されている山野草用の培養土かもしくは腐葉土を穴の2/3程度まで入れます。その上に球根を並べていきます。球根と球根の間隔はあまり詰めない方が良いです。20センチ程度は空けておきます。
並べた球根に先程の山野草専用の培養土もしくは腐葉土をかぶせてゆきます。なお、かぶせる土の目安は5センチ程で問題ありません。前述の通り、アオマムシグサは多湿の場所を好むので水を多めにやります。次に鉢やプランターの場合ですが鉢の目安は5号または6号の深鉢に1球、プランターの目安は多くても5球くらいが理想的です。
まず鉢底に網をしき、先程の山野草用の培養土もしくは腐葉土を鉢の半分位まで入れます。その後は球根を並べ、先程と同じように球根に山野草用の培養土もしくは腐葉土をかぶせます。かぶせる山野層用の培養土もしくは腐葉土は3センチまたは5センチ程度が良いでしょう。やはり水は多めに、たっぷりとやりましょう。
種付けや水やり、肥料について
くどいようですが多湿の場所を好むため、水やりは頻繁に欠かさず行うことが大事です。また、林の中で自生するくらいなので特別な有機肥料や化学肥料は育てる上で必要ありません。前述の通り、アオマムシグサは受粉する際に小虫の力を借りて行います。もちろん人為的に行うことも出来ますが自然に任せても何の問題もありません。
秋ごろには赤い実をびっしりとつけます。ただし、この実は有毒です。ちなみに実を付けて栄養を使い果たすと一度、雌花を咲かせていたとしても再び雄花に戻ることがあります。あるいは茎が折れたりしても同じことが起こります。栄養状態次第で雌雄が変化します。なお、果実だけではなく根の方も毒を持っています。
サトイモ科なので他のイモ類のように球茎ができるのですが、そのままでは食べられません。生で食べることは出来ませんが、何度もゆがいては水を換え、またゆがいて、というあく抜きを繰り返せば、食べられないことはないそうです。マムシグサではありませんが、テンナンショウ属の植物を食していた事例は世界の至る所にあるようです。
例えばアイヌや北米の先住民などもこの芋をあく抜きして食べていたらしく、加工法や調理法は様々ですが癖のある味のようで好んで食べる人もいたそうです。ただし、現代の我々の口に合うかどうかはかなり疑問です。無理に食べない方が良いでしょう。この灰汁の原因は硝酸カルシウムで、里芋の茎の部分、つまり「ずいき」にも含まれている成分です。
増やし方や害虫について
害虫による被害の中で、最も多く報告事例があるのはガの幼虫です。葉っぱを食べてしまうので注意が必要です。ガにも色々な種類があって、シャクガ科、スズメガ科、ヤガ科、ドクガ科など様々です。中でもスズメガ科のビロードスズメの幼虫はマムシに擬態することで有名です。
色は一般的に茶色からこげ茶色ですが、淡褐色や黄緑色の個体も存在します。体長は5センチから8センチくらいです。頭部には目のような模様が二つついていますが、もちろんこれは目ではなくマムシに擬態しているため、そう見えるだけです。尻尾の先端に1センチ程の短い針がついているのも特徴の一つです。
こういったガの幼虫は主に夜行性なので夜の間にアオマムシグサの葉を食べることがあります。先程のビロードスズメの幼虫の場合であれば、主に食べるのはオオマツヨイグサやブドウ、ヤブカラシ、ツタなどですがマムシグサも食べてしまいます。このようなガ類の幼虫を駆除するにはやはり殺虫剤が効果的のようです。
自然界で彼らを捕食するのは鳥か大型の虫(カマキリなど)などですが、天敵を放つよりも薬剤の方が確実です。アオマムシグサのように丈の低い植物には樹木用のスプレー殺虫剤で充分です。あるいはもっと簡単に物理的に処分することもできます。ガの幼虫は人間にとって無害な種が大半を占めます。素手で触っても全く問題ないのですが棒やハサミで取り除くだけでマムシグサへの被害を最小限に防ぐことができます。
アオマムシグサの歴史
アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」(くちなわのしゃくし)、蛇の大八(へびのだいはち)、山蒟蒻(やまごんにゃく)という別名を持っています。ちなみに有毒です。名前の由来は偽茎が紫褐色のまだら模様になり、
毒蛇のまむしに似ていると考えられたという説と偽茎の形を捉えて蛇が鎌首を持ち上げたようにも見えるためマムシグサという名前が付けられたという説の二種類があります。偽茎というのは茎のように見えるけれども実際は茎ではなく、葉の基部が何重にも重なったものをこう呼びます。
マムシグサの中でも苞が紫色になる品種と緑色になる品種があり、紫色の方をマムシグサ、緑色の方をアオマムシグサと呼んでいます。なお、苞とは花の基部にあって、つぼみを包んでいた葉のことを言います。ところでマムシグサの分類に関してはかなり複雑で、緑花のマムシグサを「アオマムシグサ」と呼ぶのは前述の通りですが関東蝮草(カントウマムシグサ)としても分類されています。
同じ植物として扱っている資料もあります。しかしこの名前はあまりに不自然です。なぜならカントウマムシグサは関東よりも東に分布するということになっていますが、実際は関西にも緑花のマムシグサは分布しているからです。一説によると、関東に分布するものをカントウマムシグサ、四国や九州に分布しているものはマムシグサと呼んで区別しているそうです。
アオマムシグサの特徴
マムシグサの原産国は日本です。生息地は田舎や郊外の山、木陰などです。自生しているので見つけるのはさほど難しくありません。国内で30種類程の種が確認されています。やはり何と言っても特徴的なのは、その形です。まだら模様も印象的ですが、蛇の頭部のような花弁の形は一度見たら忘れられません。
実は花弁のように見えるのは大きな葉で仏炎苞と呼ばれています。茎から筒状の葉が伸びており、この部分は見た目通り筒部(とうぶ)と呼ばれています。ラッパの管のような筒部の先端は葉っぱを水平に折り曲げたような形をしており、こちらにお辞儀をしているようにも見えます。
この部分は舷部と呼ばれており、蛇の鎌首とは言い得て妙な表現です。花はどこにあるかというと、仏炎苞の中の底の部分に隠れています。つまり外側からは見えません。マムシグサの花部分の一般的な特徴は仏炎苞に白い筋があること、舷部は筒部より短いこと、付属体(花から舷部に向かって伸びている花芯のこと)は先端に向けて少しずつ太くなっていることなどが挙げられます。
また、この花には面白い特徴があります。最初に咲かせた花は雄花になりますが、さらに成長を続けるとその花は雌花になります。つまり途中で性転換します。花は仏炎苞の中にあるので小虫は蜜を求めて仏炎苞の中に飛び込みます。しかし、舷部が覆いかぶさっているので上からは出にくい構造になっています。
雄花は下に隙間があって出られるようになっていますが雌花にはそれがありません。ほとんどの虫は雌花の中で息絶えますが、マムシグサの目的は雄花を通過した虫が付着させている花粉です。こうしてマムシグサは受粉を行います。
-

-
ニューサイランの育て方
ニューサイランはニュージーランドを原産地としている植物であり、多年草に分類されています。ニューサイランはキジカクシ科、フ...
-

-
プルメリアの育て方
プルメリアの原産地は熱帯アメリカで、生息地も熱帯がほとんどですので、日本では基本的に自生していませんし、植物園などに訪れ...
-

-
シロバナタンポポの育て方
シロバナタンポポの特徴は、花の色が白色であることです。舌状花の数は他のタンポポと比べると少なく、1つの頭花に100個程度...
-

-
カレンジュラの育て方
日本ではキンセンカという名でよく知られているカレンジュラのことをよく知って育て方を工夫しながら栽培していきましょう。カレ...
-

-
タイリンエイザンスミレの育て方
多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすい...
-

-
あじさいの育て方
あじさいといえば知らない人はいないほど、梅雨の時期に見られる代表的な花です。紫陽花科(ユキノシタ)科の植物で6月から7月...
-

-
大根の栽培方法を教えます。
日本人の食卓に欠かせない大根は、酢漬けや煮物などで美味しく食べる事が出来ます。特に大根の漬漬けには数多くのバリエーション...
-

-
オカノリの育て方
オカノリの原産国は諸説ですが、中国が有力とみなされています。ある説ではヨーロッパが原産と考えられ、現在でもフランス料理で...
-

-
フウランの育て方
原産地は日本(関東南部・以西)、朝鮮半島、中国南部です。ラン科のフウラン属に分類され、日本では江戸時代から園芸植物として...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...




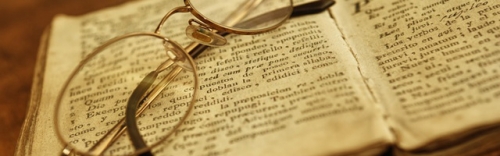





アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」(くちなわのしゃくし)、蛇の大八(へびのだいはち)、山蒟蒻(やまごんにゃく)という別名を持っています。