リトープスの育て方

育てる環境について
栽培をするとしたらどのような環境に置くことになるかですが、あまり手間がかからないとされています。砂漠、岩場で育つような植物なのでいろいろなところに対応できそうです。まずは基本的には日当たりがしっかりと得られるところを探すようにします。しかし真夏の暑さに対してはあまり強くないとされます。
直射日光などにギラギラ当てられても特になんともなく育ちそうですが、実際のところは弱さがあるとされています。真夏においては半日陰での管理が良いとされています。夏の半日陰とは午前中を中心に日差しが当たるところに置くことをさします。半日陰だから東向き、西向きのどちらかで良いように感じますが大きく異なります。
朝の日差しに比べると夕方の西日はかなり強くなります。これが植物にとっては苦手な光でもあり暑さでもあります。一方朝の日差しは比較的さわやかなこともあるのでこちらについては特に問題なく置いておくことができます。夏以外においては1日中日当たりに当たるところで問題ありません。
その他の季節も半日陰のところに置いてしまうと日光不足になり徒長してしまうことがあります。一応成長するものの力なく成長するので見た目があまり良くなくなります。日光をしっかり当ててあげることで力強さを持つことができます。一旦徒長してしまうとその後に良い状態に戻すのが難しくなるとされるので、最初から徒長しないような管理ができるところで管理するのがいいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては用土の管理、準備をする必要がありますがどのような土が良いかです。生息地においては砂漠のようなところでも育つとされています。乾燥した砂地のようなところでも成長させることが出来るようです。とはいえ栽培をするのであれば確実に育てて花を咲かせたいです。そうなると必要になるのが土をしっかりと配合することです。
鹿沼土の小粒タイプを2割、赤玉土の小粒タイプを2割、ピートモスを2割、川砂を2割、くん炭を2割にする配合土にすると良いとされます。腐葉土などを加える必要はなく、乾燥、水はけを重視した配合にしておくと良いとされています。水やりについては砂漠地帯での栽培に対応します。この植物においては水をあげすぎるとどうなるかですが、すぐに腐って枯れてしまいます。
もちろん生物なので水分は必要としますが、水分が少ないところで生活しているものは日常的に水分がたくさんあってもそれを処理しきれません。水浸しのようになりそこから腐ってしまうことがあります。1箇月に1回ぐらいで十分とされています。では真夏の暑い時にはたっぷりと2回ぐらい与えるかですがとんでもないことです。
6月から9月にかけては一切水を与えません。過酷な状況に見えますが、この花は夏に休眠するタイプになります。水を与えてしまうとやはり腐ってしまうことがあるので、屋内や屋根のあるところなどで雨が当たらないようにしなければいけません。梅雨や、一時的な雨も良くありません。
増やし方や害虫について
植え替えをする必要性としてはそれ程ありませんが、株の生育が鈍ってきたと感じたなら行ってみてもいいでしょう。また株がどんどん増えると植木鉢に合わない大きさになっていることがあります。その時には植え替えをしたほうが良くなるでしょう。行う時期としては10月から12月ぐらいが良いとされています。
その中でももっともよいとされるのが生育期とされる10月から11月ぐらいです。この植物は夏に休眠をして秋に成長、花を咲かせるようになります。その時期に株分けなどをすることができます。増やし方として株分けがあるので、この植え替えの時期を狙って行うようにします。どうしても根が出てくるのに時間がかかることがあるので、早めにやったほうが良いとされています。
この植物においてできそうになさそうですが種から増やすことができます。花が咲きます。その後に果実ができます。その果実が枯れたあとの部分に種があるのでそれを採取しておきます。秋から春の間に種を取ることができますから、それを保存しておきます。すぐにはまきません。その年の秋、10月から11月ぐらいにまくようにするといいでしょう。
行っておきたい作業としては花がら摘みをします。花が咲いたあとに種を取るならそのまま果実などになるのを待ちますが、そうでない時は株が傷むことがあります。早めに花がらを摘むとその心配も減ります。害虫はカイガラムシ、アブラムシ、サボテンネコナカイガラムシの発生があります。
リトープスの歴史
生きる化石と言われる生物がいくつかあるようです。魚においてはシーラカンスと呼ばれる魚がいて、昔からあまり形などを変えずに今も生きていると言われます。生物に関してはそれなりに進化をしながら変化しますが、昔のままいるのはその環境自体があまり変化をしないのか、その生物自体があまり変化する事ができないのか、色々なケースがあるでしょう。
変化ができないときは絶滅することもありますから、昔の環境にも今の環境にも対応している生物であることがわかります。リトープスと呼ばれる植物があり、生きる化石、宝石と言われることがあるようです。見た目は非常に原始的で石のように見えることがあります。
その一方で非常にきれいな花を咲かせるのでその部分については宝石が輝いているように見えないこともありません。原産地としてはアフリカの南部とされています。国で言えば南アフリカ、ナミビア、ボツワナあたりを生息地としている植物になります。別名としてはイシコロギクと言われることがあります。
花が咲かない時はまるでその辺りに落ちている石、化石のように見えることがあります。しかし時期になると花をつけるようになります。その時にはきれいな菊のような花をつけてくれます。そのことからこのように言われるようです。その他においてはサンゴギョクと呼ばれるタイプもあります。こちらは色が珊瑚色、少し青い様な色をしていることからそのように言われているようです。
リトープスの特徴
この植物についてはハナミズナ科とされています。同じような種類としてメセンがあり、メセンの仲間としても知られています。園芸上においては多肉植物になります。主に観葉植物として育てられることが多くなります。多年草なのでうまく育てることによっていつまでも生かしておくことが可能です。高さとしてはそれ程高くならず5センチぐらいです。
まさに道端に落ちているイシコロのような大きさです。花が咲くのは10月から1月ぐらいになります。種類によって多少ずれることがあります。花の色としては白いタイプが多いですが、その他には黄色、ピンクなどのものも見ることができます。生息地である南アフリカは日本からすると全く逆のようなところに感じられます。
でも全く逆だけに気候としては非常に似ているところもあります。南半球の日本の位置のところといえるかもしれません。暑いイメージとは異なり、比較的温暖、場合によっては少し寒さを感じるところもあります。耐暑性はそのことから決してありません。暑さには弱いところがあります。
寒さに関しても特に強いわけではなく、日本で育てようとするならちょうどいいくらいかやや弱いところもあります。特徴としては上から見ると扁平な葉が2つ合わさったようになっています。自生しているところとしては砂漠であったり岩場です。ですからサボテンなどと非常に近いかもしれません。それだけに石に見間違えられても仕方ないでしょう。擬態をしているとも言われます。
-

-
マツバボタンの育て方
原産地はブラジルで日本には江戸時代に入ってきたといわれるマツバボタンは、コロンブスがアメリカに進出したことでヨーロッパに...
-

-
ホヤ属(Hoya ssp.)の育て方
ホヤ属の栽培をおこなう場合には、日陰などのような位場所ではなくできるだけ日のあたる明るい場所を選ぶようにしてください。耐...
-

-
アメリカアゼナの育て方
アゼナ科アゼナ属で、従来種のアゼナよりも大きく、大型だが花や葉の姿形や生育地はほとんどが同じです。特徴はたくさんあります...
-

-
風知草の育て方
風知草はイネ科ウラハグサ属の植物です。別名をウラハグサ、またカゼグサとも言います。ウラハグサ属の植物は風知草ただ一種です...
-

-
大きなサツマイモを育て上げる
サツマイモは特別な病害虫もなく農園での育て方としては手が掛からないし、家族でいもほりとして楽しむことできる作物です。
-

-
ストレプトカーパスの育て方
イワタバコ科のストレプトカルペラ亜属は、セントポーリアも有名ですが、その次に有名とも言われています。セントポーリアは、東...
-

-
スターアップルの育て方
スターアップルは熱帯果樹で、原産地は西インド諸島および中南米です。アカテツ科のカイニット属の常緑高木です。カイニット属と...
-

-
ヒメシャラの育て方
ヒメシャラはナツツバキ属のうちのひとつです。日本ではナツツバキをシャラノキ(沙羅樹)と呼んでおり、似ていますがそれより小...
-

-
アルストロメリアの育て方
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。
-

-
マキシラリアの育て方
この花の種類としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科となっています。常緑の多年草となっているので、ずっと花を咲かせる...




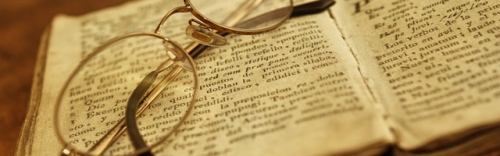




この植物についてはハナミズナ科とされています。同じような種類としてメセンがあり、メセンの仲間としても知られています。園芸上においては多肉植物になります。主に観葉植物として育てられることが多くなります。