ナツメ(実)の育て方

育てる環境について
具体的なこの植物の特徴としては、葉は光沢があり、薄い緑で、葉の厚さも薄く見えるので、さわやかな植物に見えます。色が薄めなので軽い感じで、ガーデニングでも淡い美しさを楽しむことができます。日本人にはこのような樹木は、非常に好まれるのではないかということですが、特に春には、爽やかさを庭に演出できるので、
春の気分を味わうのにも最適な植物ということができます。また花は薄い黄色で、鮮やかな花ではないですが、とてもスッキリしています。また樹の幹は日本の庭の木という感じで、親しみやすい味わいでもあります。田舎に行くとよくあるような木です。また干しナツメからもわかりますが、大きさも実が小さめなので、野鳥などにも食べやすく、
野鳥を庭で楽しみたい時にも、最適な木になるということで、その意味でも自然を楽しむガーデニングが出来るということになります。そのようなガーデニングの楽しみも味わえますので、栽培も楽ですから、庭に何本か植えてみると良いということになりますが、実の量も多くなりますので、鈴なりに垂れ下がるように実った様も美しいものがあります。
またそのまま食べても美味しいですが、それを干し棗にしてみるという体験も面白いですし、毎年作ることができ、干してあるので保存も効きますから、その点でも、保存ができる漢方薬としても頼りになる植物ということができます。特に病気などでは利用できますので、その点でも心強い植物ということができます。
種付けや水やり、肥料について
なつめの育て方ということでは、このように初心者にも簡単に育てることができ、あまり手を加えなくても自然に庭で育つので、ガーデニングでは最適な植物ですが、具体的には植え付けの最適な時期としては冬で、11月から12月頃と、春先の3月頃が良いようです。また土は水はけの良い乾燥気味の土を好むということですが、土に粘り気があると良いとも言われています。
しかし基本的にはどのような土でも育ちますが、水はけを良くするためには腐葉土などを混ぜあわせた土だと良いようです。ガーデニングでも水はけの良い植物というのは多いので、同じような環境で育つ植物を集めてあると、育てやすいということになります。これだけ有用な用途がある植物なのに、あまり環境を選ばないということでも、
ガーデニングや家庭菜園の植物としても非常に便利な植物ということになり、太古の昔での農業技術が未発達な状態で栽培されていたのもわかるような気がします。簡単に栽培出来て、食べることもでき、健康にも良いのですから、これほど優れた人間に有用な植物も珍しいということでしょう。また庭がない場合でも、
マンションなどでのベランダでも育てることができます。この植物は、過湿を嫌うので、その点を気をつければ育てることができます。それも楽しいのではないでしょうか。ベランダに緑の空間を作ることができるということになります。また棗の開花は梅雨の頃なので、プランターの場合には、雨にかからないようにすると良いそうです。
増やし方や害虫について
肥料はベランダなどでの鉢植えやプランターでは、3月頃に即効性の肥料を与えますが、庭でのガーデニングや家庭菜園ということでは、11月から12月頃牛糞、骨粉、鶏糞、油粕など有機質肥料を与えると良いそうです。また害虫などは殆ど無いそうですが、それも初心者のガーデニングでは便利です。しかしナツメコガという害虫がつくこともあるということですが、これも専門の農薬で駆除ができます。
また有名な干しナツメの作り方ということでは、まず収穫した後、5,6日ほど天日で干します。その後30分ほど蒸すそうです。そしてまた天日で干します。この蒸すということがポイントのようです。それだけで出来上がります。非常に簡単なので、誰にでもできますし、そのまま食べても、ほのかな甘味があり、美味しくいただけますし、
デザートのケーキやジャム、お茶などとしても、いただけますが、雑炊などに入れても美味しいです。また外国の料理でもスープ系の料理にもよく入っていますし、お赤飯のような炊き込みご飯でも利用できます。以前韓国のサンゲタンに入っていて驚いたことがありました。また病気の回復期に、おかゆの中に入れて食べさせても良いようです。
もともと漢方薬であり、滋養強壮にも良いということですので、少しずつ、おかゆや雑炊に入れて食べさせると、早く元気になるようです。そのように非常に役に立つ植物ですので、ガーデニングや家庭菜園では、まずこの植物から始めてみると面白いかもしれません。
ナツメ(実)の歴史
ナツメは健康食品や漢方薬でも利用されている優れた食べ物ですが、案外料理などでは日本の場合にマイナーな感じもします。しかしその歴史は古く、原産は中国で、生息地も世界中に広がっていますが、なかなか優秀な人間のためになる植物であり食べ物ということができます。中国5000年の歴史と言いますが、
ナツメの栽培は紀元前8000年頃の遺跡から栽培していた痕跡が見つかっているということですから、相当古くから栽培されていたということがわかりますし、今でも利用されているということは、その効果も大きなものがあるということになります。またこの植物は乾燥したものがよく販売されていて、干しナツメということで、
乾いた実のイメージが強いのですが、果物としても食べられていて、小さな細長い実が実り、リンゴのような感じで食べることもできるので、その点からもガーデニングや家庭菜園として栽培するのにも手頃です。系統としては、クロウメモドキ科の落葉高木ということですが、果実も美味しいですし、見た目も美しいということで、観賞用にも果物をいただけるということでも非常に有益な植物ですが、
栽培でも手がかからないということがメリットでもあります。だからこそ、今でも盛んに栽培されているということですが、ガーデニングや家庭菜園とうことでも、初心者にも簡単に栽培できるので、最初に植える植物としても選択肢の一つになります。また庭の彩りということでも、野鳥たちの餌になるということでもバードウォッチングなども楽しめるということになります。
ナツメ(実)の特徴
この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べるとリンゴのような味がして美味しく、林檎の木を育てるよりも容易ですし、またこの果実でデザートなどの料理にも利用できるというすぐれた植物です。
また色彩的にも、庭にこのような木が何本かあれば、綺麗な庭を作ることができますし、庭が狭い場合でも、あまり大きくはならないので、剪定しながら整えれば、ちょうど良い緑豊かな庭を作ることができます。ガーデニングにも最適な植物ということができます。また健康管理ということからも、昔から解熱、利尿、強壮剤効果があるということで、
漢方薬ということでも有名ですので、ガーデニングで庭に漢方薬を植えているようなものですから、その点でも非常に頼もしい植物ということになります、有名なところでは、はちみつと砂糖で、この木の実を煮て食べる、蜜ナツメなども有名ですが、ジャムなどにも甘酸っぱいので美味しくできますし、最近の料理のレシピなどでも、インターネットなどで、なつめ関係のたくさんの料理を作ることができるので、
そのような資料を参考にしながら、料理なども楽しめるということになります。そのように栽培は簡単で、美味しくて、健康にもよくて、漢方薬にもなり、料理もたくさん作ることができ、庭の彩りにもなるということでは、ガーデニングも非常に優れた植物ということができます。他の果物は何年もかかるものが多いので、それらが実るまでの繋ぎとしても面白いということになります。
-

-
植物の育て方にはその人の心があらわれます。
自宅で、植物をおいてあるところはたくさんあります。お部屋に置いておくと部屋のイメージがよくなったり、空気を浄化してくれる...
-

-
ガーデンシクラメンの育て方
シクラメンの原産はトルコからイスラエルのあたりです。現在でも原種の生息地となっていて、受粉後に花がらせん状になることから...
-

-
黄花セツブンソウの育て方
キバナセツブンソウはキンポウゲ科セツブンソウ属ということで、名前の通り黄色い花が咲きます。この植物はエランシスとも呼ばれ...
-

-
金のなる木の育て方
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなど...
-

-
オクラとツルレイシの作り方
オクラは別名アメリカネリといい、アフリカ原産の暑さに強い野菜でクリーム色の大きな美しい花の後にできる若さや食用にしてます...
-

-
バイカオウレンの育て方
バイカオウレンは日本原産の多年草の山野草です。生息地としては、本州の東北地方南部から近畿、中国地方西部などであり、深山の...
-

-
ミニバラの育て方
バラと人間との関わりは古く、およそ7000年前のエジプトの古墳にバラが埋葬されたとも言われています。またメソポタミア文系...
-

-
トウモロコシ(スイートコーン)の育て方
トウモロコシは夏になるとお店の店先に登場する夏を代表する野菜です。蒸かして食べたり、焼きトウモロコシで食べたり、つぶだけ...
-

-
エクメアの育て方
エクメアはパイナップル科のサンゴアナナス属に属します。原産はブラジルやベネズエラ、ペルーなどの熱帯アメリカに182種が分...
-

-
ベニサラサドウダンの育て方
ベニサラサドウダの大きさは、2メートルから大きいもので5メートル程度にまで生長します。若い枝は無毛で、その葉の長さは、お...




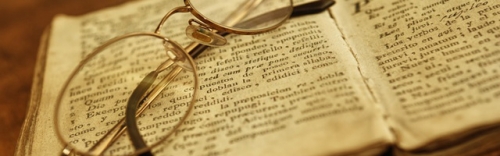





この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べるとリンゴのような味がして美味しく、林檎の木を育てるよりも容易ですし、またこの果実でデザートなどの料理にも利用できるというすぐれた植物です。