ディサの育て方

ディサの育てる環境について
ディサの育て方は一年中日光を好みますが、夏の高温は苦手です。夏は日当りが良くても高温にならない環境をつくらない限り栽培はできません。春から秋までは直射日光を避けて、できるだけ風通しの良い場所に置きます。屋外では半日陰や室内では日光の当たる場所が適しており、
0度以上に保ち、凍らせないように注意します。交雑種の中には比較的丈夫なものもあります。寒さについては、10度を下回っても大丈夫な場合もありますが、極端な低温では株が傷んでしまいます。ディサは新鮮な風に当たると良く育ちます。
閉めっきりの環境の場合では、常に換気扇などを回して空気を循環させる必要があります。生育温度は15度〜25度程度で冷涼な気候を好みます。開花期の日差しの弱い時期は日光に当てた方が花色が良くなります。夏の高温をとにかく嫌うため、夏は50%〜70%程度遮光して風通しの良い環境を作ります。
風が当たると病気にないやすいため、高いところで出来るだけ風通しの良い場所で育ててください。冬は5度以上のできるだけ暖かいところで越冬させることが大切です。ディサは5月〜6月頃に開花した株が店に出回ります。開花した株はできるだけ明るいところで、
できれば午前中の柔らかい日光に当てて育てると花色が良くなります。水を好むランなので、鉢の土は乾かさないよう鉢土が乾く前にたっぷりと水を与えます。鉢が軽くなる程度では水不足です。肥料は開花中には与えてはいけません。
ディサの種付けや水やり、肥料について
植えつけは、プラスチック鉢を使用して水苔で植えつけます。毎年は花後の秋に丁寧に彫り上げ、球根を分球して再度植えつけます。鉢内に新鮮な水が行き渡るように、鉢壁にも水抜きの穴を上げると良いです。水やりは新鮮で冷たい水を常に与えなければなりません。
水道水に含まれる残留酸素に弱いため、水道水のくみ置き水ではうまく育ちません。山の急流の流れるような不純物の少ない手を入れられないくらいの冷たい水を与えます。水質が悪いとすぐに株が腐ります。水を好むランなので、年間を通じて鉢土を乾かさないように水を与えます。
水を与えすぎて枯れることはありません。特に夏は鉢土の温度を下げるためにも多く水を与えるようにします。冬は休眠しているため水やりは控えめにします。また空中湿度を好むランでもあります。冬は乾燥するため、暖かい時間帯に霧吹きで葉に霧状の水をかけて育てることも大切なことです。
肥料は、濃い肥料を嫌います。9月中頃に植えつけてから冬の11月中旬頃まで洋ラン用の液体肥料を生育期間中に集中して与えます。主に液体肥料を規定倍率の1.5倍程度に薄めたものを施します。多くのランとは異なり、開花時期と、夏、冬の間は基本肥料は不要です。
鉢植えの場合の用土は、毛足の長い新鮮な水苔で植え込みます。乾燥を嫌うため、すぐに乾いてしまう材料は使用不可です。枯れてきた下葉は、キレイに取り除きます。そのまま放置すると株が腐る原因にもなるため注意が必要です。
ディサの増やし方や害虫について
増やし方は、株分けで増やすことで可能になります。花後の秋の早い時期に、株を鉢から丁寧に取り出し、球根を分球して増やします。植え替えは春の4月から5月頃、株分けは秋の涼しくなった9月中旬から10月上旬頃に行なうことが適しています。
枯れてしまった根を取り除き、傷んだ植え込み剤などを取り替えながら行ないます。一度開花した株は、再び花を咲かせることはなく枯れてしまいます。株元に子株が発生したら子株を丁寧にとり、ひとつずつ適度な大きさの鉢に新しい水苔に植えつけます。
根が切れやすいため慎重に行なう必要があります。根が回ったらひとまわり大きな鉢に、根鉢を崩さないように鉢増しして植え替えます。この場合、通常は来シーズンの開花は難しいです。ディサは少々病気に弱いところがあるため、専用の殺菌剤を定期的に散布して予防します。
濃いと薬害が出やすいため、薄めにして散布することが大切です。また、株元が腐りやすいため、十分注意が必要です。予防は、風通しを良くして、常に新鮮で冷たい水を与え続けることです。害虫も特にありません。ディサの属するラン科の植物は比較的病気や害虫に強いものではあります。
害虫や病気は弱った株や環境が悪い時に出やすくなるため、良い環境を整えることや元気な株を育てることが一番の予防法と言えます。特に風通しについては病気の予防には非常に大切なことです。また、早期発見で被害を最小限にとどめることが可能になるため、株は定期的にチェックすることが大切です。早期に発見することで薬剤に頼ることなく済むのです。
ディサの歴史
ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ランです。幻の洋ランと呼ばれるディサで、標高の高い湿地を生息地としており、寒すぎず暑すぎない冷涼な気候と水を好みます。
原種は120種程あり、主に店で販売されている鮮やかな色をしているものはラディサ・ユニフローラ(Disa uniflira)という南アフリカのケープ地方に生息している園芸品種です。ディサの花は鮮やかな色で、まっすぐな茎の先端に1〜数厘の花をつけます。
花もちは1ヶ月以上と長い期間楽しむことができます。切り花にしても水揚げが良く花が長持ちします。園芸的に魅力がある色彩鮮やかな大輪の種類は、南アフリカの一部に自生する種に限られ、この種をもとに各種園芸種が作られています。ディサが属するラン科は現在880属22075種はあり、
日本でも約63属170種ほど存在しています。単子葉植物の仲では最も進化した植物で、世界中に分布しており、環境に適応した多くの種類があります。ランは、歴史が古く、薬用や観賞用として使われてきました。東洋ランは日本でも古くから確認されており、
奈良時代に唐から栽培されたランが渡来したという記録があり、中国ではそれ以前より栽培されていました。洋ランは、インドと南アメリカの洋ランがヨーロッパに用いられた19世紀に、高価な植物として裕福な園芸好きの間で流行しました。
ディサの特徴
ディサはラン科ディサ属で多年草です。草丈は10〜20cm程度で、花色はオレンジ、ピンク、紫、白、黄色など鮮やかな色があります。原産地はアフリカ南部で主に南アフリカで、開花期は3月〜6月頃です。耐寒性や耐暑性は弱く落葉性です。栽培は極めて難しいランです。
冷涼な気候に生息しているため、日本の夏の高温を嫌い、夏越えが難しい洋ランで、クールオーキッドと言われています。上級者向けで開花させるのが難しい洋ランと言えます。日本での育て方は、夏は涼しく、新鮮な水がある地域でないと栽培はできません。
鉢物として、冬の終わり頃から春にかけて見かけることがありますが、日本での生産量は非常に限られており、本州では殆ど目にすることはありません。海外から切り花として輸入されることはあり、珍しい花材として人気があります。日光は好みますが、高温に弱いため、
春から秋の生育期は屋外の風通しの良い30%の遮光下に置きます。暑さに弱いため真夏は室内で約70%の遮光をして、25度以上にならないようにエアコンなどを使用して、風通しの良い場所に置き、少しでも温度を下げるよう工夫が必要です。
冬は室内で、日の当たる場所に置き、冬は最低でも5度以上を保つように注意します。99種類が熱帯やアフリカ、南アフリカ、マダガスカルのあたりを生息地としています。熱帯のランのように思われがちですが、暑さや寒さに弱く、交配により花の大きいものや花色も増えています。
-

-
ポットマムの育て方
この花の種類としてはキク科になります。デンドランセマ属に類することになります。多年草で、枯れることなく毎年咲かせることが...
-

-
ヘミグラフィスの育て方
特徴としてはキツネノマゴ科の植物になります。和名としてはその他にはヒロはサギゴケ、イセハナビと呼ばれることがあります。葉...
-

-
クレマチス(四季咲き)の育て方
クレマチスは、キンポウゲ科センニンソウ属(クレマチス属)のこといい、このセンニンソウ属というのは野生種である原種が約30...
-

-
ミニトマトの育て方について
ナス科のミニトマトの育て方について、ご紹介します。ミニトマトは、ビタミンCとカロテンを豊富に含んでおり、そのままでサラダ...
-

-
スミレの育て方
スミレの原産国は、北アメリカ南部になります。種類が豊富であるため、生息地としても種類により、適した環境で花を咲かせていま...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
ハクチョウゲの育て方
ハクチョウゲの特徴は、何と言っても小さくて可愛らしい花を咲かせる事ではないでしょうか。生長が早い植物ですが、刈り込みもき...
-

-
カリフラワーの育て方
カリフラワーはブロッコリーが突然変異で白くなったもので、原産地は地中海沿岸です。ブロッコリーと同様野生のカンランから派生...
-

-
クルクマの育て方
クルクマは歴史の古い植物です。原産としての生息地がどこなのかが分かっていないのは、歴史が古すぎるからだと言えるでしょう。...
-

-
アジサイの育て方
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるもの...




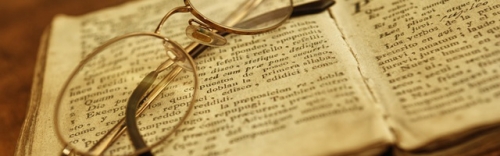





ディサは、ラン科ディサ属、学名はDisaです。南部アフリカを中心とした地域が原産で、そのエリアを生息地としている地生ランです。ディサはラン科ディサ属で多年草です。草丈は10〜20cm程度で、花色はオレンジ、ピンク、紫、白、黄色など鮮やかな色があります。原産地はアフリカ南部で主に南アフリカで、開花期は3月〜6月頃です。耐寒性や耐暑性は弱く落葉性です。