ナンテンハギの育て方

育てる環境について
ナンテンハギを育てるための環境について述べていきます。しかしながら、結論からいうと、ナンテンハギを育成するために特別な環境を整える必要はありません。つまり、決まった育て方はありません。実際に野生で自生しているものを観察するとすぐわかりますが、どこでも生息しています。
日本の北海道から九州まで幅広く自生しているので、特に寒さに弱かったり、暑さに弱いといったことはありません。日本中のいたるところに歴史的に生息しているので、日本原産の植物のひとつと言っても過言ではありません。ナンテンハギを育てたいという人にお勧めするのが、日当たりの良いところに安置することです。
日陰のところでも育ちますが、育成結果が異なります。日当たりの良いところのほうがよく育ちます。よく育った場合は1メートルくらいは伸びます。自然の中で生息しているものは、田畑や山地に生息していることが多く、人が生活しているところで言うと、里山の草地などが挙げられます。このように、どこでも生息することができるので、特別に育成するための環境は整えなくても、しっかりと育ってくれます。
もちろん、水やりや豊穣な肥料があれば、より成長に拍車をかけますので、効果的である事は言うまでもありません。もし田畑を持っている人であれば、野焼きされた後の草地がお勧めです。それというのも、ナンキンハギの絶好の生育環境ということができるからです。実際に野焼きされた草地でよく見かけます。花も非常に多く咲きます。
種付けや水やり、肥料について
ナンキンハギの種付け、水やり、肥料について書いていきます。種付けについては、特別にやることはありません。強いて言うならば、密集させておけば良いです。密集させておけば、ナンキンハギ自身が勝手に受粉します。そうすると、どんどん増えていきます。しかしながら、これはきちんと肥料をあたえた場合です。
肥料については後述しますが、ナンテンハギは基本的には花がたくさん咲きますが、栄養不足になると、その中の種子の数が非常に少ないです。もちろん、害虫に食べられることもありますが、肥料をきちんと与えておけば上記のようなことはありません。水やりについては、定期的にやることをお勧めします。
いわゆる弱い植物ではないので、放っておいても育ちますが、念のために水をやると確実に成長します。肥料については、土と石灰を混ぜ合わせたものが最も成長を促します。これは、ナンキンハギはアルカリ性の土壌を好むからです。こうした肥料で育てられたナンキンハギは非常に良く成長しますので、食べ物や薬草として育てている人には、
効果的な育成方法です。信州地方では、山菜料理でよく用いられることが多いので、こうした地方では石灰を混ぜたオリジナルの土壌を使って育てています。こうした土壌で育てたあとに、採取します。採取時期としては秋頃が一般的です。秋頃になると開花期になるので、全草を採取して水洗いして日干しにします。このようにしてから、薬草なり食用なりに使うわけです。
増やし方や害虫について
ナンキンハギの害虫について述べていきます。害虫としてはアブラムシが挙げられます。アブラムシはよく集まり食べてしまいます。また、時期によっては卵を産み付けるので、これは成長を阻害する要因になります。最もひどい場合は、枯死してしまうケースもあります。こうしたことから、アブラムシは栽培上、非常に危険な存在です。
このようなアブラムシ対策としては、天敵を置くことが効果的です。アブラムシの天敵はテントウムシです。テントウムシはアブラムシを主食としますので、テントウムシを1匹か2匹程度、飼っておくことをお勧めします。これ以外にもアブラムシ対策としては、牛乳も効果的です。牛乳をかけるとアブラムシは嫌がりますので、もしアブラムシが集まっていたら牛乳できちんと対策しましょう。
他にも害虫としてはバッタが挙げられます。バッタは主に草を食べるのですが、ナンキンハギの葉を特に好みますので、近くにくると集まってきます。この対策としては、天敵をわざとおいておくことが効果的です。バッタの天敵はカマキリなので、近くにカマキリをわざと置いておくと葉を食べにきたバッタ対策になります。
他には蝶が害虫になります。蝶自体は食べることはしませんが、その幼虫が葉を食べて成長します。その蝶の代表例はアサマシジミです。この蝶の幼虫はナンキンハギで育ちます。最後に、増やし方についてですが、これは石灰を混ぜた土を肥料としたら、あとは自然に受粉して増えます。
ナンテンハギの歴史
ナンテンハギの歴史について、あまり多くの人に知られていないので、ここでは詳しく詳説していきます。そもそもナンテンハギは、日本の各地に自生しています。つまり、北海道はもちろん、本州、四国、九州のさまざまなところに自生しています。日本以外にもアジア関係でいうと、朝鮮半島や中国にも自生しています。
おもに山野に生息していることが多いマメ科植物の多年草です。それでは、このナンテンハギの歴史について書いていきますが、まずは名前の歴史について言及します。この植物の名前の由来は、葉がナンテンの葉に似ていることから、この名前がつけられました。別名としてフタバハギとも言われています。
このナンテンハギの若葉は昔から山菜として利用されてきました。特に柔らかい若芽は、天ぷらや揚げ物にして食べたりしていました。花はドレッシングをかけて食べたりしていました。また、おひたしとして使われて食べられることも多かったです。ちなみに、中国でも歴史的に疲労回復用の薬草として服用されてきました。
その場合は、水と一緒に1日に数回飲むことが推奨されてきました。最近では、信州地方でよく栽培されており、お土産の加工品や山菜料理に使われてきました。この地方では昔からナンテンハギの若芽をアズキナと呼んできました。煮たときの香りがアズキを煮たときの匂いと似ているということから、こうした名前で呼ばれてきました。今でもこの地方では、盛んに栽培されています。
ナンテンハギの特徴
ここでは、ナンテンハギの特徴について言及していきます。ナンテンハギの特徴は次のとおりです。高さについては、1メートルに満たないものが多く、せいぜい50センチから70センチ程度が通常の高さです。植物の分類としては、多年草に分類されマメ科に属します。ただし、普通のマメ科ではありません。
ナンテンハギはマメ科でありますが、他のマメ科の植物がツルを使って他の植物に頼ることで立つ植物であるのに対して、そうしたツル性植物のように頼ることなく、硬い茎でみずから立ちます。花については、6月、7月、8月といった夏にかけて咲きます。だいたい2、3センチのものが葉の付け根につくことが多いです。色はむらさき色です。
繁殖力が非常に強いというのも、この植物の特徴です。生息地については、北海道から九州に広く分布しますが、そうした地方の平地から低山の原っぱや荒れ地に生息しています。日陰というよりも日当たりのよいところに生えています。生息しているところから見ると、山菜と見られるよりも、雑草と見られることが多く、しばしばそのように呼ばれてもいます。
関東地方では、畑や土手周りでもよく見られる植物です。もちろん、雑木林にも自生していて、野生のものがよく見かけることが多いです。山菜としては、舌触りが非常によく味わいもあります。そのため、てんぷらや揚げ物で食べることもお勧めですが、古くから、お浸しで食べられることが伝統になっています。
-

-
ハゴロモジャスミンの育て方
ハゴロモジャスミンの原産地は中国雲南省ですが、現在では外来種としてニュージーランドやアーストラリアなども生息地となってい...
-

-
トロリウスの育て方
”トロリウス”とは、ヨーロッパや北アジアを原産とした宿根多年草です。キンポウゲ科、キンバイソウ属になり別名キンバイソウと...
-

-
モンステラ(Monstera spp.)の育て方
モンステラはサトイモ科に属するつる性の植物です。アメリカの熱帯地域を原産とし、約30種の品種が分布しています。深いジャン...
-

-
バーゼリアの育て方
バーゼリアのいくつかの特徴を挙げていきます。植物としては、常緑低木に分類されます。開花時期としては、春頃です。4月から5...
-

-
ミルトニオプシスの育て方
花の種類としては、ラン科、ミルトニオプシス属になります。園芸の分類としてはランになり、多年草として楽しむことが出来る花に...
-

-
ペンツィアの育て方
特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次...
-

-
サワギキョウの育て方
キキョウ科の多年草で,アジア東部の冷温帯を生息地としている”サワギキョウ”。学名”Lobelia(ロベリア)”とも呼ばれ...
-

-
スイートマジョラムの育て方
スイートマジョラムは、ギリシア神話の愛と美の女神アフロディーテが創り出し、太陽の光をよく受けて育つように山の上に植えたと...
-

-
ミズナの育て方
水菜の発祥地は静岡県小山町阿多野といわれており、JR御殿場線、駿河小山駅近くに水菜発祥の地を記した石碑が立っています。静...
-

-
スイートアリッサムの育て方
スイートアリッサムはアブラナ科ニワナズナ属の多年草です。高温多湿や寒さに弱い性質があり、大半が夏場に枯れてしまうので、日...




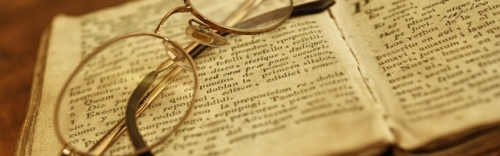





ナンテンハギはマメ科でありますが、他のマメ科の植物がツルを使って他の植物に頼ることで立つ植物であるのに対して、そうしたツル性植物のように頼ることなく、硬い茎でみずから立ちます。花については、6月、7月、8月といった夏にかけて咲きます。