ケショウボクの育て方

育てる環境について
ケショウボクは強い直射日光を避け、明るい日陰で育てるようにします。特に夏の日差しは強すぎるので注意が必要です。日除けを使って遮光したり、日陰に移したりして工夫してあげましょう。ケショウボクは熱帯性の植物ですので耐寒性はあまりありません。
その為、冬の間は室内に取り込んで管理するようにします。出来れば10度以上を保てるような暖かい場所に置いてあげましょう。最低でも5度以上は必要です。もしあれば、温室などで管理してあげるといいでしょう。大きめのホームセンターや園芸店などでは
組み立て式のコンパクトなタイプのビニール温室も販売されています。安価で簡単に設置出来、折りたたみ式のものなどもあります。場所も殆どとらないので、こういうものを使用してみるのもお勧めです。根詰まりを防止するためにも、2〜3年に一度くらいの割り合いで植え替えをしてあげましょう。
適期は4月〜6月頃です。用土は水はけのいいものを好みますので、鹿沼土、ピートモス、パーライトを等量混ぜあわせたものを使用するようにします。生育期には肥料が必要になりますので、あらかじめ堆肥や腐葉土などを混ぜ込んで元肥としておくのもよいでしょう。
加湿気味になると根腐れや立ち枯れの原因になりますので、排水性には気をつけましょう。その為、大きめの鉢は避けた方が無難です。ダレシャンピア・ディスコレイフォリアは適宜誘引して栽培します。伸びすぎた部分は切り戻してあげるようにします。
種付けや水やり、肥料について
ケショウボクは花が終わった頃に種をつけます。うまく採取出来たら、春か秋ごろの暖かい時期にまいてあげるといいでしょう。ケショウボクは生育期にはとてもよく水を吸います。春から秋までは表土が乾いたらたっぷりと水を上げるようにします。
乾燥には強い方ですが、多湿には弱いので、土を触ってみて湿り気がある内は水やりを控えるようにしましょう。また、冬になると休眠期に入り、生育が止まり気味になりますので水も殆ど必要ありません。気温が下がってきたら徐々に水やりの回数を減らしていきます。
寒い間は乾かし気味にして育てるようにしましょう。ケショウボクは非常に肥料を好む植物です。そのため、生育期には定期的に肥料を与え、切らさないようにします。植え替えの際にはしっかりと元肥を与えておくのもポイントです。暖かくなってくると新芽が伸びてきて、より多くの養分を必要とします。
新芽の成長を促し、しっかりとした枝にするために即効性のある液体肥料を一週間〜10日に一度くらいの割り合いで与えてあげるようにします。新芽がある程度成長してしまうと、開花します。開花時から秋ごろまでは、株元に緩効性のある固形肥料を
2ヶ月に一度くらいの割り合いで置き肥してあげるとよいでしょう。その際、固形肥料と株が直接当たらないように注意し、周りに埋め込むようにします。チッ素、リン酸、カリウムの3要素が等量含まれる肥料がお勧めです。冬の間は肥料も控えめにします。
増やし方や害虫について
ケショウボクは種まきと挿し木によって増やすことが出来ます。種まきで増やす場合は花後に種を採取してまいてあげます。挿し木で増やす場合、挿し穂が腐りやすくなりますので高温の時期は避けます。5月〜6月、もしくは9月〜10月頃に行うのがよいでしょう。
芽がしっかりと付いた、比較的丈夫な枝を5〜7センチ程度の長さに切って、挿し穂にします。ケショウボクの汁はかぶれることがありますので、茎や葉を切るときは手袋などをして直接触らないように気をつけましょう。葉から水分が蒸発してしまうのを防ぐために、
上部2〜3枚の葉だけを残して、残りの葉は落としておきましょう。30分〜1時間ほど水を入れたコップなどに挿して水揚げをしておきます。これによって挿し穂の乾燥予防になります。水の代わりに薄めたメネデールに浸けておくのもよいでしょう。
十分に水を吸わせたら、バーミキュライトや、小粒の鹿沼土など、排水性の良い清潔な用土に切り口を挿してあげます。挿し木の間は肥料は一切与えないようにしましょう。親株と同じ用土は使用しないでください。挿し木用の用土も販売されていますので、それを利用してもよいでしょう。
用土に挿す際、切り口の部分にルートンなどの発根促進剤を塗っておくと、より発根しやすくなります。発根するまでは明るい日陰に置いて管理します。乾燥しないように、定期的に霧吹きなどで用土を湿らせてあげましょう。発根が確認できたら鉢上げをして育てていきます。
ケショウボクの歴史
ケショウボクはダレシャンピアという名前で流通していることも多い、トウダイグサ科ダレカンピア属の常緑低木です。メキシコから熱帯アメリカ地方が原産です。成長が遅いので、鉢植えにして鑑賞するのが一般的です。ダレシャンピアという名前は植物学者のダレシャンからつけられたと言われています。
ダレシャンピア(ダルシャンピアともいう)属の植物は熱帯アメリカ地方に約100種類ほど生息しています。日本でよくみられるのはダレシャンピア・レーツリアナという種類で、明治時代にメキシコから伝わってきたと言われています。背丈は30センチ〜1メートルほどで、小さい苗の時からも開花します。
一定の気温が保たれていれば一年中開花するので、温室などで育てると長く楽しめます。またフウチョウガシワと呼ばれることもあります。ケショウボクにはもう一つツル性のタイプもあります。ダルシャンピア・ディオスコレイフォリアと呼ばれる品種で、こちらは常緑性のツル性植物です。
ケショウボクよりも葉や花が大きめになります。ツルは2〜3メートルまで伸びますので、鉢植えにして支柱を立ててアサガオの苗のようにあんどん仕立てにして鑑賞するのが一般的です。こちらはパープルウィングという名前で流通することもあります。
いずれも特徴的な樹形をしており、インパクトがあり、観賞価値も高い植物です。病気や害虫にも強く、特に難しい手入れも必要ありません。育て方は簡単ですので初心者の方でも育てやすい植物といえるでしょう。
ケショウボクの特徴
ケショウボクは熱帯アメリカを主な生息地としている熱帯性の植物です。その為、高温に強いのが特徴的です。成長が遅くて、あまり大きくなり過ぎないので、剪定などをして上げる必要も殆どありません。見た目が印象的ですので、鉢植えにして観賞用として人気があります。
ケショウボクの葉は深い緑色で、独特な倒披針形をしています。縁が波打っており、交互に生えています。葉脈もハッキリとしており、長さも10センチ〜20センチほどと、比較的長めです。6月〜10月頃には花を咲かせます。ケショウボクの花そのものは小さくて目立ちませんが、芳香があります。
主に雌花、雄花、不稔性花群で構成されています。花が目立たない代わりに、薄紫〜ピンクがかった2枚の総苞と呼ばれる部分が花のように見えるのでとても綺麗です。総苞は葉が変形したもので、花部分を包むような形になっています。
ピンクと濃い緑のコントラストが美しく、落ち着いた雰囲気のある植物です。ダルシャンピア・ディオスコレイフォリアはケショウボクとはまた違った趣があります。葉の形が特徴的で、ハート型をしています。くっきりとした葉脈があり、濃い緑色をしています。
こちらはケショウボクよりも若干紫がかった苞をつけます。ツルを誘引することが出来、なおかつ比較的日光に強い方ですので、フェンス等に巻きつけて育てることも出来ます。いずれもある程度の気温を保つことで年中開花を楽しめるのも嬉しいポイントです。
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
マイヅルソウの育て方
こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ていま...
-

-
ヤマイモの育て方
ヤマイモとナガイモは、よく混同されますが、まったく別の種類で、ナガイモは元々は日本にはなく、海外から入ってきた芋というこ...
-

-
サザンカの育て方
サザンカは、元々日本に自生している植物です。ツバキとは種が異なりますが、属のレベルではツバキと同じですから、近縁種だと言...
-

-
ブルーデージーの育て方
ブルーデージーは、キク科フェリシア属であり、このキク科フェリシア属は熱帯から南アフリカあたりを原産として約80種類が分布...
-

-
ヒポエステスの育て方
ヒポエステスは南アフリカのマダガスカル島が原産と言われており、他の生息地としてはユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱...
-

-
カラスウリの育て方
被子植物に該当して、双子葉植物綱になります。スミレ目、ウリ科となっています。つる性の植物で、木などにどんどん巻き付いて成...
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...
-

-
カモミールの育て方について
カモミールはハーブの一種です。ハーブというのは、食用や薬用に用いられる植物の総称です。人の手が必要になる野菜とは異なり、...
-

-
シロバナタンポポの育て方
シロバナタンポポの特徴は、花の色が白色であることです。舌状花の数は他のタンポポと比べると少なく、1つの頭花に100個程度...




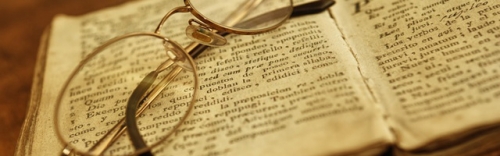





ケショウボクはダレシャンピアという名前で流通していることも多い、トウダイグサ科ダレカンピア属の常緑低木です。メキシコから熱帯アメリカ地方が原産です。成長が遅いので、鉢植えにして鑑賞するのが一般的です。