イオノプシスの育て方

育てる環境について
イオノプシスは元々が亜熱帯地域に生息しているため、耐寒性はあまりありませんが、耐暑性はあります。日当たりの良い場所を好むので、常に風通しの良い日向で育てるようにしましょう。夏の間の直射日光は強すぎますので、半日向に移すか、軽く遮光してあげるようにしましょう。
冬は寒さに弱いので日光の良く当たる室内に入れて管理するようにします。着生植物ですので、鉢植えやコルクなどに着生させて栽培します。2号程の素焼きの植木鉢に株をそのまま入れておけば、鉢に着生して育ちます。他に用土などは必要としません。
コルク着生もお勧めです。水はけがよく、腐りにくいので植え替えの必要がありません。見た目も面白くなりますし、インテリアにもピッタリです。新芽が伸び始める時期に行うのがお勧めです。傷んだ部分を綺麗に取り除き、どのような形で着生させるかを考えながら、
針金やビニールテープなどで固定していけば大丈夫です。保湿性が気になる場合は根本に新鮮な水苔を少量足してあげてもよいでしょう。園芸用のコルクを販売してるところもありますので、いろんな形のコルクに着生させてみるのも楽しいかもしれません。
水苔やバークを使って植えることも出来ますが、多湿になって腐りやすくなりますので注意が必要です。また水苔は長く使っていると腐ってきますので、定期的な植え替えが必要です。偽球茎が増えてきて鉢から溢れてきたら植えかえてあげましょう。古い水苔を丁寧に取り外し、小さめの鉢に新しい水苔と一緒に植え替えます。
種付けや水やり、肥料について
イオノプシス属は偽球茎の部分にある程度の水分を蓄えることも出来ますので、乾燥にも強い植物です。水分が多すぎると株が弱り、腐ってしまうこともありますので、比較的乾燥気味にして育てるようにします。特に水苔を使用しているときは水分が溜まりやすくなってしまいますので注意が必要です。
植え付けている材料、土台が乾いてきたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。乾燥気味を好むというよりは、水はけを好むといった方がいいかもしれません。水が一定の場所にたまらない状態にすることが重要ですので、そのためには常に風通しをよくしてあげることもポイントです。
植木鉢で育てている場合にも、鉢の受け皿は使用しないほうがよいでしょう。素焼きのハンギングバスケットや、鉢カバーなども販売されていますので、吊るして管理してあげるのも効果的です。冬の間は休眠期に入ります。耐寒性があまりないので、最低でも5℃~10℃の暖かい室内で管理するようにします。
水やりも殆ど必要としません。乾いている状態からさらに2〜3日経過した後に水を与える程度にしておきます。肥料は5月〜9月頃には規定量のさらに2倍に希釈した液体肥料を週に一度くらいの割り合いで与えるようにします。
この際も株にさっとかける程度にしておきましょう。水苔を使用して栽培している場合は緩効性のある固形肥料を置き肥しておいてもよいでしょう。冬の間は休眠期になりますので、肥料は与えません。かえって株を傷める原因にもなります。
増やし方や害虫について
イオノプシスは株分けによって増やすことが出来ます。偽球茎の部分の数が増えてきたら、その部分を使って株分けをします。時期は植え替えの時期と同じ頃に行います。一株に付きえ偽球茎が3個ほど付いている状態を目安にしてナイフなどで切り分けます。
素焼きの鉢などにそのまま入れておきます。その際に、根を張りやすいように鉢の破片などを鉢の3分の1の高さくらいまで入れておくとよいでしょう。暫くの間は半日陰で葉水を与えながら管理するようにします。ただし、イオノプシスの株分けは容易ではありません。
細かく分けすぎると花を付けなくなることもありますので、なかなか増やしにくい植物であるといえます。害虫には強い方ですが、たまにアブラムシやカイガラムシがつくことがあります。せっかくの株を弱めてしまいますので、見つけ次第早めに駆除するようにしましょう。
アブラムシはテープを使って取り除くことも出来ますし、専用の薬剤で殺虫するようにします。牛乳やトウガラシの煮汁を冷ましたものなどをスプレーすることによっても駆除できます。カイガラムシは薬剤が効きにくいので歯ブラシや竹べらなどを使ってこそぎ落とすようにしましょう。
また、たまにうどんこ病を発症することもあります。白い粉をまぶしたような状態になってきたらうどんこ病の可能性があります。植物の光合成を阻害して栄養分を吸い取ってしまい、枯らしてしまいます。オルトランなど、うどんこ病に効果的な薬剤を早めに散布してあげましょう。
イオノプシスの歴史
イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島まで広まりました。標高が高く、冬に乾燥する落葉樹林などを主な生息地としています。イオノプシスという学名はスミレという意味の
ionと似るという意味のopsisからつけられており、その花弁の色と形は確かにスミレに似ています。イオノプシスの中で最もメジャーなのがイオノプシス・ウトリキュラリオイデスという品種で、白やピンク色の非常に華やかで美しい花を咲かせます。
ラン科に属していますので、ランのような広がった唇弁を広げます。ただし、こちらは一般的に栽培されているほど大きなランのような花ではなく、背丈も20センチほどと低めで、小ぶりの花を密集させて咲かせます。全体的にコンパクトな植物ですが、
スラリと伸びた茎から垂れ下がるようにたくさんの花が咲く様はとても見事でとても見応えがあります。残念ながら、あまり一般的な園芸店では取り扱われていません。洋ランの専門店でもあまり見られませんが、まれにインターネット通販やオークションなどで出品されていることもありますので、
まめにチェックしてみられるとよいでしょう。黄色い花をつけるオンシジウムと属間交配されたイオノシジウムという交配種は、園芸品種として園芸店でも入手できます。イオノシジウムはオンシジウムの黄色い花を引き継いでいるので、黄色っぽい花を咲かせることもあります。
イオノプシスの特徴
イオノプシスはラン科の着生植物です。着生植物というのは、土壌に根を張らず、他の木や岩などに根をつけるタイプの植物です。イオノプシスという属名はあまり知られておらず、オンシジウムという名前で取り扱われていることもあります。小さな偽球茎と言われる貯蔵器官を持っており、
この部分に水分や栄養素を蓄えています。葉は細く、長めで、光沢があります。イオノプシスは2月〜4月頃、偽球茎の内側から伸びたスラリとした花茎の先に小さな花弁をたくさんつけるのが特徴的です。ガクと側花弁は小さめで、唇弁部分だけが大きく広がった形をしています。
色は白やピンクで淡いものが多く、ふわふわとしていて柔らかい花びらはとても可憐な印象があります。ハート形を逆さにしたような可愛らしい形の花がたくさん垂れ下がる様子は必見です。イオノプシスは観賞価値が非常に高い花であるといえるでしょう。
イオノプシスとオンシジウムの交配種はイオノシジウム・ポップコーンというものがあります。イオノプシスよりも若干大きめの株になります。色がより多彩で、大きめになるのでより人気があります。イオノプシスよりも入手しやすい上に、育て方も簡単な品種です。
和洋どのようなインテリアにもピッタリとマッチしてくれるのもラン科の特徴といえるでしょう。小さめの鉢でも栽培できる手軽さも人気のポイントです。一鉢でも十分な存在感をかもしだしてくれるので、お部屋のアクセントにはピッタリです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エゾエンゴサクの育て方
-

-
ゴデチアの育て方
ゴデチアは、アカバナ科イロイマツヨイ族の植物の総称です。現在では、北米西海岸を生息地の中心としており、20種類もの品種が...
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
スターアップルの育て方
スターアップルは熱帯果樹で、原産地は西インド諸島および中南米です。アカテツ科のカイニット属の常緑高木です。カイニット属と...
-

-
ステルンベルギアの育て方
ステルンベルギアの名前の由来は19世紀に活躍したオーストラリアの植物学者であるシュテルンベルク氏に因んだものです。他にも...
-

-
フロックスの育て方
フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の植物の総称で、現時点で67種類が確認されています。この植物はシベリアを生息地と...
-

-
アスクレピアスの育て方
アスクレピアスという花は、その色合いが赤とオレンジの色合いが綺麗に混ざり合い、その為に太陽などと引き合いに出される事もあ...
-

-
ギボウシ(ホスタ)の育て方
ギボウシは別名、ホスタという名前で古から世界中で親しまれています。もともとは、ギボウシは日本の里山のあらゆるところに自生...
-

-
ロドリゲチアの育て方
花の特徴としてはラン科になります。園芸上においてもランとしてになります。一般の花屋さんでも見つけることができますが、ラン...
-

-
トケイソウの育て方
原産地は、北米、ブラジルやペルーなどの熱帯アメリカです。パラグアイでは国花とされています。現在、園芸に適した品種として知...
-

-
アサリナの育て方
アサリナは、つる性植物です。小さな花を付け、その色も白、ピンク色、黄、紫、青といった複数の色があります。また、つる性植物...




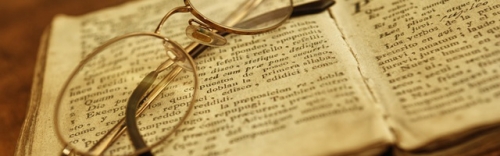





イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島まで広まりました。標高が高く、冬に乾燥する落葉樹林などを主な生息地としています。