ヤマハギの育て方

育てる環境について
ヤマハギは山に自生する所からも分かる様に、それ程環境に対して気を使う必要はありません。実際に育てる場合は庭でも十分育てる事が出来ます。ただどんな環境でも良く育つかと言ったら決してそうではありません。自生している場合は良いのですが、庭などで育てる場合は環境作りをしっかりと行う事をお勧めします。
その方がよりよく成長していくからです。まず一つは日当たりが良い所です。太陽の光が当たる方が良く成長していくからです。もし木の下等に植えると言う時は、なるべく日中に日が当たりやすい所に植えます。もう一つは水はけが良い環境と言う事です。あまり水が溜まっている場所等の場合はどうしても根腐れを起こしてしまう可能性が出てくるので注意します。
栽培する時はなるべく水はけが良い土壌を用意して、そこに植える事が必要です。植木鉢などで育てる時は、予め水はけが良い所に植えます。地面に直接植える場合は、その場所の土を改良する事が出来るとベストですがなかなかできない事も少なくありません。あまり水はけが良く無さそうだと感じた時は、
出来るだけ少し斜面になっている所に植える事が重要です。そうする事で水はけがあまり良くないと言う問題を解決する事が出来ます。寒さや暑さなどを気にする必要はなく、日本であればその環境下でしっかりと育てる事が可能です。やや乾燥にも強い種類の植物なので、こまめに水やりをする必要はありません。そのまま育てていてもしっかりと育って行ってくれます。
種付けや水やり、肥料について
萩と言えば、さやに包まれた種を付けるのが一般的で、ヤマハギも例外ではありません。さやの中には1つ種が入っています。他のハギ類と同じつけ方をしています。ジメジメとした環境を好む植物ではないので、基本的には水はけが良い所に植える必要があります。ある程度乾燥している状態でも十分育てる事が出来るので、しっかりと水やりをする必要はありません。
少々忘れてしまったとしても、すぐに枯れてしまう心配は皆無です。ただ、株分けをして植えたばかりの時は話は別で、しっかりと水やりをする必要があります。ある程度成長してしっかりと根が付いたら、後はからからに乾いてきたらある程度水を与える程度で十分です。反対に、水をやり過ぎるのは実は良くないので注意が必要です。
植物の中には朝晩水やりをする必要がある物も多々ありますが、ヤマハギはそういった類の植物ではありません。強いて言えば、夏場の暑い時、地面がすぐに乾燥してしまう時期だけはこまめに水やりをする方が良い場合もあります。基本的には厳しい環境であってもしっかりと育つ丈夫な植物です。
そのため、肥料を特別与える必要はなく、そのまま放置しておいたとしても何ら問題はありません。もし与える場合は、緩効性の粒状の肥料を少し与えます。ただこれは地面に植えている時の話であって、植木鉢などで育てている時は基本的には肥料を与える必要は全くありません。時々様子を見て水やりをすれば大丈夫です。
増やし方や害虫について
ヤマハギは種を付ける植物なので、種まきをして増やすと思う人もいるかもしれませんが、実際にはその様にして増やす訳ではありません。細い木なので、簡単に挿し木で増やす事が出来ます。古い枝の場合は3月頃に挿し木をします。また新枝の場合は7月頃に挿し木をして増やすのが一般的です。ただそれ以外にも増やし方があります。
それが株分けです。どの方法だから良いと言う訳ではないので、自分が最も行いやすい方法で行えば大丈夫です。とても丈夫な木なので、基本的には殆ど害虫が付いてしまう事はありません。そのため、とても育てやすい植物となっています。ただ100%害虫の心配がないかと言ったらそうではありません。
大体3月から4月頃、新芽が付く時期になるとアブラムシが付着してしまう事が有ります。少量しか付いていない場合は簡単に駆除する事が出来ますが、大量についているとどうしても簡単には駆除できません。そういうときは薬剤を使って駆除する事が重要です。そうすれば大量についていたとしても心配する必要はありません。
そのまま付着させておくと、生育にも影響を及ぼしてしまう事があるので注意が必要です。ヤマハギ自体はそれ程こまめに手入れをする育て方をしなければいけない植物ではなく、ある程度放置しておいたとしても困るような物ではありません。ただ問題が発生した時はなるべく早く対処する必要があります。出来るだけ良く成長させる為にも、病害虫対策はしっかりと行っておきます。
ヤマハギの歴史
秋の七草のひとつがヤマハギです。万葉集や他の歌に詠まれる事も多々あった植物で、古くから日本人に親しまれてきました。書物には「萩」とだけ書かれる事が多々あり、マルバハギなど他の萩ではないかと思う人もいるかもしれませんが、こうした書物に書かれているのは全てヤマハギだと考えて差し支えありません。
それ位、日本人にとっては身近で、どこでも見る事が出来る植物でした。様々な日本の文学に登場するヤマハギは、日本では北海道から九州まで、さらに海外では中国などを原産地としている落葉半低木です。通常は良く刈り取られる事があるので、それ程高い背丈になる事はありませんが、刈り取られずに自生している場合はかなりの高さまで成長する事も有ります。
名前から山を生息地としているイメージを抱かれる事も有りますが、実際には平地でも沢山見られる植物です。しかし、十数年前までは色々な所で見られる事が有ったヤマハギですが、実は最近その個体数を減らしているのが現状です。そのため、宅地などで開発が進んだ場所では、自生している物を見る事がかなり減りました。
ただ、今では自宅の庭に植栽している人も見られるので、絶対に宅地で見る事が出来ないと言う訳ではありません。一般的には萩と言う名前で呼ばれる事が多い植物です。その名の由来は、古いかぶから新芽が芽吹く「生え芽」から萩と呼ばれる様になったとも言われています。ただ、これはあくまでも一説でありそれ以外にも様々な説があります。
ヤマハギの特徴
植物の中には生息地が限られている物も珍しくありません。しかしヤマハギはそういった事がなく、日本全土の野山に自生しています。そのため、都市部や宅地造成された所ではあまり見る事が出来なくなっていますが、少し山の方まで行けば簡単に見る事が出来る植物です。一般的にヤマハギと言うとそれ程背丈も高くない植物だと思われる事が有りますが、実はそうではありません。
そのまま上部を刈らずに成長させると、大体2m程度までは大きくなります。根元からは細い枝が沢山出てきて、その枝には大体1㎝から2㎝程度の歯が付いています。葉の形は卵のような形になっているのが大きな特徴です。花は紅色から紫色の花となっています。枝先に多数付いていて、それぞれの花に果実が実ります。
花自体はそれ程大きくはありませんが、沢山つくのを魅力と感じる人も少なくありません。花が開花するのは大体7月から9月となっています。基本的に萩の仲間には毒があるという報告はされていない事が多いのですが、食用にする事はまずありません。しかし昔から薬として利用してきた事が有りました。
秋、ちょうど花が咲き終わった頃に根を掘り起こします。そのままでは土が付いているのでそれを洗い流し、刻んで天日で乾かせば、婦人病やめまい、のぼせなどに効果があると言われる事も有ります。ただ大量に摂取しても良いものではなく、1日に摂取する量は乾燥した根茎を5g程度水で煎じて飲むと言うのが一般的です。
-

-
植物の上手な育て方を知る
生活の中に植物を取り入れることで、とても豊な気持ちになれます。また、癒しの効果もあって、育てていく過程も楽しめます。キレ...
-

-
ストックの育て方
原産地はインドや東南アジアで、タシロイモ科タシロイモ属の植物です。和名はクロバナタシロイモで漢字では黒花田代芋と書きます...
-

-
ローズゼラニウムの育て方
ローズゼラニウムの特徴は、やはりバラのような甘い香りです。クセのある甘ったるさではなく、ミントが混ざったようないわゆるグ...
-

-
夏野菜の育て方と種まき
今では、ベランダや小さい空きスペースを使って、自給自足生活を楽しむ人が増えています。種をまき、または小さな苗から育ててい...
-

-
ナナカマドの仲間の育て方
ナナカマドの仲間は、バラ科の落葉高木で、学名がSorbuscommixta、漢字で「七竈」と書きます。「庭七竈」は、学名...
-

-
ナンバンギセルの育て方
ナンバンギセルはハマウツボ科でナンバンギゼル属に属し、別名がオモイグサと呼ばれています。原産地は東アジアから東南アジア、...
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
フィットニアの育て方
フィットニアはキツネノマゴ科フィットニア属の植物です。南米、ペルー・コロンビアのアンデス山脈が原産の熱帯性の多年草の観葉...
-

-
コリゼマの育て方
オーストラリア原産の”コリゼマ”。まだ日本に入ってきて間もない植物になります。花の色がとても鮮やかなオレンジ色をしており...
-

-
チコリ、トレビスの仲間の育て方
チコリはキク科キクニガナ属の植物で、和名はキクニガナと言います。フランスではアンディーヴと言う名の野菜で、広く生産されて...




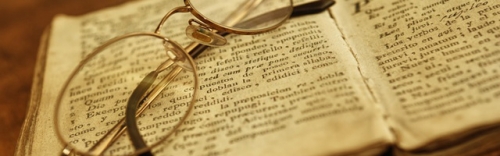





植物の中には生息地が限られている物も珍しくありません。しかしヤマハギはそういった事がなく、日本全土の野山に自生しています。そのため、都市部や宅地造成された所ではあまり見る事が出来なくなっていますが、少し山の方まで行けば簡単に見る事が出来る植物です。