ホテイアオイの育て方

育てる環境について
ホテイアオイを育てる環境についてでありますが、元々水草でもありますので、水に浮かべて育てることができます。しかし先にも述べました通り、一定の日照量が確保できない場合では枯れる可能性がありますので、可能な限り室外で育てることが理想的になります。部屋の中などでも栽培は可能な場合もありますが、日照量や光量が足りない場合では、
葉や茎に勢いが出ずに細くなり、花が開花する可能性も下がってしまいます。その他、温度的な環境と致しまして、この水草は冬季に枯れてしまう為、寒さに弱い性質があります。例えば霜は大敵であり、霜が付きますと高確率で枯れてしまいます。その為冬季の育て方では、霜に細心の注意をして育てることが大切になります。
例えば鉢で栽培する場合では、霜の影響のない屋内に置くことも一考に値します。また、庭の池などで栽培している場合では、一部を適切な容器に取り、春になってから再び池に入れることも良策になります。一方、この水草は非常に繁殖力が強くありますので、増殖しても大丈夫な場所で栽培するなど、育てる環境には留意した方が良い場合が多々あります。
仮に増え過ぎた場合では、適時間引くことも重要です。更に外来種でもありますので、栽培には一般の池や河川に影響が出ない環境で育てることが求められます。これは栽培場所から何らかの影響で溢れ出してしまい、野生化することを防ぐ為にも大切なことです。また、間引いたホテイアオイも、お住いの地域のルールに従って、ゴミとしてきちんと処分することが重要です。
種付けや水やり、肥料について
ホテイアオイの株を購入して植え付ける場合でありますと、霜を考慮する必要がない五月や六月などが適した時期になります。また、植え付けも購入した株を水面に浮かべておけば良いだけでありますので、実に手間要らずです。この植物は水草でありますので、基本的に用土は必須ではありませんが、種子から種付けする場合でありますと、底の部分に土を入れた状態で行うことも理想的になります。
自然界におきましては、種子は始めから水面に浮いている訳ではなく、水中などの土や泥に根を入れて育っていきます。そしてある程度育ちますと、葉の根元部分が膨らんで浮き袋となり、浮上してきます。この為種子から種付けをする場合では、水中にある程度の用土を入れておくことも良い方法です。一方、水やり、肥料についてでありますが、
水面に浮かべて栽培する種類でありますから、水やりという概念は特にありません。入れている水が蒸発など致しましたら、その分を補充するということになります。また肥料につきましては、特に積極的に与える必要はありません。もしも花の咲きが良くないなどの場合でありますと、
肥料などを与える場合もありますが、急激に成長したり、予想外に繁殖してしまう可能性もあります。これにより肥料を加える場合では、その点に考慮する必要があります。また、この水草は水中の泥からも養分を吸収致しますから、肥料の代わりに底の部分に土を入れるという方法もあります。
増やし方や害虫について
ホテイアオイは育て方と致しましては非常に簡単で、特に夏の時期では日照条件さえ整いましたら、基本的に随時繁殖する水草でもあります。その為、増やし方も非常に簡単な種類になります。その方法には株分けがあり、伸びてきた子株がありましたら、それをカットするだけで手軽に株分けを行うことができます。
また、この株分けを行う時期は、霜が発生しない五月から十月頃までが適しています。ただしこの水草は、水の中にある根から伸びる茎の先に新芽を出し、そこに新たなる子株を携え、その子株が更に株を作り出すという工程をループで行う性質があります。その為、増殖して収拾がつかなくなった場合では、株分け如何に関わらず子株をカットして調節する必要もあります。
一方、害虫についてでありますが、この水草にはアブラムシが付いてしまうケースが見受けられます。この場合育てている環境によりまして、多少対策が異なることになります。例えばアブラムシの数が多く、水草だけで栽培している場合では、専用の駆除剤などを用いることも可能です。
しかし、メダカなどを飼っている鉢などの水面に浮かべて栽培している場合では、駆除剤は使用しない方が賢明になります。その場合では、アブラムシの付いているホテイアオイを、水中にそっと沈めることが得策になります。そう致しますと大抵アブラムシは葉や茎から離れ、水面に浮かび上がります。後はメダカが水面に浮いたアブラムシを捕食しますので、害虫対策と致しましても有効な方法になります。
ホテイアオイの歴史
ホテイアオイという水草の原産地は南米大陸であり、現在では北米大陸や欧州やアジアなど、多くの国々を生息地として分布されています。日本におけるホテイアオイの歴史は、観賞目的として明治時代に渡来したとされています。また、メダカや金魚の飼育におきましても、卵を産み付けさせる目的で用いられてきたという歴史もあります。
一方この水草は、凄まじい繁殖力を備えていることでも有名です。田んぼなどで野生化した場合、その田んぼを荒廃させてしまうなど、そのような場合では必ずしも歓迎されてこなかった歴史もあります。更にこの繁殖力の強さが由縁となる歴史的事例は、世界の国々でも見ることができます。例えばアフリカで最も大きい湖であるヴィクトリア湖での事例もその一つです。
そこでは沿岸地域の生活などで出た排水の栄養などを得て、ホテイアオイが驚異的な繁殖を見せた為、漁船による漁業の操業に影響が出る事態に見舞われました。それらの事態を改善する為、ヴィクトリア湖沿岸の複数の国が協力して、この水草の繁殖を管理することなどを目標とした共同計画が始まった歴史があります。
また1900年代初頭におけるアメリカの一部地域では、増え過ぎたこの水草を草食動物のカバに食べさせることでエサとして活用し、そのカバの肉も食用とする計画が発案された歴史もあります。この案は結果的に採用されなかったと記されておりますが、ホテイアオイとの関わりの歴史には、凄まじい繁殖力が由来する事例も見受けることができます。
ホテイアオイの特徴
ホテイアオイの特徴は湖や池などを始め、緩い流れの川などの水辺を主な生息地として、水に浮いて育つことです。また、この水草の独特の特徴は、浮き袋を携えていることでもあります。その丸くなった葉の根元部分の形状が、七福の神の一人である布袋様を連想できることから、ホテイアオイという和名の由来になっています。
その浮き袋の部分から出ている葉自体の形状も丸みを帯びており、つややかな光沢もありますので、葉その物もこの水草の特徴の一つです。そして、夏に咲く花は少し紫色の入った薄い青色をしており、とても涼しげな美しさを見る者に与えてくれます。花ビラは六枚が基調で、主に上側の中央部分の一枚に、濃いめの紫色を帯びた青い模様が入ります。
その中心付近には更にオレンジ色を帯びた黄色系のアクセントが入っていて、綺麗なコントラストを見ることができます。一方、この水草は根の部分にも特徴があります。水の中で成長する根は、水の上の草丈よりも長く伸びていきます。その上、各々の根には多数の根毛が生えています。そして、何よりも特徴的なことはその凄まじい繁殖力であり、
主に横に広がった茎などの先で更に新しい芽を出し、そこから新規に株を形成していくことで繁殖を行います。このことで短時間の内に勢力を増やすことを実現しています。その反面、太陽の光りなどの日照に依存する傾向がとても強く、屋内などで光りを浴びる量が少ない状態でありますと、徐々に弱り始め、最終的に枯れてしまいます。
-

-
バイカウツギの育て方
バイカウツギは本州から九州、四国を生息地とする日本原産の植物になり、品種はおよそ30~70種存在し、東アジアやヨーロッパ...
-

-
フジバカマの育て方
フジバカマはキク科の植物で、キク科の祖先は3,500万年前に南米に現れたと考えられています。人類が地上に現れるよりもずっ...
-

-
アオキの育て方
庭木として重宝されているアオキは、日本の野山に自生している常緑低木です。寒さに強く日陰でも丈夫に育つうえ、光沢のある葉や...
-

-
ベンケイソウの育て方
ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多...
-

-
マムシグサの育て方
マムシグサは、サトイモ科テンナンショウ属です。サトイモ科に属するので、毒性はあるものの、用途としては、毒を取り除いて食用...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
ススキの育て方
ススキはイネ科ススキ属の植物で、秋の七草の一つです。十五夜の月見にはハギとともにススキが飾られていることが多いです。沖縄...
-

-
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)の栽培
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)は、南米原産のノウゼンハレン科のつる性の一年生です。開花時期は5月から10月過ぎる頃ま...
-

-
スノーフレークの育て方
スノーフレークは、ヨーロッパ中南部が原産です。ハンガリーやオーストリアも生息地になります。スノーフレークは、日本において...
-

-
イワギボウシの育て方
名の由来として、日本の昔の木造の付ける欄干や橋寺社などの手すりには飾りがあり、この欄干の先端にある飾りのことを擬宝珠と呼...




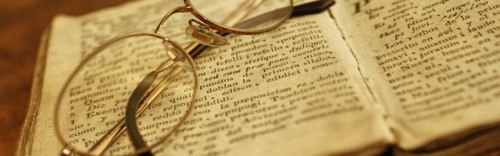





ホテイアオイという水草の原産地は南米大陸であり、現在では北米大陸や欧州やアジアなど、多くの国々を生息地として分布されています。日本におけるホテイアオイの歴史は、観賞目的として明治時代に渡来したとされています。また、メダカや金魚の飼育におきましても、卵を産み付けさせる目的で用いられてきたという歴史もあります。