ムシャリンドウの育て方

育てる環境について
ムシャリンドウは日当たりが良くて水はけのいい場所を好みます。栽培する上でそれ以外は特に注意することも無いので、比較的栽培しやすい種の部類に入ると思われます。その中でも基本的な部分はありますので、育て方は以下を参照して下さい。まず鉢は深鉢を使用すると良いです。より具体的には鉢の種類は中深鉢が適しています。
鉢内の温度の上昇を和らげるため、山野草や高山植物を育てるのに、とても適しています。鉢の中には硬質鹿沼を中心に入れるとグッドです。硬質鹿沼というのはいわゆる鹿沼土のことで軽石質の火山砂礫が風化してできた土を指します。色は黄色がかっていて粒状で販売されています。粒には大きく分けて大粒・中粒・小粒の3種類があります。
ムシャリンドウの場合はどの粒の大きさでも問題ありません。鹿沼土の特徴は肥料をほとんど含んでいないこと、そして通気性と保水性に優れていることです。ムシャリンドウは湿度を嫌うため、鹿沼土のような軽石質の土が非常に適しています。鹿沼土を鉢に入れたら、その中に軽石系の用土をさらに加えてゆきます。
一例を挙げると蝦夷砂や桐生砂、日向土などが適しています。何れも山野草向けの肥料の少ない、通気性と排水性に優れた土です。余談ですが、これらの土は保肥性に乏しいので農耕には不向きとされ、園芸用として脚光を浴びるまで見向きもされなかったそうです。持ち味を活かすという意味ではこれ以上の適役は考えられないでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ムシャリンドウに与える肥料に関してですが、全く無いよりは当然ある方が良いです。春か秋、またはその両方の季節になったら有機性の肥料を置き肥すると良いでしょう。置き肥は鉢の中の土表面に肥料を文字通り、置くやり方で主に鉢花、観葉植物などに用いられる方法です。この方法は固形でゆっくりと溶けていき、
最終的には肥料が完全に溶けてなくなってしまうタイプのものに適しています。ゆっくりと肥料が土の中に浸透していくので、ムシャリンドウのような野に咲く花には効果的です。置き肥の良いところは他にもあります。それは肥料があとどれくらい残っているかが視覚的に捉えやすいことです。
形がなくなれば溶けきったということなので、追肥のタイミングを容易に察知することができます。また、鉢の下のほうに化学肥料を入れておくのも有効です。市販の化学肥料は植物の初期生育を促進する速効性の成分に加えて、長期にわたって少しずつ溶け出してゆく緩効性の成分の両方の性質を併せ持っています。例えば雨や潅水によって肥料の成分が流れ出ることはありませんし、
植物の根が傷んだりする心配もほとんどありません。正に万能の肥料です。置き肥として使用する場合、肥料成分がゆっくりと溶け出し、肥料に敏感な植物の栽培に適応できるため、有機性固形肥料と同じ効果が期待できます。なお、水やりに関しては表土が乾いたら施す程度で充分です。休眠期は少なめににやりますが、鉢内が乾ききらない程度に水やりをすればOKです。
増やし方や害虫について
山野に自生するムシャリンドウはその個体数をかなり減らしています。特定の病害虫による被害ではなく、そこには人間の営みが大きく関わってきます。昔は家畜を飼育している農家では、家畜の餌を調達するため、早朝に草を刈り取っていました。しかしながら最近ではそのような習慣はなくなってしまった。すると草原はただの雑草はびこる荒れ地になってしまいます。
かつてのような草原を維持することができなくなりつつあります。そういった人間の生活習慣の変化によって、山野草の個体数が激減している種が多数報告されています。実のところ、このムシャリンドウもその一種です。また、登山のレジャー化も上記の現象に拍車をかけています。マナーの悪い登山客によって花は手折られ、
山頂にパラグライダーの飛行台が設置されたりなどして山の自然は容赦なく削られました。レジャー施設のある所には当然、駐車場やトイレ、土産物屋やレストランなどが建てられ、ますます山野草は摘み取られていきます。強い力、たとえば踏みつけにも弱いため、ほんの少し足の踏み場を間違えただけでムシャリンドウはあっさりと枯れてしまいます。
そのような状況も相まって現在、ムシャリンドウは絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。単純に人間の活動を批判するのはたやすい事ですし、そうやって有史以来人類は発展を遂げていきました。逆行することはもうできないでしょう。破壊の歴史を知ると同時に山野草が置かれている現実を認識する必要があるでしょう。
ムシャリンドウの歴史
ムシャリンドウという花は名前を聞けばリンドウの仲間なのではないかと考える人は多いでしょう。ですが実際は、リンドウとは何の関係も無くてシソ科の植物です。どうしてムシャリンドウという名前が付けられたのか、実ははっきりしたことはわかっていません。植物学の第一人者であり、この道の権威でもある、
かの牧野富太郎博士の書き記した書物によりますと、この花の由来は次のようなことになります。原産は日本であり、この花の種が国内で初めて発見されたのが滋賀県の武佐という場所(現在の近江八幡市の辺りです)であったこと、それに花がリンドウを連想させるからだとしています。しかしながらこの説には腑に落ちない点があります。
それならば滋賀県に大量のムシャリンドウがあってもよさそうなものですが、実際には滋賀県には自生していないことが確認されています。また、こんな説もあります。よく見ると花が武士の兜に酷似しているのでムシャリンドウの「ムシャ」とは「武者」のことではないか、とする説です。こちらの方が信憑性はありそうですが、果たして兜に似ているかと改まって言われると、首を傾げたくなります。
要するに語源に関しては様々な説があり、定説として認知されている学説はまだ存在しないということです。地名の武佐でも武者なのかどうかもわからず、リンドウの仲間ですらないのですからムシャリンドウという名前そのものが一つも実態に即していないという有様ですが、このような花は探せば、まだたくさんあるのでしょう。
ムシャリンドウの特徴
ムシャリンドウは6月~7月頃にかけて青紫色の花をつけます。花の長さはだいたい3センチ程度で、まるで唇のような形をしています。どちらかと言うと下唇の方が発達していて、花の色よりもさらに濃い紫色の斑が入っています。一見したところ、羅生門蔓(ラショウモンカズラ)という花と間違えられることが多いそうですが、羅生門蔓の開花時期は4月~5月ですし、それに葉の形もよく見るとかなり違います。
葉の形はというと葉は幅の広い線形です。もっと詳しく言うと平たくて細長く、先のほうがとがっていて、基部のほうがやや広い形をしています。いわゆる被針形という形で、しかも対生しています。対生と言うのは向かい合って生えている、ということです。また、茎は少し角ばっており、稜があるという表現を用いることがあります。
時々、葉の脇からいくつかの葉をつけた短い枝が伸びることもあります。花の後には実ができます。できる実は分果といって、ぽつぽつと小さな実がたくさんなって、まるで一つの塊のような形になります。文果というのはいくつかの子房からできた果実のことをいいます。
塊の数は決まっていて全部で4つのブロックから形成されることがわかっています。日当たりの良い山地が生息地として適しており、国内での分布は北方領土を含んだ北海道から本州の中部地方にかけて確認されています。海外では朝鮮半島や中国東北部に分布しており、なんと東シベリアのような寒冷地にも分布していることがわかっています。
-

-
リナリアの育て方
リナリアの名前の由来は生物学者だったリンネが提唱していた一つ一つの生物につけられた名前で、ギリシャ語でアマという意味があ...
-

-
カンパニュラの育て方について
カンパニュラは、釣り鐘のような形の大ぶりの花をたくさん咲かせるキキョウ科の植物です。草丈が1m近くまで伸びる高性タイプの...
-

-
アスペルラの育て方
アスペルラはクルマバソウとも呼ばれていて歴史的にはトルコの周辺が原産であるとされていて、生息地としてはアジアやコーカサス...
-

-
ヘデラの育て方
ヘデラは北アフリカ、ヨーロッパ、アジアと広い地域を生息地とする非常に人気がある常緑性のつる植物です。非常に様々な品種があ...
-

-
ホトトギスの育て方
ホトトギスは、ユリ科の花になります。原産地は日本になり、特産主として、主に太平洋側に自生する、多年草になります。主な生息...
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
スタージャスミン(トウキョウチクトウ)の育て方
スタージャスミン(トウキョウチクトウ)とは、キョウチクトウ科テイカカズラ属の植物で、学名をTrachelospermum...
-

-
アボカドの種を植えて観葉植物にしよう
アボカドというと、「森のバター」や「バターフルーツ」と呼ばれ、高脂肪で栄養価が高いことで有名です。脂肪分の80%以上が不...
-

-
ネオレゲリア(Neoregelia)の育て方
ネオレゲリアは株を植えつける植物で、種からの栽培方法はありません。株の植えつけを行う際には、ヤシの実チップや水ごけを使用...
-

-
イソトマの育て方
イソトマは、オーストラリアやニュージーランドなどの大西洋諸国にて自生している植物です。本来は多年草として知られていました...




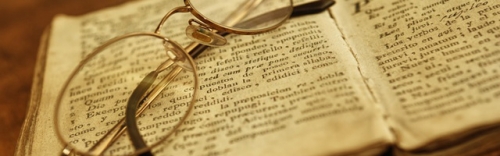





ムシャリンドウという花は名前を聞けばリンドウの仲間なのではないかと考える人は多いでしょう。ですが実際は、リンドウとは何の関係も無くてシソ科の植物です。どうしてムシャリンドウという名前が付けられたのか、実ははっきりしたことはわかっていません。