ヤナギランの育て方

育てる環境について
分布としては、ヨーロッパ、アジア、北アメリカなどの北半球が中心になります。温帯地域だけでなく寒冷地でも見られ、カナダやフィンランドにおいてもよく知られている花になります。寒い地域によく見られる針葉樹林帯などにも群生して見られることがあるとされています。日本では北海道と本州の中部以北とされています。
亜高山帯から山地帯に生えやすくなります。春のスキー場などに見られることがあります。育て方の環境としては涼しいところを好むとされます。日当たりが必要になりますが、あまり暑いところは良くないとされます。本来は東京などにおいても育つとされていますが、東京などはアスファルトやコンクリートがあるために
ヒートアイランド現象からどうしても気温が暑くなりがちになります。このようなところでは傷みやすくなるので注意しなければいけません。このようなところであっても温度をきちんと管理すれば育てることは可能になります。アスファルトやコンクリートの照り返しを受けないような調節をしたり、
温度が一定以上にならない工夫をしているところであれば育てることができます。春にはしっかりと日差しに当てる必要がありますから、日光が当たりやすいところがよいでしょう。梅雨の頃になってきたら日差しの当たる量を変化させます。朝日のみが当たるようにすると良いです。あまり日に当てすぎると葉焼けを起こしてしまうことがありますから、それを防ぐようにしなければいけません。
種付けや水やり、肥料について
栽培時に種付けをする時の準備としては植木鉢や土があります。特性としては根がどんどん伸びていきます。したの方のみ、横のみであればいいですが四方八方にどんどん伸びていきます。それを考慮するのであれば植木鉢は深めのものを選ぶようにします。どのような植木鉢が良いかですが、あまり光沢の無いタイプです。
光沢のあるタイプは水分を逃さないのには適していますが、密閉状態にしてしまいます。釉薬が塗っていない、表面がザラザラしたタイプの物を使うようにします。このタイプは水についてはそれなりに出てくることはないですが通気性が良いタイプになります。通気性も水はけも良くなります。用土としては山野草用と高山植物用を利用します。
涼しいところに咲くことが多い花ですからそれに合わせることになるでしょう。鹿沼土、日光砂、赤玉土などを配合して用意しておきます。水やりについてはかかさずに行います。1日1回に与えるようにしますが、夏以外においては朝に1回与えるようにします。夏の暑い時期においては夕方1回とされていますが、
状況を見て朝にも水を与えたほうがいいことがあります。肥料に関しては液体肥料を与えることで行うことができます。芽出しをした後には盛夏前間で行います。秋の彼岸が過ぎた頃からも行います。この花については冬になると休眠状態になりますから、休眠状態の時に行ってもあまり意味がありません。その前までに置き肥などと組み合わせて行います。
増やし方や害虫について
増やし方においては、種まきを行うことがあります。まずは結実しているものを選ぶようにします。綿毛の先端に種粒がつくようになるので、それをとってまくようにします。種があるかどうかについては、綿毛が開いているかどうかでわかります。茶色い種粒がついてあればそれを取るようにします。種粒に関しては毛が付着していますから、
それをきれいに取るようにします。毛を付けたままだと芽出しがしにくいことがあるからです。必ずしも毛をとらないといけないわけではなく、ついたままのものでも芽出し出来る場合があります。株分けでも増やすことが可能になります。植え替えをするときにおいて根の部分の状況を確認します。根が増えている場合にはそれを取り外していきます。
手で無理やり切るのではなく、カッターなどを用いて切るほうがよいでしょう。多年草ですから次の年も花を咲かせたいです。この時には花がら摘みを行います。花が咲いた後、早めに花の部分をカットします。種をとらない時に行う方法です。こうすることで株に負担がかかりにくくなり、
次の年にも綺麗に咲かせることが出来るようになります。病気としては、高温多湿の状態にすることで軟腐病が出ることがあります。根腐れの状態もあります。日本においては梅雨があり高温多湿になってしまいますから、気温が高いところでは注意しなければいけません。害虫は種類が多く、これらがつくと花が咲きにくくなるので対策をします。
ヤナギランの歴史
蘭と言いますと高価な植物の種類があります。コチョウランなどは贈答用などとして使われることがあります。きれいに育てられたものは一つで数万円ほどするものもあります。自然のものよりも人間が工作などで作ったかのようにみえるものもあります。そのイメージからか蘭といえばかなり高い、通常は購入することができない、
見ることができないもののように感じることがありますが、比較的いろいろなところで見られることがありますし、購入することも出来るようになっています。さすがにコチョウランに関しては自生するのを見かけることはあまりないかもしれませんが、その他においては道端に咲いていることもあります。
蘭と言われる花の中でも馴染みのある花としてあるのがヤナギランと呼ばれる花かもしれません。原産としては特に定められていませんが、北半球に広く見られていて、日本もその一つになっています。そのことから日本の北海道、本州の中部から北当たりにおいて生息地があるとされています。
日本においても南部の方になるとかなり見ることができなくなる花になるかもしれません。きれいな花とのことで自治体が指定する花としても知られています。岐阜県にかつてあった村において指定の花とされていました。その他カナダであったりフィンランドの地域においてその地域の花として指定することがあるようです。日本では全国的に知られていないのであまり知名度が高く無いかもしれません。
ヤナギランの特徴
花の特徴としては、まずはフトモモ目、アカバナ科、ヤナギラン属の種類となっています。多年草なので1年を通して葉などをつけていますが、花に関しては一定の季節においてのみつけるようになります。通常の花といいますと緑の茎のことが多いですが、こちらの花の茎はすべてが緑ではありません。
地面から出る部分については緑の部分もありますが、それより上の部分では紫色をした茎になっています。その茎に緑の葉っぱが付いている状態になっています。茎の高さとしては50センチから1メートル50センチほどです。自然においてはかなり高くなることもありますが、一般的には1メートルにも達しないぐらいの高さになっているかもしれません。
茎は非常に強いタイプになっていて、まっすぐと伸びています。葉や花が沢山ついてくると垂れてきたりすることがある花がありますが、この花に関してはそのようなことはなくとにかくまっすぐに伸びています。それがより美しさを引き立たせているところもあるでしょう。葉っぱの特徴は互生です。1対ごとに付いているのではなく、
一つの葉が右についていたら次の葉が左についたりと交互に付くようになっています。細長いツヤの有る葉っぱになっています。花に関しては、一般的に見られるもんは濃い紫色が美しいタイプです。一方で真っ白の花を咲かせるものもあります。一見わかりにくいですが同じ種類です。花自体はそれほど大きくないですが、1の茎に幾つもの花がついています。
-

-
ダイモンジソウの育て方
ダイモンジソウはユキノシタ科ユキノシタ属の多年草で、日本国内では北海道や本州、四国、九州などに分布しています。湿り気のあ...
-

-
ニホンズイセンの育て方
特徴において、種類はクサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科になっています。多年草ですから、一度避けばそのままにし...
-

-
ブラッシアの育て方
ブラッシアはメキシコからペルー、ブラジルなどの地域を生息地とするラン科の植物で、別名をスパイダー・オーキッドと言います。...
-

-
ガーデンシクラメンの育て方
シクラメンの原産はトルコからイスラエルのあたりです。現在でも原種の生息地となっていて、受粉後に花がらせん状になることから...
-

-
フォザギラ・マヨールの育て方
フォザギラ・マヨールは北アメリカ東部原産の落葉低木です。北アメリカに自生し、山地や森林などを生息地としています。学名はF...
-

-
ハナミズキの育て方
ハナミズキは1912年に、当時の東京市がアメリカに桜を送った際に返礼として、日本に1915年にアメリカから白花種が寄贈さ...
-

-
シスタスの育て方
シスタスは、ロックローズとも呼ばれる花になります。大変小さくて可愛らしい事から、ガーデニングをする人に大変人気があります...
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
ジニアの育て方
ジニアはメキシコが原産の植物です。生息地はメキシコあたりで、1,796年にスペインへともたらされます。スペインの首都マド...
-

-
コツラの育て方
この花の特徴はキク科となります。小さい花なので近くに行かないとどのような花かわかりにくいですが、近くで見ればこれがキク科...




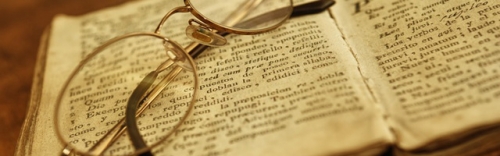





花の特徴としては、まずはフトモモ目、アカバナ科、ヤナギラン属の種類となっています。多年草なので1年を通して葉などをつけていますが、花に関しては一定の季節においてのみつけるようになります。