クテナンテの育て方

育てる環境について
クテナンテは耐陰性に優れていてやや日陰になっているような場所を好みますので、育て方としてはあまり直射日光にあたらないようなところがおすすめです。直射日光にあたり続けてしまうと葉が焼けてしまうことがありますので注意が必要です。
また、光が強いと葉が丸まってしまうことがあります。5月頃から9月頃の生育シーズンには、戸外の明るい日陰で育てることができます。冬場でも直射日光にはあまりあてない方が好ましいですので、室内のレースのカーテン越しに光が当たるような窓辺付近に置いてあげるとよいでしょう。
寒さにはあまり強くありませんので冬の寒いシーズンは戸外ではなく室内にて育てていくようにしてください。生育していくのに適している温度は、およそ20度から25度くらいだとされています。耐陰性が強く比較的栽培は容易だとされていますが、
多くの観葉植物と同じように熱帯地域が生息地の植物は耐寒性がありません。冬場も品種によって異なりますがおよそ10度から12度くらいが越冬の目安となっています。年間を通して室内で管理することができますが、乾燥には注意して葉水などを与えてあげるようにしてください。
室内で育てている場合で葉が枯れてしまうようなことがあればらもう少し明るい場所に移動をしてあげるようにしましょう。クテナンテ湿度を高めるために葉茎に水をかけることが大切ですが、用土は水はけのよい土が適していますので環境を整えてあげてください。
種付けや水やり、肥料について
クテナンテの水やりの仕方は、土の表面が乾いてきたらたっぷりと水を与えてあげます。夏は気温が高くなり特に乾燥しやすいので水が切れてしまわないように注意しましょう。高湿度を好むため水やりをする際に一緒に葉水をしてあげることがおすすめされています。
葉水をする際は霧吹きなどで水を与えるとよいでしょう。湿度が不足してしまうと葉が内側に曲がってしまったり、新しく出る葉が短くなってしまうことがありますので注意してください。冬場は生育も鈍くなりますので少し乾燥気味に管理していきます。
冬場は水の要求量も減りますので通常通りの水やりをすると根ぐされを起こしてしまう可能性がありますので注意するようにしてください。夏場とは異なり土の表面が乾いてきたと感じてから数日くらい経ってから水やりをするくらいで大丈夫です。
やや乾かしぎみの管理をおこない水やりの頻度は減らしていきますが、多湿を好みますので冬でも周に2、3回くらいは葉水はおこなうようにしていきましょう。葉水をおこなう場合には、日中の暖かい時間に少し温かめの葉水を霧吹きなどで与えるとよいでしょう。
肥料を施す場合には、5月頃から9月頃の生育期に入っている時に与えてあげることがおすすめされています。固形の置き肥を利用するのであれば2ヶ月に1回くらいを目安に、液体状の肥料を施すのであれば月に2回くらいを目安に与えてあげましょう。冬は特に肥料を与える必要はありません 。
増やし方や害虫について
クテナンテの増やし方は、株分けか挿し木によっておこなわれています。株分けをする場合には、植え替え作業と一緒におこなうことがおすすめされています。株分けに適しているシーズンは、5月中旬頃から7月下旬頃だとされています。
古い鉢土を三分の一から二分の一くらいを落としてハサミなどを利用して2、3つに分けていきます。この時葉は1、2割くらいを切り落としていきましょう。挿し芽をする場合には同じくらいの時期におこないますが、茎の先端部についた高芽を切り取って
その株元に水ゴケを巻きつけて鉢に植えつけます。半日陰の場所に置いて、水ゴケが乾いてしまわないように管理すればおよそ1か月くらいでで発根していきます。発根をしたら株に適した鉢を準備して植え付けをしていきましょう。植え替え作業は根が鉢にいっぱいになってきた株や、
傷んでしまっているような株を5月の中旬くらいから8月中旬くらいの間におこないます。鉢から掘り上げた古い鉢土を三分の一くらい落として一回りくらい大きい鉢へと植え替えをおこなっていくようにしてください。クテナンテの病気には黒斑病、斑点病があり、
春頃から秋頃に発生することがありますので発見をしたら早目に対処するようにしていきましょう。主な害虫にはカイガラムシ、ハダニなどが挙げられます。カイガラムシやアブラムシは1年中発生する可能性はありますので専用の殺虫剤などを利用して駆除していくようにしてください。
クテナンテの歴史
クテナンテは熱帯アメリカ原産の植物で、葉の色や模様などが特徴的な種類が多いことから観葉植物として栽培されています。熱帯アメリカ原産のマランタ属の植物はクテナンテ属と似ているため分類的にとても近い仲間だとされています。常緑多年草で卵状長楕円形の緑色をした葉で葉柄が長いです。
球根性で澱粉が取れることから和名でクズウコンと呼ばれています。その他にもカラテア属やストロマンテ属なども近い植物として知られています。ストロマンテも葉が美しいです。クテナンテは、ブラジルとコスタリカなどにおよそ10種類ほどが自生している常緑多年草で、
日本国内に入ってきたのは、昭和の初め頃ではないかと考えられています。幼苗期は小鉢向きで成株では大鉢仕立てとして育てられることが多いです。生育がとても旺盛で草姿のバランスが乱れてしまうことがありますので、このような場合はやすいので
大きくなってきたら切り戻しをしたり支柱立てなどの作業をすることがおすすめです。茎葉が上に伸びずに倒れたようになって伸びてきてしまった場合も支柱を利用してバランスを整えてあげるようにしてあげましょう。クテナンテには葉の部分に斑が入っている種類と入っていないものがあります。
斑が入っていない葉はとても生育が旺盛で強い性質を持っていますので、斑入りの葉を駆逐してしまわないように取り除いていくこともあります。クテナンテを栽培する場合には、用土の目安として赤玉土や腐葉土、川砂などを6対2対2くらいの割合で混ぜてあげるとよいでしょう。
クテナンテの特徴
クテナンテはの草丈はおよそ10センチメートルから100センチメートルほどになります。葉の色が美しくて、葉は細長くて長楕円形で長さはおよそ15センチメートルから50センチメートルくらいです。マーブル状など模様が入っているものが多くあり光沢がある濃緑色をしているのが特徴です。
葉の裏側部分は紫紅色をしています。ハッピードリームという別名で呼ばれることがあるゴールデンモザイクは、茎は高芽をつけて上へ伸び、濃緑色の葉に黄色やクリーム色のような矢羽根状斑が不規則に入っています。クテナンテ・バーレ-マルクシーという種類は、
株が斜上に伸びていき葉は淡緑色地に濃緑色の鎌状斑が入ります。クテナンテ・バーレ-マルクシーの変種で、葉が緑色地に濃緑色の鎌状斑が入る種類にクテナンテ・バーレ-マルクシー・オブスクラがあります。クテナンテ・バーレ-マルクシーアマグリスは、
葉が灰緑色地で葉脈が線状に緑色になります。クメリアーナはブラジル南西部原産で、草丈はおよそ70センチメートル前後になります。トリカラーと呼ばれている種類は、オッペンハイミアナの園芸品種で、クリーム色をした矢羽根模様が不規則に入りるため見た目が
とてもにカラフルなのが特徴となっています。オッペンハイミアナは草丈がおよそ1メートほどまでに達する大型種で、葉は先端のとがった長楕円形をしています。属名はギリシア語で櫛という意味があるクティスと、花という意味があるアンソスからなるのですが、この名前は花の付き方に由来しています。
-

-
レンゲツツジの育て方
この花の特徴は、ビワモドキ亜綱、ツツジ目、ツツジ科、ツツジ属になります。見た目を見てもツツジに非常に近い植物であることが...
-

-
オオアラセイトウの育て方
オオアラセイトウは別名ショカツサイとも言われる中国原産のアブラナ科の植物です。紫色が美しい小花はその昔三国志で有名な軍師...
-

-
失敗しない植物の育て方または野菜の栽培の方法
植物や野菜の育て方は、難しいと思われがちですが、植物や野菜の栽培が初心者だという人には、家庭菜園をお勧めします。プランタ...
-

-
ユキヤナギの育て方について
広い公園や河沿いの遊歩道にユキヤナギが植えられているケースが多いです。ユキヤナギの開花期はだいたい4月頃です。
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...
-

-
ボロニアの育て方
ボロニアはミカン科、ボロニア属になります。ボロニアは、3月から4月にかけて綺麗な花を咲かせる樹木になります。ですので、寒...
-

-
プテリスの育て方
プテリスはシダの仲間です。イノモトソウ科の常緑多年性シダ類に入ります。世界ではおおよそ300種類が分布しています。観葉植...
-

-
ミヤコササの育て方
ミヤコササは、イネ科でササ属の多年草です。北海道の南部から九州までの太平洋側に生息していますから、山地でよく見るササ類で...
-

-
小松菜の育て方について
最近はすっかり家庭菜園のブームも一般に浸透して、いろいろな自家製の作物を収穫している人も少なくありません。食品の安全を脅...
-

-
トラデスカンチアの育て方
トラデスカンチアは北アメリカの温帯から熱帯アメリカにかけてを生息地とする植物です。実は日本においても似たような品種の植物...




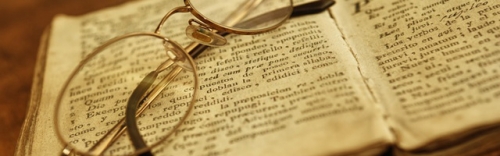





クテナンテは熱帯アメリカ原産の植物で、葉の色や模様などが特徴的な種類が多いことから観葉植物として栽培されています。熱帯アメリカ原産のマランタ属の植物はクテナンテ属と似ているため分類的にとても近い仲間だとされています。