ペトレア・ボルビリスの育て方

育てる環境について
育てる環境で一番重要となってくるのが寒さです。残念ながら最低気温が0℃以下を下回る寒冷地では地植えして育てても冬には枯れてしまいます。0℃以下にならなくても霜にあたると枯れてしまいます。そのため霜が降りてくる地域ではビニールシートで覆うなどの対策ができるように準備しておく必要があります。
また冬になると簡易なビニールハウスを作る人もいます。そうすれば、寒さと霜の両方を防ぐことができますし、費用もさほどかかりません。一方、ペトレア・ボルビリスは鉢植えで育てることも可能です。寒冷地であっても夏場は屋外で育てて、冬場は室内で育てることも可能となります。
また冬場でも上手に温度管理すれば花を咲かせることがあります。そのため、温暖地でも花を咲かせるために敢えて鉢植えをして室内で育てている家庭もあります。ただし、鉢植えで育てるときは注意が必要です。それは木の高さです。ペトレア・ボルビリスは放っておくと10m以上と大きく育ってしまいます。
そうなると持ち運んだり室内で管理するのが難しくなります。比較的生長の早い植物であるため、なるべく毎年あまり大きくなり過ぎないように剪定することが重要となってきます。ちなみに剪定する時期は春ごろがベストです。
大きく生長し始める時期なので多めに剪定したほうがいいです。地植えをするときは低温と霜、鉢植えをするときは剪定に気をつけるようにすれば、後は比較的楽に栽培することのできる植物となっています。
種付けや水やり、肥料について
水やりと肥料に関しては、それぞれ生長期と休眠期でやり方が違ってきます。まず生長期ですが、5月から9月頃だと言われています。生長期に入るとまず新芽が出てくるのでそれが目安になります。その頃では、水やりでは土を乾かしすぎないようにするのがコツとなります。土の表面が乾いてきたらたっぷりと水を注ぐ、この繰り返しで十分です。
ただし、もしも夏場でも室内で育てている人がいたら、少し水やりの頻度を増やす必要があります。クーラーによって室内の湿度が下がり、土も乾燥しやすくなるためです。ほとんど根腐れする心配がないため、水をやりすぎることはありません。一方、肥料は液体肥料ならば2週間に1度、固形肥料ならば2ヶ月に1度が目安となります。
特に5月6月の肥料が足りないと花の数が減ってしまうことがあるので注意が必要です。休眠期は10月頃から4月頃までと言われています。前述したように開花期は10月も含まれていますが、休眠期になっても1ヶ月ほど花を咲かせます。生長が鈍っている時期です。水は土がやや乾き気味になっている程度で十分です。肥料はまず与える必要はありません。
ただし、室内で育てる場合は室温によっては植物が休眠に入らないこともあります。つまり一年中生長期というわけで、花を咲かせ続けたり、新しい芽が吹いてきます。その場合は、生長期と同様に水と肥料を与えた方が良いと言われています。休眠期に入る10月11月までは様子を見ておく必要があります。
増やし方や害虫について
冬には水をやる必要はないと述べましたが、注意する点があります。それは葉っぱの乾燥です。葉っぱが乾燥するとそこにハダニが発生してしまいます。ハダニは水気に弱いため、春から夏にも出ますがたっぷりと水を与えておけばほとんど発生しません。しかし、冬場になると空気は乾燥しますし、水をやる機会が大幅に減ります。
さらには室内で育てていれば、それなりの室温が保たれています。そのため、ハダニが発生しやすい環境が整ってしまいます。特に葉っぱの裏側に集まりやすいと言われており、気がついたら大発生して植物にも影響を与えてしまうことも考えられます。そのハダニを防ぐためには、とにかく葉っぱに水気を与えることです。
塗れた雑巾などで拭いていく方法もありますが、先に述べたようにサンドペーパーバインと呼ばれるほどヤスリのような表面です。すぐに雑巾がボロボロになりますし、下手すると手に傷がついてしまうかもしれません。そのため、あまり葉っぱに触れないように霧吹きで水を吹きかけた方が無難と言えるかもしれません。
あまりにも水を吹きかけすぎると水やりになってしまうので、2週間に1度は葉っぱに湿度を与えるよう心がけるべきです。ハダニ以外では病気にも強い植物と言われているため、安心して育てることが可能です。もしも、ペトレア・ボルビリスが気に入ってもっと増やしたいと感じたならば、挿し木か種まきです。どちらも春頃にやるのが良いと言われています。
ペトレア・ボルビリスの歴史
ペトレア・ボルビリスは原産地がキューバ・ブラジルといった中南米の常緑蔓性高木です。和名では寡婦蔓(ヤモメカズラ)と呼ばれており、日本ではこの呼び方のほうがポピュラーかもしれません。このペトレアとは植物学支援者のペトレが由来とされており、今で言うところのスポンサー名といったところです。
一つ一つは桜の花のように花びらが5枚あり、紫色から薄紫色、そして白色のカラーがあり小さな鉢で育てると中南米が原産地とは思えないほど可愛らしい花をつけます。また桜は数週間と持ちませんが、ペトレア・ボルビリスは数ヶ月に渡って鑑賞し続けるメリットがあります。その仕掛けは花が散った後にあります。
その一方で地植えで大きく育てると枝が弓状にしなり、そこにたくさんの花をつけます。そのため、まるで天の川のような花の帯を広げたような優雅さがそこにあります。帯状に連なるため、欧米では紫色のものをパープルレース、白色のものをホワイトレースと呼ばれることも少なくありません。
ダイナミックに見せることもできるため、日本でも好まれる花の一つとなっています。美しい花をつける一方で比較的栽培も簡単であるため、一般家庭で育てているところもあります。外で大きく育てれば枝垂桜のように壮大に見せることができますし、室内で小さく育てれば蘭のように繊細に演出することができます。育て方次第によって表情を変えていくのもペトレア・ボルビリスの面白いところと言えます。
ペトレア・ボルビリスの特徴
ペトレア・ボルビリスの花は美しいですが、花の寿命は残念ながら2~3日しかありません。しかしこの花には大きな特徴があり、花びらが散った後も萼(がく)が残ります。その萼は花びらとほとんど同じ形同じ色をしているため、花びらが散った後でも観賞用として親しむことが可能となっています。
なぜ萼がついているかというと種子と一緒に遠くに飛べるようになっているからです。そのため、開花期は5月の初頭から10月の末期までと非常に長い間で花を愛でることができます。これがこの植物を育てる大きなメリットとなっています。また和名がヤモメカズラという名前もこの萼を未亡人(ヤメモ)のように例えたことが由来とされています。
そして、特徴的なのは花だけでなく葉っぱもそうです。葉っぱの表面が非常にザラザラとヤスリのようになっています。そのため不用意に触れて擦ってしまうと軽く皮膚に傷がつくので注意する必要があります。そのため、英名ではサンドペーパーバイン(ヤスリの蔓)とも呼ばれています。
同じ例えるにしても日本では花から、英国では葉っぱからと植物の名づけ方からでもお国柄が表れます。生息地が熱帯から亜熱帯にかけた地域であるため、暑さには滅法強いですが、寒さには若干弱めです。ただし、寒さに弱いといっても0℃から10℃以下にさせなければ越冬できると言われています。そのため、屋外で育てようとする人は冬の寒さ対策が決め手となってくるわけです。
-

-
チェッカーベリーの育て方
チェッカーベリーは原産地や生息地が北アメリカ東北部で、グラウンドカバーによく使われます。別名をヒメコウジやオオミコウジ、...
-

-
ベニジウムの育て方
ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英...
-

-
グレープフルーツの育て方
グレープフルーツの生息地は亜熱帯地方になります。ミカン科・ミカン属になり、原産地は西インド諸島になります。グレープフルー...
-

-
コマクサの育て方
高山植物の女王とも呼ばれているコマクサは高山に咲く高山植物の一つです。北アルプスなどの山々の中で見ることが出来ますが、比...
-

-
ユズ(実)の育て方
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くら...
-

-
カレンジュラの育て方
日本ではキンセンカという名でよく知られているカレンジュラのことをよく知って育て方を工夫しながら栽培していきましょう。カレ...
-

-
ソテツの育て方
この植物に関してはソテツ目の植物になります。裸子植物の種類に当たり、常緑低木になります。日本においてはこの種類に関しては...
-

-
アイビーゼラニウムの育て方
アイビーゼラニウムは南アフリカのケープ地方原産の植物です。科名はフウロソウ科で、テンジクアオイ属です。テンジクアオイ属は...
-

-
ビャクシンの仲間の育て方
ビャクシンはヒノキ科の常緑高木で、日本の本州から沖縄県で栽培されています。その他の原産地には朝鮮半島や中国などが挙げられ...
-

-
リビングストンデージーの育て方
リビングストンデージーの特徴として、まずは原産地となるのが南アフリカであり、科・属名はツルナ科・ドロテアンサスに属してい...




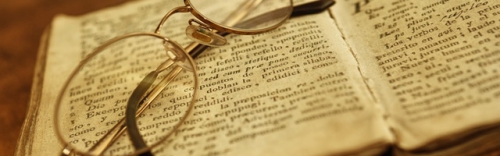





ペトレア・ボルビリスは原産地がキューバ・ブラジルといった中南米の常緑蔓性高木です。和名では寡婦蔓(ヤモメカズラ)と呼ばれており、日本ではこの呼び方のほうがポピュラーかもしれません。このペトレアとは植物学支援者のペトレが由来とされており、今で言うところのスポンサー名といったところです。