メセンの仲間(夏型)の育て方

育てる環境について
栽培するにあたって環境としてはどのようなところが好ましいかとしては、夏は半日陰、それ以外は日当たりでの管理が良いとされます。多肉植物としては、植物内において水分を確保できる強みがありますその分水の心配としては少なく、水分などがきちんと取れないようなところでも育つことが出来るとされます。
日差しにおいてはある程度の強さがあるようですが、真夏の直射日光となると必ずしも強くなとされます。朝方の緩やかな日差しなら良いですが、昼過ぎから西日がかかる夕方なにおいては日差しを当てないようにするのが良いとされます。あまり日当たりが少なすぎる状態になると成長がしにくくなるので、日当たりについては調整しやすいところがよいでしょう。
冬に関しては霜に強いタイプと弱いタイプがあります。霜に弱ければ、自ずと日本の冬越しが出来るかどうか気になるところです。購入するときにどのようなタイプかを調べておく必要があるでしょう。霜に弱いタイプであれば冬は自宅内で育てなければいけません。一方で強いなら屋外でも育てることが可能になります。
どちらかわからない時は自宅内に取り込みます。寒さに強いくても、自宅内で弱まることはないでしょう。高温多湿には気をつけなければいけません。日本の夏は高温多湿になる地域が多くなります。過湿を避ける方法としては風通しを良くすることがあります。置く場所の風通しを考えるようにして、湿度を抑えるようにします。
種付けや水やり、肥料について
育て方においては用土が関係してきます。鉢植えの時の用土としては水はけを考えて配合割合を設定します。鹿沼土の小粒を2割、赤玉土の小粒を2割、ピートモス2割、川砂2割、くん炭を2割の配合が適当かもしれません。腐葉土などを入れるわけではないので、比較的容易に配合することができるかもしれません。
多肉植物用の土をそのまま用いるのは良くないとされます。別の配合例としては赤玉土4割、鹿沼土3割、真砂土が1割、バーミキュライトが2割くらいにすることがあります。水やりとしては、乾燥地帯の植物に対応することを考えます。100円ショップなどでも小さいサボテンが売られていることがあります。
購入した後一度も水をやらなくても特に枯れることなく花をつけたりすることがあります。水をあげすぎると腐って枯れてしまうことがあります。水やりのタイミングとしては1箇月に1回くらいです。休眠をするときには一切与えないことも必要になります。夏のタイプに関しては10月から3月ころの低温期において休眠に入ります。
この時期は断水をして冬越をさせるようにします。乾燥させると植物の中の樹液が濃くなります。するとより低温に耐えられるようになります。春に新芽が出てきたら休眠から目を覚ました状態なので少しずつ水を与えるようにします。最初から一気に与えないようにします。肥料は春から秋の生育期に効果がゆっくりのタイプの肥料を少し与えるようにします。
増やし方や害虫について
増やし方では種まきができます。この種類に種があるのかと考えるかもしれませんが、花が咲きますから実もなります。実から種を取ることができます。花のあとに果実が熟するようになりますから、その後の種を採取して保存しておきます。種をまく時期としては3月から5月くらいになります。株分けをすることでも増やせます。
3月から8月にかけて植え替えをしようとするときに行うようにします。株分けが、少しやりにくいのであればさし木をすることができます。伸びている部分を切り取ってそれを挿すだけになります。植え替えはあまり行うことはないかもしれませんが、用土が古くなった時に行います。株の生育が鈍ったりした時に行うと良いとされています。
行うのが良い時期としては生育期の直前から初期の状態の頃に行えます。作業としておくことは摘心があります。どんどん成長するタイプに関しては、枝が乱れることがあります。きれいな花が咲いても、乱れた枝においてはあまり美しく見られなくなります。摘心をすることで成長を遅らせることができます。
この植物にあることとしては脱皮があります。まるで爬虫類などのように行いますが、どんどん脱皮をしてしまうと株が小さくなることがあります。あまり脱皮をするのはよくありません。脱皮が多い状態を二重脱皮と呼ぶことがあります。水が多いとそのようなことがあります。水分を控えるなどの対処をして、うまく育つようにしなければいけません。
メセンの仲間(夏型)の歴史
サボテンといえば砂漠などでも大きく育っています。砂漠といいますとほとんど雨がふらないような環境です。ですから土の中から水分を得るのは難しくなります。そのようなときは空気中から水分を得たりして生きていくようです。サボテンなどには刺などがありそれが水分を取る役割をしていることがあります。
このサボテンに関しては多肉植物と呼ばれています。なぜこのように呼ばれているかといえば、葉、茎、根などにおいて水分を貯蔵する機能があるためのようです。この多肉植物としてあるのがメセンの仲間になります。こちらについてはハマミズナ科の植物全体のことを指す言葉として知られています。
実際のところは120以上の属があり、原種としては2千近くもあるとされています。まだまだ細かい分類が進んでいない分野になるのでしょう。現在においてはおおまかに夏型、冬型があるとされます。夏型は主に温暖な時期に生育をさせるものになります。原産地としてはアフリカの南部、オーストラリアなどになります。
南半球を中心に存在している植物と言えます。この種類に関しては、かつてはメセンブリアンテマムと呼ばれる属に属していたとされます。真昼の花の意味になるようです。その後夜にも開花するものが発見されて中程度の果実の花の意味に変わります。日本においてはメセンと略され、女仙の漢字が充てられています。サボテンは漢字で仙人掌で、それに対応して女性的なサボテンの意味があるようです。
メセンの仲間(夏型)の特徴
この植物の特徴としては、まずはハマミズナ科に属する植物で多肉植物であることです。ですから茎などがかなり太くなっています。この部分に水を多く含んでいます。春から秋にかけて生育し、夜の温度が10度を下回るようになる11月ぐらいから3月にかけては低温休眠をします。
多肉植物といいますと茎などがゴツゴツしたイメージがあり、この植物においても茎の部分だけを見ると同じような印象です。なぜこのような植物を育てるのかと考えることがありますが、花がきれいなのも多肉植物の特徴になります。サボテンの花なども非常にきれいな花を咲かせることが知られています。
園芸上の分類としては、多肉植物の他観葉植物としてがあります。たくさんの種類があるために一概には言えませんが、多年草、一年草、二年草など様々になっています。高さとしては2センチから30センチぐらいとそれ程大きくはなりません。花が咲く時期もバラバラで、種類によっては夏に咲くもの、春や秋などに咲くものなどもあります。花の色は白、赤、ピンク、黄色、紫など多岐に渡ります。
それらの花の色としては淡い色よりもはっきりした色のことが多いです。赤の場合も真っ赤なきれいな花が元気よく咲くことが多いです。耐寒性と耐暑性については種類によって異なります。夏タイプとしても必ずしも夏に強い、冬に弱いわけではありません。それぞれの種類によって生息地についても多少異なってくると考えられます。
-

-
睡蓮(スイレン)の育て方
睡蓮の魅力と言えば、なんと言ってもその美しい花、そして風情のある水面に浮く沢山の葉にあります。元々は東南アジアなどの熱帯...
-

-
ゼラニウムの育て方
ゼラニウムの主な原産地は南アフリカです。南アフリカを中心にオーストラリアや中東などの広い範囲を様々な種類が生息地としてい...
-

-
サイネリアの育て方
サイネリアはキク科植物の一つで、カナリア諸島が原産のものだと考えられています。かつては「シネラリア」とも言われていたそう...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
シクノチェスの育て方
シクノチェスはラン科の植物で独特の花を咲かせることから世界中で人気となっている品種で、15000種以上の品種があるとされ...
-

-
モモバギキョウの育て方
この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形...
-

-
ギボウシ(ホスタ)の育て方
ギボウシは別名、ホスタという名前で古から世界中で親しまれています。もともとは、ギボウシは日本の里山のあらゆるところに自生...
-

-
ライチの育て方
ライチは、ムクロジ科、レイシ属になります。和名はレイシと呼ばれています。果物については果樹として育てられるのか、苗のよう...
-

-
シュスランの育て方
シュスランはラン科の植物です。ランという名前がついていますが、洋ランのように大きな花を咲かす植物ではなく、比較的小ぶりの...
-

-
ブルーキャッツアイの育て方
ブラジル原産の多年草である”ブルーキャッツアイ”。日本では観賞植物として栽培されています。別名はオタカンサスと呼ばれる花...




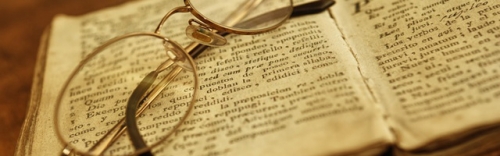





この植物の特徴としては、まずはハマミズナ科に属する植物で多肉植物であることです。ですから茎などがかなり太くなっています。この部分に水を多く含んでいます。春から秋にかけて生育し、夜の温度が10度を下回るようになる11月ぐらいから3月にかけては低温休眠をします。