ヤグルマ草の育て方

育てる環境について
しかしガーデニングでは、本命のヤグルマ草は、キク科の方のヤグルマ草でしょう。これは非常に鮮やかな青い花で、確か未魅了されるような美しさの花です。人気が高いのもうなずけます。この花はキク科のヤグルマ属ということですが、名前としてはコーンフラワーやヤグルマギクや矢車草と呼ばれていて、ガーデニングを楽しんでいる人たちには、
普通に矢車草と呼ばれていて矢車草というと、こちらの花ということになります。本当は先ほどの日本に自生しているユキノシタ科のヤグルマ草と区別をするために矢車菊ということになっているそうですが、一般的には、やはり矢車草はこちらの花のほうが通りが良いということのようです。インターネットのブログなどでも普通に矢車草というとこちらの花です。
ユキノシタ科の方はヤグルマソウ属ですが、こちらのキク科の方はヤグルマギク属ということでややこしくなってしまいます。キク科の方の矢車草は、学名ではギリシャ神話のケンタウルスという半人半馬の神様の名前がついていて、そこからもわかるように、ヨーロッパが原産地です。
またアサギ色という言葉も入っているので、アサギ色のケンタウロスという意味になるようです。どう見れば半人半馬のケンタウロスに見えるのだろうということですが、何か物語でも繋がっているのでしょう。このように両者を比べてみるとどう見てもヨーロッパが原産の矢車菊の方に軍配が上がるということですが、確かにガーデニングでは、こちらの鮮やかな花のほうが良いということです。
種付けや水やり、肥料について
栽培ということでの育て方ですが、この矢車菊の方の矢車草は、非常に人気があるので、インターネットでもたくさん育てている人がいて、ブログなどにも書かれていますから、その点は初心者でも育てやすいですし、小さな花なので鉢植えでも育てやすそうですから、マンションのベランダのようなところでのガーデニングには最適ではないかということになります。
またこの花はヨーロッパでも人気があるようで、ドイツ連邦共和国やエストニア共和国、マルタ共和国の国花にまでなっているという人気が高い植物です。日本の野草の方の矢車草が気の毒なくらいの人気で、その点でも西欧と日本の昔の違いのようで興味深い植物たちです。またキク科の方の派手な矢車草は、耐寒性一年生植物ということで寒さに強いですが、
日本のユキノシタ科の矢車草も北海道でも自生しているのでそちらも寒さに強い植物です。そのような共通点もあります。栽培ということでのガーデニングでは、種を蒔く時期が東北と関東以西の地域では違ってくるというこれも面白い特性があります。東北の方では春に種をまき、関東以西では秋に種を播くということのようです。
また8月ごろ種をまくと、気候が暖かければその年に花が咲くそうですが、普通は次の年に咲かせるように9月以降種を蒔き次の年の4月頃花を咲かせるように育てるということでした。また病害虫が少ない丈夫な植物なので初心者向きということでも人気があるということになります。ガーデニングでは非常に良い植物です。
増やし方や害虫について
また文化面ですが、この花の色が鮮やかなので、宝石のサファイヤの最高級の色がコーンフラワーブルーと言われているそうで、矢車草の青い色のサファイアということのようです。また文学でもこの鮮やかな色がロマン主義の象徴とも言われていたそうです。また古代のエジプトでも、有名な王様のツタンカーメン王の棺の上にこの花が置いてあったそうです。
措いた時には鮮やかな色だったのでしょう。またフランスの悲劇の王妃であるマリーアントワネットが好んだ花だそうで、有名な皿のデザインにも使われているということでした。このようにキク科の方の矢車草は非常に人気があり、ガーデニングでもこの花を育てないとガーデニングではないだろうという感じの代表的な花ということができますが、
面白い育て方では、両方の矢車草をそれぞれ鉢植えで育ててみるのも良いかもしれないとも考えたりします。そのような育て方をすると話題性もあり、ある意味ではステイタス的な存在になるかもしれません。そのように非常に興味い植物たちですが、キク科の派手な方のヤグルマ草の基本的な育て方ということでは、開花が4月から5月ですから、
植え付けは9月から翌年の2月頃までで、肥料はそれ以外の3月から9月ぐらいまで与えるということのようです。また水はやり過ぎると根が腐ってしまいますが、少なすぎると枯れますので、適度に土が湿っている程度に与えておきます。また過湿に弱く風通しの悪いところでも枯れやすいので環境は気をつけるという育て方をすると良いようです。
ヤグルマ草の歴史
ガーデニング関係では、多くの人達から人気のある植物もあれば、人知れず咲いている野草もあります。それが同じ名前という場合もあります。例えばヤグルマ草がそうです。矢車草ということでは、2種類の矢車草があり、ひとつはキク科の矢車草で、こちらはガーデニングの栽培でも非常に人気があり、鮮やかな青い色の花が咲きます。
ヤグルマギクとも言われていて、キク科ヤグルマギク属のひとつですが、ハーブでもあり、花も鮮やかなのでファンもたくさんいる矢車草です。もうひとつは、野草の矢車草で本来はこちらが矢車草ということですが、多分知っている人はあまりいないだろうという野草です。ヤグルマ草というと、こちらを思う浮かべる人は殆どいないでしょう。
花の色も日本の野草に多い白い色で、綺麗な花ですがホワイトレースカーテン系の野草ということになります。こちらの矢車草はユキノシタ科ヤグルマソウ属の多年草でユキノシタ科とキク科の違いということになります。やはりキク科の花のほうが鮮やかということでも美しいということになります。
ユキノシタ科という名前も奥ゆかしいですが、やはりキク科とは全く正反対で、とても面白いということになりますが、この両方の植物の名前にあるヤグルマは、矢の車と書きますが、鯉のぼりを上げる時の竿のてっぺんに矢車がついています。その飾りに似ているということでついた名前だそうですが、なかなか面白い名前です。キク科の矢車草のほうが鮮やかさでは近いような感じです。
ヤグルマ草の特徴
普通はガーデニングで楽しむ矢車草はキク科の方ですが、本来のヤグルマ草と言われているユキノシタ科の矢車草は、原産地が、朝鮮半島から本州、北海道ぐらいまでで、生息地も同じですが、日本では深い山の中の谷沿いの林など、湿り気のある場所に群生していたりするそうで、花は白いのですが非常に面白い形をしていて、花弁が細くて尖っているものがたくさん放射状に伸びていて、非常に変わっています。
確かに鯉のぼりの矢車に似ているといえば似ていますが、それよりも海の魚のハリセンボンというふぐの仲間がいますが、そちらの方に近い感じで、花のハリセンボンというイメージのほうが近いように感じます。よく見ると、とてもおもしろい植物で、これはガーデニングでの鉢植えで育ててみたいという植物です。
本当に変わっている野草です。また葉と花の間が、あいていて上下に分かれているようにみえるということも変わっていて面白いですが、この葉っぱが鯉のぼりの矢車に似ているからという説もあるようです。いずれにしろ日本に自生している野草なので、日本で栽培するのには良さそうです。
こちらは普通の野草で、食べたり、ハーブになったり、漢方薬になったりはしないようで、日本の山の深いところに、ひっそりと咲いているという植物です。こちらのほうが日本人にはあっているかもしれません。花は小さい花がまとまって咲きますが、白い花の日本の野草にはよくある形です。こんな花もあるのかと驚く花です。
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
ソバの育て方
この植物の歴史では、奈良時代以前に栽培されていたということは確実で、700年代前半の書物に関係の内容が書かれているという...
-

-
アセビの育て方
アセビは日本や中国が原産で、古くから日本人の生活になじんでいた植物です。その証拠に枕草子や古今集のなかでその名がみられる...
-

-
ディオスコレアの育て方
観葉植物として栽培され、日本でも人気を集めているのがディオスコレアであり、特に普及しているのがディオスコレアエレファンテ...
-

-
アオマムシグサの育て方
アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」...
-

-
ベルフラワーの育て方
ベルフラワーはカンパニュラの仲間で、カンパニュラはラテン語の釣鐘を意味する言葉から由来しており、薄紫色のベル状のかれんな...
-

-
タバコの育て方
特徴として、意外な事実では、このタバコはナス科の植物ということで、タバコ属の多年草ということだそうです。どう見てもタバコ...
-

-
ダイアンサスの育て方
ダイアンサスは、世界中に生息地が広がる常緑性植物です。品種によって、ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アフリカなどが原産...
-

-
ブラッシアの育て方
ブラッシアはメキシコからペルー、ブラジルなどの地域を生息地とするラン科の植物で、別名をスパイダー・オーキッドと言います。...
-

-
トロリウスの育て方
”トロリウス”とは、ヨーロッパや北アジアを原産とした宿根多年草です。キンポウゲ科、キンバイソウ属になり別名キンバイソウと...




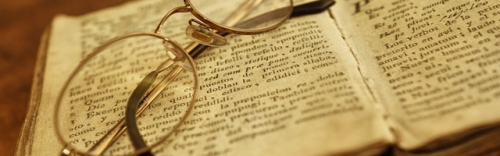





ヤグルマギクとも言われていて、キク科ヤグルマギク属のひとつですが、ハーブでもあり、花も鮮やかなのでファンもたくさんいる矢車草です。もうひとつは、野草の矢車草で本来はこちらが矢車草ということですが、多分知っている人はあまりいないだろうという野草です。