アジサイの育て方

アジサイの育て方
アジサイにとって大切なことは来年も綺麗に花が咲くようにすることです。これを失敗してしまうと美しいアジサイを見ることができません。ですが、アジサイは放っておくとどんどん大きくなっていく花です。
そのため、庭のスペースをとり、場合によっては自動車や交通の邪魔になることもあります。一定の大きさをキープさせるためにも花の剪定はきちんとしましょう。剪定の種類は様々ですが、よく見られる手段に二段階にわけて剪定をするものがあります。
花が咲いたら葉っぱが2~4枚の位置ですっぱりと切ります。アジサイの葉っぱは基本的に茎に対して葉が対になるように生えています。きちんと正しい位置で剪定をしましょう。切った花はまだ花が楽しめる状態にありますので、花瓶などに活けて楽しんでみてください。
次の剪定は秋の初めごろです。今度は前回切った場所からさらに株に近いところを切りましょう。剪定は一度だけに済ませることもできます。その場合は花の咲いている枝と咲いていない枝を判断して、咲いた枝を切ってしまいましょう。
次の年に咲く花芽は10月頃にはすでに準備ができた状態で冬を越します。冬場のアジサイは葉っぱこそないものの、枝が邪魔に感じることもあるかと思います。仮にこれを切ってしまうと、咲く予定だったつぼみまでもを切ってしまうことになるので、注意をしなくてはなりません。
アジサイの栽培
梅雨時に咲く花だけあって、水を大変好む植物です。乾燥するとなかなか成長しなくなるので特に注意をしましょう。庭などに直接植えている場合、真夏の日照りなどではない限りは特に水やりをしなくと自然に降ってくる降水量で成長します。
乾きやすい土壌に植えている時には、株の周りにわらをしいて乾燥を防ぐようにしてください。水を好むからといって湿地を好む植物ではなので、水はけがよい土壌を選んで植えるようにしてください。
最近では鉢に入ってギフト用などの形として売られているアジサイも多く見られます。鉢は土の面積が狭い以上どうしても乾きやすい傾向にありますので、土の表面が乾燥してきたらたっぷりの水を与えましょう。
こまめに乾燥してないかをチェックしてあげるようにしてください。そのような理由から土は水はけのよいものを選びましょう。例えば赤玉土は肥料分こそないものの通気性・排水性・保湿性などに優れています。
赤玉土を中心に鹿沼土とピートモスを配合したものを使用しましょう。この時に注意すべきなのが土の酸性度です。アジサイの本来の色は薄い青や青味の強い紫色で弱酸性の土を好んでいます。
赤やピンク系の花を咲かせたい場合はアルカリ性の土にすることによって咲く色を調節することが可能です。肥料は花の咲いていない冬にやると翌年の春に青々とした葉っぱが芽吹きます。例えば油かすと骨粉を混ぜたような長期的に利くタイプの肥料を選びましょう。夏から秋には10日おき程度に液体肥料を与えてください。
アジサイの殖やし方
アジサイは基本的に挿し芽によって増やす事ができます。6月の上旬、まさに梅雨に入りたての頃がちょうどよい時期です。花の付いていない枝の先を15cmほど切り取り、鉢に挿しておきましょう。平均して一カ月程度で根が出てきます。
直射日光には当てずになるべく半日陰の場所に置くようにしてください。挿し芽がある程度育ってきたら土壌に移し替えましょう。もちろん鉢で育てたい方はそのままで栽培を続けても構いません。種で増やすこともできなくはないのですがとても小さな種なので注意して育ててください。
まずは花から種を採取する方法ですが、まずは剪定などで花を落とさないようにして、咲いた後もそのままの状態で10月~11月頃まで待ちましょう。アジサイは通常花に見える部分はがくと呼ばれる部分であり、本当の花はその中央にある小さなものです。
なのでできる種も同じようにとても小さなものになるのです。花が枯れて茶色くなった頃、花を切り取り、軽く振るとそこから小さな種がこぼれます。種を採取する際は飛ばさないように注意をしましょう。また種付けの際には種が流れないようにする工夫が必要です。
特に土壌などに直接まいてしまうと小さな種粒はどんどん流されてしまいますので気を付けましょう。芽が出てきたらいよいよ植え替えです。本葉の数が4枚になった時を見計らい、ピンセットなどを使って優しく植え替えをします。
乱暴に引っ張り根を切ってしまった場合は成長がうまくすすまなくなる可能性もありますので細心の注意を払って作業してください。本来ならば挿し芽で増やすことが一般的のアジサイですが、これは要するにもともとの親株のクローンにあたります。
種をまくことによってオリジナルの品種を生みだす事ができます。もちろん挿し芽よりも育つ可能性はとても低くなってしまいますが、自分の手で育てたオリジナルの品種を楽しむことは格別だと思います。種から育てた場合、およそ3年~4年ほど楽しむことができます。
アジサイの歴史
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるものといわれています。特に原種に近いとされているガクアジサイの生息地は伊豆半島です。また、ガクアジサイを品種改良してできたものはホンアジサイといいます。
かなり古くから知られていた花で、日本の文化には欠かせない花の一つとなっています。例えばアジサイは7世紀後半から8世紀後半、奈良時代にかけて編まれた万葉集にも登場しており、大伴家持も一句詠んでいます。
また、平安の後期にも短歌として詠まれることが多い花です。また、自然学者でもあったシーボルトはオランダに帰還してから植物学者であるツッカリニと共同で、日本植物誌を記しアジサイ14種を新種として記録しています。
これもアジサイが日本にしかないことを物語っています。そこでシーボルトは当時の恋人であったお滝さんに因み、オタクサという学名をつけました。愛する恋人のように美しい花であるという意味を込めていたのかもしれません。
しかし、この学名はその後ツンベルグという植物学者によって別の学名がつけられ、現在では無効になっています。そこからアジサイはヨーロッパへと渡り、18世紀終わりにイギリスの王立植物館へと迎え入れられました。欧州でも様々な新品種が生まれています。
アジサイの特徴
アジサイの特徴は何と言ってもその花の色の美しさでしょう。この色はアントシアニンという成分由来のものによります。アジサイは植えた場所により花色が変わることで有名です。これは土壌の酸性度によって、まるでリトマス紙のように酸性なら青色に、アルカリ性なら赤色に花が変化していくことからです。
酸性の土壌はアルミニウムがイオンとなって土に溶けだすことで、アジサイが根から水分をとる時に吸収され、花色を決めるアントシアニンと結合して青色になるのです。アジサイは別名七変化ともいいます。つぼみの頃は淡い緑がかっていたものが白い状態で花開き、薄い青から藍色に変わり、さらに赤やピンクの色へと変化していきます。
もちろん種類によって色は変わりますが、やはり美しい期間は藍色の時です。藍色が集まった花というのが語源にある通り、鮮やかな藍色と緑のコントラストは素晴らしいものです。元気な株は葉っぱの緑も濃く、葉も大きいので、玉のように丸く咲く花との美しさが梅雨時の庭を美しく見せることでしょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オオチョウジガマズミの育て方
タイトル:ノリウツギの育て方
タイトル:カシワバアジサイの育て方
-

-
マサキの育て方
マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicu...
-

-
シロダモの育て方
現在に至るまでに木材としても広く利用されています。クスノキ科のシロダモ属に分類されています。原産や分布地は本州や四国や九...
-

-
トウガン(ミニトウガン)の育て方
トウガンは漢字で書くと冬瓜と書きますが、冬の瓜と言う事からも旬が冬のように感じる人も多いものです。しかし、冬瓜と書く理由...
-

-
ノコンギクの育て方
ノコンギクの歴史としまして、伝統的にはこの種には長らく「Aster ageratoides Turcz. subsp. ...
-

-
ゲウムの育て方
ゲウムは、バラ科 のダイコンソウ属(ゲウム属)であり、日本のに山に咲く「ダイコンソウ」と同じ仲間です。そのためゲウムを「...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...
-

-
ホヤ(サクララン)の育て方
花の名前からラン科、さくらの科であるバラ科のように考えている人もいるかもしれませんが、どちらにも該当しない花になります。...
-

-
マリーゴールドの育て方
マリーゴールドはキク科の花でキンセンカとも言われていて、学名はカレンデュラといいます。シェークスピアの作品にも出てくる花...
-

-
チューリップの育て方
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから...




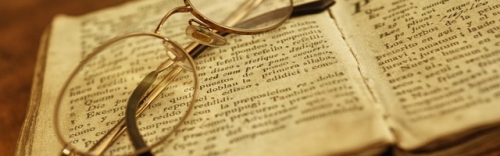





アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるものといわれています。特に原種に近いとされているガクアジサイの生息地は伊豆半島です。また、ガクアジサイを品種改良してできたものはホンアジサイといいます。