ブルメリア・クロセア・オーレアの育て方

育てる環境について
育て方ということでは、温かい地方の植物なので、冬をどう乗り切るかということですが、鉢植えなどにして、温かい室内などに移して育てるということが良いようです。生育期間は10月上旬から翌年の6月上旬までなので、その期間日当たりの良い所で、適当に水を与えながら育てるということですが、休眠期間は夏の間だそうで、その時には水は与えなくても良いということで、
先程書いたように、球根を掘り出して乾燥させて休眠させるということだそうです。肥料は秋と2月と開花後にそれぞれ与えれば良いということです。植え付けは土の深さは浅めで、3センチから5センチで、地植えの場合には、もう少し深くなり8センチから10センチぐらいだそうですが、それでもそれほど深くないところに植えるということになります。
また耐寒性ということでは強いようですが、日本の寒い地方ではやはり凍結や霜があるので室内に移動させて育てるほうが良いということでした。また種まきということでは、秋が良いということです。ブルメリア・クロセア・オーレアはユリ科ブローメリア属の多年草で秋植えの植物として扱われているということで、
たしかにそのような育て方になっています。また本場のカリフォルニア州では何種類か育てられているようですが、日本ではブルメリア・クロセア・オーレアがそれもわずかに流通している程度ということですから、その意味でも非常に貴重な植物ということができます。
種付けや水やり、肥料について
また似たような名前の花もあり、例えばプルメリアですが、白い花で、こちらはキョウチクトウ科インドソケイ属ですので桔梗に近いですが、全く関係がない花です。原産地はアメリカなので、そこは似ています。またブルメリア・クロセア・オーレアは基本的には丈夫な植物ですし害虫もあまりつきませんが、アブラムシが時々付くことがあるようですのでアブラムシ対策はしておくとよいでしょう。
また育ってくると蕾がカラフルで、花が黄色なのですが、この蕾も黄色がかって、緑の筋と黄色の筋が縦にいくつも縞のようになり、とても美しく、あめ玉のようになります。手にとって食べてしまいたいような可愛らしさがあり、それがいくつも固まって育つので、その点も魅力です。花になる前がこのように美しい植物も珍しいのではないかという気もします。
またこの時にもアブラムシがつきやすいので気をつけて駆除するということになります。また花も美しくて、6弁花ですが雄しべは先が緑色で、その後黄色になっていきます。このように美しい花なのですが、マイナー扱いされているということで、これから人気がでるのかもしれませんが、
とても魅力的なガーデニング用の植物ではないかということになります。また花の裏には蕾の時の名残の緑の縦縞のストライプが入っているので、とても魅力的ですが、見ることが少ないので人気も出ないのでしょう。これらの姿を見れば人気も高まるのではないかということです。
増やし方や害虫について
また花もひとつではなく、放射状にのびた茎からたくさんの黄色い花が直線的に咲きますので、その姿も魅力があります。非常にかわいらしい美しい花ですので、手に入れる機会があればぜひ育ててみると良い植物ですし、育てやすい植物なので初心者にも、おすすめできるのではないかということです。ただ難があるということでは、葉がしおれたように垂れてしまうらしく、そのことが難といえば難のようです。
しかし美しさを考えるとあまり気にならないのではという感じもします。育て方のまとめとしては、日当たりの良い場所を好みます。また寒さにも強いので日当たりが良い場所では霜さえなければ越冬も出来るということでした。開花期は春から初夏、植え付けは秋ということです。また寒風が当たると葉先が傷ついてしまうそうで、風が当たらないようなベランダが冬は良いそうです。
肥料はたくさん与える必要はなく植える前に土に与えておき、また液体肥料などを生長期~開花期似時々与えれば良いということでした。その点も初心者向きのガーデニングの植物のように感じます。また野生種もあり、山の傾斜地に自生するものが多いということですし、
水はけのよい土壌を好むということですので、そのような環境も考慮すると、水はけの日当たりの良い土地が良いとなります。また増やし方は球根を分ける方法と、種もできますので、その両方で増やすことができますから、増やしやすい植物でもあります。そのように初心者向に栽培できる植物です。
ブルメリア・クロセア・オーレアの歴史
ガーデニングは世界中で楽しまれている趣味のようで、新しい植物や珍しい植物も多くて、なかなか育て方がわからない植物もけっこうあります。そして色々とインターネットで質問をしたりしても、珍しいということですから、育てた人が少ないということでもありますし、ガーデニングで栽培している人たちが、全てインターネットを使いこなしているということでもありません。
特に主婦などでも、年配の人達たちも多いのですが、インターネットを触ったこともないという人達も多いでしょう。そうなると、それらの珍しい植物も育てた人がいるかもしれませんが、それらの経験が誰にも知られずに終わってしまうということにもなります。ガーデニングでの栽培では、特に珍しい種類の場合には、そのような悩みもあります。そしてそのような珍しい花に魅了されてしまうことも多いので、
そのことも不思議で面白いとも感じてしまいます。例えばブルメリア・クロセア・オーレアなどは良い例でしょう。この花は黄色い花ですが、非常に独特の色合いをしていて、表現しにくいのですが、ある人はレモンイエローと表現していました。しかし感じとしてはゴールドに近い色で、
それもブロンズのようなゴールドという感じの植物です。一目見ただけで、その不思議な色に魅了されてしまいますが、この花はとても珍しい花で、一応流通はしているのですが、ほとんど手に入れることができないようです。ときどき売られている程度の花です。
ブルメリア・クロセア・オーレアの特徴
このような花の場合には、育て方やその他の情報を知るということだけでも大変で、大雑把なことしかわからないということですが、それらの情報をそれぞれ検索しながら、確信に迫るというとてもガーデニングとは思えない作業も必要になります。ブルメリア・クロセア・オーレアという植物はアメリカのカリフォルニア州が原産の黄色い花ですが、カリフォルニア州は暖かい地方なので、
そこが原産ということでは、そのような環境で生息が可能ということがわかります。育てる場合にも、そのことが環境面ではヒントになります。またネギ科ともユリ科とも言われていますが、ユリ科という情報が多いので、ユリ科の同じような植物が近縁種ではないかということもわかります。ネギ科は、もともとユリ科だったものが独立したらしいので近いということでは親戚のようなものでしょう。
ですのでユリ科ということでしょうが、このユリ科にはチューリップやアスパラガス、ニンニクなど人間に非常に近い植物ですので、このブルメリア・クロセア・オーレアもそれほど育て方が難しいということでもないのではないかという予想ができます。
花の大きさは30センチから大きくなると70センチとか80センチになるということで、ガーデニングではちょうどよい大きさという感じもします。開花期は4月から6月で、カリフォルニア州は生息地であり原産地ですので、やはり暖かい時期に花が咲くということです。そして冬は日本は休眠期間は球根を取り出して保管するということだそうです。
-

-
ムラサキカタバミの育て方
この植物は、カタバミ科カタバミ属の植物で、日本にもカタバミという植物がありますが180種以上あるということです。また広く...
-

-
ゲウムの育て方
ゲウムは、バラ科 のダイコンソウ属(ゲウム属)であり、日本のに山に咲く「ダイコンソウ」と同じ仲間です。そのためゲウムを「...
-

-
ヒマワリの育て方
野生のヒマワリの元々の生息地は、紀元前3000年頃の北アメリカとされています。古代インカ帝国でヒワマリは、太陽の花と尊ば...
-

-
タツタソウの育て方
タツタソウ(竜田草)は別名イトマキグサや、イトマキソウ(糸巻草)と呼ばれているメギ科タツタソウ属の植物です。花色は藤紫色...
-

-
ヘレニウム(宿根性)の育て方
この花に関しては、キク科、ヘレニウム属に属する花になります。花の高さとしては50センチから150センチほどになるとされて...
-

-
ギンバイカ(マートル)の育て方
ギンバイカはフトモモ科ギンバイカ属の低木常緑樹です。ギンバイカは和名になり、漢字では「銀梅花」と書きます。これは開ききる...
-

-
観葉植物として人気のシュガーバインの育て方
シュガーバインは可愛らしい5つの葉からなるつる性の植物です。常緑蔓生多年草で育て方も簡単なので初心者の人にもおすすめです...
-

-
クコ(キホウズキ)の育て方
この植物はナス科クコ属の落葉小低木ですが、ナスの仲間ということで、その実からは何となく似ているかなという感じですが、色は...
-

-
ハボタンの育て方
ハボタンは日本で改良されて誕生したもので、海外から伝わってきたものではありません。江戸時代の前期に食用のケールがつたえら...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...




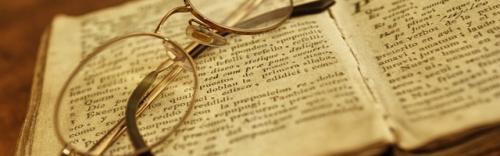





ユリ科という情報が多いので、ユリ科の同じような植物が近縁種ではないかということもわかります。ネギ科は、もともとユリ科だったものが独立したらしいので近いということでは親戚のようなものでしょう。ですのでユリ科ということでしょうが、このユリ科にはチューリップやアスパラガス、ニンニクなど人間に非常に近い植物ですので、このブルメリア・クロセア・オーレアもそれほど育て方が難しいということでもないのではないかという予想ができます。