ドイツアザミの育て方

育てる環境について
育て方としてはどのような場所にしていくかですが、日当たりを中心に場所を決めるようにします。多年草ですから毎年のように楽しむことができるので、植木鉢での管理をすることがあります。こうすれば弱い季節でも移動が可能になります。冬の寒さよりも夏の高温多湿を苦手としている花として知られています。
発芽をする温度としては15度から20度で大体春頃に徐々に発芽をするようになります。生育の適温としても15度から20度ぐらいになりますから、まさに春の時期に一気に生育をしていくことになります。暑さにもそれなりに対応しますが、この花は耐陰性もあるとされています。多少日陰においていたとしても育てることができます。
秋や冬、春などにおいては日当たりがよく当たるところで、夏になってきたら日陰のあるところに移すなどが良いかもしれません。多湿を避けるために風通しの良い所が育てるには最適になります。土壌においては中性の土壌が良いとされます。ペーハーでは6.0から7.0ぐらいです。ですから酸性に向いている、
アルカリ性に向いている場合においては土の状態を変化させてから植え付けをするようにすればよいでしょう。多年草とのことで植えっぱなしにすることが出来るかですがあまり同じ所に植えるのは良くないともされます。生育が少し弱くなってきていると感じるときは植え替えを行います。当然その時には場所を変えるなり、植木鉢なら土を変えるなりをします。
種付けや水やり、肥料について
この花の栽培に関しては中性の土壌を好みますから酸性に傾いている時には石灰などを混ぜることで中和させるようにします。もともと中性になっているようであれば特に変化させる必要はありません。種まきの時期としては秋になります。暑さが和らいできた時期を見計らって、9月の中旬から10月ぐらいを目処に行うようにします。
暑さが和らいでからとのんびりと待っていると今度は寒くなって霜が降りるようなことがあります。そうするとあまり具合が良くありません。10月内に行わないと11月になると寒くなることもあるので気をつける必要があります。最初に行うのは箱まきです。覆う土としては5ミリ程度です。軽くかぶせる程度で問題ありません。
その時には水を与えません。覆う土を予め軽く湿らせておいてそれをかぶせるようにします。いきなり水を与えると発芽が悪くなることがあるので注意をします。水やりを始めるのは翌日ぐらいからになります。本葉が2枚から3枚になってきたらポットに植え替えをして、更に6枚以上になってきたらこれから育てていく場所に定植するようにします。
水やりに関しては、鉢の土が乾いてきたら与えるようにします。乾燥にそれ程弱くありまえんから、真夏以外にはそれ程細かい管理は不要です。花壇など地植えをするときは、定植した後はほとんど水やりの必要がなくなります。肥料に関しては特に必要ありません。元肥に多少牛糞などを入れておくだけで十分育ちます。
増やし方や害虫について
植え替えをする時期としては秋の10月頃、春の3月頃とされています。鉢植えの場合は根詰まりをすることがあるため行います。根づまりすると花が咲かなくなることがあります。この花においては刺があるので十分注意して行います。素手で行うとけがをすることがあるので手袋をして行うようにすればよいでしょう。
この時には一回り大きな植木鉢を利用するようにします。用土に関しては以前使っていたものをきれいにはらうようにして全て新しい土で行います。この花は同じ環境だと花つきが悪くなることがあります。植え替えをするときにするといいこととしては株分けがあります。植え替えをするときに株が十分に大きくなっているなら行うことによって株もスッキリさせることができますし、
花も増やすことができるので育てやすくなります。花が終わったあとには花茎を切り取るようにします。そうすることで株を傷みにくくすることができます。種などを取る目的があるならそのままにすることもありますが、その次の年も普通に楽しもうとするなら早めにとっておくようにするとよいでしょう。
病気としてあるのはウドンコ病になります。若い葉、茎の表面が白っぽくなってきたらその症状になります。これは白いカビになります。特定の殺菌剤をまいたりすることで対応します。風通しが悪かったりするとかかりやすいです。アブラムシもつくことがあります。殺虫剤を利用して予防をしたり死滅させることがあります。
ドイツアザミの歴史
東京にはないのに東京なになにとつけると販売がうまくいったりサービスがうまく浸透したりすることがあります。さすがに関東地方以外でそのようなネーミングをすることはないでしょうが、関東地方であれば東京と離れていても東京なになにとつける事はあるかもしれません。その他にはイメージから外国の名前をつけるようなこともあります。
アメリカといえば世界でもナンバーワンの多い国になりますからアメリカなになになどとつけることによって良いネーミングになることがあります。アメリカと付きながらアメリカとは全く縁がないようなこともあります。花といいますと原産地などが名前に付くことがあります。学名にジャパン、ジャポンなどとついていれば日本が原産の事が多いようです。
ある花においてはドイツアザミとの名がついていました。さて原産地はドイツのどの辺りかと考えていたらなんと日本になるそうです。これは驚きです。学名においてもしっかりジャポニズムとありますから日本で見つけられたものとして管理されています。厳密に言えば日本で見つけられたではなく日本で園芸品種として作り出された花になります。
なぜドイツとついたかですが、それは大正時代ぐらいに園芸商が花を売り出すときにつけたそうです。別名としてはハナアザミと呼ばれることがあり、寺岡あざみ、楽音寺アザミなどの品種があるとされています。せっかくですから日本的な名前の方で通したほうが良いようにも感じます。
ドイツアザミの特徴
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑性もそれなりに備えている花となっています。ただし高温多湿にはあまり強くありません。日本の夏は高温多湿のことがあります。梅雨の時期はなんとか持ちこたえてもそれ以降の暑さと湿気で枯れてしまうことがあります。
草の高さとしては50センチぐらいから1メートルぐらいになることもあります。花の色は赤やピンク、その他には紫色などもあります。色はそれなりに増えているようです。発芽のための温度としては15度から20度ぐらいになりますから、春ぐらいに芽を出し始めるといえます。花が咲く時期としては5月から8月にかけて咲くとされています。
花の大きさとしては3センチ位の小さいタイプからその倍の7センチ位になることもあります。種類としてテラオカアザミがあり、これは紅色になります。ラクオンジアザミは比較的大きめの花をつけることで知られています。テラオカアザミと同じような形に咲くのがアーリーピンクと呼ばれる種類です。花の色は桃色になります。
テマリレッドと呼ばれる種類はモモベニ色になります。草丈はそれ程高くならずに70センチぐらいになります。花に関してはまさにキク科の花らしくたくさんの花びらが付きます。一つ一つの花びらは細い線のようになっています。しっかりした茎が伸びてその上につぼみが付き、上向きに花を咲かせます。
-

-
ホヤ属(Hoya ssp.)の育て方
ホヤ属の栽培をおこなう場合には、日陰などのような位場所ではなくできるだけ日のあたる明るい場所を選ぶようにしてください。耐...
-

-
バイカカラマツの育て方
バイカカラマツとはキンポウゲ科の植物で、和風な見た目やその名前から、日本の植物のように考えている人も少なくありませんが、...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
チョコレートコスモスの育て方
チョコレートコスモスは、キク科 コスモス属の常緑多年草です。原産地はメキシコで、18世紀末にスペインマドリードの植物園に...
-

-
トルコギキョウの育て方
長野県は、世界に冠たるトルコギキョウの生産地です。そしてここは、日本で初めてトルコギキョウが栽培された土地でもあります。...
-

-
ゴメザの育て方
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトス...
-

-
グラマトフィラムの育て方
グラマトフィラムの原産は東南アジアで、暑い地域の植物です。生息地では12種の原種があります。洋蘭の一種で、熱帯からヨーロ...
-

-
ウメバチソウの育て方
ウメバチソウは北半球に生息する植物です。古くから北半球に多くの地域に分布しています。品種改良が行われていて、色々な品種が...
-

-
フジバカマの育て方
フジバカマはキク科の植物で、キク科の祖先は3,500万年前に南米に現れたと考えられています。人類が地上に現れるよりもずっ...
-

-
シキミの育て方
シキミはシキビ、ハナノキ、コウノキなどとも呼ばれる常緑の小喬木です。以前はモクレン科でしたが、現在ではシキミ科という独立...




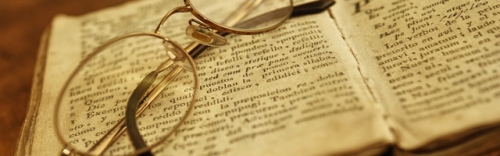





この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑性もそれなりに備えている花となっています。ただし高温多湿にはあまり強くありません。日本の夏は高温多湿のことがあります。梅雨の時期はなんとか持ちこたえてもそれ以降の暑さと湿気で枯れてしまうことがあります。