サワギキョウの育て方

育てる環境について
サワギキョウの生息地は水辺が多く、土が湿っている状態の場所を好みます。その為、比較的乾燥を嫌う植物です。しかし、しっかり根付けばそれほど環境を気にしなくても育てる事が出来ます。野山にも咲いている花ですから、とても丈夫に出来ています。ただし、日当たりの良い場所で育てる必要があります。
日当たりが悪い場所で育ててしまうと、最悪の場合花が咲かなかったり、花が咲いても色が薄くなってしまったり見栄えがあまり良くない状態の花になってしまうので注意が必要です。その為、出来るだけ日当たりの良い場所で育てるようにしましょう。ただし、鉢植えにする場合は日光の影響で高温になりやすいので、水やりには注意が必要です。
乾燥しやすくなってしまうので、夏場などは半日陰の場所に鉢を移動させる方が良いでしょう。また庭に植えている場合でも夏場、あまり乾燥した状態にしてしまうと良くないので水やりは注意が必要です。その為、直接庭に植える場合は直射日光を避け、涼しく湿気の多い所で育てるようにしましょう。
また、太陽の光が不足してしまうときれいな色鮮やかな花を見る事が出来ないので、太陽には十分当ててあげましょう。冬になると地上に出ている部分は自然に枯れてしまいます。その代わり、地下には太い根茎が残ります。この根茎が冬の寒い時期に凍りさえしなければ翌年まで越冬することができます。是非凍らないように注意しながら育てて、翌年もきれいな花を楽しみましょう。
種付けや水やり、肥料について
春または夏から秋にかけて苗がホームセンターなどで販売されるので、それらを植え付けしましょう。冬は地上部が枯れてしまいますが地下部分で根が生きているので春になると芽を出してくれます。水をあげる場合は土が乾いてきたらあげるようにしますが、常に湿っている状態を好む植物なので乾燥には十分気をつけましょう。
鉢植えやプランターで育てている場合は、土が乾燥し始めたら鉢の下から水が染み出してくるくらいたっぷりあげるようにしましょう。肥料をあげる場合は植え付けをする際に土の中に肥料を混ぜておくと良いでしょう。春から秋に掛けては液体肥料を二週間に一度くらいあげるようにします。肥料を好む植物なので、栄養が不足してしまうと生育不良を起こしてしまいきれいな花が咲かなくなってしまいます。
しっかり栄養をあげてきれいな花を咲かせてあげましょう。肥料はホームセンターなどで販売されている花と野菜の土で大丈夫です。一株だけ植えている場合でも、種がこぼれ翌年にはまた芽が出てくるでしょう。また、大きくなってきた場合、根詰まりを起こしてしまう可能性があるので植え替えをしてあげると良いでしょう。
植え替えを行う場合は、地上部が枯れてしまう11月頃か、芽が出る前の春先に行います。出来れば2年に一度程度植え替えをしてあげると良いでしょう。あまりに成長してしまい、鉢から根が出てしまう場合は、時期でなくても植え替えをして挙げた方が良いでしょう。
増やし方や害虫について
種から育てる場合は10月頃がお勧めです。秋に出来た種を収穫してまけば簡単に増やす事が出来ますが、特に種をまかなくても上記であげたように種が散らばるようにこぼれる為、勝手に増えていきます。他に秋に株分けをして増やす方法や、春先に挿し芽して増やす方法もあります。
挿し芽は摘心した穂を硬質鹿沼土に挿せば、2週くらいで根が出てきます。植え付けを行う際は緩効性肥料を入れてあげると良いでしょう。害虫はハダニが付いてしまう場合があるので、見つけ次第駆除してあげると良いでしょう。それほど害虫の心配はありませんが、虫が付いている場合は早急に駆除してあげる方が良いでしょう。
肥料を好む傾向にあるので、十分に与えてあげると色鮮やかな花を咲かせてくれます。逆に栄養が足りなくなってしまうと、色の出が悪くなってしまうので注意しましょう。サワギキョウは本当にきれいな花を咲かせてくれる植物になります。野山に咲いているだけに、環境にも順応性があり優れている植物です。華奢な花ではありますが、群生していると本当に見事です。
青紫の花だけではなく、赤い花の種類もあるので、是非その色を楽しんでみましょう。また、比較的に増やし方も容易で、自然に増えていきます。こぼれ種でもしっかり芽を出してくれるので、是非たくさん増やして、その花の色を楽しんでみましょう。緑色の葉と、青紫の花がとても似合っており、どことなく優しい印象を与えてくれる花になります。
サワギキョウの歴史
キキョウ科の多年草で,アジア東部の冷温帯を生息地としている”サワギキョウ”。学名”Lobelia(ロベリア)”とも呼ばれ、この名前は16世紀のイギリスの植物学者”Lobel”の名前にからきています。サワギキョウは日本にも自生しており、とても丈夫な植物です。原産地は日本や中国となっており、「沢に咲くキキョウ」から「サワギキョウ(沢桔梗)」の名前が付きました。
日本では北海道から九州まで生息しています。青い花のものが一般的ですが、流通しているものの中には、赤やピンクの物が多くあります。サワギキョウは花が咲くとまず、雄しべから花粉が出てきます。サワギキョウは古くからある植物になっており、きれいな花を咲かせますが実は毒草です。沖縄を除き全国に生息し約200種類ほどもあります。
日本には5種程が分布しています。見た目が特殊な形をしており、とても繊細な花を咲かせます。毒薬として有名ですが、薬としても役立てる事が出来るそうです。禁煙補助剤に使用されたり、覚醒剤やコカインなどの薬物依存症の治療薬としても使用されています。
日常的にそれほど手入れをする必要がないので、比較的育て方も簡単な植物です。鮮やかな色合いの花はとても見栄えがする美しさです。どこか上品で繊細な印象を与えてくれ、とてもきれいな花になります。花言葉は「高貴」「繊細」です。その名の通り、どこか高貴で貴婦人のような印象さえ与えてくれる花になります。
サワギキョウの特徴
このサワギキョウは”キキョウ”の名前が付いていますが、花冠が2唇形を呈し、おしべは合生しており花柱を中心に囲んでいるなど、キキョウの花とは違っている箇所がたくさんあります。サワギキョウと呼ばれていますが、花や葉の形も違います。茎や葉には毛がありません。茎は高さが50cmから100cm程で、太さが約1cm程度です。
赤い色の花を咲かせる種類のものもあり、そちらの花はベニバナキキョウと呼ばれています。サワギキョウは分枝しないのが特徴です。葉は多数が互生しており、披針形をしています。花はおく青紫色をしており大変きれいです。形も特殊な形をしており、まるで鳥が飛んでいるかのような形をしています。山地の湿った草地や湿原などに生息しており多年草です。
群生させて栽培すると大変見応えがある美しい花です。下から上へと順に花が咲いていきます。深く切れ込んだ花びらが印象的です。7月から8月にかけて花が咲きます。草丈は50cmから100cm程度にまで成長します。庭先やプランター、鉢植えなどでも楽しむ事が出来ます。毒草になりますが、一見毒草には見えない花になります。
大量に扱わなければそれほど強い毒ではありません。花の後に実がなりますが、熟すと下部が裂けて食べが散布されるしくみになっています。不思議な形をした花がとても印象的で、見ていて飽きない花になります。湿地に生息しています。緑の中で青紫色の花が一層引き立つ植物です。
-

-
セルバチコの育て方
セルバチコはイタリア原産の植物です。イタリア語で「ルケッタ・サルバティカ」といいますが、「サルバティカ」というのは「野生...
-

-
タツナミソウの育て方
タツナミソウはシソ科の仲間で世界中に分布している植物なので日本でも全国的に見ることができます。花の形が独特であるという理...
-

-
ドラセナ・フラグランス(Dracaena fragrans)...
ドラセナの原産地は、熱帯アジアやギニア、ナイジェリア、エチオピアなどのアフリカです。ドラセナの品種はおよそ60種類あり、...
-

-
シダルセアの育て方
シダルセアは、北アメリカ中部、北アメリカ西部が原産国です。耐寒性はある方で、乾燥気味である気候の地域を生息地として選びま...
-

-
スイセンの育て方
スイセン、漢字で書くと水仙。この植物は、ヒガンバナ科(旧分類だとユリ科)スイセン属の多年草です。地中海沿岸やスペイン、ポ...
-

-
枝豆の育て方
枝豆は大豆になる前の未成熟な豆のことです。大豆は東アジアが生息地で、自生していた野生のツル豆が中国の東北部で進化したこと...
-

-
ツルハナナスの育て方
ツルハナナスの名前の由来は、つる性の植物であるために「ツル」と、またナス科の仲間であるためその花は紫の綺麗な色をしている...
-

-
ニンジンの上手な育て方について
ニンジンは、春まきと夏まきとがあるのですが、夏以降から育てるニンジンは、春に比べると害虫被害が少なく育てやすいので、初心...
-

-
ゲンノショウコの育て方
この植物の原産地と生息地は東アジアで、中国大陸から朝鮮半島を経て日本全国に自生しているということですので、昔から東アジア...
-

-
観葉植物としても人気があるイチゴの育て方
イチゴは収穫が多く病気や虫に強いので、家庭菜園で人気です。イチゴの中でも比較的葉が多いワイルドストロベリーは観葉植物とし...




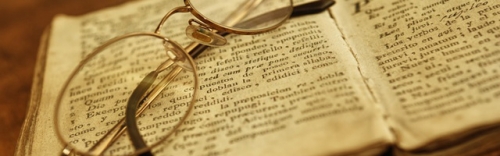





キキョウ科の多年草で,アジア東部の冷温帯を生息地としている”サワギキョウ”。学名”Lobelia(ロベリア)”とも呼ばれ、この名前は16世紀のイギリスの植物学者”Lobel”の名前にからきています。サワギキョウは日本にも自生しており、とても丈夫な植物です。