フリージアの育て方

フリージアの育てる環境について
育て方ですが、フリージアは南アフリカ出身でその生息地の多くは夏場乾燥し、冬に湿潤となる地中海性気候です。寒さには弱く、寒風や霜にあたると葉が黒く傷んでしまいます。だいたい13〜15度を適温とし、冬場も3度以下にならない場所が望ましいので、ベランダや軒下など屋根のある場所にサッと移動できるよう鉢植えにするのが良いかもしれません。
霜の心配がなければ露地での冬越しもできますが、腐葉土などで防寒対策を施してあげましょう。日当たりと風通しの良い場所を選んで栽培します。日当たりが悪いと、葉や茎がヒョロヒョロと無駄に伸びてしまいますので、よく日に当てて丈夫でバランスの良い葉や花茎を作ります。花を長く楽しむためには20度以下に温度管理すると良いでしょう。
20度以上になると急速に開花が進んでしまいます。15度くらいに保つと花も長持ちし、次々に咲いて長期間鑑賞することができます。見た目をキレイにするためと株の消耗を抑えるため、萎れた花がらはそのつど摘み取っていきます。最終的に花茎を根元から切り落としてしまいますが、葉は花が咲いた後も生長に必要な部分ですので切らずに残します。
土壌は、水はけと通気性が良く適度に保水性のある土が適しています。市販の草花用培養土でも構いません。自分でブレンドする場合は、赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1くらいの割合で混ぜます。連作を嫌うので、同じアヤメ科の植物を植えた土は避けるようにします。
フリージアの種付けや水やり、肥料について
球根の植え付けの適期は秋です。10月下旬から11月頃に行います。鉢植えは5号鉢に7〜8球、65センチのプランターに15〜20球が植え付けの目安になります。球根の頭が隠れる程度の深さに植えて、その後葉が10センチほどに伸びてきたら株元がぐらつかないように1センチ程度増し土をします。
地植えの場合は十分な深さがあるので初めから深めに、3センチくらいの深さで植え付けます。水やりは、芽が出るまでは土を乾かさないようにたっぷりとあげましょう。地上部では変化がなくとも、土の中ではしっかり根を張らせようと頑張っています。
葉が伸びてきたら今度は水を控えめに、特に冬は乾燥気味に育てます。水のやりすぎは花茎が軟弱に伸びすぎて倒れやすくなります。特に鉢植えの場合はかけすぎると花茎が垂れ下がってきてしまうので気をつけましょう。
冬0度以下になるような時も、用土が凍ってしまう可能性があるので、太陽が出ていない寒い日は無理に水やりをしなくても構いません。花茎伸びてきて株元がぐらつくようであれば、適宜支柱立てを行います。ぐらついた拍子に、重みで球根が割れてしまうことがありますので注意が必要です。
肥料は、植え付けの際にゆっくりと効くタイプの化成肥料を混ぜ込みます。鉢植えなら1ℓあたり3g、地植えであれば1㎡あたり100g程度です。その後、3月中旬頃に液体肥料や化成肥料を規定の量だけ追肥します。よく肥えた土であれば無肥料でも構いません。
フリージアの増やし方や害虫について
フリージアは球根で増やしていきます。そこで花が咲き終わり花茎を切った後も水やりと追肥を行います。球根に栄養を与え分球を促し、子球を太らせるためです。6月頃葉が少し黄色く変色し始めたら球根を掘り上げます。
掘り上げた球根は土を落とし、根や茎、古いしぼんだ球根など余分なものを取り除き、涼しい日陰で乾燥させます。ネットなど通気性の良い袋に入れ、冷暗所で雨に当たらないようにして秋まで保管しましょう。
植え付けの時期になったら、親球のまわりについた小さな子球を一つ一つ手で外して植え付けます。秋でも9月などの早い時期に植えると、冬までに葉が大きく伸びて寒さによる害をひどく受けてしまいます。そこで11月と遅めに植え付けるのがコツです。
冬は生長が遅くても春になり気温が上がると一気に葉を伸ばし花をつけるので心配はいりません。また連作を非常に嫌がる植物なので、球根の掘り上げ、植え付けは面倒でも毎年必ず行いましょう。フリージアには大きな病害虫はありません、
例として春先にアブラムシがつくことがありますので早めに薬剤を散布して駆除しましょう。また、ウイルスが原因のモザイク病にかかると葉が変形したり斑点ができ、まともに育たなくなります。ほかの株にうつるとやっかいなので、
残念ですが病気にかかった株は処分してください。茎や球根が褐色に変色する菌核病にかかることもあります。こちらは殺菌剤の使用で予防することが可能です。
フリージアの歴史
フリージアは南アフリカ原産のアヤメ科の植物です。ケープ地方に10種類あまりが分布していますが、現在よく栽培されているものは、フリージア・レフラクタ、フリージア・アームストロンギー、フリージア・コリムボーサなどをもとにした園芸品種です。
南アフリカで植物採集をしていたデンマークの植物学者エクロンによって18世紀の中頃に発見されました。フリージアの名前はエクロンの親友であったドイツ人医師フレーゼに由来していると言われます。また南アフリカの植物を研究していたスウェーデン人「フリーズ」の名を記念したという説もあります。
蘭にも似た花が春の訪れを香りで伝えるので、コウセツラン(香雪蘭)という美しい中国名もあります。ヨーロッパに紹介されるやその香りが瞬く間に人気を呼び改良が進められました。1878年イタリアで最初に交配が行われて以後、主にイギリスやオランダでの盛んな品種改良により今では150を越える園芸品種が誕生しています。
日本に入ってきたのは明治の後半、オランダから球根を輸入したのが最初と言われています。淡黄色の品種だったためアサギスイセン(浅黄水仙)の和名がつけられましたが一般的には使われていません。その後昭和になって本格的に栽培されるようになりました。
当時はレフラクタの白花種アルバと、黄花の園芸品種バターカップが栽培されていました。昭和30年代頃になって、オランダからさらに多くの園芸品種が導入され、現在のような色彩豊かなフリージアが出てくるようになりました。
フリージアの特徴
フリージアは半耐寒性の球根植物です。秋に球根を植えると春に開花します。開花期は3〜5月で、11月〜翌3月頃に市場に出回ります。やや丸みのある花を穂状に咲かせ良い香りを発し、鉢や庭に植えたり、切り花をフラワーアレンジメントや花束に使用して楽しみます。
先が尖った剣状の葉を数枚出して、そのすき間から花茎を長く伸ばします。花茎は上の方では水平に伸びていき、そこに10輪前後の花を咲かせます。色は原種の白・黄色・濃いピンクのほかに、改良された園芸品種には赤やオレンジ、ピンク・青・紫とさまざまで、咲き方も八重咲き・半八重咲き・大輪と多彩です。
初夏になると葉が黄色く枯れてラッキョウによく似た球根の状態で夏の間休眠します。草丈は30〜50センチ程度ですが、切り花用に改良されたものは1メートルになるものもあります。アフリカ原種である黄色や白のフリージアはキンモクセイのような甘い強い香りが特徴です。
その他の色はそれほど強くありませんが甘酸っぱいフルーツに似た芳香があります。バラやキンモクセイ、ジンチョウゲと並んで人気のある香りのようです。また、花の色によって異なる花言葉を有しています。
白はあどけなさ・慈愛・親愛、黄は無邪気・天真爛漫、赤は純潔、紫はあこがれ、淡紫は感受性を表しています。明るい色彩とほのぼのとした可愛らしい花の姿、さわやかで甘酸っぱい香りが純真無垢なイメージを想起させることに由来しているのでしょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヒメシャガの育て方
タイトル:カキツバタの育て方
タイトル:ブルーハイビスカスの育て方
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...
-

-
バンダの育て方
原産地は赤道を挟んだ北緯南緯とも30度の間の国々で主に熱帯アジア、インド、オーストラリア北部、台湾などがあります。また標...
-

-
温帯スイレンの育て方
スイレンは古くから多くの人に愛されてきた花です。そんなスイレンには温帯スイレンと熱帯スイレンがあり、温帯スイレンは耐寒性...
-

-
スイカの育て方
栽培スイカの原産地と言うのは、色々な説が在ります。しかし、最も有力とされるのが、1857年にイギリス医療伝道者がアフリカ...
-

-
ミヤマクロユリの育て方
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下...
-

-
主婦の間で密かなブームとなっている栽培方法
現在、主婦の間で密かなブームとなっているのが、お金のかからない種取り栽培です。これは、スーパーで買ってきた野菜や果物のタ...
-

-
ザゼンソウの育て方
ザゼンソウは、ザゼンソウ属サトイモ科の多年草の草木です。学名はSymplocarpusfoetidusで、漢字では座禅草...
-

-
スイートピーの育て方
スイートピーは西暦一六九五年に、カトリックの修道僧で植物学者でもあったフランシス・クパーニによってイタリアのシシリー島に...
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
ユリオプスデージーの育て方
特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当...




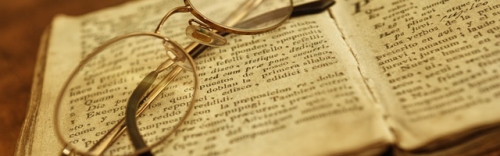





フリージアは南アフリカ原産のアヤメ科の植物です。ケープ地方に10種類あまりが分布していますが、現在よく栽培されているものは、フリージア・レフラクタ、フリージア・アームストロンギー、フリージア・コリムボーサなどをもとにした園芸品種です。