オカヒジキの育て方

オカヒジキの育てる環境について
オカヒジキは生育期間が短く根群が比較的貧弱で、果菜類などの間作に適しています。育て方は、日あたり・風通し・水はけ・水もちの良い環境で行います。英名salt-wort(塩の草)というくらいで潮風には強いですが酸性の土壌は嫌い、適したpHは6.0〜8.0くらいです。
また粘土質な土壌でも発芽や発育が悪くなります。種をまく前に苦土石灰や完熟堆肥を混ぜ込むなどして、水もちのよい弱アルカリ性の土作りをしておくと良いでしょう。例として、種まき1ヶ月ほど前に苦土石灰を1㎡あたり100グラム施し、2週間ほど前になったら、
完熟堆肥1~3キロと即効性の化成肥料を40~50グラム施すというように行います。暑さには強いですが、真夏には発芽率が低下し立ち枯れの危険性も増します。生育に適した気温は15~25度です。7~10月日が短くなる頃に花を咲かせます。
花がつくようになると葉や茎が硬くなり食用の利用に適さなくなってしまいますので収穫はその前に行いましょう。種をまく時期が遅いと花がつきやすくなりますので、種まきの適期を逃さないようにします。草丈10~15センチになったら収穫ができます。
柔らかい先端の10センチほどを摘み取り収穫します。収穫が遅れても葉茎は硬くなるので、大株にしないようして早めに摘み取り利用します。収穫後に追肥すると新しくわき芽が伸びてきて長期間にわたって収穫をすることができます。株ごと抜き取って収穫してしまってもかまいません。
種付けや水やり、肥料について
種まきの適期は4~5月で、発芽の適温は20~25度です。10度以上あれば芽を出しますが、30度以上になると発芽しにくくなります。種は休眠が深く、休眠中の種をまいても発芽しません。種まきの前に、種を1日水につけて湿った状態で冷蔵庫に10日程度入れて低温に合わせてあげると発芽率が良くなります。
また短命種子で2年目のものはほとんど発芽しません。適期になったら土作りをして、20センチ間隔でスジまき、またはバラまきします。プランタを使うのであれば深さ10センチ以上の容器を使用し株間10センチ程度を目安にします。それから厚さ5ミリほど薄く土をかぶせ、
ギュッと軽く押さえて種が土から水を吸いやすいようにしてあげます。種まきの後強い雨にあたると、種が流れ出したり土がかたくなって発芽不良になることがあります。できれば芽が出るまでは不織布で覆うなどしておくと良いでしょう。
初期はゆっくりと発育する植物ですのでなかなか発芽・生育しなくても心配する必要はありません。ただ周りの雑草に負けてしまわないよう、丁寧に草取りを行ってください。本葉が出たら間引きを行い、本葉3~4枚の時に株間8センチくらいで1ヶ所1本になるようにします。
その後も混み合ってきたら間引きます。水と肥料が不足すると葉や茎は硬くなります。土を乾かさないように適宜水やりを行います。生育中の追肥は2週間に1回程度、液肥または固形肥料を与えます。水と肥料を切らさないようにして管理しましょう。
増やし方や害虫について
オカヒジキは、収穫の適期をすぎ花をつけた後に種ができるので採取して翌年まくことができます。秋に採取した種は数ヶ月間休眠します。とくに採取しなくても、自然に種がこぼれ落ち春になったら芽を出し増えていくこともあります。もともと海岸に自生する植物ですので強いと言えます。
まれに連作障害が出ることがあるので、健全に育てようとするなら同じ土壌は避け少なくとも1~2年は土を休ませたほうが良いでしょう。収穫後の耕作前に、十分に堆肥を入れておくと連作障害を和らげることができます。また病害虫には強いですが、高温多湿で病害が発生することがあります。
対策としては、畝を高くするなどして水はけを良くし、株が混み合ってきたら間引いて風通しを良くしておきます。アブラムシがつくことがあるので、日頃からよく観察して早めに見つけて速やかに駆除するよう努めましょう。ついてしまったら殺虫剤を散布するか、
殺虫剤の使用がためらわれるようであれば石けん水を薄めたものか牛乳を散布してこまめに駆除します。完熟堆肥などの有機物をたっぷりと土に与えて、よく根がはるような土作りを心がけましょう。根が健康で丈夫に育てば、地上部の葉や茎も健康に育ち結果的に、
病害虫に強い株になります。近年の海岸開発などで徐々に自生地を減らし天然のものは絶滅が危惧されている状況にあります。比較的育てやすく、栄養豊富でクセのない野菜ですので、家庭菜園で育てて楽しむのに大変適しています。
オカヒジキの歴史
オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地とする野草の一種です。見た目がヒジキに似ていることからこの名がつきました。陸の海藻とも呼ばれます。
漢字では「陸鹿尾菜」と書き、水松菜(ミルナ)・オカミルの別名もあります。古くから自生していましたがそれほど認知されていませんでした。室町時代以前の文献にはオカヒジキについての記述が見当たりません。江戸時代中期、財政の貧しかった米沢藩の藩主上杉鷹山が、
食料費節約のために食べられる野草を探すよう家臣に命じました。その時海岸に自生するオカヒジキも注目され、新たな農産物として栽培が推奨されたといいます。山形県庄内地方について書かれた「松竹往来」(1672年)にも、北俣の「岡ミル」が物産品として紹介されています。
北俣は海から離れた山間部にあるのでオカヒジキが自生していたとは考えにくく、この頃には栽培が始まっていたのではないかとされています。そのような歴史から山形県では現在でも身近な野菜として広く食べられています。江戸時代後期の本草書「本草図譜」(1828年)にも絵付きで登場しています。
最近ではその栄養価の高さに注目が集まりスーパーなどでもよく見かけるようになりました。市場に流通しているものはハウスなどで栽培されているものです。山形県のほか長野・静岡・千葉などでも栽培されています。
オカヒジキの特徴
オカヒジキはアカザ科オカヒジキ属の一年草です。草丈は30センチほどで多数の枝を生やして地面に広がっていきます。細い円柱状の肉質な葉をしており、若い茎や葉を食用にします。淡白で食感がよく近年需要が高まっている食材です。
栄養価が高くビタミン類、ミネラル類、葉酸などをバランスよく含みます。100グラムあたりのβカロチンは小松菜より多く、カルシウムも牛乳よりも多くホウレンソウの3倍以上も含まれています。ほかにも食物繊維が豊富です。
食材として選ぶ時は、葉や茎にツヤとハリがあり柔らかく、みずみずしい緑色のキレイなものを選びます。鮮度が落ちると葉や根元が変色してしまいます。また育ちすぎたものは葉がかたく食べにくくなります。乾燥すると食感が悪くなるので、
ポリ袋や保存用の袋に入れて野菜室で保管しますが、あまり日もちはよくありません。おひたし、和え物、炒め物、揚げ物、サラダ、汁物の具材にと幅広く活躍します。シュウ酸が含まれているので水でよく洗って1〜2分ほど軽く茹でてから調理すると良いでしょう。加熱のしすぎは食感を損ないます。
根元がかたい時には切り落としておくと食べやすいです。炒め物や天ぷらにする時にはそのままでかまいません。イタリアのトスカーナ地方でもよく食べられており、茹でてオリーブオイル・レモンとあえたり、パスタにからめたりします。「修道士のヒゲ」という意味の「バルバ・ディ・フラーティ」という名前で呼ばれています。
-

-
皇帝ダリアの育て方
ダリア属は、メキシコから中米に27種が分布しており、茎が木質化する3種がツリーダリアと呼ばれています。皇帝ダリアもその一...
-

-
チューベローズの育て方
チューベローズはリュウゼツラン科であり学名をポリアンテスツベロサと言い、球根に由来するラテン語となる塊茎状のツベロサの意...
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...
-

-
ネオレゲリア(Neoregelia)の育て方
ネオレゲリアは株を植えつける植物で、種からの栽培方法はありません。株の植えつけを行う際には、ヤシの実チップや水ごけを使用...
-

-
ヒマラヤスギの仲間の育て方
ヒマラヤスギはヒンドゥー教では、古来から聖なる樹として崇拝の対象とされてきました。ヒマラヤスギの集まる森のことをDaru...
-

-
ウェデリア(アメリカハマグルマ)の育て方
ウェデリアは地面を這いながら成長が特徴の這い性のキク科の植物であり、常緑の多年草になります。原産地は中央アメリカから南ア...
-

-
サボテンの育て方
サボテンといってもその名前が指す種類はとても幅広いです。一つ一つ特徴も異なることでしょう。しかし、一般の人々がサボテンと...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
セルバチコの育て方
セルバチコはイタリア原産の植物です。イタリア語で「ルケッタ・サルバティカ」といいますが、「サルバティカ」というのは「野生...




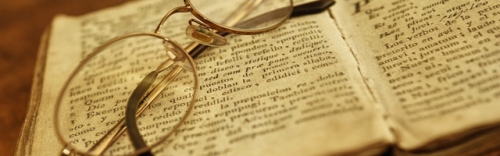





オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地とする野草の一種です。見た目がヒジキに似ていることからこの名がつきました。陸の海藻とも呼ばれます。