アジュガの育て方

アジュガの育てる環境について
日陰でも育ちやすいシェードガーデンに向く植物として、イングリッシュガーデンでは扱われていますが、日本でも同様に、あまり日が当たらない場所に植えても育ち、管理が難しくない植物として広く栽培されています。土質は乾燥に弱いので、水はけが良い事が大切で、日当たりは半日陰が向いています。
直射日光が強く当たる時間が長いと枯れる事があります。また、枯れた状態のまま放置するとうどん粉病などにかかりやすいので、花が終わった後の落ちた花びらなどをこまめに取り除く事が大切です。高温にさらされたり、湿度が高くなりすぎると病害虫の被害が増えますので注意する必要があります。
雑草の除草の必要が減るので、アジュガやシバサクラを植える地域もありますが、シバサクラが一定の広さへ広がる早さと比べ、アジュガの方が1.5倍程度早く広がるので、広い場所に植えられています。花の勢いが4~5年ほどすると弱くなるので、その場合は株分けで新しくしておくと長く楽しめます。
密集したランナーは一定間隔で抜いたり切ったりして風通しを良くする事で、株が蒸れるのを防ぐ事ができます。特に気温が高い時は水の与えすぎは禁物です。鉢植えの場合は腐葉土やピートモスが多目の、赤玉土7、腐葉土3の割合で混ぜ込んだ土に植えます。
地植えなら植え込みの手前や落葉樹の下、畑の畦などが向いています。だいたい10~20cm間隔で植えていきます。鉢植えでは数年たって株が枯れてきたら株分けをして植えなおします。また、寒さが0度を下回る地域では霜よけを必要とします。
アジュガの種付けや水やり、肥料について
ランナーで増やす方が一般的で、種で増やす事はあまりありません。種で育てると株分けよりも育つスピードが遅くて管理がしにくい事が理由です。種付けをする場合は種まき用土でごく浅く土をかぶせて発芽を待つ必要があります。
一方、株分けは時期をあまり選ばずにできる事でアジュガを栽培する時には多く選ばれている増やし方です。植えつけてからランナーを伸ばして増えていく植物ですので、混雑させると株が蒸れてしまい、病気や害虫がつきやすくなるので注意します。
あまりにも勢いが良くなっている時は、一定間隔を保って生えるように切って整える必要があります。また、立ち上がって咲く花も切りそろえておくと整った印象になります。水の与え方は、暑い時期には乾燥に注意してほど良く水やりをしますが、日の当たる時間に与えない事を注意します。
株が蒸れてしまって枯れる可能性が高くなります。育て方が簡単ですが、花後の花の処理として、こまめに捨てる事を心がけます。枯れた葉もカビ菌を付着させる伝染病を発生させる原因となるので除去を早めにする事が大切です。肥料はあまり必要がない植物ですが、
ゆっくり効く肥料を植えつける前に土に混ぜ込んでおく方法があります。あまり肥料を与えすぎると逆効果で、株が弱ってしまって枯れる可能性がありますので注意が必要です。肥料を与える場合は株が弱っている様子なら、花が終わった後に、ごく少量、ゆっくりとした効果がある肥料を使う事が大切です。
アジュガの増やし方や害虫について
アジュガを育てる時に、株が集まりすぎる事によって発生する、蒸れなどの湿度の高さには注意する必要があります。株がどんどんランナーで増えていくので、そのままにしておいても多くの場合はグランドカバーの植物として初心者にも管理が簡単ですが、
ランナーが伸びにくい段差がある場所や、狭い所に新しい株が育っている場合、密集してしまう事があります。この場合は早めに株分けをし、他の場所へ植え替える事が大切です。そのままにすると湿度が高い状態になり、病気や害虫がつく原因となりますので、生育環境をチェックする必要があります。
また、ミントなどと違って生育が遅いので、ランナーで広がりすぎて他の植物を圧迫するほどの勢いが無く、管理はしやすい植物です。油断して放置しておくと、蒸れている状態に気がつかず、うどん粉病や立ち枯れ病になりやすいので注意します。
土が固くて排水が悪い場合は土にピートモスや砂を混ぜ込んで植えつけると良い状態になります。ランナーで増えていく植物ですから、ランナーを乾燥させすぎないことも注意しておきます。過剰に水やりを気にする必要はありませんが、広がってきたランナーが見苦しい場合は切りそろえます。
害虫はハダニ、アブラムシに注意する必要があります。アジュガはアリを受粉のために呼び寄せているので、アブラムシもつきやすくなります。こまめに葉の状態を見て、薬剤を散布して除去します。主に春先に多く発生します。
アジュガの歴史
薬草や園芸観賞用の花として、アジュガはヨーロッパ、中央アジア原産で江戸時代に伝来した歴史があります。また、日本でも数種類が本州や九州に自生しているとされ、シソの仲間です。アジュガは40種類と種類が多く、和名をキランソウと言い、漢方薬として鎮咳、去痰、健胃などの効果があるとされています。
キランソウの名前の由来として、2つの説が存在します。びっしりと開花時には地面を美しい花で覆いつくす事から、同じく美しい織物である金襴から連想して名づけられました。また、もう一つは花の色にちなんだ命名ではないかとする説、紫を意味する古語は、
キ、そして藍色を意味するラン、この紫藍色が語源となった説があります。また、日本にあるアジュガでは、ジゴクノカマノフタという名前を持つ種類があり、これは薬用として医者要らず、医者泣かせ、などの別名を持っています。
一説によると、この薬草としての効果を教えたのは弘法大師であるとされ、この植物の別名としてコウボウソウの別名もあります。アジュガの仲間は薬草やハーブとしても、様々な研究の対象となっている有用な植物です。園芸品種としてのアジュガは、グランドカバーとして好まれていますが、
花の時期になると20cmほどの花序が立ち上がって開花します。また、ハーブではビューグルという呼び名があり、カーペンターズハーブという異名を持っていました。昔ヨーロッパで、血止め、打ち身や切り傷の治療薬として使われていた為です。
アジュガの特徴
アジュガはシソ科で、生息地をあまり選ばないで育てやすく、ジュウニヒトエなどが仲間であり、日本でも馴染みのある植物です。そして、植え付けに際しては育て方が簡単である事と、ほふく性の広がり方で増えていく所が特徴的です。
多年草ですが、その管理は植えてから翌年以降には中級程度の知識を必要とします。それというのも、生育のスピードがあまり早くないので、どのように庭などで栽培するのかをイメージして植えていく必要があり、しかも、株がランナーで増えていくので、その広がり方を管理できるかどうかで、
グランドカバーとしての役割を発揮させられるからです。植え方の組み合わせに関しても、色合いを考えて配置していく必要があります。葉の色が暗めの緑色なので、理想的な組み合わせとしては明るい葉色の植物との対比を考えて植えられる事が多くあります。
カメムシの仲間などがあまり好まない事から、虫除けの効果を期待して植えている地域もあります。作庭やガーデニングではカバープランツとして表示活用されている事が多く、雑草の発育を妨げる目的で植えられる事が多くなっています。
植えて美しく花を楽しめて、そのうえ、アジュガは古くから薬用の効果が国内外で民間療法として広く認識されている事が特徴で、アジュガの40種類ほど仲間のうち、特にキランソウ、生薬としての表示名を筋骨草、別名をジゴクノカマノフタ、などという種類は、有用植物として漢方薬で現代でも活用されています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アマドコロの育て方
タイトル:アスコセントラムの育て方
-

-
植物の育て方を勉強する
現在は、家庭菜園などで野菜を栽培している人たちも多く存在しています。自分で手入れをして栽培した野菜を食する事ができるのは...
-

-
フィゲリウスの育て方
フィゲリウスはゴマノハグサ科に属している植物です。また別名をケープフクシアといいますが、花の形は他の植物と少し変わってお...
-

-
ヒメツルソバの育て方
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。...
-

-
キキョウの育て方
キキョウとは日本史が好きな方なら、ご存知の方も多いことでしょうが明智光秀の家紋として使用されているのが、このキキョウなの...
-

-
スズメノエンドウの育て方
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草...
-

-
バラ(バレリーナ)の育て方
バレリーナの特徴としてはまずはつる性で伸びていくタイプになります。自立してどんどん増えるタイプではありません。ガーデニン...
-

-
ビオラの育て方
ビオラの生息地は世界中に広がっており、温帯地帯に500種ほどが自生しているとされ、私たちにとってもっとも身近な植物の一つ...
-

-
エランギスの育て方
エランギスとは、アフリカ東部原産で、ラン科に所属するエランギス属の植物の総称です。品種的にアングレカム属に近いとされ、長...
-

-
ニゲラの育て方
地中海沿岸から西アジアが原産の一年草の植物です。ニゲラの仲間はおよそ15種類がこの場所を生息地としています。この中でもニ...
-

-
ポンテデリアの育て方
ポンテデリアの生息地は主にアメリカとなります。原産地は北米南部となっていますが、北アメリカから南アメリカの淡水の湿地など...




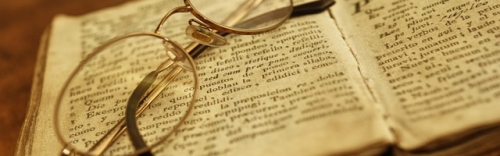





薬草や園芸観賞用の花として、アジュガはヨーロッパ、中央アジア原産で江戸時代に伝来した歴史があります。また、日本でも数種類が本州や九州に自生しているとされ、シソの仲間です。