モミジアオイの育て方

育てる環境について
モミジアオイのようなフヨウ類の魅力は、夏の暑さにびくともしないというところです。どんなに世話をしても夏の暑さにだらりとする植物が多い中、この花だけは、凛と輝いています。暑さに強い花でも、半日は、日陰が必要ですが、この花は、炎天下も平気で、大輪の花を咲かせ、そのハッとする鮮やかな姿で、栽培者を迎えてくれます。冬は地上部が無くなり、根の状態で越します。
寒さには強い方ですが、地上部は枯れます。土の中で根だけで生きていて、春がくるのを待ち続けます。ほかの草花は、移動させて、霜に当てないようにするなど、手がかかりますが、この花は、根以外が枯れてしまいますので、気の遣いようもありません。せめて、土が凍らないように腐葉土やわらなどを、そっとかぶせて、土が凍らないようにしてやればよいでしょう。
気にすることは、ひとつだけで、湿り気が必要だということです。湿気を好みますから、水は、欠かさないようにしてやることが大事です。そうしているうちに春になると、芽が出てきますし、つぼみも付きます。そして、夏には、去年同様の、背の高い大輪の鮮やかな花が、庭に咲き、北アメリカの東南部の雰囲気を漂わせます。
一般的な園芸店などには、あまり出回っていないので、植え替えで株分けをして、増やす人もいます。流通が盛んでないので、まだまだ珍しい花ですから、大きすぎるところが難儀ですが、見る人たちの驚きを見るだけで、栽培して良かったという快感を味わうでしょう。
種付けや水やり、肥料について
モミジアオイを鉢植えで育てるのであれば、土の表面が乾きだしたら、流れ出るくらいにたくさんの水やりをします。春夏秋冬に強いと言っても、乾いた土に根を張り続けられる植物ではありません。湿気を好みますので、雨水が少ない時は、しっかりと補充しましょう。ただし、どの植物もそうですが、必要以上に土が湿気ていることは、環境を悪くしますから、水はけには気を付けておきましょう。
受け皿に水をためるという形で、吸い上げられるようにしておくという工夫をするのも良いでしょう。庭植えの場合は、植木鉢のように、水をやり続けなくても、適度に土が保水されますから、植えつけた時から、落ち着くまでの10日程度、土の表面が乾かない程度に与えれば、その後は不要です。
放っておいても育つ強い花ですが、放ったままですと、育ちが悪いですし、花もあまりつかなかったりしますので、生育の状況を見ながら、肥料を与えましょう。植えつけの時に、じわじわと効果のある肥料を混ぜ込んでおけば、順調に育ち、たくさんの花をつけて、魅惑的な姿を、毎日楽しませてくれるでしょう。
植えつけに良いのは、春の終わりから初夏です。用土が肥えていれば、それだけ、しっかり根を張ります。背が高い花ですから、根が張ることは、とても大切です。だから、植木鉢の場合は、できるだけ大きなものを用意して、根が長い茎を支えられるようにしておかなければなりません。土そのものも、たまの栄養補充も心得ることと、よどんでしまい腐ることのないようにすれば、無事に育ちます。
増やし方や害虫について
かかりやすい病気も害虫被害も、特別にない草花です。水持ちの良い土を好みますから、水のやりすぎや水が土にたまり、履けない状態などを作ってしまうと、腐ってしまったり、湿気による病気や湿気を好む害虫に食べられたりする可能性もあります。モミジアオイの仲間の中には、ハマキムシにやられやすいものが多いですが、この花には、それもないと言われています。
それでも、何気ないその辺にいる虫にかじられることがないとは言えません。大きな被害にあうことは、ないかもしれませんが、葉っぱひとつ欠けても、栄養の周りが悪くなったりします。特別気を遣って育てなくても育つ植物といっても、水と土と栄養だけは、気を付けて、たまにチェックをするようにしましょう。
観察が、たまに状態でも、虫がついても、そんなに食べられないうちに取り除くこともできます。モミジアオイは、株分けで増やすこともできますが、花をそのままにしておいて、種子を作り、翌年の五月にまいて、発芽させることもできます。でも、実をならせて種子をつくると、種子に優先して栄養が回されるので、株が栄養不足になり、
次の花が咲きづらくなるというのも、辛いものがあります。株分けで十分増えますから、そちらのほうが良いかもしれません。翌年を、どのように花を咲かせるかは、栽培する人の気持ちのままに楽しめばよいことですから、種から育てたいと言う気持ちが、あるのなら、それもいいでしょう。初心者にも簡単な栽培ですから、色んな育て方や増やし方にチャレンジしてみましょう。
モミジアオイの歴史
北アメリカ東南部の湿地が、原産地のモミジアオイは、ハイビスカスの仲間です。けれども、葉が大きく五つに避けているところから、日本では、この名前で呼ばれています。五枚の花弁は本当に鮮やかな燃える紅で、光沢もある上に花弁の大きさも15cmほどもあり、はっとするような感じの花です。
冬は、枯れますが、実は、枯れるのは地上に出ている部分だけで、地下で根の状態で生きています。毎年、花を咲かせる宿根草の部類です。開花期は、主に夏場で、朝咲いたら夕方にはしぼんでしまうという花です。次々とつぼみがついて、シーズンは、常に咲き続けます。生息地が湿地なので、日当たりが良い、少し湿り気のある土壌で育ててやると、順調に育ちます。
庭上でも鉢植えでも楽しむことができるので、庭に植えて、その大輪を来客に印象付けるのも良いでしょうし、庭先にインテリアのように、その朱色を見せるのも素敵です。大型で、派手な草花なので、非常に目立ちます。暑さに強いですから、夏の間は、どこに置いても、良く育ちますし、花も咲かせます。
しかも、地中で冬を過ごすため、寒さに強いので、栽培に手のかからない草花です。見かけは、非常にあでやかでゴージャスな花ですから、訪れる人たちは、すごい植物を育てたと驚きますが、土の表面の渇きにだけ気を付けて水を与えてさえいれば、どんどん成長して、惜しまずに花を次々と咲かせてくれるような世話のないモミジアオイです。初心者の栽培には、もってこいの植物でしょう。
モミジアオイの特徴
モミジアオイは、ハイビスカスの仲間で、花は、非常に鮮やかな赤色で、花弁も大きく、よく似ています。いかにも夏の花という感じですから、冬には、弱くて、世話がかかるようなイメージがありますが、冬にも非常に強い草花です。寒さで、地上から出ている部分は、全て枯れてしまいますが、根は元気に地下で生きていて、春になると芽吹く宿根草です。
その名の通り、葉っぱがモミジや楓に似ていることからついている、日本での通り名です。花が一日花というところも、この植物の特徴の一つです。朝咲いたら夕方にはしぼんでしまいます。けれども、次の朝には、新しいつぼみができており、花を咲かせます。次々とついたつぼみが花開くので、夏の間は、ずっと新しく咲き続けて、栽培者を楽しませてくれます。
ハイビスカスのように、多くの花をわんさか咲かせてくれる花ではありませんが、確実に次のつぼみにバトンタッチをしてしぼみますから、秋になる前まで、花が途絶えることはありません。世話なく、すくすく育ってくれるのは良いですが、高さがひまわり以上になりますので、ちょっと雰囲気の変わったものを栽培したくなったという人たちに人気があります。
たくさん植えて、庭の様子をがらりと変えることも可能です。園芸体験がある人たちが、栽培しているため、ある程度、体験をつんでいなくてはいけないように見えますが、実は、育て方は、非常に簡単な植物なので、園芸の最初に、このモミジアオイから挑戦を始めるのも、なかなか面白いでしょう。
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
ミント類の育て方
ミントは丈夫で育てやすいのが特徴です。家庭菜園でも人気があり、少しのスペースさえあれば栽培することが出来ます。ミントには...
-

-
奇想天外(ウェルウィッチア)の育て方
ウェルウィッチアは生息地をアフリカのアンゴラ及びナミビアのナミブ砂漠にしている裸子植物の一つです。日本では2つの和名があ...
-

-
ゲッケイジュの育て方
英語ではローレル、フランス語ではローリエ、日本語では月桂樹と呼ばれています。クスノキ科の常緑高木植物で地中海沿岸の原産と...
-

-
アカネスミレの育て方
特徴としてはバラ類、真正バラ類に該当します。キントラノオ目、スミレ科、スミレ属でその中の1種類になります。スミレの中にお...
-

-
ミズバショウの育て方
ミズバショウの大きな特徴としては白い花びらに真ん中にがくのようなものがある状態があります。多くの人はこの白い部分が花びら...
-

-
トケイソウの育て方
原産地は、北米、ブラジルやペルーなどの熱帯アメリカです。パラグアイでは国花とされています。現在、園芸に適した品種として知...
-

-
デルフィニウムの育て方
デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん...
-

-
トウワタの育て方
トウワタ(唐綿)とは海外から来た開花後にタンポポのような綿を作るため、この名前が付けられました。ただし、唐といっても中国...
-

-
唐辛子の育て方
中南米が原産地の唐辛子ですが、メキシコでは数千年も前から食用として利用されており栽培も盛んに行われていました。原産地でも...




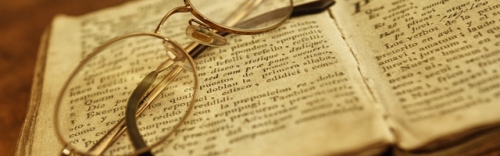





モミジアオイは、ハイビスカスの仲間で、花は、非常に鮮やかな赤色で、花弁も大きく、よく似ています。いかにも夏の花という感じですから、冬には、弱くて、世話がかかるようなイメージがありますが、冬にも非常に強い草花です。寒さで、地上から出ている部分は、全て枯れてしまいますが、根は元気に地下で生きていて、春になると芽吹く宿根草です。