あじさいの育て方

あじさいの育て方
紫陽花は耐寒性もあり、鉢植えから露地植えが出来中級者無向けの植物です。基本的に自生する力を持っている植物なので日当りや水やりにさえ注意すれば育ちます。紫陽花の育て方で剪定なしでも花は咲き木々も元気に成長しますが、年々大きく成長し花の咲く位置も高くなるので剪定を行います。
育て方の必須条件として、まず置き場所は日当りの良い所か半日陰で良く成長します。ただし西日が強い場所は乾燥して葉焼けすることがあるので注意しましょう。紫陽花は水を好む植物なのでたっぷりと水をあげましょう。適度な湿度は重要ですが水はけも同様に生育に影響します。
水はけの良い土で育てるようにしましょう。乾燥を嫌うので根元が乾燥しないようにバークチップや落ち葉などで覆うと良いでしょう。耐寒性は十分ありますが、寒い風にあたると木や根元が痛んでしまうので注意が必要です。肥料は冬と夏?初秋にかけて行います。
冬の肥料は新しい葉の生育と花を咲かせるためのもので、夏?初秋にかけての肥料は、新芽を大きく健康に育てる為のものです。肥料の成分は、冬のものは油かすと骨粉をまぜたものを株元にまきます。夏?初秋にかけては化学肥料や液体肥料を10日に一度ぐらいの程度で与えます。このように肥料の与え方も育て方のポイントとなっています。
あじさいの栽培
基本的に庭植えの場合は植え替えの必要はありません。鉢植えの場合は、根がきちきちになって根詰まりをおこすので一年に一回、花が咲き終わった7月下旬ごろ行うようにします。用土は水はけのよいものを選ぶようにします。赤玉土6:鹿沼土3:ピートモス1の割合が良いでしょう。
前記で述べたように、あじさいの花は土壌の酸度によってその色を変化させます。本来の花色の基本は、青や青紫ですがアルカリ性の強い土壌では紅色やピンク色の花を咲かせます。あじさいの株の大きさを一定に保つために剪定を行います。あじさいの剪定は一度に行ってしまうものと二度に分けて剪定するものがあります。
翌年に花を咲かせるために失敗しない剪定は2段階のやり方で、1度目はまず花が咲き終わった後、花から2?4枚の葉の位置で枝を切り詰めます。2度目は秋の初めで、1度目の剪定の後切ったすぐ下の芽が伸びて枝になっています。その一つ下の葉の根元に花芽が出来るので注意してその上で切り詰めます。
2度剪定するのが面倒な人は、花後すぐに咲いていた花の枝を、花が咲いていなかった枝との分かれ目で切り落とします。単純に花が咲いた枝は切って、花が咲かなかった枝を残すという方法です。剪定の注意点として、翌年咲く花芽を切り落とさないように注意することです。
新しい花芽は10月ごろ完成しており、万全の体制で冬に備えます。9月以降に剪定をばっさり剪定を行うとせっかく出来た花芽を切り取ってしまう可能性があるので万全な注意が必要です。このようにあじさいの栽培は一度要領をつかめば難しくありません。
株の大きさを上手に調節することも可能になってきます。鉢植えなどの観賞用として決められたスペースで美しく栽培するためには、剪定を上手にすることです。栽培の際、注意したいのが害虫や病気です。病気は腐敗病、害虫はハダニが一般的です。気温が上がるとハダニの被害が目につきます。
葉の裏側にシャワーをすることによって軽減出来ますが、発生してしまった場合は殺虫殺菌剤を使用します。昼夜の気温差がある場合はうどんこ病も発生しやすくなります。被害が広がってからでは遅いので、初期の状態で殺虫殺菌剤を散布することが重要です。
あじさいの種付け(植え付け)
あじさいを植え付ける場合は、基本的に休眠期の冬に行います。寒冷地では寒さを出来るだけ避ける為に3?4月に行います。あじさいの種付け、増やし方は挿し木が一般的です。
適期は6月下旬ごろで花の付いていない枝の先端を15cmほど切り土にさす部分の葉の半分を取り除き、30分ほど水につけておきます。そして砂などを入れた鉢植えに挿します。市販の挿し木用土を利用するのも良いでしょう。
1ヶ月ほどで芽が出てきますが、注意点は直射日光は避け出来るだけ半日陰の場所に置いておくようにしましょう。枝の切り口に植物成長調整剤をまぶしておくと発芽を促進させる事が出来ます。種付けはさほど難しくなく骨をつかめば簡単に挿し木で増やして行く事が可能です。一度種付け(挿し木)の芽が出るとあじさいの好む土壌に植え付けます。
しばらく小さい鉢植えで生育させてもいいでしょう。ただし根詰まりにならないように十分注意します。このように、あじさい栽培は比較的簡単でガーデニングを初めて間がない人でも栽培をチャレンジ出来る植物の一つです。
また梅雨のじめじめした時期を華やかな気分にしてくれる楽しみがあります。株の大きさを調節してお庭やベランダを美しく飾る事が出来るあじさいの魅力を十分楽しんでください。
あじさいの歴史
あじさいといえば知らない人はいないほど、梅雨の時期に見られる代表的な花です。紫陽花科(ユキノシタ)科の植物で6月から7月にかけて青や白、ピンクの可愛い花を咲かせます。一般的に見られる手まり型のあじさいは原型種のガクアジサイを品種改良して生まれたものです。
あじさいは日本原産で関東地方の海岸に自生していたガクアジサイが原型種と言われています。紫陽花の語源は、「藍色が集まったもの」を意味する「あづさい(集真藍)」がなまったものという説が有力とされています。日本では平安時代にその名前が記された書物が出ています。
現在あじさいには様々な品種が作られており日本だけでなく、ヨーロッパやアメリカなどに広く観賞用として栽培され、その生息地を広げています。ヨーロッパで品種改良されたものは西洋あじさいと呼ばれ親しまれています。
ヨーロッパに紫陽花を持ち帰ったのは、鎖国時代にオランダ人と偽って出島に滞在し医療と博物学的研究に従事した博物学者シーボルトです。シーボルトは紫陽花だけでなく多くの日本の植物に興味を持ちヨーロッパに持ち帰ったと記されています。
あじさいの特徴
花弁のように見えるものは正式には装飾花と言いガクが変化したものです。あじさいの本当の花は装飾花の近くにある丸いポツンとした粒のような部分のことです。紫陽花は花の色を変えることでもよく知られています。咲き始めの頃は白っぽく、次第に色が変わっていくことから「七変化」と呼ばれています。
その秘密は土壌の酸度や土壌の酸度により紫陽花に吸収されるアルミニウムイオンの量によって、花に含まれる色素が変化すると言われています。土壌の酸度が酸性なら青色に、アルカリ性ならピンク色に変化する傾向にあります。樹高は1?2mで、葉は光沢のある淡緑色で葉脈のはっきりした卵形です。
葉の周りは鋸歯状になっています。紫陽花は日本の文化とも深く関わりを持ち愛されている植物です。俳句や短歌などの日本文学、歌や和菓子に至るまで使用されています。その他、切手に使用されるなど日本原産の植物としてその名を定着しているのが良くわかります。
また、日本の代表的な市町村の植物として制定されており、親しまれています。日本国内で紫陽花の名所とされている場所は多くあり、神戸の裏六甲ドライブウェイや奥摩耶ドライブウェイ沿いに延々と紫陽花が自生しています。北海道各地にも紫陽花が自生しており初夏に美しい花を咲かせています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ノリウツギの育て方
タイトル:カシワバアジサイの育て方
タイトル:アジサイの育て方
タイトル:マーガレットの育て方
-

-
ムラサキサギゴケの育て方
ムラサキサギゴケは、ハエドクソウ科のサギゴケ属になります。和名は、ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)でその他の名前は、サギシバな...
-

-
ハンカチノキの育て方
ハンカチノキはミズキ科ハンカチノキ属の落葉高木です。中国四川省・雲南省付近が原産で、標高1500~2000m位の標高の湿...
-

-
ノリウツギの育て方
ノリウツギはアジサイ科のアジサイ属の落葉する背の低い木で原産国は中国やロシア周辺であると考えられています。和名のノリウツ...
-

-
フジの育て方
藤が歴史の中で最初に登場するのは有名な書物である古事記の中です。時は712年ごろ、男神が女神にきれいなフジの花を贈り、彼...
-

-
風知草の育て方
風知草はイネ科ウラハグサ属の植物です。別名をウラハグサ、またカゼグサとも言います。ウラハグサ属の植物は風知草ただ一種です...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
ドイツアザミの育て方
この花はキク科アザミ属に属します。ドイツとありますが日本原産です。生息地も日本となるでしょう。多年草で、耐寒性があり耐暑...
-

-
ホトケノザの育て方
一概にホトケノザと言っても、キク科とシソ科のものがあります。春の七草で良く知られている雑草は、キク科であり、シソ科のもの...
-

-
サラセニアの育て方
サラセニアは北アメリカ大陸原産の食虫植物です。葉が筒のような形に伸びており、その中へ虫を落として食べることで有名です。生...
-

-
手まりかんぼく(スノーボール)の育て方
手まりかんぼくとは、名前からも分かるように手毬のような花が咲く肝木(かんぼく)です。原産地は朝鮮半島だと言われています。...




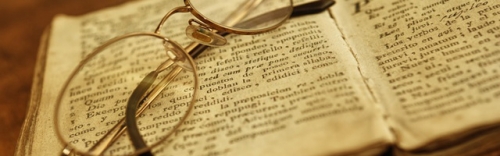





あじさいといえば知らない人はいないほど、梅雨の時期に見られる代表的な花です。紫陽花科(ユキノシタ)科の植物で6月から7月にかけて青や白、ピンクの可愛い花を咲かせます。一般的に見られる手まり型のあじさいは原型種のガクアジサイを品種改良して生まれたものです。