ケイトウの育て方

ケイトウの育てる環境について
ケイトウの育て 方で、適した栽培環境も気になるところです。必要とされるのは、水はけが良いことと、お日様の暖かな陽の光が当たる場所であることです。この2つは必須であり、このポイントをおさえてさえいれば、土質に関しては、それほど細かいことは言いません。
土地がとても肥えており、農作物もよくできるような土地は、普通は良さそうなものですが、ケイトウの場合は少し異なります。条件が良すぎる土環境は、葉っぱがスクスクと大きくなります。それが栄養が良いために、茂り過ぎになります。そのため、土地に関しては、やせた土地で構いません。
むしろ、そのほうがマッチします。堅いやせた土地という、一件過酷条件とも思える土状態ですが、そういった場所でコンパクトに育ててあげると、意外と見栄え も良くなります。タネから育てるもので、発芽の適温としては20℃から30℃くらいになります。
4月下旬のヤエザクラがひらひらと咲く頃から、太陽が眩しい真夏の8月くらいまで、タネをまくことができます。植物としては、相対的短日性になります。そのため、時期的にも遅くにタネをまくほどに、草丈は低くなって開花することになります。
植物が成長していくのに最適な温度としては、15℃から30℃くらいがベストになります。比較的、温度としても幅が広いので、暖かいシーズンには育てやすいです。品種はたくさんありますから、分枝や草丈であったり、株張り何かにも違いがあります。
ケイトウの種付けや水やり、肥料について
植え替えや植え付けについてですが、移植が好みではない植物です。育て易さ はあるものの、移植はイヤだという姿勢を崩しません。そのためプランターや花壇に、直接タネをまいてしまって構いません。もしくはポットを用意して、そこにタネをまいて、しばらく育苗させます。
植え付けをする時には、くれぐれも根鉢を、ボロボロと崩さないよう気をつけながら作業を行います。タネは太陽の光が苦手なタイプです。まいたら土を軽くかけておいて、芽が出てくるまでのあいだは、上に新聞紙等をかぶせておくと良いです。
新聞紙を1枚かけることで、お日様の光からもガードできます。初釜では、太陽の光を当てないように対策をしてあげることです。植え付け作業をすると気には、根っこの部分をうっかりカットしないよう気をつけましょう。元気に育てるためには、水やりも十分にして あげることが大事になります。
特にしっかりと根が張るまでのあいだは、土が極度に乾燥する状態にしてはいけません。タネを巻いて、苗もまだ小さくて弱々しい時には、土も乾燥しすぎないように気をつけることです。プランター栽培や鉢植えの場合は、乾燥させてしまわないようにします。
感想により、下葉が特に枯れ上がりやすくなるためです。肥料を上げることについてですが、庭に植える場合においては、ほとんどの場合肥料は与えなくても大丈夫です。プランター栽培の場合は、液体肥料をひと月のうちに、3回くらい施してあげると良いです。
ケイトウの増やし方や害虫について
ケイトウを育てていくときに、天敵となる害虫は、いくつか存在します。害虫の主なメンツとしては、植物を 育てると、だいたい登場するアブラムシ、あとはヨトウムシ、そしてハダニです。特に環境の感想が長く続くと、ハダニが発生しやすくなりますから、感想のしすぎは注意が必要です。
害虫とともに、病気にも気をつけたいところです。灰色かび病であったり、立枯病や連作障害などは、栽培していく上でも気をつけたい病気です。水はけが良くなかったり、日あたりが良くない状態が続くと、灰色かび病であったり、立枯病なんかも出てきやすくなります。
これも気をつけたいのが、連作障害が出てしまうという点でしょう。綺麗な花を長く楽しむためにも、何年かしたら場所を移すというのを繰り返すことです。同じ場所にずっとではなく、数年ごとに位置を帰るのが、長く花を咲かせるコツにもなります。
増やし方ですが、タネまきをして育てるものになります。一年草であるため、種を毎年まいて成長を楽しみにします。自家採種をするのであれば、個体差が出ることも頭において、できるだけ良さそうな株を選び抜いて、タネとりを行いましょう。
タネとりをしたら、次の春が訪れるまで、乾燥させた状態で貯蔵しておくことです。花は、鮮やかな赤いビロードのような印象が強いものです。ですが、実は園芸品種はとても種類が多いものです。本草図譜は江戸時代の植物図鑑ですが、さきわけけいとうや、ゆりげいとうなども掲載されています。タネをまく楽しみにもなりそうです。
ケイトウの歴史
ケイトウの原産地は、アフリカやアジアの熱帯地方であるとされており、主な生息地としても熱帯アジアインド方面です。日本へわたってきたのは、時代としては8世紀くらいで、朝鮮半島や中国を経由して渡来してきたものです。昔は韓藍という名称でも呼ばれていました。
この呼び方は、万葉集の中での詠まれかたですが、ノゲイトウであるのかはわかりません。1681年刊の花壇綱目と、1709年刊の大和本草には、鶏頭花といった書き方で紹介がされています。この方が、今のケイトウにより近いのではないか、とされています。
このほかにも、1828年刊の本草図譜には、とさかけいとうだとか、さきわけけけけいとうなど、ルーツとなるような意味合いのものが掲載され ています。漢名では鶏冠と書きますが、この文字通り、咲いた花の形状が、まるでニワトリのトサカにそっくりです。
ヨーロッパ方面やアメリカなどにおいては、雄鶏の鶏冠といった呼び方をされていることもあります。日本国内で山形県では、とさかと方言で言われることもあります。奈良県においても、一部の方言になりますが、にわとりのとさかと、ダイレクトな呼び方をしている地域もあります。
日本においても、馴染みのある、割とカラフルなカラーもキュートな花です。夏のシーズンから秋くらいが見ごろです。観賞用として、国内でも庭で栽培している家庭も、昔から多かった植物です。お彼岸などにも、わりとよく登場する花です。
ケイトウの特徴
ケイトウの 花はフサフサした見た目で、鮮やかなカラーが印象的な花のカラーを持つのも特徴的です。日本でも、古い時代から多くの飛雄に親しまれてきた、馴染み深い花です。鶏頭と呼ばれるのは、ニワトリのトサカとに通っているためであり、その形状も特徴があります。
花房の先端は扇のように広がっていて、平たくなっています。鮮やかな色と、特徴のある咲き方をしているため、目立つポイントとなっています。セロシア属はケイトウの仲間であり、種類も60ほどあります。アルゲンテアというのがその中の一つですが、
その変種の花が栽培されているケースが多いです。5つくらいのグループに分かれていて、園芸品種であることが多いです。チャームポイントとも言えるトサカにならないのが、ノゲイトウグループ です。枝分かれをするため、花穂を多く付けるタイプです。
馴染みのある形状なのは、トサカ系のクリスタータグループでしょう。個体差はありますが、トサカがポイントとなる、ケイトウの花を咲かせてくれます。久留米ゲイトウグループになると、球状であり、花は折り重なるような状態でかたまります。羽毛ゲイトウグループは、柔らかい円錐形の花穂のタイプになります。
羽毛の部分が玉状になるのは、ヤリゲイトウグループです。形状としては一年草であり、育て方にしても初心者であっても、育てるのが楽な植物であり、しかも開花する期間が長めですから、長いあいだ花を楽しむことができます。赤やピンク、オレンジや黄色など、カラーも豊富です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ケストルムの育て方
-

-
プルメリアの育て方
プルメリアの原産地は熱帯アメリカで、生息地も熱帯がほとんどですので、日本では基本的に自生していませんし、植物園などに訪れ...
-

-
アカネスミレの育て方
特徴としてはバラ類、真正バラ類に該当します。キントラノオ目、スミレ科、スミレ属でその中の1種類になります。スミレの中にお...
-

-
グロキシニアの育て方
グロキシニアの科名は、イワタバコ科 / 属名は、シンニンギア属となり、和名は、オオイワギリソウ(大岩桐草)といいます。グ...
-

-
ギボウシ(ホスタ)の育て方
ギボウシは別名、ホスタという名前で古から世界中で親しまれています。もともとは、ギボウシは日本の里山のあらゆるところに自生...
-

-
サツキの育て方
日本が原産のサツキの歴史は古く5世紀から8世紀頃の万葉集にも登場します。江戸時代に多くの品種がつくられました。盆栽に仕立...
-

-
アガパンサスの育て方
生息地の南アフリカから明治時代の中ごろに日本に伝わりました。最初に伝わったのはアフリカヌスという品種だと言われています。...
-

-
温帯スイレンの育て方
スイレンは古くから多くの人に愛されてきた花です。そんなスイレンには温帯スイレンと熱帯スイレンがあり、温帯スイレンは耐寒性...
-

-
リンゴの育て方
リンゴの特徴として、種類はバラ目、バラ科、サクラ亜科になります。確かに花を見るとサクラとよく似ています。可愛らしい小さい...
-

-
イチゴノキの育て方
マドリードの旧市街の中心地には、「プエルタ・デル・ソル」(太陽の門)と呼ばれている広場が有ります。この広場はスペイン全土...
-

-
ぶどうの育て方
ぶどうの歴史には、その品種の多さゆえに諸説あり、最も古いものは紀元前8000年頃のヨルダン遺跡から、初期農耕文化における...




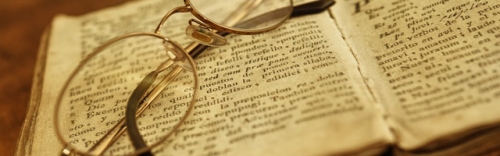





ケイトウの原産地は、アフリカやアジアの熱帯地方であるとされており、主な生息地としても熱帯アジアインド方面です。日本へわたってきたのは、時代としては8世紀くらいで、朝鮮半島や中国を経由して渡来してきたものです。