トリテレイアの育て方

育てる環境について
トリテレイアの育て方として、好ましい環境は水はけがよくて日当りのよい場所を選ぶことです。夏の初めに開花させた後に地上部が枯れて休眠に入り、秋頃に再び葉が伸びてくるという生育サイクルを繰り返していくのですが、冬の寒いシーズンの管理方法は注意が必要です。
寒さには強い性質がありますので多少霜にあたっても枯れてしまうということはありません。ただしマイナス5度以下になるような寒冷地の場合は、霜が降りて枯れてしまうことがあります。寒風にさらされ続けていると葉の咲きが傷んで茶色っぽく変色してしまいますので注意してあげてください。
寒冷地で育てていくという場合には、露地植えをする時に霜よけなどの対策をすることがおすすめされています。鉢植えで栽培している場合は軒下などで管理するようにしましょう。タネを採種する必要がないという場合は、花が咲き終わった後に花茎を付け根部分から切り落としていくようにしてください。
10月上旬頃から6月上旬頃までは生育期に入っていますので戸外に置いて日光があたるようにしてあげてください。夏は休眠に入りますので直射日光をあてる必要がありませんので注意するようにしましょう。
雑草が多い場所や案層しやすい場所などで育てていく場合には、水やりや草とりなどをして管理してあげるようにしてください。植えっぱなしにしていても何年も花を咲かせてくれますが、株が込み合ってきたと感じたら株分けをすることがおすすめです。
種付けや水やり、肥料について
10月上旬頃から6月上旬頃までの生育期には、土の表面が乾いてきたら水やりをするようにしていきます。夏の休眠期には水やりをする必要は特にありませんので、水やり過ぎて腐らせてしまわないように注意してください。夏場は乾燥するシーズンで地上部も枯れていますので、
水をあげたくなってしまいますが、地上部が枯れてしまっていても球根部分は生きていますので大丈夫です。生育期には表面の土が濡れている状態の時に再び水をやりをしてしまうと球根が腐って枯れてしまうことがありますので、土が乾いてきてからあげるようにしましょう。
庭植えをして育てている場合には、自然の雨で生育しますので特に頻繁に水やりをする必要はありません。ただし、日照りが続くようでしたら様子を見ながら水やりをしてあげてください。庭植えをしている場合には梅雨のシーズンに移動させることはできませんが、
鉢植えで育てているような場合は雨があたらない場所に移動させてあげてください。庭植えをしている場合の肥料は、植え付けをする時に元肥として、腐葉土や堆肥などの有機質と緩効性の肥料を混ぜ込んでおくことがおすすめです。
春と秋頃に骨粉入りの油かすなどを施すとよいでしょう。鉢植えをしている場合は、1か月に1回程度緩効性の肥料を施していきます。開花をするシーズンには肥料が必要になってきますが、やり過ぎてしまっても球根が腐ってしまうことがありますので注意してください。
増やし方や害虫について
トリテレイアの増やし方には株分けによる方法が用いられています。球根がよく増えていきますので秋頃の植え付け時期と一緒に株分けをおこなっていきます。植え付けをする際はよく耕して緩効性の肥料を入れておき、およそ5センチメートルから10センチメートルほど間隔をあけて、
深さは5センチメートルくらいにすることがおすすめです。雨ざらしにしていると自然と弱酸性になってしまいますので、2年に1回くらいは、石灰を撒いて中和させていくと効果的です。過湿はあまり好みませんので、川砂などを1割ほど混ぜて水ハケをよくすることもおすすめです。
鉢植えをする場合には、18センチメートルほどの鉢に4、5球ほどを深さおよそ5センチメートルくらいで植えるのがよいでしょう。鉢植えをして育てている場合は、2、3年に1度植え替えをしていきますが、タイミングとしては芽が出始める秋頃に掘り替えていきます。
庭植えをしている場合でも株が増えてしまって窮屈になってくると、花付きが悪くなってしまうことがありますので分球していくようにしましょう。分球をする必要が特になさそうな場合は、植えっぱなしでも大丈夫ですので掘り上げる作業はおこないません。
トリテレイアは、こぼれタネでも増えることがあります。トリテレイアの場合は、特に病気や害虫に食害されてしまうような心配はありません。トリテレイアの葉は細くて少ないですので開花し終わった後でも花壇の美観を損なうことはありません。
トリテレイアの歴史
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体として複数年にわたって生存する植物のことを言います。かつてブローディアエア属に属していた植物で、
現ブローディアエア属にはカリフォルニアヒアシンスやムラサキハナニラなどがあります。現トリテレイア属には、トリテレイア・ブリッジェシーやトリテレイア・ヒアシンシナ、トリテレイア・イクシオイデス、トリテレイア・ラクサ、トリテレイア・ペダンクラリスなどが挙げられます。
トリテレイアの原産は、北アメリカの太平洋側の他、カナダのブリティッシュコロンビア州からアメリカのカリフォルニア・ネバダ州北部にかけて分布しています。生息地は、草原や林などです。トリテレイアという名前は、ギリシア語でトリアが3つと言う意味で、
テレイオスが完全という意味が語源となっています。花の各器官が3の倍数で成り立っている構造にちなんでいるとされています。開花するシーズンは、5月頃から6月頃になります。青紫の小さな花をたくさん咲かせるトリテレイアは、アガパンサスを小さくしたような形状にも見えることから、
ヒメアガパンサスと呼ばれることもあります。園芸ショップなどで広く普及している品種には、トリテレイア・ブリッジシーやトリテレイア・ラクサなどが挙げられます。庭の花壇に植えて楽しんだり、切花として使用されることもあります。
トリテレイアの特徴
トリテレイアは、草丈はおよそ30センチメートルから40センチメートルほどになります。花茎の先に小花が放射状につき、花色はブルーやパーブル、ホワイト、イエローなどさまざまな種類があります。秋頃から春頃に生育して夏の初め頃に開花した後は茎葉が枯れてしまい夏には球根の状態となって休眠に入ります。
秋頃になると再び球根の部分からは線状の細い葉が2、3枚伸びてきて開花シーズンに入ると、花茎を長く伸ばしていきその先端部分に10数輪ほどの花を咲かせます。花の先端部分が6つに裂けたようにラッパ型になって上向きについています。
野放し球根は、環境が適していれば比較的植えっ放しにしていてもよく育ち、手間をかけなくても毎年きれいな花を咲かせてくれることが多いです。葉が枯れたら球根を掘り上げて秋頃まで乾燥保存させることもありますが、鉢植えで育てている場合は掘り返す必要がありません。
雨があたらない場所に鉢植えを移動して土を乾燥させておくようにします。トリテレイアは比較的寒さにも強いのが特徴です。秋に球根を植え付けした場合は、冬から春頃にかけて芽を出して2枚の葉を展開して夏の初めに花茎が伸びて開花します。
英名では、旧属名が残ったホワイトブローディと呼ばれています。簡単に広がる植物ですのでイネ科のグラス類やタイム、エリゲロンなどの間に植えてあげると引き立ちますのでおすすめです。トリテレイアの球根は小さめですので取り扱いしやすいです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シライトソウの育て方
タイトル:ショウジョウバカマの育て方
タイトル:エンレイソウの育て方
タイトル:アブチロンの育て方
タイトル:アスペルラの育て方
タイトル:ナバナ類の育て方
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...
-

-
リトープスの育て方
この植物についてはハナミズナ科とされています。同じような種類としてメセンがあり、メセンの仲間としても知られています。園芸...
-

-
ヘリクリサムの育て方
このヘリクリサム、ホワイトフェアリーの一番の特徴は何といってもその触り心地です。ドライフラワーかと思うような花がたくさん...
-

-
ミルクブッシュの育て方
種類は、トウダイグサ科、トウダイグサ属になります。ユーフォルビア属に該当することもあります。園芸として用いるときの分類と...
-

-
カマッシアの育て方
カマッシアの原産は北アメリカ合衆国の北西部です。生息地も北アメリカ合衆国を中心に6種類が分布されています。カマッシア・ラ...
-

-
ダイアンサスの育て方
ダイアンサスは、世界中に生息地が広がる常緑性植物です。品種によって、ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アフリカなどが原産...
-

-
ランタナ・カマラの育て方
ランタナ・カマラは通称ランタナで、別名をシチヘンゲやコウオウカ、コモン・ランタナといいます。クマツヅラ科ランタナ属の常緑...
-

-
コリアンダーの育て方
地中海東部原産で、各地で古くから食用とされてきました。その歴史は古く、古代ローマの博物学者プリニウスの博物誌には、最も良...
-

-
シカクマメの育て方
シカクマメは日本でも食されるようになってきましたが、どちらかというと熱帯を原産とする植物です。元々の生息地は東南アジアや...
-

-
カリフォルニア・デージーの育て方
科名はキク科であり、学名はライアであり、別名にライア・エレガンスという名を持つのがカリフォルニア・デージーであり、その名...




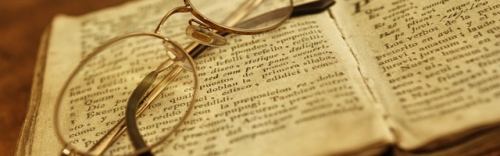





トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体として複数年にわたって生存する植物のことを言います。