ショウジョウバカマの育て方

育てる環境について
ショウジョウバカマは湿り気のある明るい日陰を好んで育ちますので、風通しの良い、明るい日陰で管理するようにします。夏場の直射日光は強すぎて葉焼けを起こすこともありますので、日除けをして50%ほど遮光してあげるようにしましょう。
耐寒性があるので寒さには比較的強い方ですが、やはり株を傷める原因にもなりますので、冬の間は霜の付かない軒下などに移動させて管理することをお勧めします。地植えにしている場合は、株元を防霜シートなどで覆ってあげると防寒になります。
庭に植える場合も落葉樹の下など、日陰気味のところがよいでしょう。乾燥に弱いので、ある程度湿り気のあるところで栽培するようにします。ショウジョウバカマは肥料が重要です。植え替えの際には、元肥としてリン酸とカリウム分の多い緩効性の化成肥料を与えるようにします。
用土は水はけのいいものを好みますので、鹿沼土、赤玉土、軽石を4:3:3程度の割り合いで混ぜあわせたものを使用します。もし乾燥気味であればこれらに腐葉土を足して保水性を上げておきましょう。ヤマゴケを混ぜても効果的です。適期は花が終わった頃か、暑さが和らいだ9月〜10月頃です。
鉢から丁寧に抜き取り、古い土を落として新しい用土に植えかえてあげましょう。地植えの場合は、3〜5年に1度で植え替えます。掘り起こして、株を整理し、再び植えかえてあげましょう。その際に大きく育った株は株分けとして使用するようにします。
種付けや水やり、肥料について
ショウジョウバカマは5月頃に種を採取することが出来ます。保存できないので、採取したらすぐにまいてあげましょう。用土は親株と同じ物でも構いませんが、水苔などを足して、さらに保水性を上げておいた方が無難です。ただし、実生から育てる場合、
花を咲かせるまでに3年ほどかかると言われていますので、株分けなど他の方法で分けるのをお勧めします。ショウジョウバカマは潤沢な用土を好み、根が乾燥することを嫌いますので、生育期には水切れを起こさないように注意します。用土の表面が乾く前には水を与えるようにします。
夏場は特に乾燥しやすいので、毎日霧吹きで葉水を与えてあげるようにしましょう。害虫の予防にもなります。庭に植えている場合、よほど日照りが続かない限り水やりは必要ありません。乾燥していたら与える程度で大丈夫です。冬になると水やりは控えめにしておきましょう。
ショウジョウバカマは肥料が足りないとせっかくの可愛らしい花を咲かせないことがあります。植え替える時にしっかりと元肥を施しておくのも重要なポイントです。4月~10月の生育期には、油かすや粉骨などの固形肥料を土の上に置き肥してあげるとよいでしょう。
その際、葉に直接肥料が当たらないようにします。また、月に2〜3回ほどの割合で薄めた液体肥料を与えるのもよいでしょう。3月〜5月頃はチッ素分を多く含んだものを与え、6月以降はリン酸とカリウム分を多く含むものを与えます。
増やし方や害虫について
種でも増やすことが出来ますが、年数がかかってしまいますので、葉挿しや株分けで増やすのが一般的です。葉挿しで増やす場合、適期は6月〜7月です。付け根から切り取った葉を半分にカットし、湿らせた鹿沼土に刺しておくとおよそ2週間ほどで発根します。
ある程度根が成長したら鉢上げをし、親株と同じ用土に植え替えます。また、栄養状態がよく健康な株の場合、葉の先端部分から不定芽と呼ばれる新芽が出てくることがあります。栄養繁殖と呼ばれる方法です。発芽している部分を水苔などで乾燥しないように抑え、ピンで止めておくとそこから成長してきます。
株分けで増やす場合、植え替える時に同時に行うといいでしょう。大きく育った株は、手で簡単に取り外せますので、丁寧に取り分け、用土に植えておきます。しっかりと芽をつけた株を選ぶのがポイントです。ショウジョウバカマは殆ど病気の心配がありません。
ただ、新芽の時期にはナメクジやアブラムシを発生させることがあります。どちらも栄養分を吸い取って株をどんどん弱らせてしまいますので、見つけ次第早めに駆除することが重要です。ナメクジは卵を生むので、本体を退治してもまた新しいナメクジが発生してしまいます。
その為、ナメクジ専用の薬剤を使用して駆除することをお勧めします。アブラムシにも専用の薬剤がありますが、出来るだけ薬剤を使いたくない場合には牛乳、もしくはトウガラシのエキスを霧吹きなどでスプレーしてあげても効果的です。
ショウジョウバカマの歴史
ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は九州まで幅広く分布しており、山地や高山地域、小川の近くなど、湿り気の多い場所を主な生息地としています。
ショウジョウバカマ(猩々袴)の名前の由来は、中国の伝説上の生き物である猩々(ショウジョウ)の顔に似た赤い花を咲かせることと、葉の重なり方がハカマに似ていたことからつけられたと言われています。別名をジャパニーズ・ヒヤシンスとも呼ばれているだけあって、
いくつかの花弁が集まって咲く様子はヒヤシンスにも似ています。日本中の里山のどこでもよく見られる植物で、非常に馴染み深い植物の一つです。放射状に広がる細めの葉の中心に10〜20センチ前後の茎が伸び、その中央に小さなユリに似た花が咲きます。
洋花のような派手さはあまりありませんが、日本人好みの素朴さと清楚さを兼ね備えた花です。色もピンクや白、薄い紫と様々ですが、どれも淡くて品のある色をしています。ショウジョウバカマは花の時期を過ぎても色あせた花がそのままの状態で残る常緑草です。
耐寒性があり、さらに暑さにもある程度まで耐えます。育て方も比較的容易ですので、初心者の方にもお勧めの植物です。和に非常に合いますので、盆栽としても人気があります。寄せ植えにしてアクセントにすることも出来ますし。最近ではけと土に植えつけたり苔玉にしたりして使用されることも多いようです。
ショウジョウバカマの特徴
ショウジョウバカマの葉は、根本から地面を這うように放射状に広がります。出来るだけ広く葉を広げることによって、光合成をしっかりと行うことが出来るのです。やや厚みがあって深い緑色をしており、光沢があるのが特徴です。冬の時期には若干赤みがかかって、
さらに濃い色に変化しますが、これはアントシアニンという成分を多く含むことによって、厳しい冬の間でも葉が凍らないようになっているからです。その葉の中心からしっかりとした花茎が伸びます。開花時には10センチ程度にしかなりませんが、
花が終わった後はぐんと成長し、30〜50センチほどになります。花は小ぶりのものがいくつか集まって花茎の先に咲きます。基本的には3〜4月頃に咲きますが、高山地帯では雪が溶けてしまった6月頃から花を咲かせます。一つ一つの花は1センチ程度と小さいのですが、
いくつかの花が集合して3センチほどの球体になった状態で咲くので、丸くてフワフワした非常に可愛らしい印象を受けます。花の色は薄紅色のものが多いですが、品種によっては白やピンク、薄い紫色の花をつけるものもあります。また生育場所でも変わってくるようです。
非常に丈夫で初心者の方でも育てやすい植物です。盆栽などの鉢植えとして育てることも出来ますし、露地植えにして庭のアクセントにすることも出来ます。葉挿しや株分け、種まきなど、増やし方も様々ですので、色々な増やし方にチャレンジしてみたい方にもお勧めです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シライトソウの育て方
-

-
オーストラリアビーンズの育て方
オーストラリアビーンズは学名をCastanospermumaustraleといい、マメ科になる植物です。名前にもビーンズ...
-

-
ヘリコニアの育て方
ヘリコニアは単子葉植物のショウガ目に属する植物です。大きく芭蕉のような葉っぱから以前はバショウ科に属させていましたが、現...
-

-
ビタミンCの豊富な夏野菜ピーマンの育て方
次々と実を付け霜の降りる頃まで長く楽しめるピーマンの育て方を紹介します。ピーマンは放置しててもそれなりに収穫できるのです...
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
イチゴの育て方
イチゴは比較的古くから人間に食されていた果物です。その歴史は石器時代にさかのぼります。農耕技術や養殖などを行う前から野生...
-

-
オシロイバナの育て方
日本に入ってきたのは江戸時代に鑑賞用として輸入されたと言われており、当時この花の黒く堅い実を潰すと、白い粉が出てきます。...
-

-
グミの仲間の育て方について
グミと言うとお菓子を連想する人は多いものですが、お菓子のグミと言うのは、グミの仲間となるものを原料として、果汁を搾りだし...
-

-
カリンの育て方
カリンは昔から咳止めの効果があると言われてきており、現在ではのど飴に利用されていたりします。かつてはカリン酒等に利用され...
-

-
オウコチョウ(オオゴチョウ)の育て方
オウコチョウの特徴を記載すると、次のようになります。植物の分類上はマメ科のカエサルピニア属に属します。原産地としては熱帯...
-

-
タアサイの育て方
中国が原産となるタアサイの歴史は中国の長江付近となる華中で、栄の時代となる960年から1279年に体菜より派生したと言わ...




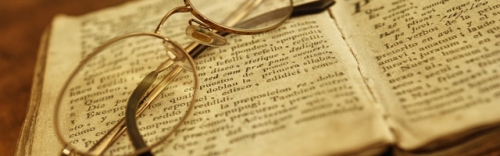





ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は九州まで幅広く分布しており、山地や高山地域、小川の近くなど、湿り気の多い場所を主な生息地としています。