シカクマメの育て方

シカクマメの種付けと栽培の周期
シカクマメは暑い地域の植物ですから、寒い時期に種付けをしても育ちません。種付けをするのは5月ごろが適しています。成長は早く、適切に追肥を行っていれば8月くらいには収穫できるようになります。また、暑い時期には次々と実がなりますから、11月の中旬まで収穫を楽しむことができます。
5月の中旬に種まきを行います。直まきをしても良いですし、ポットなどに蒔くのも良いです。どちらの場合にも、2粒ずつくらい蒔いていきます。種まきをすれば、10日くらいですぐに発芽します。その中から最も生育の良い芽を残して間引きます。ポットに種付けをして植え替えをするのも良い方法ですが、その時期は4枚くらいの葉がついた時期が適しています。
育て方の基本としては地植えが良いのですが、プランターでも育てることはできます。プランターで栽培する場合、できるだけ大きいものを選んでおきましょう。株と株の間は40センチから60センチくらいは開けた方が良いです。密集して植えると生育が悪くなることもありますから注意が必要です。
ツルが育ちますから、ネットを張っておけばカーテンのように元気に育ちます。正しい育て方をしていればぐんぐん成長します。2メートルから3メートルくらいまで伸びるでしょうから、たとえば二階建ての家のベランダくらいまで伸ばしてみるのも良い育て方です。
シカクマメを育てるときの注意点
シカクマメはマメ科の植物ですから、連作障害を起こしやすい傾向があります。連作というのは、同じ場所に同じ植物を植えることによって成長しにくくなることです。シカクマメを植えて収穫をし、翌年にもう一度植えると、同じように栽培をしてもうまくいかないことが多いです。マメ科で必要とする栄養分が共通していることにも注意が必要です。
シカクマメではないマメ科植物を植えた場合でも、翌年には育ちにくくなります。育て方の注意点としてはこのことを頭に入れておかなければなりません。水は表面が乾いたらたっぷりやるというようにしていけば問題はありません。なお、肥料については7月から8月くらいに追肥を行います。注意しておかなければならないのがツルぼけという現象です。
肥料をたくさんやれば栽培がうまくいくと考える人もいるようですが、これは必ずしも正しくはありません。肥料をやり過ぎると成長は良くなるのですが、ツルが伸びて葉が茂り、その代わりに実がつきにくくなります。これをツルぼけと呼びます。実の収穫を楽しもうと思っているのなら、肥料をやり過ぎないように注意しなければなりません。成長が良くなりすぎると、根元から別のツルが生じてきますし、メインのツルから枝分かれします。
そのままにしておくと成長しすぎて、広がりすぎることがあります。支柱で育てている場合、支柱と支柱の間に幕を張ったように伸びてしまい、強い風が吹くと倒れてしまうことがありますから注意が必要です。根元から述べた小さな芽は摘み取ってしまい、横に伸びた芽も摘み取ってしまうようにすれば、このような被害を防ぐことができるでしょう。
シカクマメの栄養分について
シカクマメにはタンパク質が豊富に含まれていますが、これは根粒菌のおかげです。マメ科植物には根粒菌というバクテリアが根っこに寄生しています。タンパク質を合成するためにはいくつかの栄養素が必要なのですが、その中で最も重要なものが窒素です。肥料でも窒素が含有されていることが多いです。
これは生命の維持に必要な窒素を補給するためのものです。植物は、窒素源をアンモニアや硝酸塩などから吸収します。肥料に含まれているものはアンモニアや硝酸塩などとなっています。根粒菌は、アンモニアや硝酸塩が全くなかったとしても、空気中の窒素を吸収できるという特徴があります。この窒素からタンパク質を合成できるわけです。
空気中の窒素を吸収できる仕組みを窒素固定と呼びます。窒素固定を行うためには多くのエネルギーを必要とするために、根粒菌が単独で存在しているときには窒素固定を行うことはありません。シカクマメなどに寄生した場合、シカクマメからエネルギーをもらい、それによって窒素固定を行います。双方が協力し合ってうまく成長していると言えるでしょう。
ここまでは他のマメ科植物にも共通したことなのですが、シカクマメは根っこにデンプン質を蓄えることができるという点で特徴があります。デンプン質を根っこにためる植物としては、イモ類が有名です。そのために、イモ類を主食とする文化は色々な地域で栄えました。
シカクマメも根っこに多くのデンプン質を含みますから、主食として古くから栽培されていたのです。一般的なイモ類にはデンプンが多く含まれているだけなのですが、シカクマメはデンプン質だけではなくてタンパク質も含まれているという事からも、栄養素としては非常に適していると考えられます。
シカクマメの歴史
シカクマメは日本でも食されるようになってきましたが、どちらかというと熱帯を原産とする植物です。元々の生息地は東南アジアやオセアニアで、ビルマやパプアニューギニアでは好まれていたそうです。マメ科の植物だと言うこともあって、根っこにはタンパク質が豊富に含まれているために、タンパク源として古くから用いられていたのです。
どちらかというと西洋の野菜だと思われているようですが、西洋で用いられるようになったのは17世紀頃です。日本の歴史に出てくるのは比較的古くて、1,900年頃には文献に登場します。ただ、このときにはあまり普及しませんでした。日本で普及し始めたのは1,980年だと考えられています。
その目的は沖縄での野菜不足を補うためだと考えられています。シカクマメはウリズンと呼ばれることがあるのは、1,980年頃に開発された品種の名前がウリズンで、これが品種として広まったものと考えられます。品種の開発や普及を進めたのは旧農林水産省の熱帯農業研究センターです。現在は国際農林水産業研究センターと名前を変えています。
シカクマメの特徴
名前からも分かるように、断面が四角形に見えます。食用として栽培されることが多いです。現在ではマメの部分を食べるのが普通ですが、根にも栄養があります。原産地では、古くから根っこを栄養源としていました。マメ科の植物は根に根粒菌というバクテリアが寄生していて、これらが窒素固定を行うことによってタンパク質が多く含まれるようになります。
そのため、根っこを食べるのが効率的なタンパク質の摂取方法だというのは、現在の科学では明らかにされていますが、それ以前から根っこが食用になっていたのです。根っこを成長させるために花を摘み取ると言ったことも行われていたそうです。根っこにはデンプン質も多くあるために、栄養分は豊富で食用として適しています。
栄養が豊富なだけでなく見た目が特徴的な事からも、食用としては好まれています。ウリズンというのは沖縄の方言から来たもので、新芽が吹くときの美しさを表現した名前です。そのままの意味は「新緑の季節」という意味だそうです。マメ科植物で、多年生の植物です。
元々熱帯地方を生息地としていた植物と言うこともあって、暖かい地域では多年生の植物として成長しますが、日本の本州あたりでは寒さに耐えることができず、そのために一年生の植物として扱われるのが普通です。
-

-
ビデンスの育て方
アメリカを主とし世界じゅうを生息地としていて、日本でもセンダングサなど6種類のビデンスが自生しています。世界中での種類は...
-

-
ギンバイカ(マートル)の育て方
ギンバイカはフトモモ科ギンバイカ属の低木常緑樹です。ギンバイカは和名になり、漢字では「銀梅花」と書きます。これは開ききる...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...
-

-
ギョリュウバイの育て方
ギョリュウバイはニュージーランドとオーストラリアの南東部が原産のフトモモ科のギョリュウバイ属に分類されている常緑樹で、日...
-

-
バラ(ピュア)の育て方
その特徴といえば、たくさんありますが、特徴を挙げるとすれば、その香りが最大の特徴ではないかと考えられます。もし、いくら花...
-

-
カーネーションの育て方
母の日の贈り物の定番として、日本でも広く親しまれているカーネーションですが、その歴史は古くまでさかのぼります。もともとの...
-

-
ネムノキの育て方
ネムノキは原産地が広く、日本や朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ、インドなどが代表的なものとなっています。このほかにもイラン...
-

-
ニシキギの育て方
ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅...
-

-
ウコンの育て方
ウコンという名前は知っているものの、現在では加工されて販売されていることがほとんどのため、実際にはどのような植物であるか...
-

-
カランコエの育て方
乾燥に強い性質のある多肉植物で、育てるのに手間がかからず、鮮やかな色の花だけではなく、美しい葉そして面白い株の姿を鑑賞す...




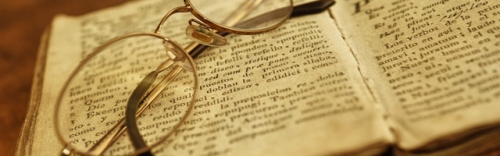





シカクマメは日本でも食されるようになってきましたが、どちらかというと熱帯を原産とする植物です。元々の生息地は東南アジアやオセアニアで、ビルマやパプアニューギニアでは好まれていたそうです。マメ科の植物だと言うこともあって、根っこにはタンパク質が豊富に含まれているために、タンパク源として古くから用いられていたのです。