オーリキュラの育て方

育てる環境について
育てる環境は、原産の生息地をイメージするとわかりやすいです。オーリキュラは比較的高い山の上で育つ植物です。光や水の条件、あるいは温度の条件などについても、だいたいイメージをつかむことができると考えられます。開花する時期には光をたっぷり当ててやります。
芽が出た頃から日当たりの良い環境で育てると花を咲かせやすくなります。ですから、基本的には日当たりの良い場所におくと良いです。花が咲き終わってからは葉を広げるために少し遮光をしてやると良いです。30%くらいの遮光をしておけば葉が広がりやすくなります。
雨が長く続くと良くありませんから、梅雨入り前には取り込んでおいた方が良いでしょう。室内に取り込んで育てる場合にはできるだけ光の当たる明るいところへおくようにします。温度については、もともと高山植物と言うこともあって、寒さには強いです。
ただ、植え替えたばかりの時など、株が少し弱っているような状態では凍結することで枯れることもありますから注意が必要です。土壌については通気性と水はけの良いものが適しています。多湿になると根が傷むことがありますから、できることなら素焼きのものが適しています。
そこに開いている穴が小さいものや、あるいは釉薬のかかった通気性の悪い鉢はあまり適していません。土壌については市販の山野草用のものを用いると良いです。肥沃な土壌である方が良いですから、肥料もこまめにやらなければなりません。
種付けや水やり、肥料について
オーリキュラの苗を買ってくると、適度な穴を掘って植え込みます。植え込み後はたっぷりと水やりをして、直接光の当たらないところで1週間くらい育てます。1週間くらい経てば落ち着きますから、通常の光の当たるところで育てるようにします。
最初の内はしっかりと水やりをしなければなりません。オーリキュラは根の乾燥を嫌う植物ですから、毎朝水をたっぷりやるようにしましょう。植え付けたばかりの時にはもちろん水やりは必要ですが、それ以外の時のも必要です。ただ、夏の昼間は高温で鉢の中が蒸れてしまう可能性がありますから、
昼間の暑い時間の水やりは避けた方が良いです。このような時期には、夕方になってから水やりをするのが良いです。冬はあまり頻繁に水やりをしなくて良く、乾いたら水やりをするくらいで十分でしょう。肥料は、3月下旬から6月下旬まで、一般的な液体肥料をやると良いです。
11月くらいには花芽形成に入ります。この時期には窒素分が少なくて、リンの多いもののほうが良いです。春と秋には置き肥をするのが良いです。置き肥をする場合には、肥料が直接は似当たらないようにするのが基本です。鉢の中で言えば、できるだけ端っこの部分が適しています。
肥料のバランスによって生育状況に影響を与えるのは言うまでもないことですが、花の数や花の美しさにも影響します。微妙なバランスですから、具合を見ながら肥料をやるようにします。花つきが悪い場合などには、少し控えてみるのも良いです。
増やし方や害虫について
増やし方としては株分けと種蒔きとがありますが、品種によって異なります。有名な品種の場合、短柱花であることが多く、そのために結実しにくいです。そのため、種を取るのは難しいと考えておいた方が良いでしょう。プベスケンス系であれば、5月下旬から7月くらいには種を採取できます。
この時期にすぐ蒔くか、あるいは保存しておいて1月から3月くらいに蒔くようにすると良いです。タネで増やすと遺伝子が変化しますから、元のものとは全く異なるものができることもあります。たとえば、花の色が違っているということはあります。
株分けの場合には遺伝子に変化はありませんから、同じものが生まれます。株分けは難しくはありませんが、あまり小さいものは育たないこともありますし、育ったとしても育ちは悪いです。ある程度の大きさになってから株分けするのが良いです。
その基準についてですが、子株から根っこが数本は出ている状態が理想的です。病気や害虫に悩まされることもあります。高温多湿になると軟腐病が発生して株元から痛んできます。ウイルス関連の病気も色々なものがあって、葉に色むらが出た場合には対処が必要でしょう。
風通しが悪いと病気になりやすい傾向がありますから、風通しの良い場所で育てるのが基本です。害虫はいろいろあって、ナメクジやアブラムシ、ハダニなどがあります。ブラ虫やハダニは芽の中や葉の裏につくことがありますから注意が必要です。早めの棒状を心がけましょう。
オーリキュラの歴史
オーリキュラは、本来はヨーロッパのアルプスに自生する植物です。高山植物として扱われていて、日本でも栽培されています。原産がヨーロッパのアルプスですが、この地域を生息地としていたオーリキュラを栽培品種として確立したのはイギリスです。
イギリスは園芸の盛んな国で、交配選別が繰り返し行われました。16世紀頃から栽培されていたと考えられています。17席になると園芸品種としての立場を確立します。たとえば、通常の花弁は5枚ですが、これが6枚か、あるいは8枚になるものが園芸品種として栽培されています。
このような歴史がありますから、品種は様々です。代表的なものがグリーン・エッジと呼ばれるものです。園芸種としては代表的なもので、エッジと呼ばれる花弁が特徴的です。グレー・エッジも愛好家の中では人気があります。エッジの部分が白くなっているという特徴があります。
エッジの部分がほとんど白くなっているものがホワイト・エッジです。他にも、エッジがなくて、サークルがきれいな丸に見えるショウセルフ、センターリングの色が黄色いゴールドセンター・アルパイン、花弁が八重咲きになっているダブル・オーリキュラ・などがあります。
長い間に渡って品種改良が行われてきたために、品種の数は非常に多いです。日本でも愛好家は多くいますから、流通しているものも多くあります。品種については系統に分けられていて、現在ではショウ系、アルパイン系、ストライプ系、ファンシー系、ダブル系、ボーダー系と細分化されています。
オーリキュラの特徴
フランスからハンガリーの山地に自生していた多年生です。高山に咲く花を持ち帰り、そしてそれをイギリスで品種改良が施されるようになります。イギリスの産業が一気に広まった産業革命の時に、多くの系統が生み出されるようになります。
最初はプリムラ・アウリキュラという野生種をベースとして、プリムラ・ヒルスタなど、同じ系統のプリムラを交配して当たらしものが作られるようになります。その中で、オーリキュラと呼ばれるものはごく一部です。まず、花弁の数が6枚から8枚であることが求められます。
春になると冬芽が開いて葉が開き始めます。っしてつぼみがやがて開花します。花が最多後には葉が大きく広がって、夏を迎えます。高山植物ですからどちらかというと夏の暑さは適しておらず、そのために夏の間は少し成長を止めているようです。
夏の暑さが過ぎて秋になると再び旺盛な成長が始まります。そして、冬になると花芽形成が行われ、古場が枯れて冬芽が形成されるというサイクルになっています。育て方は簡単ではなく、そのために価値があるとも考えられます。プベスケンスなど、育て方の簡単な品種もありますから、
まずはこのようなものから初めて見ると良いでしょう。品種によって育て方の難易度は異なりますから、簡単なもので慣れてから難しいものに挑戦してみると良いです。コツをつかめば意外と簡単に育てることができるようになります。花の種類もいろいろありますから、楽しむことができると思います。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オモダカの育て方
-

-
タチツボスミレの育て方
タチツボスミレに代表されるスミレの歴史は大変古く、日本でも最古の歌集万葉集にスミレが詠まれて登場するというほど、日本人に...
-

-
ホウセンカの育て方
ホウセンカは、ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、東南アジアが原産です。中国では、花を鳳凰に見立てて羽ばたいているよ...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
キャットテールの育て方
キャットテールは別名をアカリファといい、主にインドが原産地で、熱帯や亜熱帯地方を生息地としている植物でおよそ300種類か...
-

-
イワヒゲの育て方
イワヒゲの生息地は日本の本州の中部より北の鉱山の地域です。かなり古くから日本にあり、栽培品種として流通しているものは日本...
-

-
より落ち着いた雰囲気にするために 植物の育て方
観葉植物を部屋に飾っていると、なんとなく落ち着いた雰囲気になりますよね。私も以前、低い棚の上に飾っていましたが、飾ってい...
-

-
カサブランカの育て方
カサブランカは、大きな白い花が見事なユリの一種です。その堂々とした佇まいから、ユリの女王とも呼ばれています。カサブランカ...
-

-
アボカドの育て方・楽しみ方
栄養価も高く、ねっとりとした口当たりが人気のアボカド。森のバターとしてもよく知られています。美容効果もあり、女性にとって...
-

-
ヒマワリの育て方
野生のヒマワリの元々の生息地は、紀元前3000年頃の北アメリカとされています。古代インカ帝国でヒワマリは、太陽の花と尊ば...
-

-
カンパニュラ・メディウムの育て方
カンパニュラ・メディウムは南ヨーロッパを原産とする花で、日本には明治の初めに入ってきたものとされています。基本的な育て方...




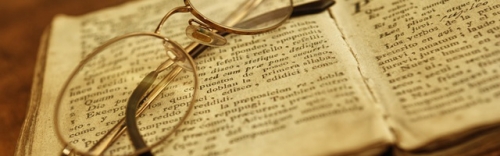





オーリキュラは、本来はヨーロッパのアルプスに自生する植物です。高山植物として扱われていて、日本でも栽培されています。原産がヨーロッパのアルプスですが、この地域を生息地としていたオーリキュラを栽培品種として確立したのはイギリスです。