キフゲットウの育て方

キフゲットウの育て方
キフゲットウは成長が早く大きくなるので、どちらかといえば庭や玄関の外などに向いている観葉植物です。コンテナや大鉢に、他の観葉植物類と一緒に寄せ植えされたキフゲットウは、エキゾチックな雰囲気を醸し出します。観葉植物用の土に緩効性の化成肥料を元肥に使って植えます。
強い直射日光は苦手なので、柔らかい日のあたる日向や明るい半日陰などに置きます。地植えにする場合は、植える場所にもよりますが、1年草として考えた方が無難です。水遣りは、鉢内がカラカラに乾燥してしまわないように十分気をつけますが、土がいつも水浸しで過湿になっても根腐れを起こして枯れてしまいます。
室内に置いてある観葉植物や庭で地植えの花などよりは、水遣りの回数をやや多くするのが良いでしょう。夏期は高温のために土が乾きやすいので、様子を観察して、必要であれば朝夕水遣りします。また、できれば朝夕葉水を与えます。肥料は緩効性の化成肥料を毎月用法どおりに与えます。
株をあまり早く大きくしたくない場合には、用法より少なめに施します。キフゲットウは実生・株分け・根茎分けで増やすことができます。株分けは株にボリュームが出すぎたら、随時行います。根茎分けは3年以上経過した株で、冬場に掘り上げて保管するときなどに行います。
キフゲットウの冬越し
地域や置き場所にもよりますが、晩秋から冬にかけて葉が枯れ始めるようであれば、真冬は地上部がすべて枯れることが予想されます。根茎植物なので地上部が枯れても土が凍ったり雪がかからないようにしておけば、5月頃に芽が出てくる可能性があります。心配な場合は、冬だけ室内に取り込むか、ショウガのような根茎を掘り上げて光が当たらない場所で保存します。
室内に入れた場合は、窓から日が射す場所に置きます。成長が止まっているので肥料は与えず、水遣りも控えめにします。土の表面が乾いてから1~2日後に、鉢底から水が出てくるまでたっぷり水を与えます。1日数回、しっかり霧吹きをします。地上部が枯れてしまった場合は、翌年は花がつきません。
室内に取り込んで管理している間に小さな白い塊がつくことがありますが、これはカイガラムシという害虫なので、葉を痛めないように気をつけて、そっと濡らしたティッシュなどで拭き取ります。放っておくとどんどん増えるので、見つけたらすぐに退治します。
葉がすすけたように色が悪くなったり、ガサガサと細かい傷がついたような感じに見えるときは、ハダニがいます。
ハダニは小さすぎて見分けがつかないので、市販のハダニ駆除薬を使うのが、手間はかからずに済みます。薬を使いたくない場合には、ハダニは水に弱いので濡らしたティッシュですべての葉の両面を拭いて様子を見ます。数日置いて2~3回繰り返すほうが確実です。カイガラムシやハダニがつくときは株が弱ってきている場合が多いので、管理自体も見直します。
キフゲットウの種付け
5~6月に咲いた花は、秋になると丸い実をつけます。中の灰色の種が見え始めたら収穫し、日のあたらない場所に置いてそのまま追熟・乾燥させます。種を取り出して湿度の低い場所で保管して冬を越し、4月中旬~5月に種まきをします。市販の苗用のポットに種まき用の土を入れ、中央辺りに2~3粒ずつ、深さ1~1.5センチくらいで埋め、底から水が流れ出るまで水遣りします。
芽が出るまで1~3ヶ月かかりますが、この間、土が乾いたら水遣りします。芽が出て、本葉が見え始めたら一番元気な芽を1つ残して、残りの芽を摘みます。そのまま暖かい日当たりや温室などで栽培を続けます。なるべくこまめに霧吹きします。
苗は条件と手入れが良ければ成長が早く、油断すると根詰まりするので、たまにポットの下をそっと覗いてみて、根が出てきていたらなるべく土を崩さないようにしてポットから抜いて、鉢上げして栽培を続けます。鉢上げ後は一週間ほど日陰で休ませます。その後は屋外で育てても大丈夫です。定期的に鉢底を確認して、必要ならさらに大きな鉢に植え替えます。
種付けして実生で育てた株は花が咲くまでに3年かかります。この間は根茎も発達していないので、冬は室内に取り込んで管理します。苗の間は根茎が形成されていないため、地上部が枯れると何も残らずに終わってしまうので、親株よりは丁寧に面倒を見ます。
晴れた日の暖かい日中は窓辺に起きますが、曇りや雨の日と夕方以降は窓ガラスを通して冷気が伝わってしまうので、部屋の中のテーブルの上など、なるべく暖かい場所に置きます。あまり暖房の熱源の近くは乾燥しやすいので、避けます。部屋の暖房を切る夜間は室内でも急速に冷え込む場合があるので、市販の室内越冬用の鉢の上から被せるカバーを使用するのも有効です。
ただ、ずっと被せ続けていると光量不足になるので、被せるのは夕方以降にしましょう。少し大きな鉢の中に入れて2重鉢にしたり、ダンボールの中に入れても防寒になります。ただしダンボールに入れても部屋の床に置くと、夜明けに床から冷気が伝わって株が弱る場合があるので、置き場所に注意します。
キフゲットウの歴史
キフゲットウは東アジアとインド原産のショウガ科ハナミョウガ属の高さ1メートル以上になる熱帯性多年草です。日本でも沖縄県から九州南部にかけてが屋外でも地植えで越冬できる生息地となっています。ちなみに沖縄では古くからゲットウのことをサンニン、サニ、サニン、サヌイン、サネン、ムチガシャムチザネン、マームチハサーなどと呼びます。
斑の入らないものを月桃(ゲットウ)といい、沖縄ではゲットウの葉で餅を包み蒸した「ムーチー」(鬼餅)という菓子を食べ、一年の厄を払い健康を祈願する風習があります。これは夜な夜な鬼となって暴れまわる兄に、妹が鉄の釘を入れたムーチーを食べさせて退治したという沖縄本当に伝わる古い昔話が元になっている伝統行事です。
キフゲットウは黄斑月桃と書き、このゲットウから斑の入る株が選抜・育成されました。ヨーロッパではシェル・ジンジャーと呼ばれています。同じハナミョウガ属でキフゲットウと似た感じで白い斑の入るフイリゲットウという植物がありますが、こちらは見た目が似ているだけでゲットウとは違う種類の植物です。
キフゲットウの特徴
ゲットウもキフゲットウも槍型の葉で長い茎をしており、ボリュームのある印象的な草姿です。特徴はどちらも同じですが、黄色い斑が美しいキフゲットウは観葉植物として扱われています。黄色い斑と葉のグリーンの部分のバランスには、個体差があります。
また、通常、開放的な花屋の店内などでは分かりませんが、観葉植物として家の部屋の中に置いておくと、エアコンなどの風があたったり、水遣りのときなどにショウガを青臭くしたような特徴的な香りが漂います。そのためゲットウやキフゲットウには蚊やゴキブリなどの害虫を寄せつけない効果があります。
花は日本では5~6月に前年度の株に、花茎ではなく葉柄が伸びていって先端から長い花穂が垂れ下がって咲きます。個々の花は外側が淡いピンク色を帯びた光沢のある白い巻貝のようなシェル型で、内側の中央は赤く、下側のリップ部分は黄色をしていて美しく、満開時は香りがします。
東アジアの生息地では年間を通して最低気温がほぼ18度以上と温暖です。降水量もかなり多いのですが、地域によっては弱い乾季があります。サバンナ気候ほど明確な乾季ではありません。生息地での上層にあるさまざまな木々は、おもに落葉広葉樹です。
乾季に落葉した葉が雨季の高温期に微生物によって分解されますが、午後に降るスコールによって流されてしまい、残った鉱物や酸化物が作り出す痩せた酸性の赤い土がキフゲットウの育つ土壌となっています。
上層の木々の枝葉が広がっているため、中層から下層に向かうほど日差しは弱まりますが、乾季には下層まで届く光量が増えます。そのためキフゲットウは日向から明るい半日陰に生息していますが、極端に強い紫外線では葉焼けを起します。
観葉植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:パキラ(Pachira glabra)の育て方
タイトル:フイリゲットウの育て方
-

-
ミズナの育て方
水菜の発祥地は静岡県小山町阿多野といわれており、JR御殿場線、駿河小山駅近くに水菜発祥の地を記した石碑が立っています。静...
-

-
ハイドロカルチャーの育て方
土を使わず、ハイドロボールと呼ばれる素焼きの石や、炭、砂等に植物を植えて育てる水耕栽培の植物栽培方法です。ちょっとした観...
-

-
クリサンセマム・パルドーサムの育て方
クリサンセマム・パルドーサム(ノースポール)は、キク科フランスギク属に分類される半耐寒性多年草です。ただし、高温多湿に極...
-

-
サカキの育て方
サカキは日本・朝鮮・台湾・中国に自生する、比較的温暖な地を好みます。葉の形で先が鋭くとがっているものは神の宿るよりしろに...
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
イワコマギクの育て方
イワコマギクは和名としてだけではなく、原産地となる地中海海岸地方においてはアナキクルスとしての洋名を持つ外来植物であり、...
-

-
多肉植物の育て方のポイント
初めての人でも比較的簡単に栽培することが出来る多肉植物の育て方のポイントについて記述していきます。まず、多肉植物は、乾燥...
-

-
ゼラニウムの育て方
ゼラニウムの主な原産地は南アフリカです。南アフリカを中心にオーストラリアや中東などの広い範囲を様々な種類が生息地としてい...
-

-
グレコマの育て方
グレコマの科名は、シソ科 / 属名は、カキドオシ属(グレコマ属)となります。和名は、カキドオシ(垣通し)、その他の名前:...
-

-
ツルウメモドキの育て方
人間や動物には性別があります。見た目ではよく見分けすることができない魚や虫にもあります。植物にまであると知り、意外だと驚...




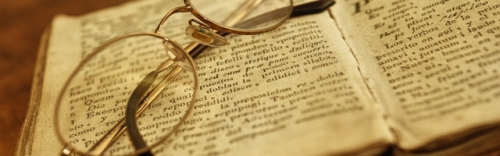





キフゲットウは東アジアとインド原産のショウガ科ハナミョウガ属の高さ1メートル以上になる熱帯性多年草です。日本でも沖縄県から九州南部にかけてが屋外でも地植えで越冬できる生息地となっています。ちなみに沖縄では古くからゲットウのことをサンニン、サニ、サニン、サヌイン、サネン、ムチガシャムチザネン、マームチハサーなどと呼びます。