ジギタリスの育て方

ジギタリスの育てる環境について
真夏の直射日光や暑さに弱いので、朝は日が当たり、昼以降は日陰になる反日陰の場所に植えます。もしくは真夏には木の日陰になり木漏れ日が注ぐ場所が適しています。よって、温かい土地では夏を越えるのが難しいと言えます。
庭植えの場合、関東で夏を越せるのは4割以下です。関東では反日陰で管理するのが必須条件です。北陸では宿根して毎年咲くようです。株が大きくなると暑さに弱くなります。環境があえば、こぼれ種で発芽するほど強い植物ですが、暑さ管理がやや難しいと言えます。
ジギタリスは、品種によってはいくらか暑さに強いものもありますが、やはり暑さには弱く、夏に枯れてしまうことが多いです。その対策として、春に開花したら脇芽を挿し芽しておき、夏を越させます。苗の状態だと夏を越えやすくなります。
この苗を涼しくなってから地面に植えると春に開花するので、その脇芽を挿し芽にする、というのを繰り返すことによって毎年ジギタリスを楽しむことができます。種類によっては2m近く成長するものもあり、大きな花を咲かせます。花色も豊富で、特に鮮やかな白は目を奪われるほど存在感があります。
ガーデンに植えると存在感と特徴ある姿で華やかなアクセントになります。アメリカの著名なガーデナーも、ジギタリスを育て、広大な庭の中で存在感を放っていました。夏を越すのには工夫と手間がかかりますが、そんなところに愛情を感じ毎年手をかけて育てるファンも多いようです。
ジギタリスの種付けや水やり、肥料について
育て方ですが、前述のとおり暑さに弱いため、反日陰の水はけのよい土に植えます。草丈が高くなるので十分に間隔を取って(50cm程度)植えます。水はけのいい土地を好みますので、水はけの悪い粘土質の土壌の場合、有機物の堆肥やパーライトなどを混ぜこむとよいでしょう。
発芽温度は20度から25度です。乾燥を好むので、水のやり過ぎには注意が必要です。やり過ぎると腐って枯れてしまいます。土が乾いたら、水をしっかりとやりましょう。やや乾燥気味くらいで管理します。鉢植えの場合は鉢の底から水が染み出す程度にやります。
肥料は植えつけの時だけでほとんど必要ありません。生育が悪い時のみ追加します。肥料を多くやると葉も丈も大きく育ちます。並べて植えたものの肥料を吸って大きく育ち過ぎ、景観を損ねたり、他の植物の日光を遮ることもあります。種を採取しない場合、ジギタリスの蕾が咲いてきた頃に根元から切り落とします。
2番目の花が咲きますので、茎を切り取り手入れをしましょう。土を水はけのよいように改良しておくこと、水やりをし過ぎないこと、肥料をやり過ぎないこと、日光のあたり過ぎない反日陰の場所に植えること、これがジギタリスを育てる秘訣です。
暑さに弱く、夏を越せるかどうかが問題になるところですが、害虫にも強く丈夫な植物です。環境が大きく影響する植物で、日本の気候では栽培がやや難しく中級者向けといえます。育て方はやや手間が掛かるので、中級者向けといえます。
ジギタリスの増やし方や害虫について
ジギタリスは種付けで増やすことができます。発芽温度は20~25度なので4月から5月に種を取って撒き、発芽したらポットに植え替えます。重要なのは、ポットの苗を秋に定植するまでに、しっかりした苗に育てておくことです。大きな株に育てておくと翌年花が咲きます。
ポットに植えた苗は、できるだけ直射日光を避け、風通しがよく涼しい場所に置きます。多湿にも弱いので、夏場は苗を雨に当てないよう気を付けて育てる必要があります。種撒きが秋以降になると、翌春は開花せず、もう一度夏と冬を越して翌々年の春に開花します。
好光性の種で光を必要とするので、種を撒いた後はごく薄く土をかぶせます。開花したら、成長に合わせて鉢を替えてあげるとよいでしょう。挿し木をする場合、春から初夏にかけて株元にできた枝を取って挿し木をします。丈夫な植物ですが、アブラムシには注意が必要です。
開花中からアブラムシが発生します。体長2~4ミリの小さなアブラムシが、新芽や茎に群がって汁を吸います。種を取らない場合は、アブラムシの発生した花茎を早めに切る必要があります。残す場合はオレイン酸ナトリウムを含む殺虫剤を散布します。
一般家庭の庭であればスプレータイプが使用しやすいです。ジギタリスは、古くから薬草として使われ、18世紀には強心剤として使われてきました。しかし、口にしなければ問題はありません。ただし、ペットが葉や花を口にした場合、体調不良を起こす可能性があるので注意が必要です。
ジギタリスの歴史
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではないため、野原で繁茂し、身近な植物として親しまれていました。その毒性の中に薬効成分が含まれていることが中世から知られており、薬用植物として育てられました。
また、ジギタリスはヨーロッパでは妖精の花と親しまれており、様々な妖精の名前で呼ばれてきました。学名のDigitalisは本来はディギタリスですが、日本ではジギタリスと呼ばれています。学名はラテン語で指を意味し、花の形が指サックに似ているところからきているそうです。
和名はキツネノテブクロです。ドイツ名ではキツネの帽子、あるいは指の帽子と呼ばれています。ノルウェーではキツネの鈴やキツネの音楽と呼ばれています。ジギタリスの花の神秘的でかわいらしい雰囲気や、鐘のような花の形、キツネの神秘的なイメージと結びつき、物語を感じさせる名前といえます。
ジギタリスにかかわる話はヨーロッパでは多く残されていて、当時の人々がいかに身近な植物として親しんでいたかを物語っています。明治時代に日本に渡来したと言われています。薬効のある植物にもかかわらず、園芸種としてこんなにも人々に親しまれてきた理由には、
やはりその姿の可憐さや美しさにあると言っていいでしょう。妖精の花と思われていたように、いくつもの下向きに垂れた鐘がまるで妖精が奏でる楽器のようです。道端に生息していたら、思わず足を止めて見入ってしまうでしょう。
ジギタリスの特徴
ジギタリスは毎年咲く多年草か花が咲いた後に枯れる二年草です。約19種あるジギタリスの中でももっとも普及し、一般的にジギタリスと言えばプルプレアです。学名のプルプレアは紫色を意味し、名の通り紫色の花を咲かせます。現在は花壇などに観賞用として植えられています。
地面に張り付くように冬を越しますが、春になるとどんどん茎が伸び、1.2m~1.8mの背丈になり5月~7月に鐘状の花を多くつけます。紫の花の内側には黒っぽい斑点ができます。そのほか、野生種としてルテアがあります。ヨーロッパや北西アフリカが生息地です。
白や黄色の小ぶりな花を咲かせます。ルテアは黄色を意味し、花の色に由来します。グランディフロラは、ヨーロッパから西アジアに自生します。花色は黄色で、グランディフロラは「大輪」を意味します。メルトネンシスは、プルプレアとグランディフロラの雑種で、濃いピンクの花を咲かせ、香りがあります。
園芸品種としてエクセルシアがあります。1.8mになる大型種で、大輪の花を咲かせます。グロキシニフローラは、多くの花が開き、内側の斑点も多く入ります。フォクシーハイブリッドは50cmくらいになると開花します。90cmほどの小型種で、花色が豊富です。小型の花壇でも楽しむことができます。
AAS賞を受賞した優良品種です。アルビフローラは純白の花を咲かせ、内側の斑点が全く入らずとても美しい品種です。エクセルシアハイブリッドは、花色はピンク、クリーム、白、黄色などのパステルカラーです。1.8mになる大型種で花は水平に開き、茎の片側だけでなく周囲に咲きそろいます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ティアレ・タヒチの育て方
-

-
オカワカメの育て方
オカワカメと言うのは料理のレシピなどでもお馴染みの食材です。ワカメ名の付くことからも見た目がワカメに似ていたり、栽培する...
-

-
モモ(桃)の育て方
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染...
-

-
カラント類の育て方
カラント類は、ヨーロッパが原産です。フサスグリ全般のことをトータルで、英語ではカラントと呼んでいます。カラント類は真っ赤...
-

-
カルセオラリアの育て方
カルセオラリアはゴマノハグサ科の多年草です。原産は南アメリカであり、一般的には温室で観賞用として栽培する品種として現在に...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
イオノプシジウム,育て方,栽培,原産,生息地
花の分類としてはアブラナ科に属します。花については庭植えとして育てられることが多く、咲き方としては1年草になっています。...
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
ヘメロカリスの育て方
ヘメロカリスの生息地はアジア地域で、原種となっているものは日本にもあります。ニッコウキスゲやノカンゾウ、ヤブカンゾウなど...
-

-
ギンヨウアカシアの育て方
ギンヨウアカシアの原産地はオーストラリアで、南半球の熱帯や亜熱帯を主な生息地としています。ハナアカシア、ミモザ、ミモザア...
-

-
キンバイソウの育て方
キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。過去どのような形で進化してきたのか...




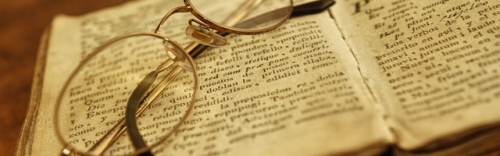





ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではないため、野原で繁茂し、身近な植物として親しまれていました。