スイートピーの育て方

スイートピーの育てる環境について
スイートピーを植える場所ですが、連作を嫌います。ですから、露地植えする場合はマメ科の植物を育てた場所に植えないでください。また、直根性のため誤って根を切断してしまうと再生しにくい植物ですので、植え替えは避けたほうがいいです。
最初から最後まで育てたい場所を選定してください。そして日当たりの良い場所を選んでください。日当たりが悪いとつぼみが付きにくかったり、あるいは咲かずに枯れてしまう可能性があります。あとは風通しと水はけの良い場所を選んでください。
どうしても水はけの悪い場所に植えるときは、パーライトなど入れ土を盛ってください。耐寒性はけっこう有りますが、霜のせいで痛む恐れがあります。霜の可能性があるのなら敷きワラをするなどして霜よけをしてください。プランターで栽培するなら軒下に置けば霜よけできます。
スイートピーは酸性土を嫌います。そこで、一メートル平方あたり百グラムの苦土石灰を土にまぜて中和するようにしてください。最初から市販の土を用意するのであれば問題ありません。また、腐葉土や堆肥を土に混ぜて深く耕しておきましょう。根が深く張るからです。
茎は自立できないので絡むことのできる添え木か何かを用意してください。園芸用ネットを張るのもよいでしょう。すぐそばにフェンスがあるのなら、フェンスに任せてもよいでしょう。プランターを使用する場合は、深く根が張るので大きめの物を用意してください。小粒の赤玉土を8、腐葉土を2の割合で土を入れてください。
種付けや水やり、肥料について
スイートピーは春咲きのタイプが主流なので、春咲き用の育て方を説明します。春咲きの開花時期は4月下旬から六月上旬頃です。品種によって違うので前もって確認しておいてください。十月から十一月中旬に種をまきます。種の表面をナイフややすりなどで傷をつけて、一晩水に浸して吸水させておきます。
そうすると発根しやすくなります。種をまく時は深さ2cmほどの穴を掘ります。複数ヶ所植えるのであれば、20cmの間隔をあけてください。種はひとつの穴に3粒ほど直蒔きします。芽が出てきたらひと穴につき一つ、一番元気な芽を残して他は間引きしてください。
無理に抜くと残しておきたい株の根を傷つけてしまうかもしれないので、株の元を切るようにしてください。草丈が20cmくらいになったら5~6節目あたりの上の部分をつみ取り、わき芽を伸ばすようにしましょう。すると、枝の数が増えます。草丈の伸びない品種であれば必要ないです。
土が乾いていたらたっぷりと水やりをしてください。特に春になると成長期に入りますので、水やりを欠かさないようにしましょう。ただし、発芽前後は水やりを控えてください。三月頃に、化成肥料を追肥してください。窒素肥料が多いとツルは成長しても花のつきが悪くなってしまいます。
リン酸分を含む化成肥料を与えるようにしましょう。開花時期が近づいてきたら二週間に一回、その日の水やりを休む代わりに液肥をまいてください。花が咲く頃に、巻きひげを摘み取るようにしましょう。せっかく花が咲いても巻きひげが絡みついてしまい花が潰されるのを防ぐためです。
増やし方や害虫について
スイートピーは一年で枯れてしまうので、採取した種で増やします。花が咲き終わった頃にサヤエンドウに似た果実ができるので、さやが茶色く変色したら種をとり出します。これを涼しく乾燥した場所に、種まきの時期まで保管しておきます。
害虫としては、アブラムシやアオムシ、ダニが発生することが有ります。特にアブラムシは茎、葉、花などで栄養を吸汁します。月に一度、害虫駆除剤を使って防ぎましょう。他にはヨトウムシにも注意が必要です。夜になったら葉の裏や茎についていないかチェックしましょう。
もちろん見つけたら駆除します。オルトラン粒剤を株元に蒔いておけば効果的です。スイートピーがかかる病気といえば、うどんこ病があげられます。発生時期は春と秋で、茎や葉に小麦粉の粉をかけたように白くなります。これはウドンコカビ科の寄生菌で、葉の栄養を吸われたり、
光合成を妨げられたりします。ですから早いうちに薬剤を散布して広がらないようにしましょう。ただし、薬剤が花や蕾にかかると変色してしまいます。散布するときは花にかからないように注意が必要です。他の植物に比べたら病気や害虫の発生する可能性は低い方ですが、
水やりや肥料があまりに多すぎるとかえって病気になりやすいので気をつけてください。水やりは1回の量は多くて構わないのですが、回数を多くしないようにしてください。あとは、花がらをまめに摘んだり葉が茂りすぎた時はピンチをするなどして、清潔な状態を保って病気を予防しましょう。
スイートピーの歴史
スイートピーは西暦一六九五年に、カトリックの修道僧で植物学者でもあったフランシス・クパーニによってイタリアのシシリー島にて発見されました。その後はイギリスやオランダに伝わり、園芸植物として発展していきました。本格的に品種改良がされるようになったのは、十九世紀後半になってからです。
イギリスのヘンリー・エックフォードが改良・交配に力を注ぎ、たくさんの品種が生まれました。彼は「スイートピーの父」と呼ばれています。発見された頃の原種は小型のものでしかなく雑草扱いされていましたが、彼の品種改良によって現在親しまれている形が生まれたのです。
二十世紀はじめにはイギリス国王のエドワード七世の王妃にあたるアレクサンドラがスイートピーをこよなく愛し、祝賀の席でふんだんに使われエドワード朝を象徴する花となりました。その後、息子のジョージ五世の戴冠式にも使用され、その美しさに世界中から注目をされたといわれています。
一方、日本に渡ってきたのは幕末の頃です。しかし、実際に栽培や品種改良を行うようになったのは大正時代になってからです。日本での知名度を決定的にあげたのは松田聖子が一九八二年に歌って大ヒットした赤いスイートピーのおかげでしょう。
しかし、歌のイメージに合うような赤い品種は当時はなく、赤色でも黒っぽい感じのものしかありませんでした。歌のヒットから十八年たってから、日本の農家の品種改良により納得のできる赤い品種が生まれています。
スイートピーの特徴
スイートピーはマメ科レンリソウ属の一年草、もしくは宿根草です。イタリア南西部にあるシシリー島が原産で蔓性の植物です。生息地は地中海地域、アジア、南北アメリカ、東アフリカなどです。和名は、ジャコウエンドウ(麝香豌豆)、ジャコウレンリソウ(麝香連理草)、カオリエンドウ(香豌豆)などと呼ばれています。
花言葉はデリケート、ほのかな喜びなどです。茎は自立できず、他のものに巻きひげで絡むようにして伸びていきます。草丈は小さいもので40cmぐらいですが、大きなものは3mにもなります。花は品種によって開花時期が違い、春咲き、夏咲き、冬咲きがあります。
最も多いのは春に咲くもので、俳句でも春の季語として扱われています。スイート(香りの良い)とピー(エンドウ豆)が合わさってスイートピーという名前になっている通り、昔から芳香を放つ植物と知られてきました。日本でもカオリエンドウなどと呼ばれているのはそのためです。
また花が咲き終わるとサヤエンドウに似た豆果ができます。ただし匂いとは裏腹に、痙性麻痺を起こす毒を持っているので食べることはできません。加熱しても毒性は消えませんので注意してください。あと、豆以外の部分にも微量ですが毒があります。主に観賞用として栽培されていますが、
今では品種改良が進んでバリエーションに富んでいます。発見された時の原種の花の色は紫から赤紫のグラデーションの色合いだったのが赤、ピンク、オレンジ、白と増え単色だけでなく複色のものもあります。なお、黄色のものは自然界に存在しません。あるとすれば着色したものです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ステルンベルギアの育て方
-

-
スターアップルの育て方
スターアップルは熱帯果樹で、原産地は西インド諸島および中南米です。アカテツ科のカイニット属の常緑高木です。カイニット属と...
-

-
ヒベルティアの育て方
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にも...
-

-
ソレイロリアの育て方
特徴としては、イラクサ科の植物とされています。常緑多年性の草になります。草の高さとしてはそれ程高くなりません。5センチぐ...
-

-
ビャクシンの仲間の育て方
ビャクシンはヒノキ科の常緑高木で、日本の本州から沖縄県で栽培されています。その他の原産地には朝鮮半島や中国などが挙げられ...
-

-
簡単な人参の栽培の仕方について
野菜作りなどの趣味の範囲でも、人参の栽培は簡単に作る事ができます。ベランダなどでのプランター栽培でも作る事ができるのでお...
-

-
パッションフルーツの育て方
パッションフルーツは和名をクダモノトケイソウという、アメリカ大陸の亜熱帯地域を原産とする果物です。かつてはブラジル、パラ...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
アルブカの育て方
この植物に関しては多肉植物として知られています。一般的な花とはかなり異なるように感じていましたが、比較的身近な花の科に属...
-

-
ハーデンベルギアの育て方
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベル...
-

-
ウコンの育て方
ウコンという名前は知っているものの、現在では加工されて販売されていることがほとんどのため、実際にはどのような植物であるか...




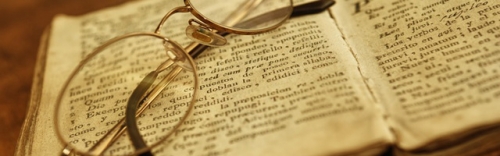





スイートピーは西暦一六九五年に、カトリックの修道僧で植物学者でもあったフランシス・クパーニによってイタリアのシシリー島にて発見されました。その後はイギリスやオランダに伝わり、園芸植物として発展していきました。